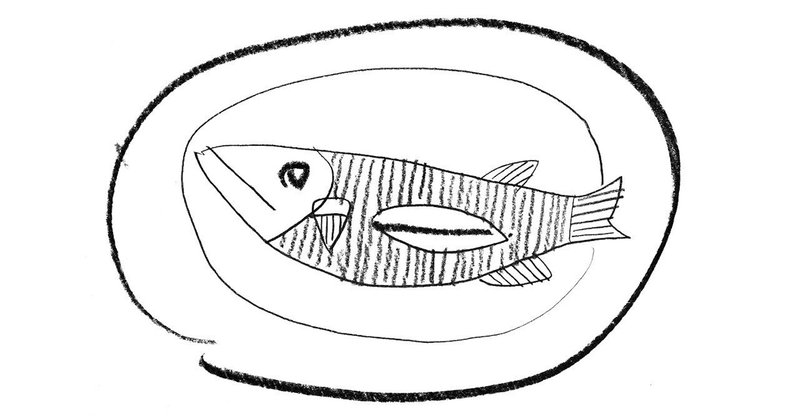
ただ、いる、だけ、なんて。 〜『居るのはつらいよ』覚書〜 (17/40)
おいしい料理には2種類あると思う。
ひとつめは、強烈で感動的なうまさで、とうぶん食べなくても満足なおいしさ。
ふたつめは、すこし物足りないんだけど、もうちょっと食べたかったなぁというおいしさ。
これを「本」に置きかえてみると、読んでいる時間そのものがすばらしい本と、読んだあとの時間にじんわり効いてくる本とにわけられそうだ。
どんなことにも例外はあって、とってもおいしかったのに後味がわるい、というレアケースの本をだった。
『居るのはつらいよ』というタイトルのこの本は、医学書院というおかたいイメージの出版社が発行していて、「ケアとセラピーについての覚書」とサブタイトルがついていた。
ヘヴィーな学術書のようだけど、表紙はポップで内容はノンフィクションのストーリー仕立てのライトなものでもあった。
本書のテーマは「居る」ということについて。
主人公は、著者でもある京都大学で臨床心理のハカセをとった意識高い系の男。
卒業後、その彼はセラピーの専門家として活躍できる場を求めて沖縄の精神障害のある人たちが通うデイケア施設に意気揚々と就職する。
しかし、そこでまず求められたことは、なにかをすることではなく、「ただ、いる、だけ」だった‥‥。
そして、そこで過ごした4年間の日常と心情と風景が、「セラピー」と「ケア」というキーワードをまぜこみながら、ていねいに描かれている、という内容だった。
わたし自身、対人援助の「ケア」に近いしごとをしているということもあり、「セラピー」よりのハカセの視点から描かれているストーリーは逆に興味深く、なるほどと感心することがおおかった。
そんなハカセのストーリーが、心理学だけではなく哲学や精神医学、文化人類学、社会学など、ちょっとかしこくなったような豆知識もおりまぜながらバランスよく言語化されていることもあって、おもしろく、さいごまでイッキ読みだった。
人によっては、ソーシャルワークの視点がないとか、ケアのとらえかたについてご意見も出てきそうな内容でもあるかもしれないけれど、細部にこだわれば著者の言わんとしていることを見失うことになる。

しかし、しかしだ。
あれほどおいしく読んだのに、あの後味のわるさは、いったい何だったんだろう。
よくよく考えてみると、ストーリーと豆知識と編集という名のすばらしい調理がされているおいしい料理なんけど、とりあつかっている素材はシリアスなものだった。
そのままでは食べられないテーマを、なんとかして食べられるようにおいしく調理された作品だけど、後味まではどうしようもなかったとも考えられる。
でも、もしかりに、著者がどんなものでもおいしく調理できるすご腕の持ち主だったとしたら‥‥。あえて後味をわるく設計したとするならば、相当な腕の持ち主じゃないかとも思われる。
いや、後味もスッキリおいしくできるはずなのに、あえてこんな仕上げにしたにちがい! とも思えてくる。
というのも、おいしく調理できる素材かどうかは別にしても、この素材は「ああ、おいしかった」と食べおわってしまうわけにはいかないテーマだったからだ。

あとがきのさいごに、このように書いてあった。
書きながらわかってきたことは、この本は精神科デイケアを舞台にしたお話ではあるのだけど、それはただデイケアという局限された場における医療行為について語ろうとしたものではないということだ。
そうではなく、これはケアしたりされたりしながら生きている人たちについてのお話だ。あるいは、ケアしたりされたりする場所についてのお話だ。そう、それは「みんな」の話だと思うのだ。
職場、学校、施設、家庭、あるいはコミュニティでの「居る」を支えるものと、「居る」を損なうものをめぐって、本書は書かれた。
だから、そのように、読者にも届いてくれたら、著者としてこれ以上うれしいことはありません。
おいしくできるのにあえて後味をわるくしている料理は、著者のねらいどおり、読者のわたしに届いた。
ごちそうさまでした。
お口直しのデザートは、じぶんでつくるしかない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
