
週3日フルリモートで働きながらフロントエンドの難題に挑む。つくったもので誰かが喜んでくれる、いまの仕事の魅力とは | エンジニアインタビュー
株式会社ヘンリーは、「社会課題を解決し続け、より良いセカイを創る」というMissionのもと、クリニック・中小病院向けの基幹システムであるクラウド型電子カルテ・レセプトシステム「Henry」を開発・展開しています。
今回お話を伺ったのは、「Henry」のフロントエンドエンジニアを専任する河村和始さんです。はじめは副業で関わりはじめたヘンリーでの仕事ですが、21年11月に正式入社。働き方として「週3日勤務」を選択しています。
河村さんの働き方の背景にある「自給自足」というテーマに始まり、エンジニアとして今も覚えているファミレスで見た友人の顔、そして料理とエンジニアの意外な関係まで。フロントエンドの視点からヘンリーの魅力をたっぷり語っていただきつつ、河村さんの目指す世界についてもお話を伺いました。
山梨県で野菜を育てながらリモートワーク
— 河村さんは現在、ヘンリーではどういった役割を担ってらっしゃるんですか?
フロントエンドのエンジニアです。
今は病院さま向け「Henry」をつくっている最中で、フロントエンドは僕が専任で見ています。デザイナーやプロダクトマネージャーと連携しながら、フロントエンドのコードを書くのがメインの仕事です。その他にも、フロントエンドエンジニアの採用では技術面談や技術課題の評価を担当しています。
— 河村さんは、正社員でありながら「週3日勤務」という働き方を選択しているそうですね。
そうですね。普段は山梨県で暮らしており、基本的には「週3日・フルリモート」で働いています。ちなみに週3日や週4日勤務という働き方を選んでいる社員は私だけでなく他にもいるので、ヘンリーにおいては勤務日数の多い少ないで働きにくさを感じることは全くありません。
— フルリモートで働いている方は他にもいらっしゃるんですか?
たくさんいます。むしろ基本的にフルリモートがメインです。僕のように地方で暮らしている方は他にもいますし、海外では上海からリモートワークしている方もいます。そういった環境なので、ヘンリーでは月に1回、希望者が東京のオフィスに集まりオフラインでコミュニケーションを取る日があって、僕もときどき参加しています。
プロダクトが未完成のときから頂けたフィードバック
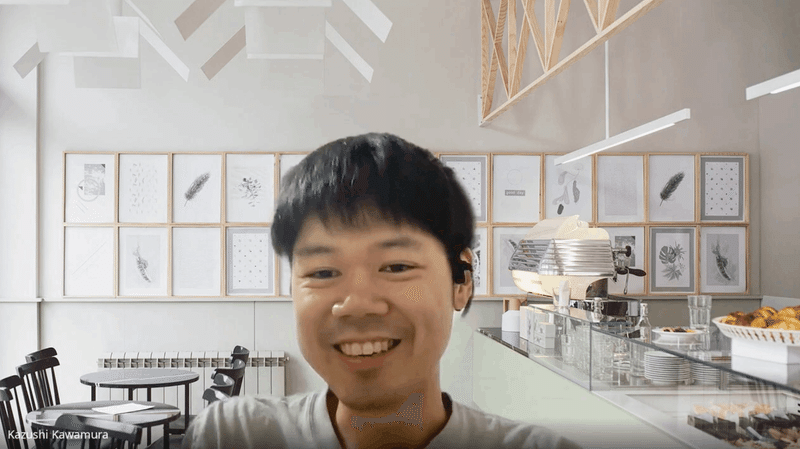
— そもそもヘンリーとの出会いは?
前職では超小型人工衛星の設計開発を中心事業とする宇宙ベンチャーでソフトウェア開発を担当していました。大学から新卒入社した会社を含めると7年間くらいWeb系の畑でソフトウェアのプログラミングをしてきていましたが、別の領域にも挑戦してみたい気持ちが湧いてハードウェアの会社に転職したんです。結果的にソフトウェア開発を任されることになるのですが、言語もプログラミング手法もプラットフォームもWeb系とは異なる環境でした。すると逆に、Web系の技術を忘れてしまいたくない思いも出てきて、できれば副業をしながら技術は錆びないようにしたいとぼんやり考えていたんです。そんなときにLinkedInでヘンリーから声をかけてもらったのが最初のきっかけです。
— では21年11月の正式入社までは副業で関わっていたんですね。
そうですね。2020年7月から副業でジョインしました。
その当時のヘンリーは2~3名が正社員、10~20名が副業人材というチームでした。おもしろい組織だなと思った記憶があります。すぐに正社員になることを求められると困るなと当時の僕は思っていましたが、副業で関われる安心感があったので、まずは話を聞いてみようと思えたんです。
最後の決め手は、面談相手だったCEO逆瀬川さんが、話していて信頼できる人だなと感じたことでした。何を話したかはさっぱり忘れているんですが(笑)、そう感じたことはなぜか覚えています。それから今に至るまで2年くらい一緒に働いていますが、当時感じた印象は変わっていないですね。僕は緊張しやすいタイプなんですが、逆瀬川さんにはいい意味で全くなくて。不思議ですが。それって逆瀬川さんが上下関係ではなくフラットな関係を大事にしているうえに、それを口だけでなく行動で示しているからだと思います。社長だから言いづらいとか、何かを隠したい、というものは全くないので。
— もともと副業のつもりでジョインした河村さんですが、正式に入社することを選択したのはなぜなんですか?
1つ目は、先ほどお伝えした通り代表の逆瀬川さんの人間性ですね。
2つ目は、医療ドメインは規制産業ならではの泥臭いハードルがたくさんあって、1人では絶対にできないチャレンジができる環境があったことです。せっかくチームでやるなら、自分が100人いてもできないことに挑戦できる会社に入りたいと思っていたので。
もちろん、ほとんどの会社の仕事はそうかもしれませんが、ヘンリーには他にも魅力を感じる部分がありました。例えば、僕は「生産性を上げるプロダクト」が好きなんです。個人でもToDoリストやカレンダーアプリをよく使っているので、生産性に寄与できるプロダクトをずっとつくってみたいと思っていたほどです。それでいうと「Henry」の電子カルテは、プロダクトが使いやすくなればなるほど、医師や医療事務の方の生産性を上げることをお手伝いできるので、個人的には魅力的でした。
また、当時はプロダクトがまだ完成していなかったんですが、理念に共感してくださったいくつかのクリニックさんがすでにユーザーとして製品の改善に協力してくださっていました。現場のみなさんにフィードバックをいただきながら開発していたのですが、これはフロントエンドエンジニアとしては大きなやりがいです。個人開発をしていると顧客からフィードバックをもらうことがいかに貴重か肌で感じるので、フィードバックをたくさんもらえるヘンリーの環境はエンジニアとして恵まれていると思いました。
料理とプログラミングの不思議な関係
— そもそも「週3日勤務」にしている背景を伺ってもいいですか?
時間を言い訳できない環境をつくって、自分のやりたいことをもう一度頑張ろうと思ったというのが大きな理由ですね。ひとつの「テーマ」というか「将来の夢」のようなものがあって、それが「自給自足」なんです。
例えば「お金」に関しては、自分が生きる上で必要なお金は、いずれは個人開発など自分のサービスでつくれるようになりたいと思っています。他にも、これはイメージしやすいかもしれませんが「食」という観点では、自分が食べるものをなるべく自分で育てたくて。いまは稲作農家の方からひと区画お借りして野菜の栽培をはじめています。ゆくゆくは、鶏を飼って卵をとってみるなんてこともしてみたいです。
そういった目標に向かって生きていくために、会社員として働く時間をなるべく少なくしていきたいという思いはずっとありました。それを応援してくれる環境がヘンリーにはあるのでありがたいなと思います。
— では、ヘンリーの仕事以外の時間は畑に出たりしているんですね。
そうですね。それ以外には個人開発だったり、家庭菜園だったり、老舗の洋食屋でアルバイトしながら料理の修行もしています。もともと自給自足に関心を持ったのも料理が入り口で、子どものころは料理人になるのが夢でした。でも、テレビのドキュメンタリーで料理人が厨房で殴られてるシーンを見て「この仕事は俺には無理だ」と思ってあっさり諦めたんです(笑)。それでも自分につくれるものは自分でつくりたい内なる欲求というか……そういうものはずっとあって、このテーマにつながっているんだと思います。食材を自分でつくったら、次は料理する必要があるので、一度は諦めた料理の勉強をこの年になってまたはじめています。
— 河村さんにとって「料理のたのしさ」と「プログラミングのたのしさ」は重なる部分があったりするんでしょうか?
言われてみればあるかもしれないですね。僕、いまでも忘れていないことがあって。学生時代に自分で初めてまともにつくったプログラムが「テトリス」だったんですね。それを「つくったからやってみてよ」とデニーズで友達に遊んでもらったら、「どうやってつくったの?!」「おもしろいね!」って喜んでくれて、そのときの友達の顔はいまも覚えています。あるいは、その顔があったからエンジニアを続けられている部分もあるかもしれない。
自分で考えてつくったものをユーザーに触れてもらって、それで喜んでもらえることはエンジニアの仕事ならではの魅力だと思います。そういう意味で料理とプログラミングに惹かれる理由にはどこか共通点があるのかもしれないです。
フロントエンドの細部にもこだわるカルチャー

— フロントエンドエンジニアの河村さんから見たヘンリーの魅力について教えてください。
先ほどの「現場からフィードバックを頂ける」点も魅力ですが、他にも「細部へのこだわり」についてヘンリーはすごいなと思います。細やかなデザインまでユーザー目線で考えられてるんですよね。例えば、線の太さも0.5ピクセル単位で意図を持って使い分けられていたり。
スタートアップでは、フロントエンドのそういうデザイン面って、重要じゃないと切り捨てられるケースも多いんです。僕自身もヘンリーに関わる以前は正直あまり意識できていなかったと思います。でもヘンリーでは、ユーザーの使いやすさに厳しくこだわって、「なあなあに実装しない」カルチャーがあります。フロントエンドにこだわるメンバーがいて、みんながそれを大事だと分かっているチームがあることは、フロントエンドを任される身としてはやりがいですし、妥協しないことで僕自身の学びにもつながっています。
— そういったカルチャーはどこから生まれてると思いますか?
やっぱり「人」ではないでしょうか。特に初期のメンバーが未来のことを考えて、デザイン面にも厳しい視点を持って開発をはじめたこと。そして、メンバーがその思想に賛同して、引き継いで頑張ってきたこと、それにより生まれたカルチャーというか。僕が副業で関わらせてもらった当初から明確なデザインシステムが整備されていて、それを珍しいなと思った記憶があります。おかげで「Henry」は統一的で見やすいシステムになっているのではないでしょうか。
— フロントエンジニアとしての成長可能性はどんなところにあると思いますか?
ヘンリーのプロダクトは複雑なUIがたくさんあるからこそ、フロントエンドエンジニアとして学べる技術的課題も豊富なのが特徴かなと思います。インタラクションやショートカットの追加も多く、難易度の高い画面がいっぱいあります。
例えば、スプレッドシートのような画面やカルテのエディター画面。他にもドラッグ&ドロップなど、ユーザーが直感的に動かせる仕様にしていく必要もあります。医療現場の方の生産性に直結する部分ばかりなので、ただ実装するだけでなく、フロントエンドの視点でユーザーのパフォーマンスが上がるように、いろんな技術を駆使してつくり上げていきます。そういった部分は成長可能性であり、おもしろさでもあると思っていますね。
— ありがとうございます。では、最後に河村さんの今後の目標についてお聞かせください。
会社のマイルストーンとして、まずは病院版「Henry」の開発が一つ大きくあるので、それに向けてフロントエンドエンジニアとしてできることは全てやって、導入を目指すのが直近の目標でしょうか。
その後は、周辺分野の新規プロダクト開発を進めていく計画なので、僕も積極的に関わっていきたいですね。ヘンリーでは、フロントエンドだからずっとフロントエンドをやらないといけないというわけでもないので、新たな分野も勉強しながらチャレンジしていきたいです。
そして個人目標は「自給自足」というテーマがあるので、今できることを焦らずに一歩ずつ進んでいけたらいいなと思っています。家づくりにも興味がありますね。現代の便利なものに頼りすぎず、自分にできるものはできるだけ自分でつくる。そういう人生を送りたいというのが僕の大きなゴールです。
インタビュー:中田 達大
ヘンリーでは、さらなる成長に向けて採用も積極的に行っています。ご興味をお持ちいただけた方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
