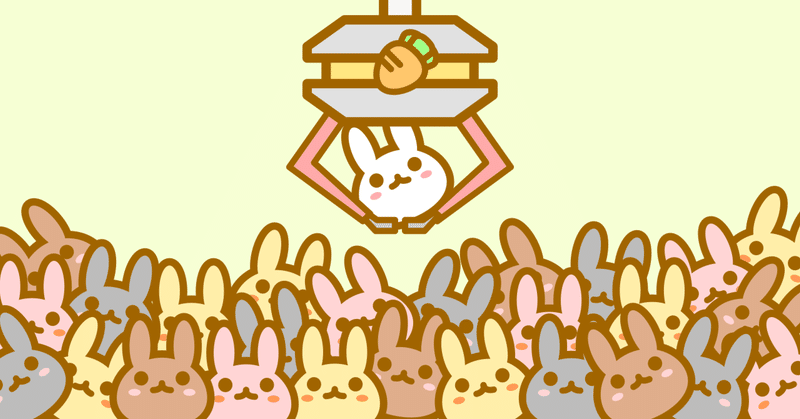
ゲーセンの営業ノウハウを記していく⑦
集客からみたプライズ原価率戦略
はじめに+α
注意点(テンプレ)
1・(もちろんですが)元所属会社の営業秘密は記しません。
2・勤務していたのはコロナ前なので、現在には当て嵌まらないことも多いと思われます。
3・とはいえ、普遍的?な基礎の考え方や現状も鑑みて記事は書きます。
4・なるべく早いペースで書いていくため、文章が変だったりわかりにくい場合があるかもです。
質問等はコメントにお願いします。なので、後日記事の修正が入り得るのでご了承下さい!
5・有料記事も含みます(読んでくれる人がいるのか・・・) 今回は無料ですー
以上ご留意のうえお読みください。
というのをコピペで毎回貼っていますが、今回は特に注意してください。
1・に書いてますが、今回の話は具体的な数字が出ますけれども、これは営業秘密ではございません。私の免責というよりも、読まれる方が勘違いされても困るので特に記しておきます。
今回の話は私が初めて店長をやったときにどのように集客するかを考えて出そうとした数字・考え方であり、元所属会社の中で特に会社的なコンセンサスとして採用されていた考え方ではございません。
根拠としては、特に一定以上の大きなお店ではあまり気にしない考え方になりますので、当時の会社からすると既にメインストリームになり得なかった、ということです。
また、このやり方をして結果が出た話自体も20年前の話なのでそこも頭に入れてください。
とはいえ、数字的に突っ込んでるのでお勉強がてらにお読みください。
プライズの原価率ってなーんだ?
プライズというのはいわゆる「UFOキャッチャー」(セガの商標です)などの「プライズ機」で「景品」(これの法的立ち位置もややこしいけど割愛します)を獲得できるゲーム機です。
原価率というのは、そのゲーム機に入る売上に対して、お客様が獲得した景品の金額が果たして何パーセントか?という数字です。PO率や配当率と呼ぶ会社もありますね。
食事で例えたら、牛丼の売価が500円で原価が250円だった場合、原価率は50%となりますね。
実務では〇〇円で景品が必ず1個出る、というような性質ではないので、ある一定期間の売上に対して、どれだけ出たか、というような見方をします。
プライズの原価率はどう決まっているか?
色々と先輩に聞いたり、外部の方に聞いてみたりしてみたのですが、この原価率をどう決めているのか!?というのは実はハッキリとしないんですよね。(してたらすいません。私の観測範囲内の話です)
ハッキリしているのは、「これぐらい利益を残さないと立ちいかないから。〇〇%」というお店・会社側理由で決まっている場合。大半はこれでした。
もちろんこれも正しい考え方ではあるのですが、例えば先にあげた外食産業では「原価率は概ね30%」と言われていますが、ではメニューの端々までどれも原価率30%なのかというと、そんなことは無くて、それぞれお店の戦略や味と価格のバランスなどなどの理由で原価率は変わってくるはずです。
自分語り
私がこの業界に入ったのは、当時増えつつあった「大型店」と言われる大きなゲームセンターのオープン時だったのですが、その後も新規にオープンした大きなお店に転勤になりました。大きなお店というのは売上も高くて、次々と景品が無くなっていくので、どんどん到着する景品を景品が無くなったところに当て込んで、設定を出して・・・の繰り返しで、原価率も会社で決められていた数値に合わせて設定することが当たり前でした。
2年ほど大きなお店に勤めた後に、店長になるということで、小さなお店での勤務に変わったのですが、売上が数分の1から十数分の1という売上のお店になったので、入った景品はしばらく無くならないし、待っててもお客様は来ないが、売上の入らない景品を入れ替えたらどんどん在庫は貯まっていくし???ということで、発想を変えないといけない・・・となったわけです。
お客様をどうやって集めるか
ということで発想を変えたわけですが、大事なのは「お客様をどうやって集めるか」なわけです。
端的に言えば「客数を増やす」という話なのですが、客数を増やすというのは、今風に言うと・・・
・ユニークユーザー数を増やす
・ログイン回数を増やす
の2通りがあるわけです。
厳密にいえば、ユニークユーザー数を増やすことが客数を増やすということになるのですが、売上に注目すれば、お客様がお金を使う回数が大事な訳なので、この2通りを考える必要があります。
で、この2つを実現する手段としては、
・ユニークユーザー数を増やす → 新規に入ってくる人を増やす
→ 店頭や店外でのプロモーション
・ログイン回数を増やす → 既存客のリピート率をアップする
→ 飽きさせないお店づくり
小さいお店だとプロモーションなどの費用は出ないので、消去法で「飽きさせないお店づくり」にならざるを得ない、という結論になりました。
「原価率をいくらにするか」は問題ではない
で、プライズの話に戻るのですが、今1カ月に1回来ているお客様が、1カ月後にお店に来た時に、中に入っている景品その他が全く1カ月前と同じだったらどう思うでしょうか?
「んー変わんないな」
で、1回目は終わるかもしれません、でも次の月も同じだったら?
変化がないお店というのはそれだけで面白くないし、変化がないということは「来なくてもいい」に直結するのです。
なので、リピート率をアップしようとすればそのお店に来るお客様が「どれぐらいの頻度で来るのか」、それに合わせて「どう景品内容を変化させるか」が重要ってことになります。
景品はカートン単価・入り数がほぼ一定なわけですから(まーそれでも色々ですけど)、それを予想される売上で、想定されるリピート期間の間に消化しようと思えばどれぐらいの原価率で出さないといけないか、が計算で算出されるんですね。
なので、「集客から見た原価率」というのは原価率がいくらだからお客様が来る・来ないではなくて、「見た目の新鮮さ・変化」を重視した結果の原価率、ということなのです。
現実的にどうなの・・・?
で、ぶっちゃけこの計算方法の問題点は何かというと、お店の規模が小さくなればなるほど、原価率がバカ高くなってしまうということですね・・・
また、売上も「予測」でしかないので(当時は過去の何週分かの売上から推測してたような)、予測がぶれると着地数字も随分と変わってしまうという欠点もあります。
しかして、売上そのものはどうなったか!?というと、昨年数字と比べて「〇割」というような数字で上がっていきました。もちろん、この原価率計算だけで上がったわけではないとは思いますし、もう20年前の話なので今の参考になるかは微妙ですが、一つ成果が出たのは確かです。
なので、実務では着地点を決めておいて、これぐらい売上が上がったら原価率をどれぐらいまでに抑える(この数字は経営的に)、としていた方が良いと思います。
まとめ
まとめっぽいのは上で書いているのですが、そのまま写すと、
「集客から見た原価率」というのは原価率がいくらだからお客様が来る・来ないではなくて、「見た目の新鮮さ・変化」を重視した結果の原価率
ゲーセンに限らず、お店というのはいつも新鮮さ・変化がないと飽きられてしまうのですが、店員をやっているとそういった部分に鈍感になってしまいがちです。
お客様に対して、意図して新鮮さや変化を与えていくということをしないと、集客にマイナスになってしまいます。
ちなみにこの考え方自体は、ちょっと見方を変えると、「限られた景品をどのぐらいの期間、景品機の中に入れておくか」という計算にも使えるので、覚えておいても良いかもしれません。
次回予告
とりあえず、正月は記事休みます!というのだけお伝えしておきます・・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
