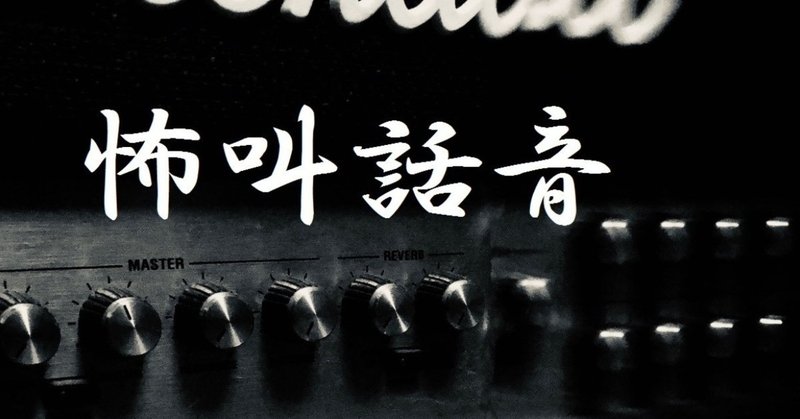
機材車 その2
Mさんが破格の値段で手に入れたロング・バンは、バンドの機材車としてライブの遠征に練習スタジオへのメンバー送迎にと活躍をした。
誰も乗っていない運転席に時折人影が見えるのは相変わらずで、少し気味悪くもあったが、実害があるわけでもない。自分やメンバーが乗り込むときにはその姿も消えているのだからと、Mさんは努めて気のせいだと思うことにしていたという。
ある日の深夜。
Mさんはバンドのスタジオ練習を終え、メンバーを順番に家まで送り届けた。
最後のメンバーを降ろし自宅に向かう途中、赤信号に引っ掛かり停車した。
日常的に通っている民家に囲まれたごく普通の小さな交差点である。
Mさんは信号をぼんやりと見上げ、赤が青に変わるのを待っていた。
バンッ。
突然、ボディの左後ろから大きな音がしたかと思うと、鈍い振動が車内にひろがった。
同時に、
「ひゃっ」
と、女性の小さな悲鳴が聞こえた。
―――酔っ払いか何かがふざけて車のボディを叩いたのか?
―――あるいはそいつが通りすがりの女性に何かしたのか。
Mさんは咄嗟にそう思った。
慌てて左のサイド・ミラーを見る。
誰もいない。
何かに引っかかったのかTシャツの袖口が妙に引っ張れていたが、それでもMさんは急いで後ろを振り返り、さらには運転席の窓を開けて外を見やった。
やはり誰もいない。
後続車も対向車もなく、しんとした交差点に止まっているのは、自分の車だけである。
しかし、あの音はどう考えても、何かが風で飛んできて当たったという音でもないし、温度変化などで車体自体が自然に鳴る音でもない。
大人の力で思い切りボディを叩いた、そんな音だった。
そんなことを考えているうちにMさんは、あの女性の悲鳴が外からではなく、もっと近くで聞こえたことを思い出した。
はっと気づいて、Tシャツの左の袖口を見る。
湿った手でぎゅっと握りしめたような皺がついていたという―――。
深夜の交差点。
信号は三回目の青に変わろうとしていた。
その3へ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
