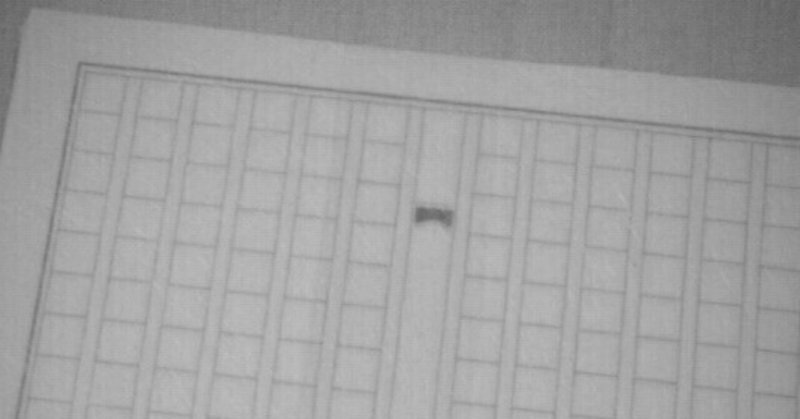
掌編小説 猫 (2)
まさか苛めているとは思わなかったが、気になって近づいた。
お姉さんは私に一瞥をくれ少し微笑んだように見えたが、すぐに視線を下に向けた。
お姉さんはしゃがんでスカートの両端を摘み、ハンモックのようにして二匹の仔猫を包んでいた。
お姉さんの視線は仔猫に向けられていたが、仔猫の可愛さに心を奪われているという風でもなく、なにも見ていないような、目の前の仔猫ではないなにかについて深く考えているように見えた。
もう一匹はどうしたのかと辺りを見回したが、近くにいるようすもない。もしかしたら死んだのかも知れなかった。
親猫は気をつけのような正しい坐り方でお姉さんを見上げていた。
私は仔猫が心配なのだろうと思った。
もしかしたらこのお姉さんに仔猫を拾ってもらいたい、それが仔猫の幸せだと思っていて、けれどもお姉さんが仔猫を可愛がって育ててくれるとは限らず、お姉さんに拾われたために可哀想な目に逢うかもしれないと思いめぐらせているのではないかと思った。
親猫は泣きながら笑っているような顔をしていた。
親猫は自分もああしてお姉さんのスカートに抱いてもらいたいのではないかとも思った。
すると私は同時に、自分をスカートに抱かれる猫に重ねていることにふと気づいて恥ずかしくなった。微かな困惑は行き場を失い、すぐにわかりやすい意地悪な気持ちに変った。
「虫付くで」
私はいった。
「ばい菌持っとるかもしれんで」
とも。
中学生のお姉さんは、そんなことないわ、というだろう。こんなに可愛いんやもん、と。
するとお姉さんは私の予想を裏切り、
「かまへんのよ」
といった。
「ほなら、大きい方も抱いてあげてや」
私はいった。
汚いし気持ち悪いっていうだろう。嫌だというだろう。そらみろ。
私は親猫に近づいた。抱き上げてお姉さんに渡そうと思った。
親猫は私の勢いに驚いたのか、私に捕まる前に草むらに逃げ込んだ。
お姉さんは私に怒るでもなく、
「あんたらもお母さんの所に帰り」
と仔猫を地面におろした。
仔猫たちは親猫を追いかけるように草むらに消えた。
私はその後いちどもお姉さんを見かけることはなかった。いま思えば、地元の中学校の制服だったかどうかも記憶は曖昧である。
猫の親子もいつの間にか空き地の草むらから居なくなった―――。
私はいまでもこうして、あの猫の親子を思い出すことがある。
人生には自分の意志や努力ではどうすることもできないこともある。その冷厳な現実のかけらを、どの大人よりも早く私に見せて教えてくれたのが道端の猫たちだったのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
