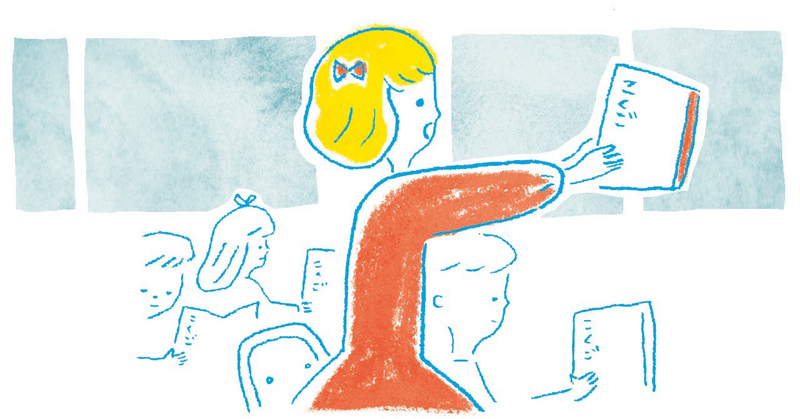
音読の効能、読み聞かせのもつ力
前号に続き、国語の実践について。
何だかんだ、どの年でも国語の実践には力を入れている。
国語の力こそが全ての学びのベースとなるからである。
「クラス会議」のような話し合いも、言葉を伝え合う力があってこそ生きるといえる。
「聞く力」はまさに国語科を中心に育む力である。
前号でも紹介した神戸の多賀一郎先生からの学びで、一つ大きな気付きがあった。
それは「音読」の重要性の再認識である。
音読は、再び脚光を浴びてきている。
その様々な効能については各方面で言われているのでここでは書かない。
今回学んだのは、特に低学年における音読の重要性である。
通常、大人は音読するよりも、黙読する方が圧倒的に読み進める速度が速い。
何倍もの速さである。
しかし、こと理解に関してはどうか。
定期的に読書会等に参加していると実感するが、音読すると確かに理解が深まる。
(ちなみに毎回の使用テキストは、『修身教授録』森信三著 である。)
音読すると、速くはないが、理解は深まる。
実質、どちらの方が「効率的」な学習ができているのかということである。
つまり、音読するということは、理解そのものを促す効果がある。
この時、速さや読み方などに気を取られすぎると、しっかりとした理解に繋がらないので注意である。
低学年、特に一年生において、指摘されるまで気付かず盲点となっていたことがある。
それは、
「音読している方が、黙読している時よりも読む速度が速い子どもがいる」
ということである。
つまり、言葉を覚えたての子どもたちにとって「黙読そのものが難しい」ということである。
また、「斉読(一斉音読)」についても同じようなプラスの効果が期待できるという。
「一斉に声を揃えて読む」ということの効能。
これは、読むのが苦手な子どもにとって、大きな手助けとなる。
理解や読み方があやふやであっても、斉読の中であれば、何とかついていける。
読むことが苦手な子どもにとっての、補助輪のようなものである。
低学年に限らず、これらは上学年であっても、言葉が苦手な子どもたち全員に当てはまる可能性がある。
つまり、音読は「負担」ではなく、むしろ「補助」としての機能面が強くあるといえる。
そう考えると、低学年においてよく「音読」の宿題が出ることにも合点がいく。
「音読カード」を用いるかどうかの話ではなく、音読そのものに価値があるということである。
それと同時に、宿題として出す側は「一人で音読」の実施が厳しい子どもへの配慮も必要となる。
ある程度上手く読めるのであれば、一人で読んでもいいのだが、理想は聞いてもらった方がよい。
特に、読み方があやふやな低学年の時期はそうである。
しかしながら、昨今の共働きの多い家庭環境の状況から言って、そこを求めるのは酷かもしれない。
そうなると、頼みの綱は、やはり教室での音読ということになる。
つまりは「学力形成は、授業中で勝負」という至極当たり前の結論に至る。
教室の中で、いかに音読の機会を設けるか。
また、いかに豊かな言葉に浸らせることができるか。
この辺りが勝負の分かれ目である。
音読の機会は、国語に限らないことである。
算数だろうが社会科だろうが理科だろうが、事あるごとに音読を促す。
また、手紙を配っても音読する。
これだけで、教室に一日いれば、相当読むことになる。
また、豊かな言葉に浸らせるには、絵本や物語の読み聞かせに敵うものはない。
読み聞かせを教室の当たり前にしていけば、確実に言語の力が変わってくる。
さらに、直接心を教育しようとするのは難しいが、子どもの言葉が変われば、行動も変わってくる。
学習指導要領で定められた道徳教育の位置づけである「学校の教育活動全体を通じて行う」にも繋がる。
昨年度実践したのは、毎朝の子ども同士の読み聞かせである。
その日の担当の子どもが、全員の前で読み聞かせを行う。
朝の時間では足りないので、国語の時間を使って実施した。
トータルするとかなりの時間を食ったが、それだけの価値は十分にあった。
読む子どもは入念に準備をし、他の子どもたちは心待ちにして聞く。
「聴く」の文字にある通り、目も耳も、心をも傾けて全力できくのである。
でも本当は誰よりも自分が読みたいので、時々時間をとって、教師による読み聞かせも行わせてもらった。
子どもはこれも楽しみにしている。
つまりは、学校生活全般を通して、言葉を好きになることに繋がる。
拙い実践かもしれないが、こんな些細なことで確実に効果は出る。
言葉の力をつけるためにも道徳教育のためにも、音読と読み聞かせの実践は強くおすすめしたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
