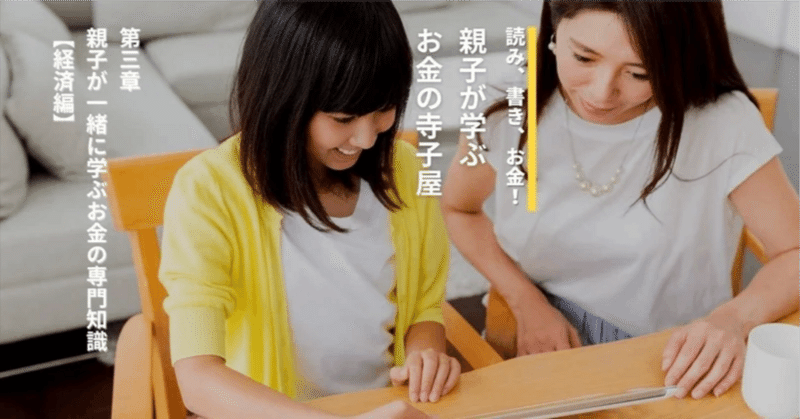
6.世のため人のために働こう 経済とは?
「経済」という言葉の意味
「経済」と言う言葉の意味を改めて聞かれたら、皆さんは何と答えますか?
英語では「economy」と訳されますが、economyと言う言葉から受けるイメージは、「お得」とか「安上がり」のように何となく軽く感じるのはボクだけでしょうか。
しかし、実は「経済」は思っているほど軽々しいものではありません。
「経済」とは「経世済民(けいせいさいみん)」が略された言葉です。
この「経世済民」の意味は、「世を経めて(治めて)民の苦しみを済う(救う)」と言う意味です。
起源は相当に古く、6世紀〜10世紀頃の中国の古典に記載があるそうです。
今では「経済」というと、お金のイメージばかりが先行しますが、当時は、お金の流れを意味していたものではないことが分かります。
本来「経済活動」とは、「世を治めて民を救う」活動のことだと言うことが分かります。
振り返ってみると、今の世界、そして日本の経済は、果たして世を治めて民を救っているのでしょうか。
確かに民を救うためには、お金が必要であることは間違いないでしょう。
しかし、今の世の中を見渡してみると、人を救うためというよりも、自分のお金儲けのことばかりに目が向いているのでしょうか。
と、本道から外れてしまいそうなので、この辺で、話を戻します。
現代の経済活動
現代の経済とは、ものすごく簡単に言うならば、モノとお金の動きです。
日常生活の中で商品やサービスの受け渡しの際、それに伴いお金も一緒に動きます。
人々の生活を豊かで便利なものにするために、人々が限られた資源を有効に活用し、生産、分配、交換、消費などの活動を通じて、生計を営む社会的なシステムやプロセス、それが経済です。
その経済活動を円滑に動かすための潤滑油、それがお金です。
お金は、働いて手に入れるものです。私たちは仕事をしてお金を稼ぎ、それを使って生活しています。そのお金を稼ぐための仕事には、さまざまな産業やサービスがあります。例えば、製造業では商品を作り、サービス業では人々のニーズに応えるために働いています。
ところで経済には、需要と供給という大切な考えがあります。需要は、人々の「必要だ」「欲しい」と言う欲求であり、供給はその欲求を満たすための商品やサービスを提供することです。
この需要と供給のバランスが上手に取れると、経済は円滑に、安定して動いていきます。
様々な製造業やサービス業などに携わる企業が、需要に応じて様々な商品やサービスを生み出し(供給し)、市場で取引されます。
その市場で人々がこれらの商品やサービスを購入すると、お金が供給した企業に流れ込みます。
企業はその収入をもとに従業員に給与を支払ったり、新しい資源や商品を仕入れたり、新しい商品やサービスを開発するための資金にしたりします。
また政府もこの経済活動の仕組みの中で動き、世の中の経済活動を支えています。
例えば税金を徴収して、加熱しすぎた経済活動を鎮静化したり、減税を行い経済活動を活発化させます。
通じて社会に貢献したり、経済政策を立てて景気をコントロールしたりします。
そして教育、医療、公共インフラなど公共投資を行い、私たち国民のために社会全体の発展に貢献します。
このように経済は複雑な仕組みから成り立っており、これらの要素が調和していることで、持続可能な発展が可能になるのです。
経済活動の重要人物、高橋是清とは
ところで、近代の経済を語る上で欠かせない、ある一人の人物を紹介します。
その人の名は高橋是清(たかはしこれきよ)と言います。
高橋是清は財政家であり、1911年に日本銀行総裁、1918年に大蔵大臣を経て1921年に第20代内閣総理大臣に就任しました。
1931 年 12 月から 36 年 2 月に 実施された高橋是清蔵相による独創的な財政政策は、「高橋財政」と呼ばれています。
就任と同時に金本 位制度からの離脱を決定し、発券制度改革を行うことで、わが国の通貨制度を事実上の管理通貨制度へと移行させた功績がありますが、1936年、俗に言う、あの2.26事件で凶弾に倒れました。
氏はダルマ宰相と言う愛称で親しまれていました。
また、高橋是清は日銀副総裁就任時、1904年に始まった日露戦争の戦費調達のための外債募集を成功させました。
そして翌年の日露戦争後は、日銀総裁として、また蔵相として、「積極財政」で日本経済の礎を築き、諸外国に先んじて世界恐慌(昭和恐慌)後の景気回復にも大きな力を発揮しました。
その功績から「日本のケインズ※」とも呼ばれています。
が、その一方でインフレ抑制のために緊縮策を唱え国防費を削ろうとしたことから、軍部には目の敵にされました。
それが2.26事件暗殺につながってしまったのです。
ボクはこの高橋是清こそが、経済活動最大の功労者の一人ではないかと思っています。
何故ならば、日本を大恐慌から救うべく、積極財政を行い、世界が不況で喘ぐ中、日本が先乗りで経済回復を果たしたからです。
新型コロナの影響で経済回復が世界に遅れ、いまだ抜け切れていない、現在の日本の状況とはまるで真逆です。
※ケインズとは、20世紀初頭のイギリスの経済学者で、本名をジョン・メイナード・ケインズと言います。
ケインズは現代のマクロ経済学の基礎を築きました。
ケインズは、景気を循環させるための手段として、財政政策(政府の支出や課税などによる経済調整)と金融政策(中央銀行の操作による金融供給の調整)の有効性を強調しました。
これは、特に大恐慌後の経済復興期において、多くの国で採用されました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
