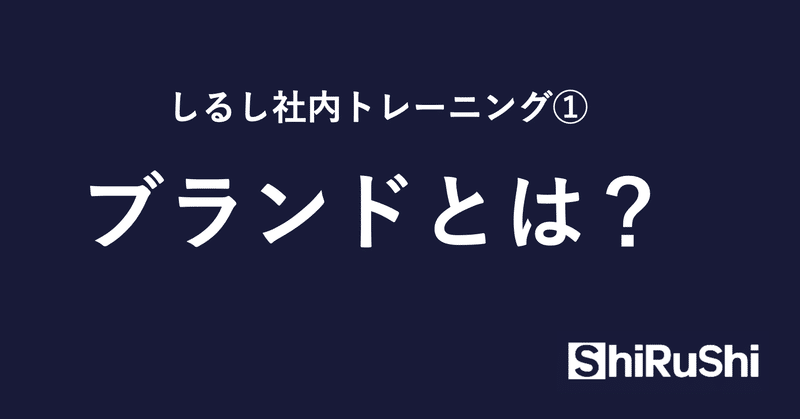
しるし社内トレーニング① 『ブランドとは?』
こんにちは、しるし株式会社 代表取締役の長井です。
しるしでは、月1回の頻度で、現役のブランドマーケターを招き、「ブランドマーケティング講座」を開催しています。ブランドに寄り添い、成長を共にすることを目的とした投資です。
実際のトレーニングではケーススタディを挟みながら進めていますが、noteでは概要をシェアしていきます。
タイトルにもある通り、今回は「ブランド」という単語について深掘っていきたいと思います。普段何気なく目にする「ブランド」とは何か。そしてそのブランドの商品を適切に消費者に届けるための「ブランドマーケティング」とは何なのか。
トレーナー(顧問)
日系化粧品会社マーケティング部バイスプレジデント
外資系消費財メーカー入社後、日本とシンガポールにてアジア全域のブランディングに携わるなどの幅広いマーケットでのブランドマーケティングに従事。
手掛けた新製品が日経トレンディ・日経MJ優秀製品サービス賞を受賞するなど、新製品開発・新規の価値開発で多くの結果を残す。
その後、日系化粧品メーカーへ転職、バイスプレジデントとしてメンズブランドを伸長し、メンズ美容市場を牽引している。
1. 「ブランド」とは?
「ブランド」という言葉を聞いて、どのようなイメージを思い浮かべますか?
バッグや化粧品、松坂牛のようなブランド食材など、世の中には様々な分野に「ブランド」が存在します。また、ブランド=高級、というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
「ブランド」という言葉が持つ本当の意味は何なのでしょうか?
「ブランド」という言葉にはどのような力が秘められていて、その力を最大化するにはどうしたら良いのでしょうか?
2. 「ブランド」とは、生活者の頭の中に蓄積する記憶を使って出来上がった「意味」の集合体

前回の記事「しるしのミッション『ブランド体験を最適化する』とは何か?」でも取り上げましたが、上記の2つの紙コップに入ったコーヒーの写真を見比べて、みなさんはこれにどう値段をつけますか?
何も書いてないノーブランドのコーヒーと、スターバックスのロゴが入ったコーヒー。
ノーブランドのコーヒーは恐らく、100円~150円くらいを想像するのではないでしょうか?
そこにスターバックスのロゴを載せるだけで、おそらくそのコーヒーに倍以上の値段をつけるでしょう。
さて、ここでみなさんはスターバックスのロゴから、どのようなイメージを連想しますか?
・おしゃれでスタイリッシュ
・美味しい(味や品質が保証されている)
・高級感がある
・スタッフさんのサービスが親しみやすい
・お店の空間が仕事に快適
このような感じでしょうか。
これらは、皆さんがこれまでの人生でスターバックスに触れてきた中で生まれた記憶から作られた、スターバックスの意味です。
そしてこの意味こそが「ブランド」になるわけです。
何も書いてないコーヒーはただの「製品」ですが、スターバックスのコーヒーは製品にブランドがプラスされて「商品」になるのです。
つまり、ブランドとは、『蓄積された記憶を使って出来上がった意味の集合体』であり、その意味が「製品」を「商品」に昇華させるのです。
3. ベネフィット=自分に起こるよい変化
ビジネスでよく耳にする言葉で、「ベネフィット」があります。
直訳すると、利益や便益という意味になります。
メリットと混同されがちな言葉ですが、両者には明確な違いがあります。
・メリット=商品そのものの良いところや、他と比べて長けているところ
・ベネフィット=その商品を通して、自分に起こる良い変化
「メリット」と「ベネフィット」に関して、有名なドリルの例があります。
ドリルのメリットが、高速回転やバッテリーの持ちが長いことに対し、ベネフィットは、ドリルを使うことで、簡単、かつ正確に穴が開けられるという体験なのです。
消費者が欲しいのは、高性能なドリルそのものではありません。簡単に正確な穴が開けられる、という体験が欲しいのです。つまり、消費者が求めているものは製品そのものではなく、ベネフィットなのです。

ブランドとは、『蓄積された記憶を使って出来上がった意味の集合体』であると先に述べました。そして、その意味は、消費者にとって良い変化を起こす体験、すなわちベネフィットでなくてはなりません。
ブランドの意味は、消費者の記憶や認識次第で変化していきます。
その記憶や認識を様々な施策を通じて新たに構築していくことが、ブランドマーケティングになるわけです。
4. ブランドマーケティングとは何なのか
ブランドマーケティングでは、消費者である消費者を中心に施策を考えていきます。その上で、以下の2点が重要になります。
・ブランドによる意味作り
・消費者の理解

まず自社製品に目を向けるまえに、消費者のニーズを正しく理解する必要があります。同時に競合にも目を向け、市場を理解します。その上で消費者のニーズを満たし、期待を上回るような意味作りやブランドの価値を構築し、提供していくことが大切です。
プロモーションのためのバナー広告やテレビCM、ランディングページなどで伝えるべきことは、製品そのものの機能ではありません。消費者がその商品を通して体験できるベネフィットを伝えていくことが重要となるのです。
5. ブランドの育成方法

まず考えなければならないことは誰に(WHO)の部分です。
つまり消費者は誰なのか?の部分を考えます。消費者の顕在ニーズや潜在ニーズに仮説を立て、そのニーズを満たすベネフィット(何を/WHAT)は何なのかを考えること。
そして最後にどうやって(HOW)の部分を考えます。
どうやって価値提供していくのか、についてはターゲットとなる消費者や、それに伴う競合(WHERE)に合わせて、柔軟に変化していくことが大切です。
6. ブランドの意味や価値をどのように伝えていくか
HOWの部分を考えていくには、消費者と競合に対して深く考え、理解することが大切です。特に競合については、本当の競合は誰なのか、を正しく理解する必要があります。
数年前に一大ブームを巻き起こしたタピオカ。ブームが去った今も、ポストタピオカとなる製品は登場していません。その背景には、タピオカの主顧客である10代の女性が、タピオカのどこにベネフィットを感じていたのか、をブランド側が正しく理解できていなかったということがあります。
タピオカのベネフィットは、「インスタ映えするドリンクをインスタ映えするスポットまで長時間保存したまま移動できた」という点にあります。単に、持ち運びが簡単だったり、美味しいドリンクを開発するだけではそのベネフィットは満たせず、色が変わってしまうバナナジュースや、アイスが溶けてしまうフロートはポストタピオカになれなかったのです。
7. 1つの商品の魅力は山ほどある

1つの商品につき、消費者に伝えるべき魅力は当然1点だけではありません。
山ほどある魅力の中から、今の消費者のニーズや競合を考えて、ベストなものをベネフィットとして設計し、伝えていく必要があります。
昨今のコロナ渦が象徴的なように、世の中が変われば1つの商品から伝えるべき側面も変わります。
そして、そうやって設定したベネフィットを一目見ただけで伝えることができる重要な役割として、パッケージやデザインがあるというわけです。
消費者のブランドの認知はロゴなのか?それともパッケージデザインなのか?もしくは全体的な色合いなのか?
様々な側面から総合的に考えて、ブランドイメージを構築していくのです。
まとめ
ブランドとは何か、ブランドマーケティングとは何かについてここまで述べてきました。
ブランドとは、消費者の頭の中に蓄積されていく意味であり、その意味は消費者にとって良い変化をもたらすベネフィットであること。
意味やベネフィットは、作り手のアプローチによって創られます。
ポジティブなイメージで信頼や保証を提供すること。また、時代や消費者のニーズ、競合に合わせて絶えず変化し、進化させていくことで愉しさやわくわくを創造していくことが大切です。
ブランドを守り、消費者と共に成長していくためには、消費者の中に蓄積されている意味をまずは理解すること。消費者のニーズを知り、仮説を立て、ベネフィットを設計し、的確に伝えていくことが必要なのです。
-----
弊社の社員は、過去のトレーニング動画を全て観ることができます。
ブランドにまつわるビジネスに興味がある方、是非ご連絡ください!!
各ポジションでメンバー募集しておりますので、ご興味ある方は、ぜひお話ししましょう!
DMか、応募していただけたら嬉しいです。
しるし株式会社
代表取締役 長井秀興
p.s. 長井個人、しるし社に興味を持ってくださった方は、ぜひ連絡ください!
Twitter: https://twitter.com/adcbefghide
FB: https://www.facebook.com/hideoki.nagai1
▼さらにしるしを知りたい方はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
