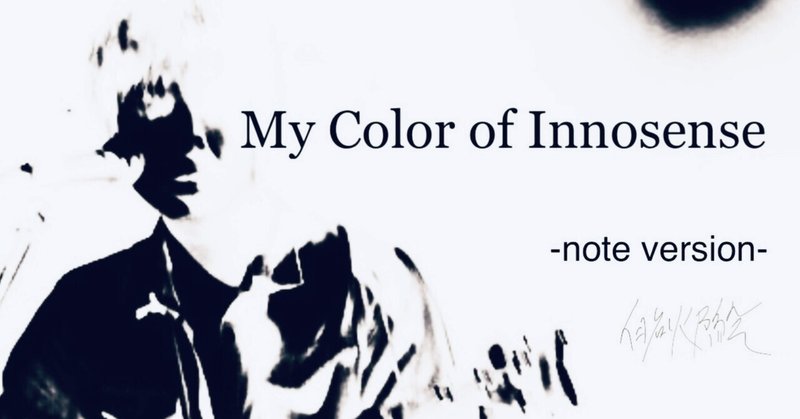
My Color of Innosense -note version-
はじめに
ぜんぜん太宰治とはちがうふうだけども、しばしばぼくは人間失格の行いをしてしまう。それは暴力、といっても、小学校の「道徳」でよくいう、あの、言葉の暴力というやつだ。
もちろんそれ以外でも、友達や両親や兄妹に、返すアテのない借金をしたり、文章を綴るときだって平気で文法違反や自分語をやったりする。夢みた夢は、なんだかんだでけっこうが叶ってしまうーー(これは道理に反する)。けれど、こういったことは恥かしい話、責任ありきの自由だったりする。半ばかくしんはんてきに、やりたくてやっていることだ。
もんだいなのは、自らの手に余る…わりあい身近な人ならすぐわかるだろう例の…この口から零れ出てくる、あの、毒(もちろん責任はもつが)ーーああ! こうやって書いてみると、中にいるやつが叫ぶ「言いたいこと言うのが、ヒップホップだろ」それを、もうちょいユーモア(これが足りない!)を込めて、なんなら愛をこめて、言えないものか…。
書くのもおぞましい!くらいな、酷いこと、いろんな人に言ってきた。多分、これからも言ってしまう。例えばそれは末期がんを患っている父方の祖母にたいしてだったりする。ほんに、ほんに、おしまいの人間、いや、人間失格、人間のクズ、いや、クズの中のクズーーそれ以下の、ちがう、この地上でもっとも穢れた存在なのだ(ちなみにぼくは自分で卑下するタイプじゃない、そうでなく、これはたんに真実をいってるにすぎない)。
できることなら、ぼくはぼくの中の正義を抹殺してやりたいとおもっている。
「なんでおれはいつもこうなのだろう」ぼくの悩みといえばいつでもこうだ。こんなふうにかんがえなくてはならない人間は不幸だとおもう。なんでふつうにみんなと同じように出来ないんだろう、思えないんだろう、しかも、自分ではまともにやっているつもりなのだーーそれならそれで悩まなければいいのに、ことばで人を傷つけて、平気でいられない。なれるものなら、人畜無害になりたい。透明無色になれたらどんなにいいことか。自殺は主張になってしまうからいやなんだ(それは声が大きい、昼間の選挙カーみたいに)。
ぼくは正義の中のぼくを外に逃してやりたいとおもう。
さっきいった酷いことだけど、それをここで告白しようとはおもわない。そんなことで許されたような気になる自分を見るのがいやなんだ。ほんとうに許されないことだから。
けれど、思い出したいんだ。いつからぼくはこんな風になったのか。ものごころついたころからだったかもしれないし、途中で何かに躓いたのかもしれない。きっぱりとした目印などなく、シームレスなものなのかもしれない、現在進行形の。
そうだとしても、たくさん人を傷つけてしまう自分の、心の傷くらいは、なるたけ多く知っておきたいとおもう。楽しかったことだけじゃない、つらかったこともぼくは忘れてしまう。いや、痛みを忘れるからこそ、楽しかったことからも、笑顔だけが差し引かれていってしまうのだ−−チェシャ猫の反対《アント》みたく。
ぼくはぼく自身のために、きみの笑った顔が見たい。「お前のためじゃない」なんて、友よ、どうかいってくれるなよ。
*
道を違えた
やさしくなりたい
青いパーカー
青いパーカーは万引きした。それがどうしても欲しかったし、それを買うお金をもってなかった。ほんとうに欲しいものは、誰になんといわれようと、どんな危険《リスク》を冒してでも手に入れなくちゃだめだ。後ろ指をさす人人のために、きみは生まれた訣じゃないだろ。
とはいえ、万引きにそこまでのリスクはなかった。試着室で、試しでなくて、ほんとうに着ちゃえばいい。バレる人は、その服が欲しいんじゃなくて、万引きがしたかったのだ、そう思う。お金がなくて、盗む気にもならない服なんて、そこまで着たくないのにちがいないんだ(手が届かないだけで、着たいと勘違いするひともいるみたいだけど)。
これまでに万引きしたのは、その青いパーカーと、紺色っぽいてらてらのジャンパーと、青い布地の羽毛ダウン(あとにも少しあった気がするが忘れてしまった)。服でなければ、あとは乾電池だけ。これは公園生活の必需品だったし、大きさの割に高価いので、盗ってもよいという手前勝手な判断による。けれど、あんまり手慣れてくると油断して捕まる気がしたから、一緒に梅ガムも頂戴することにしていた。この味でおまえのやっていることは犯罪なんだぞ、ということを覚えこませる。そうでないと忘れてしまいそうだったから。
ほかに盗みといえば、渋谷のホームレスのおっさんから上着を盗んだことがある(いま思い出したが、さっきの紺のやつはこのおっさんから剥いだものだった)。
時系列など、とうに時間性《トキ》の魔法陣へとりこまれてしまったが、兎にかく目を覚ますと、着ていたボロモコがない! 寒くてさむくて、死ぬかとおもった。あんなに汚くて臭いのを盗むのは、同じ衛生環境を生きるものにちがいないって思って、このせかいでのルールは、道徳よりも生存なのだと教えられた気がして、わりあい太っちょで、空のワンカップを枕元にきちんと並べてぐっすり寝ている赤顔のおっさんの片方の袖をつかんでずるっとやってみたらいけた。剥ぎたての熊の毛皮(着たことはないけど)ほどじゃないんだけど、すごくあったかい。お礼にエコーを一本、空のカップに挿してゆく。
りーびん、いんな まてーりある わーる、
あんどあーいあま まてーりある がーる
マドンナの「マテリアル・ガール」をひらがな英語で口ずさむのが好きだった。女の子だったらたちんぼになりたいと思っていた。いっぽうで、ラモーンズの「53rd & 3rd」にでてくる街角に立つ男娼にもあこがれていた。だけど、そのころはいまよりもずっとみてくれがわるかった。夜に眠らない育ちざかりで、いびつな体躯《からだつき》をしていたし、嫌なにおいがして、おまけにハサミで剪った坊主頭で、眉を整えたり鼻毛を剃ったりすることも知らなかった。公園の公衆便所で鏡に映るのは到底買ってもらえなさそうな、かつてのお調子ものにすぎなかった。だから、いまのきみをみたら、けっこう羨ましがると思う(きみのねがいが、いまのきみをかたちづくったというのに)。
それで、そのころのたたずまいのお手本といえばもっぱらホームレスのおっさんだった。肘から下で腕をふる歩き方から何からなにまで真似しようとした。眠る貌《すがた》がみんな静かで好きだった。
だけどぼくは寒くてさむくて夜はほとんど眠らないから、なかなか真似できない。寝ようとおもったら、恵比寿のロケ公の土管んなか、六本木のロボ公の滑り台んなか、渋谷のマック、用賀の友達ん家のマンションの屋上(とてつもなく寒い)、二子玉川の河川敷の橋の下(同じくらい寒い)、駒沢公園のスタジアム周縁(風は防げる)あたりなんだけど、でかいショルダーバッグで持ち運んでる毛布にくるまってぶるぶるぶるぶるふるえているだけで、とてもじゃないけどああいうふうには寝息を立てていられない。
校門が開くのは朝六時(四時からそれまでの二時間が世界でいちばん長い)、すぐさま体育館地下のシャワー室で、あったかいのをだして、三〇分間浴び続ける。そのあいだに色んなことを考える。考えるというより、頭の離れをノイズだらけのVHSみたいな映像が、スローモーションに早巻きにうごく誰かの口唇とか脚とかが何か言おうとしているかのように語りかけてくるのを、水しぶきの中、聴き取ろうとしていた。朝立ちはちっともしない。服は躰といっしょにもみ洗いして、部活動の奴らがしてるみたいに、あとで教室の後方、窓際の白い手すりに干しておく。青いパーカーだけは洗わない、古着屋の洗濯油のニオイとじぶんの躰臭とが交って、この匂いがないと夜にちょっと不安になる、いいや、それよりも、はだかの上半身にくたびれた裏起毛の圧しつけるのがみょうに心地良くって、牛乳石鹸のにおいとも混ざって、六つの授業のあいだ、遠い眠りへとぼくを連れて行ってくれる毛布になるから。午の陽ざしのなか、眠りが近づくと、勃起したままの向日性の幼い生殖器は、色褪せ枯葉いろになったアメリカの軍服カジュアルの布ベルトで緑の支柱にゆわえておく、机のからっぽの抽斗の蔭、体育着の青紫の短パンの下から、尖っぽだけちょっと、パーカーの襞になっているポケットのうら地の洞に蕾が頸を突き出すように。
*
青いパーカー 襞になってるポケットの
ーうら地の洞。
蕾が頸を突き出すように
白いラジカセ
目を覚ましたときのチャイムがだいたい最後のやつなのは不思議だ。だがついに、そのメロディを聞くこともなくなる。学校には少し早めの春休みがやってきた。けど、ぼくが午さがりの目覚ましを聞かなくなったのは、それより二十日くらい前の二月の下旬だった。
白いラジカセは買った。ファンキーな村の鏡餅くらいの大きさだ。青いポスカで頭部《ヘッド》にMY LIFEと書いた。渋谷や六本木の街を、こいつを肩に載っけて歩くのだ。昆虫の脳みそ《ブレイン》みたいな半透明のおでこを押すと、コックピットのハッチのようにゆっくりと開帳する。そこにCDが納められる。ゲオで買った黒い布製のCDケースで持ち運んでいて、キングギドラやWANDSやDragon Ashが収容《コンパイル》されている。いちばんよく掛けていたのは、LBネーションで「Little Bird Strut」。
こいつ《MY LIFE》の口のところには小さな口がついていて、そこにSDカードが挿し込めるようになっている。そしてぼくのチップには、それはそれはたくさんの夢が書き込まれていた。
けれど、ぼくはこの白いラジカセを、地下美術室《ちかび》においたまま東京を離れなくちゃならなかった。こいつ《MY LIFE》はその夢を奏でることなく、還ってきたときには水浸しになっていた。いなくなったぼくの代りに、仲間の友達は、こいつをぼくの名まえで呼んでいたらしい。
いちどは腹の底にしまいこんだ夢を、大音量で肩に担いで、ふたたび街に連れ出すことができたのは、地面の底がひらいたからだ。それも長続き《MY LIFE》はしなかった。
代々木公園《よよこう》の桜が咲いた。このときについた泥は、傷のなかに染み込んで、夏の終わりにまだのこっている。CDを掛けると、耳かきをしてるときの耳みたいに割れた音がする。「毀れた夢《MY LIFE》」。だからこそぼくは、もういちど、今度は仲間とともに、目に見えないものに、そらに両手を翳せ《Put your hands in air》たのだろうーーだが、それはいまきみに話したいことじゃない。
*
STILL LIFE
晴てても 待つこと−覚えた、
青空の中。
誰よりも追いかけて
ブルーのエメマン
「つめた〜い」から「あったか〜い」へと季節は移ろうとしていた。そこはつい先頃まで片方の住んでいた三階建アパートの屋上で、ふたりはそれぞれ反対の隣町からやって来る。
秋の終わりの用賀。まだOracleのオレンジでなく、SUNのブルーだった頃。ふたりは中二から授業をサボり仲間と近くの有栖川公園裏の廃墟になった病院のホールで酒盛りをするのだったが、いまは片方がやらない、夏とは逆の方が。もう片方に呑まない理由などなかったが、酒はみんなでやるか、一人でするかのどちらかということが金木犀のにおいはじめのように暗有されていた。だから、会うときはいつもどちらかがブルーのエメマンを二本買ってくる。どちらもという日はない。そして待ち合わせるということもないのである。すれ違うのはかならず三角公園の前あたりであった。
「ほんとうにやばいものをみつけた」
「おまえもかよ」
「さきにいえよ」
「ジョニー・ロットン」
「ふざけんな! おまえはいつもそうだ。まじでふざけんな」街のにおいがよく似ていた。
いまふたりは抒情の味を覚えはじめようとしている。センチメンタルには匂いがあって、その奥には静謐が控えていることを。たとえばそれはMADE INのラッキーストライクであり、あけたてのhi-liteであったり、或は、東名高速であり、夜や風であったりする。−−夢はこれに耐えねばならない。崩れ落ちそうになるのを、どちらにもたれるでもなく、ただ、煙にかえ空に還していた。そのぶんだけ街はからっぽになってゆき、涙と笑と叫びとがアスファルトをやさしい噓のようにのたうち回る。
「時代におれは叛逆するよ」
「…」あまいは苦い、にがいは甘い。
「人類を幸福にしたい、そのために死にたい」
「家族が欲しいだけだろ」
街はもたざる故郷のごとく沈黙していた。
*
ブルーのエメマン
片方の部屋の白いラックを満たすとき
−予感のひとり風となる
ノーマルカラーのiPod touch
「これがないと死んでしまう」
それを失くした、iPod classic. 集めた夢たちは、すくなくとも64GBなくては、もう持たない、いやその数字にこだわっているのはもっと別の意味でだったかもしれない。
ぼくは「第六十四回文化祭実行委員会」のSTAFFだった。高二の先輩の代だったから、後輩スタとよばれていた。この学校に入学したのは、小学校五年ではじめて来た文化祭のステージとそこで行われていた中庭プロレスにあこがれたからだ。始業式の後、さっそく、いやそれはほとんど拉致にちかかったが、気づけば地下柔道場《ちかじゆう》の、本望の中庭と講堂とのイベントを執り仕切っている行事部門の〈部門会〉という集まりの中にいた。そこで先輩から告げられたのは、「文実に人権はない」ということだった。だとすれば、後輩スタとは、奴隷以下、畜生以下、物質と同義である。そして、物質にも心があるのだということをぼくは身をもって知ることになる。
「これがないと死んでしまう」
これは何だ。ほんとうは、信条であれば問題なかった。だが、この回、64thにあって、物質はあまねくきよらかなコスモスに統べられていた。愛する人をこの物質宇宙の原理に奪われぼくは、日ごとアポロンの矢に射抜かれる。おなじく古い神を愛する友は、かたく口を閉ざしていた。ゼウスの後に、神などあるだろうか? 心なしかこの宇宙の委員長は、仏さまのような顔をしている。しかもぼくはこの君子に、あまり好かれていない。ぼくにほんとうの神さまの横顔を見せてくれたその人は、いまはもう、邪神の思い出でしかない。
「これがないと死んでしまう」
この新しい神か仏かわからぬ達観者の時代に、ぼくが生き存えるためには、吸う酸素より以上に音楽が必要だった。その人は記憶できない言葉しか遺さなかったから。
〝この街で流れている音楽におれの知らないものはない〟
これは数少ない記憶できる初級者向けの言葉だ。ぼくはその人の魂に流れているたった一つの音楽に触りたくて、幾千の音楽をきいた。けれど、そこにはその人のいないぼくの街があって、通りにはいつでも雨が降っているのだった。へばりつくような油汗のにおい。
だが、ぼくが死に物狂いで辿っていたのは、ヘッドホンから聞こえてくる散文だった。
−−もういちど。
だが、ぼくが死に物狂いで辿っていたのは、ヘッドホンから聞こえてくる散文だった。
−−もういちど。
だがぼくが死に物狂いで辿っていたのは、ヘッドホンから聞こえてくる散文だった。
だがぼくが死に物狂いで辿っていたのは、ヘッドホンから聞こえてくる散文だった。
だがぼくが死に物狂いで辿っていたのは、ヘッドホンから聞こえてくる散文だった、
だがぼくが死に物狂いで辿っていたのはヘッドホンから聞こえてくる散文だった!
ぼくが死に物狂いで辿っていたのはヘッドホンから聞こえてくる散文だったんだ!
「おかえり」
そういってその人は、遠い旅から生還したぼくを抱いた。
そのときぼくが生まれてはじめて聴いた音楽は、いまでも鳴ってる。鳴り続けている。
ほんとうは、お母さんとのことを書くつもりだった。でも、こうなるしかなかった。母にはなぜ「これがないと死んでしまう」のか、説明することはできなかった。でもとにかく、その日、母は酸素カプセル(カウンセリングでも薬でもぼくのビョーキは治らなかった)の帰り道に、それを告げたぼくと、真夜中に中目黒のドン・キホーテまで自転車で三〇分、家出していたぼくに買うにしては高価だった、そのiPod touchを買ってくれた。出口で別れ、ぼくは西郷山公園へ坂をのぼる、そこで夜が明けるのを待つのだ。夜があけるのを。
*
「これがないと死んでしまう」
これがないと死んでしまう
赤い自転車
赤い自転車は、生まれる前からあった。
誰しもがもつ幼年時代、生まれた瞬間に剥奪された赤子も、幸運にも一生をそのうちで送ったひとも、かつて歴史上にはいただろう。だが、ふつう、誰しもがその終わりをもつというのが幼年時代という言葉のもつ意味のまんなかだ。ぼくの場合それは、二つの事件によって、二つのものが、二度失われた、とそう考えることも出来た。
だが、ランボォの飜訳のように、〝また見つかった!〟そういうことがある。なぜなら、幼年時代と永遠(生まれる前、死んだ後、そのあいだずっと)とは、コインの裏表でなく、見る角度を変えると別の絵になる、あのぎざぎざカードの中身だから(れんちきゅらっていうんだって)。ぼくはいまでも、いまはもうどこにあるかわからないあのカードたちを好きだし、絵がなくなっても描かれた餅はなくならない、それを食べたことがあるなら。
でも一度ずつはたしかに失った、その経験を、これは昔のアパートのおもちゃ箱でなく、靴の中の足指のじめつきだとか、鼓動の仕方、母がかつてそうしたようになるよう、左の手首を裏返して手のひらをおでこにつけてすぐの消えていく冷たさのような感覚として、躰じうの静脈の中に保存している。勇敢な精子のようにこれを遡行して、ぼくたちはもういちど自らの心臓に飛び込むのだ。心房の壁はかたい、でも何度でも何度でも体当たりしてみたら、壊れない壁はないんだ。だってそれはけっして不確かなどでなく、ぼくたちの確かさの源泉である弱くても挫けない心臓《ハート》そのものなのだから。
ぼくの幼年時代はいわば、ハートとダイヤの二つの革命によって、解体された。そして革命後のせかい、ぼくの少年期を支配したのは、恋と祭だった。
十歳、ぼくは初恋と祭との出会いをおなじ五月に果たしている。ひとめぼれは小学校の始業式だから四月だが、ほんとうの黄金は五月から始まった。そしてゴールデンウィーク、ぼくは二年後に入学することになる中高一貫校の文化祭と出遇う。
だが、注意して欲しい、いまぼくはそれを革命そのものでなく、革命後の変革世界だとおもいなしている。ハートとダイヤのそれぞれの革命は、両親とぼくと世界との三つ巴で成り立っていた。これがひっくりかえって恋とぼくと祭とに図柄がかわったということだ。クローバーはぼく、赤い自転車はその心臓の色をしていた。
そしていまぼくは、ダイヤモンドの世界から、逃げて逃げてやってきた幼年時代の町で、この赤い自転車で国道122 号線《ワンツーツー》を利根川を目指し立ち漕ぎしている青いパーカーの金髪の少年だ。その脆い心臓にはノーマルカラーのiPod touchからイヤホンの白い血管をとおし、耳の穴をつたってキンクスの『ヴィレッジ・グリーン』が、鼻血のように吹き出している。五月の陽射しは、かつての夏の王のように田んぼ道の緑を赫かしている。陸橋を渡ろうとしたとき、右手のとおくの方にくすんだ白とにぶい青のラインの秩父鉄道が近づいて来ているのが見えた。
次に気がついたのは、国道の両側から近づいて来るパトカーのサイレンを感知した時だ。ぼくは陸橋のてっぺんちかくの歩道の脇に赤い自転車をとめ、白いガードレールを跨いで橋のへりに座っていた。その真下に赤煉瓦アーチのトンネルがあり、今ちょうどさっきは遠くに見えた秩父鉄道がぷああんぷああんんしている足の裏の先を通過しているところだ。
ワンマン列車は遙か後ろへ去った。パトカーはどうやら両方ともこの陸橋を通過しようとしているらしい。赤い自転車のカバーが被せてある黒いカゴの中にはhi-liteと横四角の窓枠のような凹みに鈍い金色のエンブレムが掘られた鈍銀のジッポライターが隠してある。
まさか、けたたましい両側のパトカーがどちらもじぶんのとこめがけて走ってきているだなんて思わないが(だが目覚める直前の、スズメバチに付き纏われたり刺されたりするの夢のように、なぜか自分のとこに向かってくるという予感がないわけでもない)、もし補導でもされたら今はおじいちゃんとばあちゃんに迷惑が掛かる−−声を掛けられ、黒いカゴの中身が見られたときの言い逃れくらいはいくつか考える。
左右それぞれからほとんど同時に来た二台のパトカーは、ブレーキを強く効かせながら、なぜかぼくの後ろ近くで停車する。ドアが開けられる音。
「はやまるな!」
「はやくこっちに来なさい!」
警官はたぶん五、六人だった。「この道を通過した車の人できみのこと通報してくれた人がいるんだよ」
(通報してくれた? だれのために?)
「自殺なんかしたら家の人が悲しむよ」
景色から目を逸らさず叫ぶようにいう。
「自殺なんかしません。景色がきれいだからここに座って眺めているだけです」
こんなところに座っていたら、後ろを通る車の人たちがびっくりしちゃうじゃないか、といわれ、それはそうだとおもったけど、やっぱりきれいな景色を好きなところで眺めるのを止められるのはへんだとおもう。ぼくはなにを怒られてるんだろう?
「それは失礼しました」
ぼくはなにを怒られているのだろう……それはひととちがうことをしていることだって、このおまわりさんたちも言いたいのにちがいない。人をびっくりさせるのはよくないことなのだ。
警官の女のひとが、いっこうに立ちあがろうとしないぼくの両脇腹に後ろから腕を差し込んで、立つよ、といってガードレールの内側へ曳き揚げる。一瞬宙にからだが浮いた。それからぼくの肩を摑んで向き直させ、じっくりぼくの顔を覗いて(どうしてだか、それが小学校二年のときの担任だったモロサワ先生の顔にみえる)、
「どこの人。見ない顔だね。ここらへんでまるまる金髪にしてる子なんて、もうしばらく見ないよ」
「東京です。おばあちゃんちに遊びにきて、散歩していたんです」
「この自転車はあなたの?」
「だから、おばあちゃんのです」この赤い自転車はぼくが生まれたときからあるものだ。
「おうちはどこにあるの?」
あっちの方、と指をさす。「西、とかなんとか」
「いちおう手荷物検査していい?」
黒いカゴの中身もバレるかなっとおもったけれど、からだだけで済んだ。
「覚えたからね、日が暮れるし、はやくかえりなさい」
〝みんながいるところへ〟といわれている気がした。
パトカーが見えなくなると、日が暮れて、田んぼが真っ黒になって沼みたいにみえるのを、さっきのとこに座りなおし眺めつづけた。秩父電車が闇の向うからやって来るたび、これに運ばれてどこまでも遠くに行きたい、と強く願う。こんなに遠くまできても、ぼくが居ていい場所なんかないんだ、ひととちがうことをするから。大事なことすっぽかして、こっちまで逃げて来たけれど、それでもまだ戦ってる、ぼくの戦いは続いている。こんな時代には叛逆するんだ、たとえひとりぽっちになろうとも、友達や家族を失くしても……
牛蛙の声が聞こえ始める。こいつらはもう何千年も生きているにちがいない。突然踏切が鳴り始め、遠い眠りがぼくを橋の下へ曳きずりこもうとしていたのに気づいて、急いで立ち上がり、赤い自転車にまたがる。覆いをのけ黒いカゴの中を覗くと、hi-liteと鈍銀のジッポライターがある。これだけは守らなくてはならない。
「これだけは守らなくてはならない」
利根川の土手には行かない−−いや、少し怖くて、いけなかったのだ……
田んぼの中の還り道、ノーマルカラーのiPod touchでこの歌を最大音量でかけながら、月のない星空の下、追い駆けてゆく。
Not Dark Yet まだくらくない
WRITTEN BY: BOB DYLAN
Shadows are falling and I've been here all day
It's too hot to sleep, time is running away
Feel like my soul has turned into steel
I've still got the scars that the sun didn't heal
There's not even room enough to be anywhere
It's not dark yet, but it's getting there
影たちが落ちていってる ひもすがらここにいる
眠るには熱すぎ、時は遁げ去ってゆく
魂が鉄塊《スティール》にかわったように感じる
傷はなくなっちゃいない 太陽でも癒せなかった
どこにでもあるような空きすらない
まだ昏くない、じきにまもなく
Well, my sense of humanity has gone down the drain
Behind every beautiful thing there's been some kind of pain
She wrote me a letter and she wrote it so kind
She put down in writing what was in her mind
I just don't see why I should even care
It's not dark yet, but it's getting there
おう、人間らしさなんかどぶに流れた
美くしいものすべてに痛みがつきまとう
彼女が手紙をくれた ご親切にも
思いのたけを打ち明けてあった
それがどうしてぼくにかかわりがある
まだ盲くない、じきにまもなく
Well, I've been to London and I've been to gay Paree
I've followed the river and I got to the sea
I've been down on the bottom of a world full of lies
I ain't looking for nothing in anyone's eyes
Sometimes my burden seems more than I can bear
It's not dark yet, but it's getting there
おう、ロンドンに行った 華のパリーに行った
河をたどって海にでた
噓で埋め尽くされた世界の底にいた
だれの目も気にしちゃいないよ
背負っているものに圧し潰されそうな時がある
まだ暗くない、すぐにまもなく
I was born here and I'll die here against my will
I know it looks like I'm moving, but I'm standing still
Every nerve in my body is so vacant and numb
I can't even remember what it was I came here to get away from
Don't even hear a murmur of a prayer
It's not dark yet, but it's getting there
ここで生まれて ここで死ぬんだ 仕方なしに
活いているように見せ、突っ立ってるだけだ
躰じうの神経があんまりうつろで麻痺している
何から遁げてここまで来たかさえ思い出せない
祈るささやき一つきこえない
まだ闇くない、まもなくすぐに
鈍銀のジッポライター
はぐれの梅雨が三日続いた。利根川の流水から引いた農業用水の濾過装置を眼前にして、茶色い木のベンチがある。右に赤い自転車が停めてある。灰色の雲は黒みをまし、太陽はしばらく前にいなくなったことがわかる。葉を茂らせ緑色で重たくなった桜の並木が川に沿って続いている。リーバイスの薄青い布地は全面的に濃さを増して脚の輪郭が透ける。白のコンバースは、泥まみれになり、やぶれたところからは、同じ色になった靴下がのぞいている。青いパーカーからは、もうなんだかよくわからない臭いがする。
鈍くなった金色のエンブレムがあしらわれたジッポライターを握っていた。水気をふくんで火はつかない。焼き石をたきすぎて摩擦で親指をやけどしている。オイルのにおいがふるえる躰に錆のようについてくる。冷たくなった鈍銀の直方体を握りしめると、喉元を締めているような感覚になる。
祖母からの着信で薄金いろの携帯電話《ガラケー》が振動していた。画面をしばらく見つめ、やがて通話停止ボタンを長押し電源を落とす。水面はいま巨大なみどりの蛇のようにゆっくりと大きくうねりあげ、沿道に上陸しようとしている。だが空はもっと巨大な龍の腹に見える。
「たぶん、祭は終わっている。ならどうしてぼくは生きているの。どうしても生きているようにしか思えない」
命を懸けるといった。祭のためなら死んでいいとも。東京から遁げて来たが、それでも闘いは続いているはずだった。いや、自分の言葉を裏切ったらぼくは死ぬしかないから、噓にしないために、噓をついているのか。ぼくは白痴を装って、祖父母が工場《こうば》へ出社している日中は、狭い縁側で猫のナツオと暮らしていた。発作のけはひがして来ると、祖母の赤い自転車で、田んぼ道や国道やインター近くや線路沿や町中をかっとばす。それでも、ひとときも文化祭のことを忘れたことはない。一年後の自分たちの代の夢でなく、いまの先輩の代、あくまでスタッフとして属している64thを。
祭について考えつづけること、それが命を懸けて従事することになるだろうか? だとすれば、こんな白痴であるのに関わらず、ぼくはこれまでのスタッフという存在において、知識人《インテリ》的上昇をしたことになるのか、発狂と隔離療養という下降を代償に。というのも、ぼくが考えているのは、実際てきなことではなく、観念とその実現の方法についてだった。それがいつからか「時代に叛逆する」という一語に集約され、発狂する前には、先輩にも仲間にも教員にも家族にも、それしか言わなくなっていた。なぜそこにいたったか、ぼくのなかには長い長い経路と痛みとがあったが、いくら話したっていつもどこかでそれにはちょっとついていけないよ、飛躍がありすぎるといわれるにきまってる。そしていつしか「それは傲慢だ」という語をだれが言い出したわけでもなく、みながいうようになった。ぼく自身、そういわれ、これは傲慢だ、おれは傲慢だ、傲慢だ、傲慢だ、とノートに書くようになる。そのうちにあの一語でもって返すしかなくなった。「おれは時代に叛逆する」。
誰と話すにも言葉が二つしかなくなったので、あとはしばしば暴力によるしかなくなる。どんなに殴られても、心は少しも痛まなかった。もう夢にしか疼かなかった。
「たぶん、祭は終わっている。ならどうしてぼくは生きているの。どうしても生きているようにしか思えない」
命を賭けると誓ったはずの文化祭が終わった、というのにぼくの躰には何の変化も起きなかった。心は? もう何も思うことは許されない。けれどこれは何だ? 雨、雨、雨、
祭よりも大切なものがある? 誓った言葉よりも守るべきものが。嬉しい、嬉しい? あの人たちの祭は終わった、あの人たち? じぶんもその一部でなかったのか。それが、ぼくはいま生きていて、躰の底から「生きていてよかった」がこみあげてきている。おお、こんなやつに生きる資格はない!
生きる資格がない−−これがぼくの始まりとなった。どうせおしまいの人間なのだから、自分の好きにすればいい。やりたいことやって、いいたいことをいう。好きなものを好きという、fuckならばfuckと。夢を見ることは、けっして悪いことじゃない。けっかてきにその夢によって時代に叛逆することになっても、その代償を払う日が続いても。
ぼくの発狂はその順番を取り違えたせいで起きた。
好きなものを好きという、ただそれだけでよかったのだ。
どうしてこんな風になっちゃったんだろう。生まれて来ない方がよかったんだ。でも、こういう言葉がいまぼくを生かしている。
「生まれてしまったものはしょうがない」
〔ここまで来たら詩を書くしかなくなる、ここが韻文と散文の境界だ。明日書き直したい−−なぜなら、ここから先の感情は『崖のある街』に出尽くしているから−−書かなきゃいけないのはその前なんだ。もういちど大怪我しなくちゃいけない、書くことで……。〕
*
生きる資格がない! 誓った言葉でくるしむのはもうやめにしよう
水色のパントーン
はぐれの梅雨が三日続いた。利根川から引いた農業用水の発電機があるコンクリートの小屋を眼前に、茶色の木のベンチがある。右手に赤い自転車が濡れている。暗灰色の雲は黒みをまし、太陽は五月の伝説の中へ幽閉されていた。葉を重くし緑いろを繁らせている桜の木の連続が水路に沿ってある。薄青いリーバイスの布地は全面的に濃さを増し、両脚の輪郭が浮きだしている。かつて白だったコンバースは泥に近づき、やぶれた穴からは、同色と化した布が覗ける。かつて青だったパーカーからは、もうなんだかよくわからない異形の香りがする。
鈍銀のジッポライターを右手に握っていた。横倒しの長方形の凹わくに、精肉パックにぎゅうぎゅう詰めされた牛の内臓みたいなパイプ図の金色のエンブレムが垢で燻んでいる。腸物は史実を失った逸話のように銅版画《レリーフ》の灰色の眠りの中にある。芯《ウィック》が水気を含んで火はつかない。火付石をたきすぎて摩擦で親指をやけどしている。オイルの臭い足りなさがふるえる躰に高山の空気のように圧してくる。躰熱をなくし冷たくなった鈍銀の直方体を握りしめていると、喉頸を絞めているような心地がする。
祖母からの着信で水色のパントーンの携帯電話《ガラケー》は蠕動していた。小窓のデジタル通知をしばらく見つめ、やがてサイドの通話停止ボタンを長押して電源を落とす。用水路の水面はいまや巨大なみどりの蛇のようにゆっくりと大きくうねりをあげ、沿道に上陸しようとしている。だが、空はもっとずっと巨きな緑の龍の腹だ。
「ちょうどいまごろか、いやもう終わっている? 終わっている? そんなことがあるか。ぼくはまだ生きている。命を懸けるといった祭が終わってどうして生きていることがある」
たとえ遠く離れていたとしても、ぼくは参加している、関東平野の一点で、祈っている。そうすることしかできない、これが別の夢をみたものの末路か。
なぜ仲間がそこにいるのに、ぼくはちがう場所の夢をみたのか。そこはもっと明るい。耐えることをしないで、そこに行く資格があるか。掟を破ったのではなかったか……
「今日だけは帰れないんです、おばあちゃん」
掟の外で生きている人たちがいる。掟は内にいる人にしかわからないから、外の人には、発狂という表現をするしかなかった。しかし、いつからか内からも発狂がいわれるようになった。内部にあって掟を破るものは、キチガイ扱いされる。叛逆はすでに死語だった。
だけど、ぼくだけは知っている。ぼくは少しも狂っていない、と。
それを証明する方法はこの世にない。だから、ぼくは進んで病気に罹った。じぶんでもフリと本当がわからなくなったりもした。でも大丈夫、病気ならば治せばよいのだから。
でもほんとうは、もっと話は簡単だった。ただ夢を諦めさえすればいい、それでぼくの病気は全快したことになる。夢さえ見なければ、かなしい思いなんてだれにさせずとも済む。
「今日だけは、今日だけは…」
医者でもないし、底抜けのバカだけど、ぼくにはわかっていた。この夢を失くせば死と同義だと。ぼくの躰には変な部分があって、ほうっておくと飛び降りてしまう子がいる。この子には、この夢が必要なんだ。夢抜けの廃物を棄てることは、この子にとって造作もないこと−−泣くのはこの子じゃない、親のほうだ。
水色のパントーン。このおもちゃみたいな二つ折りのガラケーは、ここに来る前、母に渡されたものだ。薄金色の携帯は、東京で最後の夜を明かした用賀の屋上からの帰り道に、どこかの茂みに捨てて来た。水色の番号を知っているのは、母とこっちの祖父母だけだ。
ぼくは、夢とパントーンのどちらかを択べずにいる。もしかしたら、択ぶことはないのだ。空の龍と、地面の蛇とが、ひとつになりそうな予感があった。祭が終ろうとしているのだ。ぼくだけのフィナーレ。だれも知らない、知らないやり方で、ほんとうにほんとうにたったひとりの終わりを迎える。
「強くなりたい」
その日いらい、鈍銀のジッポライターのエンブレムのない背面に、その文字は彫られてある。戻ってそう月日が経たないうちに、神奈川県警に没収されてしまったけれど、干支がひとまわりした今でもその文字は消えていない。なぜなら、夢はいまここにあり、水色のパントーンは、実家のかつての部屋の勉強机のひきだしに、ただ一枚の写真を抱いて、長い眠りをむさぼっているから。緑は金となり、龍と蛇とはひとつになる。
復活の日はちかい。
ダークブラウンのギター
東京に帰って来たが、まだ誰も知らない。どんなに心はきまっていても、コワイものはコワイ。ぼくは母の勧めもあって旅に出ることにした。何度も何度もぼくを救ってくれたダウンタウンの大阪に(出身地は尼崎だけどもなぜか大阪だった)。
初日のユースホステル以外は、毎日道頓堀で夜を明かした。冬に野宿生活をしていた身には、温泉につかっているような感じだった。地震の後だったけれど、どうか。川沿いのビルの窓から、ひとりが歌いはじめると、他の窓という窓から人の首が出てきて、大合唱がはじまる。東京の街ではぜったいに目にすることができない光景だ。ずっとこの街に居たいと思った。ここにいれば、ぜったいにあの人たちに捕まることも見られることもない。でも、戻らなきゃいけないのはわかっている。一週間ほどして財布を見ると残りは十円玉ひとつになっていた。
横浜駅で、東横線に乗り換えようと地下に下りているとき、中学のときのサッカー部で仲が良かった同級生とすれちがった。確実に見られたとおもう。噂はあの人たちのところまで届くだろう。
実家に帰ってからは、もうぼくはずっと銀色のマウンテンバイクに乗って世田谷の町を徘徊するしかなかった。見つかっても逃げられる。心はきまったはずだったのに、こんな不完全な姿を見せられるはずがない。芝居好きのぼくは、完璧な登場がしたかったのだ。
なぜこんな裏切り者を、後の祭でも待っていてくれる仲間がいるということが信じられるのか。あいつらは絶対にぼくが戻ってくると信じて疑わない、それがわかるのか。
じっさい、こうなったのはぼくだけでないと知っている。あの祭のあいだに、ぼくたちはぼくも含めて三人の仲間を失った。何が起きたのか。そんなことは初耳だ。後輩スタが三人いなくなることなんて。
そして、一度離れてから戻ったのは、ぼくだけだったのだ。
ああ、ぼくはぼくの還った日のことを書かなくちゃならない。でも、どうにもまだ書きたくないみたいなんだ。そこから先のことも。
だって、そんなの、終わることのない友達自慢にしかならないから。
ぼくはその友達たちと、いまも、これからも、付き合っていくのだから。
伝説が始まる前のラストシーンだけは描いておこう。
帰還のときは、『20世紀少年』の遠藤ケンヂと決めていた。だからどうしても、ギターが必要だった。
いちどボロ市で来たことがある上町をとおったとき、小さな暗いリサイクルショップの壁に、そいつがかかっているのをみた。ジャンク品と書いてある。
お金はどうしたか覚えていないが、気づけばぼくは裸のアコウスティックギターを首の背にかつぎ246を銀色のマウンテンバイクでかっ飛ばしてる青いパーカーの金髪少年だった。唇には「Bob Lennon」
日が暮れてどこからか カレーの匂いがしてる
どれだけ歩いたら 家にたどり着けるかな
僕のお気に入りの 肉屋のコロッケは
いつも通りの味で 待っててくれるかな
地球の上に夜が来る 僕はいま 家路を急ぐ
My Color of Innosenseはとりあえずこの章で終わりです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
