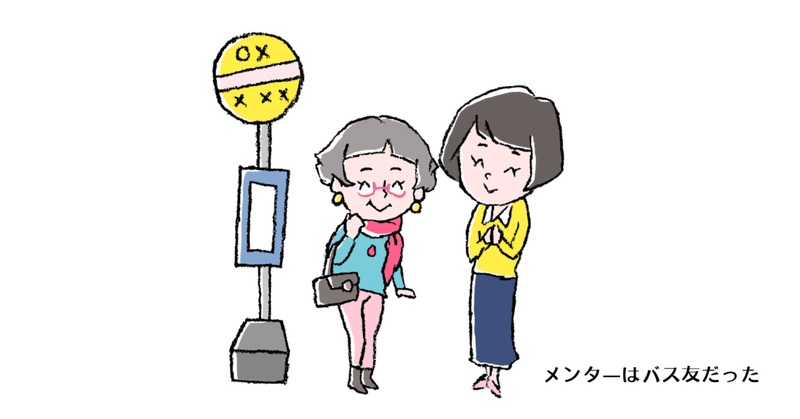
メンターは88歳・❶
主人公、29歳のわかめさんは会社以外に居場所がなく、日々の生活に悶々としていました。会社の人間関係に依存し、週末はひとりぼっちにならないように必死です。自己分析をしても何の特技もないことに打ちのめされます。SNSを見ながら他人の充実した生活に心揺れ動かされてばかり。自己啓発にチャレンジしようと思っても行動に移せず時間だけが過ぎていく。自称言い訳名人。孤独と将来への不安に心がザワザワする日々を送っていました。そんなわかめさんが88歳のなおえさんとバス友になり、「パラレルキャリア」という新しい生き方を教わります。この変化がわかめさんの人生に新たな色を加えるのです。
第1章「普通ってなに?」結婚も出産の予定もない毎日がつまらないわかめさんのモヤッとした悩み

・唯一の居場所が職場しかない
「お先に失礼します」定時、同僚たちに挨拶をして職場を出る。今日は誰も飲みに誘ってくれなかった。
毎日、おなじ風景の中を通り抜ける。オフィスビルの狭いエレベーター、白く明るい照明の下のデスク、無機質なパソコンの画面。もうすぐ30歳のわたしは、会社の往復だけが日々の生活であるかのように感じていた。
つまらない日々。
会社に行って仕事をして帰る。それだけ。職場の人間関係しかない。だから会社の人にご飯や飲みに誘われると行く。誘ってくれるのが会社の人だけだから。
土日は会社が休みだからどうしようと思う。週末はひとりだ。ひとりぼっちにならないように、予定のない自分のことをかわいそうと思わないようにする。予定があるふうにつくろうのだ。
「土曜日か日曜日にうちの子の勉強を見てくれない? 」「 テニスのメンバーが来られないから来て 」と 声をかけてくれる人はいる。
都合のいい代理役、 メンツ集めで困って声かけられた感じがするけれど。
ただ「予定を埋めたい」というわたしの気持ちが出ちゃっているのだろうか。
あの人はウイてるって思われたくない。あの人 ひとりなんだって思われたくない。あの人変わっているって思われたくない。
そのような気持ち が心の奥深くにある。いつもいつも悪目立ちしないように注意をはらう。ドのつく田舎育ちの感性がはらってもまとわりつく。
おそらく唯一の居場所である会社の人間関係をただ大事にしておきたい。仕事を優先しているってこと。唯一の居場所を居心地のいいものにしたいだけ。悲しいかな自己分析はきちんとできる。
・ライフプランが頼りない
会社の帰り道、地下鉄までのアーケードでウィンドウショッピングをする。いつものように店のガラスに映る自分の姿が目に入る。そこには疲れ切った寂しい女の顔が映り込んでいた。
華やかな商品が並ぶウィンドウの中で、わたしは色褪せた存在。
がっかりして目を背けて駅まで早足で歩く。
毎日がグレーに染まっているように感じていた。
30歳目前にして、わたしのライフプランは霧の中。自分にはなんの特技もなく、資格もなく、不器用で、周りの目が気になってばかりいる。
心は常にザワザワと波打ち、やりたいことも一つに定まらず、迷走していた。
なにかをやろうとする勇気が出ない。そのくせ「このまま年を取るのは嫌だ」という思いが、さらに心を重くする。
こういうときに彼氏がいればいいのにと思う。
社会人になってから恋人はいない。空き時間を利用しては婚活アプリを開く。画面に映るさまざまな顔ぶれや条件を眺めながら、図々しく自分が選ぶ側の気持ちでいる。しかし、いつもその先に進む勇気は出ない。
このままずっとひとりなんだろうか。
このまま年を取るのは嫌だな。
「グレーな世界から抜け出したいよ」とつぶやいた。
こんなはずじゃなかったよね。あ、また言っちゃった。
・「まとまった時間がない」という言い訳で、自己啓発の一歩を踏み出せない
実は「リスキリング」という言葉には心を動かされている。
新しいスキルを学び、自分を変えていくことへの憧れがあった。頭の中では、自己啓発の書籍を読んだり、オンライン講座に申し込んだりする自分の姿が描かれる。
しかし、その一歩を踏み出すのはいつも「また今度」という言葉に阻まれる。
仕事から帰ると、疲れ切ってソファに沈み込む。スマートフォンを手に取り、新しいスキルを身につけるためのアプリを眺めるが、すぐに他のアプリに気を取られてしまう。
気がつくと時間は無情に過ぎていて、自分に対して失望感を募らせる。
「わたしはダメなんだ」という思いが心を支配する。自分自身に厳しい評価をしてばかりいる。
変化への願望と現状維持の間で揺れ動く。自己啓発の本やアプリも遠い理想のように映る。行動に移す勇気を持てずに、わたしはただ時間を過ごす。
・将来に対する暗闇の中の漠然とした恐怖
理想の未来がなんなのか描けない。
ある日、知人から結婚式の招待状が届く。今年もお正月に届いた年賀状は、友人や知人の結婚や子どもの成長の報告であふれていた。結婚式の招待状や幸せにあふれた年賀状は自分の孤独をより強く感じさせる。
弟や妹たちも次々と結婚し、幸せそうな家庭を築いている。ローンを組んで家を買ったり、子どもが生まれたりと、彼らの人生は確実に前進している。
それなのに自分の人生は停滞している。
親や親戚からの無言の圧力を感じずにはいられない。独身でひとりぼっちのわたしに、時折、言葉にならない心配を見せる。
わたしにとってさらなる重荷。心の負担。
「みんなの幸せを心から祝えない」「つまらない自分」という思いで自己評価は地に落ちていた。
一生懸命、自分の人生になにか輝きを見出そうとするけれど、その答えは常に霧の中に隠されていく。
・「宝の地図」を手にいれたのかも
寒い冬の月曜日の朝、吐く息は白く空気中に溶け込んでいく。空はグレーで、朝日がぼんやりと光を放ち始めていた。足元には薄い霜が降りて地面は白く光っている。
最寄り駅へと向かうバスを待つために、小さなバス停に人々が集まっている。わたしも厚手のコートにマフラー、手袋をつけ、冷たい風に身を縮めていた。
周りには、通勤や通学に向かう人々の小さな会話が聞こえるけど、それも静かに抑えられたものだ。バスの到着を待つ間、スマートフォンを取り出して時間を確認し、それからまたコートのポケットへと戻す。
遠くにバスが見えると、待っていた人々の中にわずかな動きが生まれる。バスが近づくにつれ、みんなが並び直してバスに乗り込む用意をする。一日の始まりに向けての小さな儀式。
わたしの後ろにはこのバスの時間に見慣れないおばあちゃまがいた。結構なお年寄りだけど、混んだバスで座れるのだろうか。誰か席を譲ってくれるだろうか。先回りして勝手に心配する。もし、席が空いていたらわたしが席を譲ればいいんだ。
言えるかな。「ここのお席どうぞ」って。
緊張してひとつ咳払いをする。モゴモゴと口のなかで座席を譲るセリフを練習をする。
プワーン、バスがついてドアが開く。
「ここどうぞ」
ひとつ席が空いていたから。順番で行けばわたしが座ってよい席だけど、おばあちゃまが「あらぁ、いいんですか」笑顔を返してくれた。「もちろんです」会社のお局様の言い方をマネて言った。小声での練習がよかったのかも。
わたしって咄嗟の反応はうまくできないけど、ゆっくりやればきちんとできるんだよなとぼんやり思う。すこし先に起こることが事前にわかればわたしって神かもねと調子にのる。
バスが駅に向かう間、おばあちゃまとたわいない会話を交わした。おばあちゃまの昔の話を聞き入る。話はあたたかくて、わたしの心にやわらかな光を灯した。笑顔と話し方が心を和ませるステキなおばあちゃまだ。
駅に到着すると、おばあちゃまは再び「ありがとう」と言い、わたしは「どういたしまして」と答える。「しばらくこのバスに乗りますの。明日も会えるかしらね」「あ、席を譲ってねという意味ではないのよ、おほほ」といたずらっ子のように顔をクシャッとして笑って手を振る。
「また明日ご一緒できますね」再び、会社のお局様の言い方をマネした。
バスで友だちになったバス友なおえさんとの出会いだった。
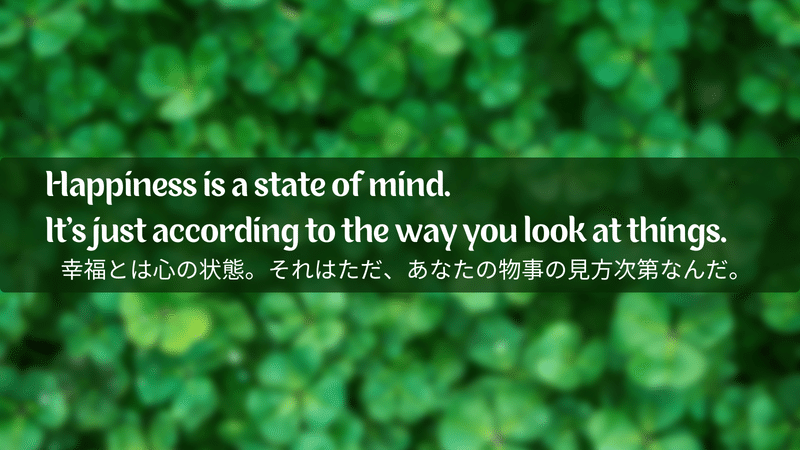
【第1章まとめ】
日常の停滞と孤独感、不透明な将来に対して不安でいっぱい。
自己啓発への憧れはあるけれど、一歩踏み出すことに躊躇する。
「なんとかなる」「なんとかできる」と思えるといいかも。
第2章
第3章
第4章
よろしければサポートお願いいたします!

