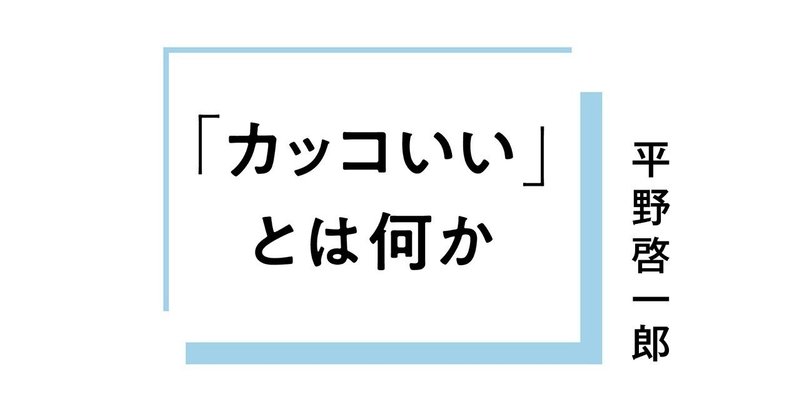
新書『「カッコいい」とは何か』|第3章「しびれる」という体感|3心理学から見た体感主義
生理的反応は、必ずしも一対一で何らかの情動に結びついているわけではないのではないか? なぜ震えるからといって、恐いと感じるのか?――。平野啓一郎が、小説を除いて、ここ十年間で最も書きたかった『「カッコいい」とは何か』。7月16日発売に先駆けて、序章、終章、そして平野が最も重要と位置付ける第3章、4章を限定公開。 「カッコいい」を考えることは、「いかに生きるべきか」を考えることだ。
※平野啓一郎が序章で述べる通りの順で配信させていただきます。
「全体のまとめである第10章にまずは目を通し、本書の肝となる第3章、第4章を理解してもらえれば、議論の見通しが良くなるだろう。」
3.心理学から見た体感主義
情動二要因理論
一八八四─八五年にアメリカの心理学者ウィリアム・ジェームズとデンマークの心理学者カール・ランゲは、私たちの一般的な思い込みに反して、情動に関しては、恐いから震えるのではなく、震えるから恐いのだ、という説を唱えた。周囲で起きていることをまず頭で理解し、それに従って体が反応するという順番ではなく、まずは体の方が先に反応し、あとから感情がそれについて行く、というわけである。この考え方は、一般に、ジェームズ=ランゲ説と呼ばれている。
ジェームズ=ランゲ説は、言われてみれば、確かにそうかも、と思い当たりはするものの、とは言え、疑問がないわけではない。
私たちは、体に戦慄が走る時、必ずしもいつも〝恐い〟と感じるわけではない。寒くてガタガタいっていることもあれば、ボードレールのように美に打ち震えていることもあり、また将棋の羽生善治名人の手は、勝ち筋が見えた瞬間に震え出す。
生理的反応は、必ずしも一対一で何らかの情動に結びついているわけではないのではないか? なぜ震えるからといって、恐いと感じるのか?
その通りである。この尤もな疑問な対して、社会心理学者のスタンレー・シャクターとジェローム・シンガーは、情動二要因理論(一九六四年)という説を唱えた。私たちが、生理的興奮を感知した後、それが何であるのかがわかるのは、置かれている状況を通じて解釈するからである、というのだが、これは、至極、当然と思われるだろう。お化け屋敷に入ってゾッとすれば、当然恐いからだし、大海原に真っ赤な夕日が沈んでゆくのを見て鳥肌が立ったならば、その美しさに感動しているからと思うだろう。
しかし、この話は誤解という問題が絡んでくると、俄然、興味深くなる。
カナダの社会心理学者、ドナルド・ダットンとアーサー・アロンは、若い男性たちを二つのグループに分け、高さ70メートルの吊り橋と揺れない橋とをそれぞれに渡ってもらい、その途中で、突然、若い美女にアンケートへの協力を求められる、というユニークな実験を行っている(一九七四年)。なぜそんなところに女性が?という感じだが、「結果に興味があれば、後日電話をかけてきてください。」と伝えておいたところ、揺れない橋の被験者はほとんど電話しなかったのに対して、吊り橋の方は、半数が電話をかけた(!)という。なぜか? 後者は、吊り橋を渡っているためにドキドキしているにも拘らず、あとでそれを、その女性に対する〝恋心〟と勘違いして解釈してしまったのである。俗に「吊り橋理論」と呼ばれるものである。
恋愛感情とまで言わずとも、これまで「カッコいい」について考えてきた私たちは、少なくともこう言うことは出来るだろう。彼らはその時に感じた生理的興奮を、彼女と電話で話すことで、もう一度体験したかったのだ、と。
そして、これらの情動実験の歴史は、ドラクロワ=ボードレール的な体感主義が、モダニズムを開化させ、第二次世界大戦を経て、ロックやファッションに代表される「カッコいい」ブームを巻き起こす歴史と、時期的には完全に併走している。因みに、神学者のルドルフ・オットーが、著書『聖なるもの』の中で、「ヌミノーゼ」という戦慄的な宗教体験を示す造語を用いたのも、芸術に於けるモダニズム時代の一九一七年だった。
情動(アフェクト)理論
アメリカ文学研究者の竹内勝徳は、ホーソンやメルヴィル、それにエドガー・アラン・ポーといった作家が活躍した一九世紀中葉の「アメリカン・ルネサンス」は、
「精神至上主義とは裏腹に、あるいは、精神至上主義から付随的に生じる形で、人間の身体の存在感や、意識をすり抜けて湧き上がる情動の存在が浮上した時代」
だったとしている。ホーソンの名作『緋文字』を読んだ人は、ディムズデール牧師が、遂に自らの罪を公衆の面前で告白する、あの戦慄的な場面を思い出すだろう。そして、心理学者シルヴァン・トムキンズの『アフェクト・イメージ・意識』を引きながら、「情動(アフェクト)」を次のように簡潔に説明している。
「神経細胞が外部刺激を脳の中枢に伝達し、脳はそれに対する反応を情動として感覚系へとフィードバックするが、その際、神経細胞は刺激の入力からフィードバックにかけて、刺激そのものをそれとは異なる『イメージ』へと翻訳して感覚系に届ける。人間の意識ではこの中間経路における翻訳や伝達を把握することはできず、結果として受け取った情動のみを受動的に意識する。例えば、ある一定の刺激が怒りという情動を引き起こすとして、怒りはあくまで翻訳された結果であり、その刺激そのものや情動へと変換される過程を人間は意識することはできない。人間は怒りの情動を意識的に学んで覚えたわけではなく、外界と神経細胞の相互作用により作られたイメージとしてそれを受容してきた。トムキンズはこうした過程を含めて現れる情動をアフェクトと呼ぶ。」(傍点平野)
アルゼンチンの作家ホルヘ・ルイス・ボルヘスは、
「一八世紀の末葉か一九世紀の初頭に、人間は多様なプロットを創造し始めました。恐らく、この試みはホーソーンとともに、エドガー・アラン・ポーとともに始まったと言えるかもしれません」
と語り、
「物語は最後の文章のために、詩は最後の一行のために書かれるべきだ、と述べたのは他ならぬポーでした。これが堕落して生まれたのがトリック・ストーリー」
だと説明している。
今でも、ミステリーの売り文句として常套句となっている「予想もつかない驚愕のラスト!」といった類いのアレだが、これらはいずれも、人間のアフェクトに対する「効果」として考えるべきだろう。重要なのは、最後のドンデン返しで、いかにドキドキするかである。
「神経の作家」ポー
ポーに有名な『告げ口心臓』という短篇がある。これは、冒頭の
「神経が──そりゃもう、恐ろしく神経が立っていました、いまだって立っていますぜ!」
という主人公の言葉通り、全篇、生理的興奮の描写で埋め尽くされていて、老人の殺害もそれが原因であり、また、せっかく死体をバラバラにして床下に埋めて隠したにも拘らず、訪ねてきた警官に、意志とは反対に自白してしまうのも心拍があまりにも高鳴って苦しいからだという、奇怪な、しかし、当時としては極めて斬新な物語だった。ポー自身は「神経」と書いているが、彼は、生理的な身体反応と情動、それに人間の意志が、決して合理的な、単純な関係にあるのではないことを非常によく理解していた作家だった。
ポーは、『詩の原理』という詩論の中で、
「一篇の詩が詩の名に値するのは、魂を高揚し、興奮させる限りに於いてであるのは言うまでもない。詩の価値はこの高揚する興奮に比例する。」
と語っている。
ボードレールは、ドラクロワからだけでなく、このポーを通じて、彼自身が体感として知っていた「戦慄」についての考察を深めたのだろう。
『E・ポー その作品と生涯』の中で、彼はポーのことを正に「神経の作家」と呼び、その作品は、
「意志の座を無理矢理に奪ってしまうヒステリーを、神経と精神との間に潜む矛盾を、そして苦しみを、笑いによって表に現すまでに調子の狂った人間」
について語ると説いている。つまり、人間には精神とは自立して外界に独自に反応するシステムが備わっているということである。
また、『ポオについての雑稿』では、ポーの作品は、
「本文を字義通り辿ろうと努めねばならない。もし私が自分を虚しくして文字に即しようと努める代わりに、作者の意のあるところを解釈しようなどとすれば、ある事柄はまったく別の意味でわかり難くなったことであろう。」
と、その翻訳者としての経験を語っている。
生理的興奮自体は、私たちの身体に基本的条件として備わっている。その上で、その反応と状況とを関連づけながら、私たちは何を感じ取ったのかを自覚する。
イスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリは、それを「経験する自己」と「物語る自己」と二分して呼んでいる。
鳥肌が立ったのは、なぜだったのか?
美しいという感動だったのか、スゴいという衝撃だったのか、気持ち悪いという嫌悪感だったのか?
その意味づけには、ジェームズ=ランゲ説のような一対一の対応関係があるわけではなく、常に環境の解釈次第で、しばしば誤解とも言うべき混乱が生じる。
一八世紀の啓蒙主義者たちの本を愛読したドラクロワは、趣味を巡る「美の多様性」という当時の議論を引き継ぎ、自らが様々な作品に触れて感じ取った「戦慄」を、「美」であると一元的に解釈した。なぜなら、彼はルーヴル美術館にいて、目の前にはルーベンスの絵があるからである。
尤もだが、すると、こういうことが起きる。つまり、結果として、美自体が多様化せざるを得なくなるのである。
私たちが散々見てきたように、「戦慄」のきっかけは様々である。しかし、その「経験」がすべて「美」という言葉で物語られてゆくならば、気がつけば、何でもかんでも「美」のカテゴリーで語られるようになるだろう。実際、彼の死後の世紀末的デカダンスに至っては、ギュスターヴ・モローやオスカー・ワイルドの『サロメ』のような、淫猥で酷たらしい主題までもが、美の範疇に回収されることとなったし、キュビズムもフォーヴィズムも、「美しい」という言葉とは必ずしも絶縁できなかった。
他方、ボードレールも、基本的にドラクロワの「美の多様性」という考えを引き継ぎつつ、詩人としては、自らの戦慄の由来を、もっと具体的に、多様に詠っている。
「戦慄」のすべてを美と解釈するわけではなく、「経験する自己」が驚きとともに世界に反応し得たことに対して、「物語る自己」は豊富な分析と判断の言葉を持っていた。だからこそ、『悪の華』には、ベンヤミン的な矮小化には決して収まらない、ありとあらゆる主題の詩が収録されているのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
