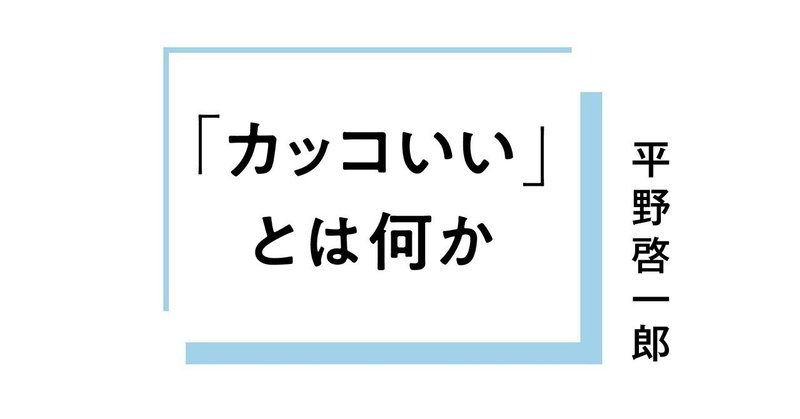
新書『「カッコいい」とは何か』|第10章「カッコいい」のこれから|3「カッコいい」の今日
私は何度となくマイルス・デイヴィスやボードレールなどの言葉を引用したが、「カッコいい」とされる人々の必須の条件は、「カッコいい」名言を有している、ということである――。平野啓一郎が、小説を除いて、ここ十年間で最も書きたかった『「カッコいい」とは何か』。7月16日発売に先駆けて、序章、終章、そして平野が最も重要と位置付ける第3章、4章を限定公開。 「カッコいい」を考えることは、「いかに生きるべきか」を考えることだ。
※平野啓一郎が序章で述べる通りの順で配信させていただきます。
「全体のまとめである第10章にまずは目を通し、本書の肝となる第3章、第4章を理解してもらえれば、議論の見通しが良くなるだろう。」
3.「カッコいい」の今日
マージナルな場所から
資本主義と民主主義が組み合わされた今日の世界に於いて、「カッコいい」は、依然として巨大な力を有している。
その政治的プロパガンダの威力は決して衰えず、期待もされている。二〇一九年に、自民党が「新時代の幕開け」と題して、安倍晋三首相らを、凡そ実物とは似ても似つかない、「カッコいい」侍風の姿で描いた広告を展開したことなどは、そのわかりやすい例だろう。手がけたのは、画家/キャラクターデザイナーの天野喜孝だった。
また、ハリウッドや中国のエンターテインメント映画が、ワイヤーアクションやブルーバックのCGに象徴されるような「カッコよさ」をひたすら追求しているのは周知の通りである。
昨今では、経産省が音頭を取っている「クールジャパン」然り、日本文化の「カッコよさ」は、日本人自身によって過剰なまでに意識されている。
確かに戦後、日本は、黒澤明の映画『七人の侍』や川久保玲のコム・デ・ギャルソン、『ドラゴンボール』から『キャプテン翼』、『ワンピース』に至るまでの漫画やアニメ、ソニーのウォークマンや日産GT-R、日本料理、K-1やPRIDEのような格闘技興行、空手や柔道、忍術などの格闘技、……と、数々の「カッコいい」文化を輸出してきた。
それが可能となったのは、明治以来、欧米の文化を追い続けてきて、戦後は取り分け、大西洋を跨いで形成されていった世界的な「カッコいい」ブームに巻き込まれながら、そのセンスを吸収したからである。日本はつまり、「カッコいい」という言葉を通じて、六〇年代以降のトレンドのグローバル・スタンダードをフォローし、分野によってはしばしばリードすることが出来たのだった。無論、日本発の「カッコいい」文化には、南部鉄器のような伝統的なものもあるが、カラーリングや、どういう店で販売するかなど、その見せ方には、「カッコよさ」の意識が今日、不可欠である。
ヒップの歴史について、ジョン・リーランドは、アメリカ建国以来の中心と周縁の物語をダイナミックに描出したが、更に視野を拡大するならば、それはイギリスを呑み込み、極東の敗戦国日本にまで及んで、グローバルな規模でその運動を展開した、と見ることもできよう。日本はその間、まさにマージナルな場所から世界規模の「カッコいい」運動に参加し続けてきたのである。
また、日本に来た外国人が、独自に伝統文化や建築、あるいは思いもかけない場所や店を「クール」と評価することもあった。それとて、日本人が独力ではなし得なかったことである。
〝体感〟がなくてはならない
しかし、タワー・オヴ・パワーの《What is Hip?》の歌詞にもあったように、今日、「カッコいい」とされているものは、明日にはもう「カッコ悪く」なっているかもしれない。
政府が日本のコンテンツ輸出を支援することは必要だろうが、新しい価値をクリエイトしていく人を地道に応援するのではなく、もう何年も前に「カッコいい」とされたものを後追いで持ち上げてみても、必ずしも支持はされまい。
「カッコいい」は、常に現状に対する個々人の反抗であり、そもそも政府が出張って、「クールジャパン」などと夜郎自大に謳って応援していること自体が、端から見ればどうしようもなく「カッコ悪い」。日本ではなく、中国やアメリカがそんなことをやっているところを想像してみれば、簡単にわかる話である。
六〇年代以降、日本人が「カッコいい」と「しびれて」きた海外の文化は、ロックにせよ、ヒップホップにせよ、いずれもメディアを通じた「カッコいい」の世界的ネットワークの中から自力で生まれてきたものだった。支援するのであれば、政府は飽くまで黒子に徹し、一切、存在感を消して行うべきだろう。
ネットの登場以来、コンテンツ産業は、インタラクションに注目し、一方的な鑑賞ではなく、〝体験〟をこそ重視してきた。
他方で、すべては文脈次第であり、物の消費よりも、〝物語〟の消費こそが重要だとも語られてきた。
しかし、「カッコいい」とは何かを歴史を辿りつつ見てきた私たちには、これが些かソフト・フォーカスの議論に見えるだろう。
つまり、〝体験〟だけでは不十分であり、その核には必ず〝体感〟がなければならない。散々、色々なことを〝体験〟させられながら、まったく「鳥肌が立つ」ような瞬間がなければ、単に退屈で疲れるだけだし、不満が残る。
また、幾ら〝物語〟がお膳立てされていても、〝体感〟が実質として備わっていなければ、つきあうだけ面倒である。
「しびれる」ような生理的興奮がある〝体験〟が、それを的確に「カッコいい」に結びつける〝物語〟に内包されている時、私たちは十分な満足を覚える。コンテンツの企画会議でも、その〝体験〟と〝物語〟のどこに〝体感〟があるのか、といったより焦点化した議論がなされるだろう。
〝体験〟と〝物語〟の重要性とは、「体感」を中心とした「経験する自己」と「物語る自己」との最適化に他ならないのである。
「カッコいい」人々は名言を残している
エンターテインメントは、今後ますます正確に、人間の生理的興奮をターゲットとしてあらゆる創意工夫を行い、それを遺漏なくコンテンツへの支持へと繋げる言葉の誘導を強化していくだろう。ファン・コミュニティの重視というのも、その一つである。
私は、必ずしもそれを手放しで理想化し、推奨するわけではないが、現実的にはそう予想せざるを得ない。例えば、VRがリアルな体験として人を虜にしようとするならば、これが徹底されなければ不可能である。そして、VR空間の方が圧倒的に「鳥肌が立つ」機会が多くなれば、現実の価値は、相対的に低下するかもしれない。
「カッコいい」人物についてリサーチしていて、私は一つ気がついたことがある。
私は何度となくマイルス・デイヴィスやボードレールなどの言葉を引用したが、「カッコいい」とされる人々の必須の条件は、「カッコいい」名言を残している、ということである。
どれほど優れたスポーツ選手であっても、言葉を持っていない人は決して「カッコいい」存在としてカリスマ化されない。なぜなら、その当人の言葉による補助線がなければ、パフォーマンスを見て「しびれた」体験も、うまく「カッコいい」と意味づけることが出来ないからである。また、共感が芽生えにくく、その人物なり商品を、理想的な憧れの対象として良いかどうか、判断できないからである。
勿論、メディアがその役割を代替することもあるが、本人の言葉に勝るものはない。
ミュージシャンは、今日ではマスメディアだけでなく、SNSを通じても常に言葉を発し続けているし、自伝の類いも驚くほど刊行している。どんなに音楽が「カッコよく」ても、コメントが「カッコ悪い」人は、ガッカリされるだろう。もし、モハメド・アリがただ強いだけで、言葉を持っていなかったならば、決して今ほど「カッコいい」存在にはなっていなかったはずである。(2)
脚注
(2)「カッコいい」女性としてしばしば名前が挙がるココ・シャネルの名言集は、日本だけでも、『ココ・シャネル 99の言葉』(酒田真実)、『ココ・シャネル 凛として生きる言葉』(髙野てるみ)、『仕事と人生がもっと輝くココ・シャネルの言葉』(同)、『ココ・シャネル 女を磨く言葉』(同)、『ココ・シャネルの言葉』(山口路子)、『私は私 超訳ココ・シャネル』、『シャネル──人生を語る』(ポール・モラン著 山口登世子訳)、……と驚くべき数が出版されており、更に伝記を含む膨大な関連本がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
