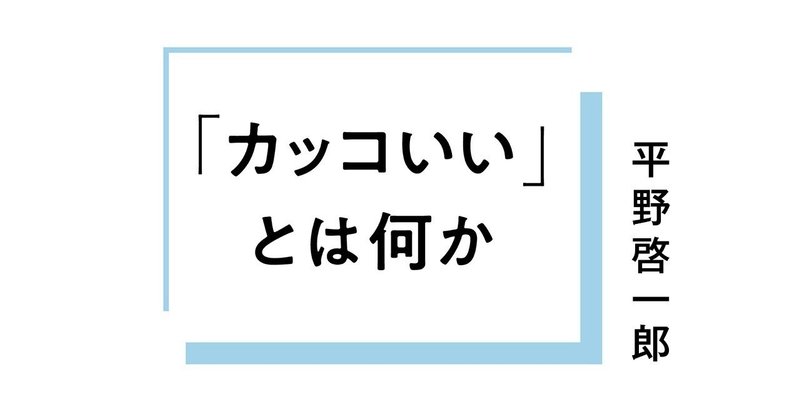
新書『「カッコいい」とは何か』|第3章「しびれる」という体感|2ドラクロワ=ボードレール的な〝体感主義〟
「カッコいい」対象は多様であるので、何に「しびれる」かというのは、自分がどういう人間であるのかを、その都度快感とともに教えてくれることになる――。平野啓一郎が、小説を除いて、ここ十年間で最も書きたかった『「カッコいい」とは何か』。7月16日発売に先駆けて、序章、終章、そして平野が最も重要と位置付ける第3章、4章を限定公開。 「カッコいい」を考えることは、「いかに生きるべきか」を考えることだ。
※平野啓一郎が序章で述べる通りの順で配信させていただきます。
「全体のまとめである第10章にまずは目を通し、本書の肝となる第3章、第4章を理解してもらえれば、議論の見通しが良くなるだろう。」
2.ドラクロワ=ボードレール的な〝体感主義〟
ドラクロワの主張
「カッコいい」対象は多様であるので、何に「しびれる」かというのは、自分がどういう人間であるのかを、その都度快感とともに教えてくれることになる。
BTSのコンサートに行っても、「しびれる」人と何も感じない人がいる。そうすると自分は、BTSに「しびれる」人間なのだと自覚するし、それが他の人とは違う個性となり、なぜそうなのかと考え、自分を理解するきっかけになる。だからこそ、自分が「カッコいい」と思う人や物を貶されると、まるで自分自身を侮辱されたような不快を覚えるのである。
私たちは既に美の多様性について、一八世紀ヨーロッパの趣味論を参照したが、ここでは一九世紀のまた別のアプローチを通じて、「カッコいい」の多様性を考えてみよう。
美の多様性の認識は、一九世紀のロマン主義以降の芸術家たちに、多大な創作の自由をもたらした。それはそうだろう。芸術家は一人一人、個性的なのに、みんながみんな古代ギリシアを理想化し、ラファエロを手本にして絵を描かなければならないというアカデミーの指導は、窮屈で堪らないからである。実際、美術史を振り返れば、そこには十分すぎるほどに多様なスタイルの絵画が存在しているのである。
こうした主張を断固として実践したのは、ロマン主義を代表する画家のドラクロワだった。
「美の多様性について」(『両世界評論』一八五四年七月一五日号)という、そのものズバリの論文の中で、彼は、次のように主張している。
「ギリシアの美だけが唯一の美というのか! そのような冒涜的な言葉を流布させた人々は、どこに行っても美を感じ取ることが出来ず、美しいもの、偉大なものを前にして戦慄する(tressaillir)あの奥深い反響の場所を、自らの内部に微塵も有していない人間に違いない。私は、我々、北方の人間が好むものを創造する能力を、神がギリシア人だけに与えたなどとは決して信じない。」(拙訳・傍点平野)
彼のこうした思想と、創作を通じてのその表現は、とにかく理想は古代ギリシアという新古典主義の息苦しい芸術観から、その後の画家たちを解放する。
この時、重要なのは、彼の所謂「戦慄(おののき、ふるえる)」である。これは、私たちが「しびれる」、鳥肌が立つ、という言葉で論じてきた、生理的興奮を指している。
今日でも私たちは、ルーヴル美術館でドラクロワの《サルダナパールの死》の前に立ったり、ブルーノ・マーズがコンサートで《Just the Way You Are》を歌い出したり、ワールドカップでメッシがスーパーゴールを決めた瞬間などには、激しく「戦慄」し、「しびれる」ような生理的興奮を味わう。何かスゴいものを目にした時には、「うわっ、鳥肌が立った!」と、その証拠に服の袖を捲って、わざわざ見せてくれる人までいる。
ドラクロワは、美を端的に、「戦慄」をもたらす感動の対象と捉えていた。「戦慄」があれば、つまり、それは美なのだという彼の確信は、それだけ、芸術家としての自らの感受性に自負を抱いていたからだろう。この時代、美に対して崇高という概念は、このような「戦慄」的な体験を指していたが、ドラクロワは飽くまで、美に接した時の輝かしい喜びの根底にある「戦慄」について語っている。
彼が美の多様性を断固として信じていたのは、新古典主義者たちが崇め奉るラファエロだけでなく、ティツィアーノを見ても、ミケランジェロを見ても、ルーベンスを見ても、「戦慄」し、鳥肌が立ったからだった。彼は、その戦慄を覚えるという体感だけは、誰にどう批判されても否定できなかったし、それがない人たちは、絵画をただ理屈だけで見ている、鈍感な人たちだと考えていた。
この作品は、美しい。なぜなら、鳥肌が立つから。──
この審美的判断の〝体感主義〟とでも言うべきものに強く共感し、多様性の断固たる擁護者となったのが、一九世紀最大の詩人にして美術批評家だったボードレールである。
ヴァルター・ベンヤミンの古典的エッセイ『ボードレールにおけるいくつかのモチーフについて』以来、ボードレールは、夙に美的モデルネ(芸術に於けるモダニズム)の先駆者として理解されてきた。彼が注目したのは、ボードレールの詩に見られる「衝撃」の体験であり、その身体的反応としての「痙攣」や「戦慄」だった。
ボードレールはリストよりやや年下の世代だが、この時代に「電気ショック」に喩えられるような生理的興奮の感覚は、かなり意識化されていたのだろう。
ボードレールに『七人の老人』という詩を捧げられたヴィクトル・ユーゴーは、その感謝を認めた手紙に、「あなたは新しい戦慄(frisson nouveau)を創造されました。」という有名な言葉を記している。
しかし、ベンヤミン以後、アドルノに至るボードレールの「戦慄」への注目は、今日の心理学の成果などを踏まえると、その意味づけが矮小化されているので、ここではボードレールがドラクロワとエドガー・アラン・ポーから発展、洗練させて、ワーグナー受容に繋いだ〝体感主義〟の現代性を、私の理解を通じて指摘しておきたい。
新古典派に対抗したボードレール
ボードレールは、ドラクロワの「美の多様性について」が掲載された翌年、「一八五五年の万国博覧会、美術」という、彼の美術論としては「一八四六年のサロン」評以来、九年ぶりの評論を発表している。
注目すべきは、実はこの間、ボードレールは、一八五二年に発表した『E・ポー その作品と生涯(初稿)』を皮切りとして、五四年に至るまでエドガー・アラン・ポーの作品を集中的にフランス語に翻訳していることである。
「一八五五年の万国博覧会、美術」は、タイトル通り、一八五五年のパリ万博の美術展示のレビューなのだが、実際にはアングル論とドラクロワ論しかないという異例の構成で、ただ、その冒頭には「批評の方法──美術に適用した進歩という現代的理念について──生命力の移動」という、美術批評家としての彼の基本姿勢を説明する章が置かれている。これは、彼を真に現代的な批評家たらしめた、白眉とも言うべき内容を含んでいる。
ボードレールは、狭量な新古典派の理論に対抗するために、まず美術鑑賞者は、「完全無欠な素朴さ」で、「感ずることに満足」すべきだと説く。なぜか? 「一つの体系に閉じ込もってその中で好き勝手な説教をしよう」とすると、「普遍的生命力の自然発生的な予期せざる産物が現れ」る度に、その新しさに対応できず、後れを取ってしまうからである。
彼にとって、「多様さ」は「生の必須の条件」であり、「芸術の多彩な産物の中には、学校の規則や分析から永遠にはみ出すような何か新しいものが存在する」のであって、そのことこそが「真実」なのである。そして、こう続ける。
「驚き、これは、芸術や文学によって引き起こされる大きな喜びの一つであるが、それも、類型や感覚そのものの多様さから生まれるのだ。」
近代という時代は、社会が機能的に分化し、職業の種類が増え、階級の解体が進み、中央集権化と国際化で様々な出自の人間が交わることとなり、必然的に多様性を増していった時代だった。
あるいは、こうも言うべきだろう。これまで分離していた多様性が交わり合い、更なる多様性を増幅させていった時代だった、と。
芸術も当然、そうした混淆の渦中にあって、アカデミズムの伝統には到底収まりきれない様々な作品が生み出されてゆく。
さてその時、新しく出現した美は、何によって良し悪しを判定されるのか?
ヒュームなら、自然本性に基づいて、趣味のエリートたる「批評家」が、その役割を担う、と答えただろう。
しかし、ドラクロワやボードレールは、それは理屈ではなく、実際に体が反応するかどうか──戦慄し、鳥肌が立つかどうかなのだと主張した。これを、「ドラクロワ=ボードレール的な体感主義」と呼ぶことにしよう。
わからないながらに評価する
彼らは、まっさらな状態で作品の前に立った時に、思わず声が漏れそうな体の震えがあるかどうか、喜びとしての「驚き」があるかどうかを重視した。あればそれは、評価に値する何かなのである。
この体感主義的な審美観は、ドラクロワのように、ラファエロだけがすべてでなく、ティツィアーノやルーベンスを再評価し、過去の美術史を自力で再編しようとした画家にとって揺るぎない根拠となり、ボードレールにとっては、現代及び未来を受け容れるための前提となった。
ボードレールが、「未来の音楽」と揶揄されていたワーグナーを聴き、「かくも強く、かくも激しい」快楽を覚え、「私の力を以てしては定義できなかった新しいもの」を感じつつも、「この定義できないということが私に、奇妙な無上の快楽が入り混じった怒りと好奇心を引き起こ」したと認め、熱烈な賛美者へと転じ得たのは、この体感主義的態度の故に他ならなかった。もし彼が、「一つの体系に閉じ込もってその中で好き勝手な説教をしよう」とするだけの頭でっかちで、偏狭な批評家だったなら、決してその新時代の音楽を受け容れることは出来なかっただろう。
結果、ボードレールは、文学に於いてはポー、美術に於いてはドラクロワ、音楽に於いてはワーグナーと、保守的な芸術観の人々が無視するか拒絶するかしていた、それぞれのジャンルの最も新しい、最も重要な芸術家たちを、断固として擁護することが出来たのである。ここにモダニズムの先駆者たるボードレールの真骨頂がある。
百数十年後の世界に生きている今日の私たちは、彼らの作品のどこがどう素晴らしいかをよく知っている。歴史はその評価を確定し、彼らについての膨大な研究が、私たちの理解を助けてくれる。けれども、最初に見たことも聞いたこともない作品を受け止めるには、ボードレールがそうしたように、何かわからないものを、わからないながらに評価するという態度以外にないのである。何を頼ってか? それこそが、体感に他ならない。
芸術への参入障壁を撤廃した
この時代以後、身体こそは、多様な美を発見し、その価値を判定するセンサーの機能を果たしてゆく。体感にも、何となく、というものから強烈なものまで、様々な種類があるだろうが、その最も激しいものが「戦慄」として自覚されたのだった。恐らく、ニーチェの言う「ディオニュソス的なるものの陶酔」も、ここからそう遠くはなかったのではあるまいか。
なぜ人々は、モネを素晴らしいと認め、ピカソに圧倒されたか? その作品を目の当たりにした時に、体に何かを感じたからである。そして、その生理的興奮は、「一つの体系に閉じ込もって」いた頑迷な保守主義者たちには決して訪れず、彼らは古臭い芸術理論を盲信して、「こんなのは芸術じゃない!」と罵倒し、歴史的な恥を掻いたのだった。
重要なのは、一九六〇年代に世界的に巻き起こった「カッコいい」ブームに於いても、若者たちが未知なる文化に触れ、それを素晴らしいものとして享受し、またそれに触発されて更に新しい何かを創造していったのは、基本的にこの体感主義に基づいており、それは今日の私たちに至るまで、ずっと変わらないということである。
ドラクロワ=ボードレール的な体感主義の功績は、これによって美の多様さを擁護しただけではない。同時に、何が美であるかというジャッジを、ヒューム的なエリート主義から解放し、万人に開き、言わば民主化したのである。つまり、何が美しいかについて、誰もがその生理的興奮を根拠に自説を語ることが出来るようになり、それ自体がまた作品の多様性を拡大していったのだった。
なるほど、ドラクロワもボードレールも、人並み外れた審美眼に恵まれ、且つ教養豊かな天才であり、だからこそ、多様な美に対して繊細に反応する身体を備えていたのだ、とは勿論言えよう。
しかし、彼らの体感主義は、原則的に誰にでも適用可能な方法だった。
これ以降、私たちは、新しい多様な文化に対して、誰もが、これは美しい、これは美しくないと主張する権利を与えられた。なぜなら、生理的興奮は、階級や生まれ育ちを問わず、才能を問わず、人間の基礎的な身体的条件として、平等に備わっているからである。
それは、芸術への参入障壁を、事実上、撤廃した。
これこそが、二〇世紀のモダニズム運動の大前提だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
