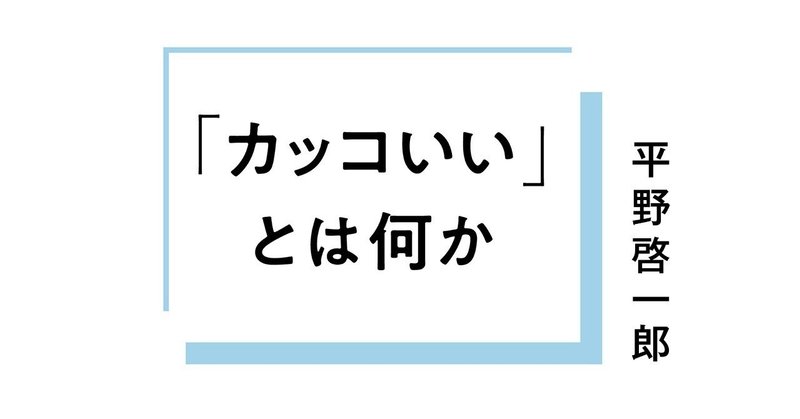
新書『「カッコいい」とは何か』|第4章「カッコ悪い」ことの不安|2文明開化と「カッコ悪い」
私たちが、自分は「カッコ悪い」と思われていないかを心配するのは、一つに、新しい環境に飛び込んでゆく時である――。平野啓一郎が、小説を除いて、ここ十年間で最も書きたかった『「カッコいい」とは何か』。7月16日発売に先駆けて、序章、終章、そして平野が最も重要と位置付ける第3章、4章を限定公開。 「カッコいい」を考えることは、「いかに生きるべきか」を考えることだ。
※平野啓一郎が序章で述べる通りの順で配信させていただきます。「全体のまとめである第10章にまずは目を通し、本書の肝となる第3章、第4章を理解してもらえれば、議論の見通しが良くなるだろう。」
2.文明開化と「カッコ悪い」
羽織袴の岩倉具視
私たちが、自分は「カッコ悪い」と思われていないかを心配するのは、一つに、新しい環境に飛び込んでゆく時である。
その世界の標準がわかっていれば、「カッコ悪い」振る舞いを回避できるわけだが、それを知らなければ、簡単に「カッコ悪く」なってしまう。一人だけ普通からズレていて、奇異な目で見られ、酷い時には笑われ、馬鹿にされる。対等な人間として扱われない。
相手に軽んじられないためには、どうにかうまく適応する必要がある。
服装など、努力して変えられる部分の話ならば、この「カッコ悪い」は、やはり表面的な問題だとも思えるが、ダサいヤツだという認識は、対人関係に大きなマイナスの影響を及ぼすアイデンティティの本質に関わる問題でもある。
一枚の有名な写真がある。一八七二年に岩倉使節団がサンフランシスコで撮影した記念写真で、木戸孝允、山口尚芳、岩倉具視、伊藤博文、大久保利通が写っているが、中央の岩倉だけは羽織袴に公家の結髪で、他はみんな洋装である。しかも岩倉は、よく見ると革靴を履いている! 何となくちぐはぐで、福沢諭吉的な野蛮(未開)→半開→文明という進歩史観で、近代的な──欧米的な──ライフスタイルの導入を是とする認識に立てば、岩倉一人が頑なな守旧派だったという印象になる。年齢的にも、木戸が三十八歳、大久保が四十一歳、伊藤が三十歳であるのに対し、岩倉は四十六歳と最年長だった。

岩倉使節団(左から、木戸、山口、岩倉、伊藤、大久保)
ところが、この写真の解釈は、どうもそう単純ではないらしい。そもそも、公家の岩倉が、武家の伝統的な服装だった羽織袴を着ているのである。
私たちは、日本人が洋服を着るようになったのは、欧化政策によるものだ、と漠然と考えている。不平等条約の改正というのは、明治政府の大きな外交的課題で、欧米諸国に蔑まれないために、和装から洋装に変えたのだ、と。
こうした対外的な理由は、勿論あったが、刑部芳則(日本近代史家)の『洋服・散髪・脱刀〜服制の明治維新』によると、むしろ国内的な事情もあったことがわかる。以下、我々の議論に必要な箇所を確認しよう。
和装は恥ずかしい?
明治政府は、皇族、公家、諸侯、藩士等の寄り合い所帯だったので、そもそも位階を有しない藩士が御所に昇殿できなかったり、昇殿の際に、公家と武家とで服装が違っていたりと、不都合が生じていた。
公家は公家、武家は武家で公私にわたって身分に応じた服制があったが、新政府ではこれがゴチャゴチャになり、対外的にも、誰が偉いのかわからないという問題が生じていた。
大体、今のようにテレビやネットもなく、顔写真付きのIDカードなどがあろうはずもない時代に、伊藤博文がどんな顔でどんな背格好なのか、全国的には(勿論、全世界的にも)知っている人はほとんどおらず、服装の統一と立場の明確化は不可欠だった。
そのため、新たな服制が策定されねばならなかったが、当初は「王政復古」というくらいなので、『延喜式』や『続日本紀』などの編纂物や法隆寺の聖徳太子像、多武峯の藤原鎌足像などを参照して、古代の官服を再現しようとしていたらしい。しかし、これがうまくいかず、結局、当時の公家が着用していた「衣冠・狩衣・直垂」をそのまま「礼服・制服・軍服」に当て嵌める、ということになった。
しかし、公武の調整は難航した。「儀礼や天皇に拝謁する際には衣冠着用とし、それ以外の昇殿には狩衣・直垂を使い分ける」、「洋服は軍服に限り、火急であっても軍服での参内は認めない」、「服制制定の目的である身分の上下を判断させるため、位階に応じて服の形状・色・素材、冠などを区別」といった基本線では合意が出来ており、また、武家は羽織袴での参内を認めるなどの柔軟な規定もあったが、いざ運用され始めると、京都御所に軍服を着た警護の藩兵が出入りしたり、羽織袴では、結局、上下の身分差がわからないなどといった問題が次々に噴出した。
明治元(一八六八)年に、天皇が初めて京都御所を出て「東京城」(旧江戸城)に入るという東幸の際にも、公家と武士との格好がバラバラで、軍服も混じっており、その光景は、かなり見苦しいものとなった。
特に藩士出身の武家は、衣冠や狩衣という公家の服の着用に苦労させられた。
刑部は、明治四(一八七一)年の興味深い珍事件として、大嘗祭に、参議であった西郷隆盛が遅刻しそうになった逸話を紹介している。儀式に向かう途中で、衣冠の紐が切れてしまい、狼狽していたのだという。
歴史上の存在感でも、実際の体格でも、〝大物〟とされている西郷だけに、公家の服に手間取って、汗だくになりながら切れた紐を結ぼうとしている姿を想像するとおかしいが、こうした「カッコ悪い」状況に、当事者たちは、大いにストレスを感じていただろう。
服制は、明治新政府の発足後、三年を経てもまだ定まらなかったが、機能性を重視し、早々に洋服が採用された軍服は、陸軍がフランス軍、海軍がイギリス軍を模したデザインとなっていた。
また、一般には、「非常並旅行服」という、戦争などの非常時と国外旅行時に限られた、軍服並びに機能的な服が、大学の学生や官僚の間に普及してゆく。彼らが外国へ行く際に洋服を着たのは、やはり和装だと馬鹿にされるからである。つまり、「カッコ悪い」思いをしたのだった。
日本で本格的に洋服への移行が進んだのは、廃藩置県後、四民平等となった社会で、実務官僚たちが、出自の違いが政治運営に影響を及ぼすことを嫌ったからだという。
「さすがに立派だったのは岩倉公」
さて、件の岩倉使節団の写真に戻ろう。
岩倉が一人だけ着物を着ているのは、実は、洋式服制の制定が、間に合わなかったからである。そのため、大統領や皇帝などに謁見する際には、従来通り、小直衣・狩衣・直垂と定められ、それ以外は洋服を着ても着なくても構わない、ということになった。他の使節団員は出発前に洋服や小物の類いを買いそろえ、アメリカ到着後も、宴会や夜会に出席するために、独自に燕尾服を購入している。特に旧幕臣出身の書記官たちは、既に留学経験もあり、当然のことだった。
また、あまり知られていないが、使節団には北海道開拓史から呼ばれた五人の女子留学生も同行しており、彼女たちも、サンフランシスコに到着するや、洋服を購入して着替えている。
服制を巡る公武の混乱の渦中で、岩倉は平服として羽織袴を着用しつつ、重要な場面では小直衣に着替えていたが、その彼でさえシカゴに到着すると、先に留学していた岩倉具定、具経という二人の息子に説得されて、ついには散髪し、燕尾服を着用するようになる。しかも、岩倉の説得を子供たちに頼んだ森有礼は、岩倉の結髪に直衣姿の写真と、散髪して洋服を着た写真とをホテルの晩餐会で並べて見せ、「古い日本と新しい日本」として紹介したのだという。岩倉は、複雑な心境だっただろう。
しかし、大礼服という最上級の正装は、依然として本国と同様の方針だったため、アメリカ大統領グラントとの謁見式では、大使・副使は衣冠帯剣、書記官は直垂帯剣を着用している。この時の逸話が、また非常に興味深い。
藩士出身者たちは、ここでも衣冠、直垂をまとうのに難儀したらしい。ところが、公家の岩倉はやはり違っていて、佐佐木高行は、
「礼式ニ習ハサル人々多ク、衣冠等ニテノ体裁、甚ダ以テ見苦敷向モ不少、自分モ其一人ナリ、流石立派ナルハ岩倉公ナリ、其ノ挙動宜敷(礼式に不慣れな人たちが多く、衣冠などをまとった格好が、甚だ見苦しい者も少なからずいて、自分もその一人だったが、さすがに立派だったのは岩倉公だった。その挙動は素晴らしかった)。」
と記録している。
明治になって、急に公家の服装を身にまとうようになったかつての武士たちは、どうしても、それをうまく着こなすことが出来なかった。しかし、同じ服なのに、岩倉が着ると、非常に「カッコいい」というのは、その生まれ育った環境のせいである。
使節団の写真の中で、一人和装の岩倉はかなり浮いているように見えるが、いざ伝統的な公家の格好をさせると、「流石立派」と敬意を払われていたのであり、本人も大いにその自負を抱いていたのだろう。
中身が肝心
とは言え、彼らの出で立ちに、現地で好奇な目が注がれたことは事実だった。不平等条約改正の事前交渉という大役を担う彼らにとって、これは甚だ不都合だった。
結局、ヨーロッパに移動し、イギリスでヴィクトリア女王に謁見するに際して、岩倉使節団は、洋式の大礼服を着用するに至る。国内でも、太政官左院でフランスの服制に倣って洋式大礼服制の準備が進められた。なぜフランスなのかというと、当時のヨーロッパでは、ナポレオンの服制が一般的な基準として広まっていたからである。
大久保利通は、この洋式大礼服のお陰で、
「随分到ル処賞讃セラレ(随分と色んな場所で賞讃され)」、「皇国ノ威権ニモ関シ面目ヲ施シ候事ニテ、岩倉大使ノ衣冠ニテ米国桑港ヘ御着節霄壌ノ感(皇国の威信にかけても面目が立ったわけで、岩倉大使が衣冠でアメリカのサンフランシスコ港にご到着になった時とは、天と地ほどの差である)。」
と誇らしげに語っている。
その後、岩倉たちが現地で導入した洋式大礼服制と、国内で太政官左院が定めたそれとの齟齬という問題が生じ、また、廃刀令に対する士族の激烈な反発があったりと、服制は必ずしもスムーズに進んだわけではなかったが、次第に文明化=洋装という考え方が定着してゆく。
刑部は、その前後の事情についても詳細に記しているが、私たちの議論にとって重要な点として、もう一つ紹介しておきたい。
西郷隆盛が、衣冠に手こずって大嘗祭に遅刻しかけた逸話には既に触れたが、当然のことながら、洋服もすぐにスマートに着こなせたわけではない。
アメリカで小直衣・狩衣・直垂では体裁が悪いと洋服を着用するようになった使節団について、理事官の長与専斎は、
「始めて西洋の衣服を着けたることとて、おのおのにしだらもなき風体にて三々五々相携え、右を顧み左を眄み市街を闊歩横行する有様は沐猴の衣冠とも謂いつべきか、往来の人々立ち止まりゆびさし合い何かささやき語らいける(初めて洋服を着たというので、各人だらしない恰好で、数人ごとに分かれて周囲をキョロキョロしながら街中を闊歩する様子は、猿が衣冠をまとっているとでも言うべきか、往来の人たちも指差しながら何か語り合っている)。」(「松香私志」)
と記している。
この有様に失望した木戸孝允は、
「近来使節連は衣服其外形ち丈は随分相調居候へとも(このところ使節たちは服装や恰好だけは随分とそれらしくなってきましたが)」「欧米之礼節等も弁へ不申、自然一般人之誹笑をも招き候様なる事に而、全国開化とは中々難受取(欧米の礼節なども弁えなければ、自然と一般人に嘲笑われることになりかねず、日本中が開化したとは中々、受け止めがたい)」(『木戸孝允文書』四)
とし、刑部は彼が、
「外見や体裁を取り繕うだけでは意味がなく、その内実をよく理解しなければならないと考えるように」
なったと指摘している。
さて、この間の消息を伝える文献に、特に「恰好が良い/悪い」という表現が見られるわけではないが、私たちはこれを敢えて、「カッコいい/カッコ悪い」という議論に引き寄せて整理してみよう。
まず、明治期に日本人が洋服を着るようになったのは、一つには、旧体制の身分制度を反映した着物を着続けたために、公的な場での服装が混乱し、非常に見苦しかったからである。つまりそれは、旧体制時代よりも「カッコ悪く」、全体としての見栄えのみならず、衣冠を着こなすのに難儀した西郷のように、武士階級出身者は取り分け、個々人が「カッコ悪く」見える場面が多くあった。また、機能性にも難があった。
他方、当然に、対欧米という意味では、衣冠や直垂は、物珍しがられ、「カッコ悪い」ものと意識された。それは単に、異なる土地の普通という基準に照らして異質に見られた、というだけでなく、日本人自らが進歩史観を導入し、洋服を文明開化の象徴として受け容れ、和装を「半開」、「野蛮」として単線的に位置づけていったからである(勿論、それに対する反動もあったが)。
つまり、和服は国内的、対外的の両方から「カッコ悪い」と目されていったのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
