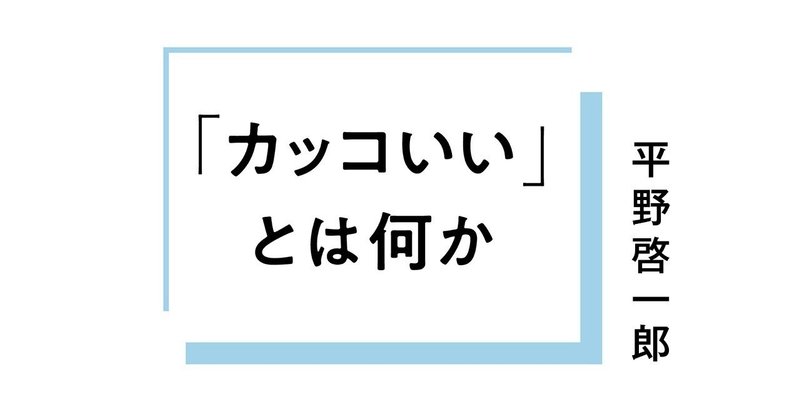
新書『「カッコいい」とは何か』|第10章「カッコいい」のこれから|4「カッコいい」は受難の時代か?
「カッコいい」には、人に憧れを抱かせ、そのようになりたいと模倣・同化願望を抱かせる力があるが、だからこそ、引き起こされる問題がある。意識的な政治的悪用は既に批判したが、もう一つは、修整の影響である――。平野啓一郎が、小説を除いて、ここ十年間で最も書きたかった『「カッコいい」とは何か』。7月16日発売に先駆けて、序章、終章、そして平野が最も重要と位置付ける第3章、4章を限定公開。 「カッコいい」を考えることは、「いかに生きるべきか」を考えることだ。
※平野啓一郎が序章で述べる通りの順で配信させていただきます。
「全体のまとめである第10章にまずは目を通し、本書の肝となる第3章、第4章を理解してもらえれば、議論の見通しが良くなるだろう。」
4.「カッコいい」は受難の時代か?
「カッコいい」と差別
しかし、「カッコいい」は、必ずしも順風満帆ではない。
むしろ今日、その転換点に差しかかっていると言うべきだろう。
まず、ネットの登場が多様化を促進し、単線的な流行を形成し難くなったために、「ダサい化」戦略が、非常に難しくなっている。また、そもそも他人の趣味を「カッコ悪い」と貶めること自体、今日では、かつてよりも遥かに強い反発を招くようになった。
殊に、この「カッコ悪い」化に差別的な視点が盛り込まれている場合には、社会的に大きな非難を招く。「カッコいい」ものを「カッコいい」として何が悪い?といったナイーヴな開き直りは、世界的に決して通じなくなってきているのが実情である。
二〇一九年に日清食品のCMアニメが、テニスプレイヤーの大坂なおみ選手を白人のような肌の色に描いて、「ホワイト・ウォッシュではないか?」と炎上する事件があった。取り分け、欧米のメディアは敏感にこの問題を批判し、ハッとした日本人も少なからず見受けられた。
CMの制作者に、差別的な意図はなかったのだろう。「色白は七難隠す」と言い、「美白」を謳う化粧品が溢れている日本の感覚で、ただ、白くした方が「カッコいい」とでも思ったに違いない。実際、イラストは、そうした、いかにも「カッコいい」テイストで描かれていた。
しかし、人種の多様性を前提とするならば、それは、肌の色に序列を作ることであり、白人の方がより「カッコよく」、有色人種はより「カッコ悪い」という意味になってしまう。取り分け、当人の肌の色が褐色であるのに、白くするというのは、差別云々以前に失礼極まりないが、これは、プロパガンダについて検証した通り、グラフィック・デザインが抱えている表面と実体との乖離という問題とも直結する。つまり、実体を何か隠すべきものとして扱う、という意味である。批判されて当然だろう。
差別は、生まれ持った、変更不可能な属性に向けてなされるものであり、そこに「カッコいい」という価値観を導入すれば、意図の有無に拘らず、「カッコ悪い」化されてしまう属性をも作り出すことになる。
人種のみならず、例えば性的指向に於いても、ゲイの人を、より「カッコよく」するという意図でストレートだと称して広告に起用したとなれば、大問題だろう。
「そんなつもりじゃない!」
とは言え、この考えはどこまで徹底されてゆくのだろうか? そんなことを言い出したら、生まれながらにして恵まれているどんな特質も、賞賛してはいけないのか?という反発も起きている。
日本では、「足が長い」とか「鼻が高い」といった身体的特徴を以て「カッコいい」とする傾向が強いが、それも批判されるべきなのか? 近代以後の「恰好が良い」にせよ、戦後の「カッコいい」にせよ、常に欧米の文化を導入しつつ、それを追求してきた日本人は、自らの体型にコンプレックスを抱き、欧米人風の身体的特徴をステレオタイプ化して無条件に賞賛してきたが、まさにその欧米自身の反省の故に、今日私たちは、そのステレオタイプ化を批判され、更に白人の身体的特徴を特権的に「カッコいい」とする価値観も否定されている。
実際に、二〇一四年には、ANAのCMが日本のタレントを金髪のカツラと付け鼻で白人に扮装させ、人種差別的だとして炎上しており、また、ダウンタウンの浜田雅功が、米俳優エディー・マーフィに扮して顔を黒塗りにし、コントを演じた際には、アメリカのミンストレル・ショーの歴史にまで遡って批判がなされた。
日本では、こうした批判に対して、「そんなつもりじゃない!」と、こちらの意図に基づく反発がよく見られる。決して悪意ではないものを、悪意に解釈する方が悪い、というわけで、これは、日常生活から外交に至るまで、この国に根深く存在している問題である。
しかし、こちらの意図を説明することは必要だろうが、いきなり感情的になるのは「クール」ではなく、相互理解のためには相手がなぜ批判するのかも知らねばなるまい。黒人差別はアメリカの問題であって、日本は歴史的に関係ない、という強弁もあるが、私たちには人類的見地も必要であろう。現実に周囲を見渡せば、今や日本でも様々な国にルーツを持つ人が生活しており、ネットでも旅行でもあらゆる人と交わり得る時代なのだから、その理屈は到底、通用しないはずである。
新しい「真=善=美」
人間を見た目の「美醜」で判断するルッキズムに対して、「カッコいい/カッコ悪い」という判断は、本来は、より多面的で、複雑なはずだった。外観がどうであれ、生き様が素晴らしければ、私たちはその人のことを「カッコいい」と評しているはずである。それは、私たちの時代の新しい「真=善=美」を批判的に創造してゆくことに他ならない。「カッコいい」は、「美人」や「ハンサム」を褒め言葉として使用し辛くなったとしても、むしろ他者に対する肯定的な言葉として、今後も有効であり続けるだろう。
その上で、笑いのネタにする、というのは確かに賛成できないが、誰かを「カッコいい」と言っただけで、同時にその他の人を「カッコ悪い化/ダサい化」することになってしまう、というのは、幾ら何でもやりすぎじゃないか?という意見もあるだろう。そんなことを言い出せば、人を褒めることさえ出来ない社会になってしまう、と。
ケイス・バイ・ケイスだが、この批判には一理あり、実際、ハリウッドで今起きていることは、多様性の肯定によって、「カッコいい」ことが相対的に「カッコ悪い」ものを生んでしまう弊害を防ごうとすることである。
具体的には、「カッコいい」ヒーローが白人男性に偏重しているのに対して、黒人がヒーローの『ブラックパンサー』や女性がヒロインの『キャプテン・マーベル』といった映画が製作されていることである。
同じ監督がすべてを撮っているわけではないが、業界として、このようなバランスが実現されてゆけば、『スーパーマン』や『スパイダーマン』が製作されても、白人男性だけを「カッコいい」化し、つまりはその他の人々を「ダサい化」している、とは直ちに批判されないだろう。だからこそ、アカデミー賞などでも、昨今はジェンダー・バランスや人種のバランスに非常に敏感になっている。それが偏ってしまえば、結局のところ、自分たちの首を絞めることになるからである。
「カッコいい」には、人に憧れを抱かせ、そのようになりたいと同化・模倣願望を抱かせる力があるが、だからこそ、引き起こされる問題がある。意識的な政治的悪用は既に批判したが、もう一つは、〝修整〟の影響である。
フォトショップの登場以来、写真や動画の「レタッチ(修整)」が一般化し、「ホワイト・ウォッシュ」問題も、大いにこれと関連しているが、昨今、モードの世界で議論されているのは、モデルが痩せすぎだという問題である。
これは、モデル自身の健康上の懸念もあるが、パソコンで画像が修整された非現実的なほどスタイルの良いモデルの写真は、単に美的な鑑賞の対象となるだけでなく、「カッコいい」存在として社会に影響を及ぼすことになる。すると、それに直接憧れる若い女性も、またその極端な痩身が模範化されることで、自分の体型を「カッコ悪い」と感じ、痩せなければと思いつめてしまう女性も、挙ってダイエットをするようになる。
しかし、ロック・スターやスポーツ選手に憧れ、必死に努力するのとは違い、そもそも現実に存在しない、写真修整技術で作られた体型になるためには、病的なダイエット以外に方法がない。従って、修整済みの写真は、その事実を表示すべきだ、という動きが出ている。これは、「カッコいい」の影響力を自覚し、倫理的にどのようにコントロールしていくか、という取り組みの一つの実例だろう。
私たちは、結局のところ、「カッコいい」存在に「真=善=美」を期待している。さもなくば、それは、社会の「人倫の空白」を埋める機能を果たし得ないからである。
倫理的な配慮を欠きながら、「カッコいい」の動員と消費の力を利用しようとする態度は、今後、ますます難しくなってゆくはずである。
若者は勝てるか?
「カッコいい」とは何かは、時代とともに変化してゆく。
近代以降、長らく個人のアイデンティティは、労働と消費、それに余暇の活動が担ってきた。仕事にやりがいを感じているならば、職業がそのアイデンティティを支え、余暇をこそ重視してきた人は、何を買い、所有しているかを誇り、また、趣味やボランティア、友人とのつきあい、恋愛などが生き甲斐ということもあっただろう。
しかし、今後、景気の悪化や自然災害、AIの発展などで、多くの失業者が出てくれば、自分のやりたい仕事をしていると自慢することも、誇示的な消費も、「カッコ悪い」と見做されることになるかもしれない。既に日本に関しては、平成の長いデフレ経済下の価値観が、「カッコいい」の判断にも大きな影響を及ぼしている。
「カッコいい」がビジネスの上でインパクトを持ってきたということは、裏を返せば、「カッコよく」なるためには金がかかる、ということであり、だからこそ、「カッコ悪くない」ファストファッションで十分、という考えにもなる。
実際、ネットを通じて様々なサーヴィスがタダで利用でき、シェアリングが普及し始めると、それらを活用して、いかにローコストで、いかに身軽に生きるか、ということの方が、遥かに「カッコいい」という価値観に傾くかもしれない。バリバリ働いて、ジャンジャン稼いでパーッと使う、などというのは、ダサいことなのだ、と。
職業に関しても、ユーチューバーのように従来通りのキャリアのイメージとは異なった新しい方法で収入を得ている人たちが、若い世代からは「カッコいい」と共感を集めている。また、VRの中で行うeスポーツの人口なども、急速に増加している。
また現在でも、SNSのアイコンを動物の写真やアニメのキャラクターにする人がいるように、VR空間内では自分とはまったく異なる「カッコいい」アバターを──それも複数──使用することが出来るし、こうなると、表面と内実との乖離は、当然の前提となるだろう。
政治意識の高さは、人間の活動の一つとして、古代ギリシアの「アンドレイア」以来、「カッコいい」こととされてきたが、それが「ダサい」とされてしまえば、政治への無関心は強くなる。SEALDsのような運動は、そういう時代の新しい「カッコよさ」を目指して、国民に政治参加を呼びかけるものだった。
日本の懸念としては、やはり、少子高齢化が挙げられるだろう。というのも、「カッコいい」の世代間闘争は、人口のグラフがピラミッド型であればこそ、新しい価値観の若者たちが勝利することが出来るからである。猶且つ、若者たちが裕福であることも重要だろう。そこにヴォリューム・ゾーンがあれば、どれほど年寄りが顔を顰めても、ビジネスは若者の「カッコいい」を中心に動いていくのである。
ところが、〝棺桶型〟になってしまえば、社会は、いつまでも古臭い「カッコいい」に依存せざるを得ず、つまりは、既に「カッコ悪く」なってしまった文化が更新されることもなくメインストリームであり続ける、という事態が生じる。残念ながら、その兆候は既に見えているだろう。
テクノロジーと「カッコいい」
今日のテクノロジーは、「面倒臭さ」に焦点を当て、それを生活の中からいかに駆逐するかに躍起になっている。eコマースも、IoTも、自分で体を動かしてすればいいことを率先して代替していっているが、そうした風潮によって、「面倒臭い」ことは、まさに「ダサい化」しつつある。
プロダクト・デザインはディーター・ラムス以降、深澤直人やアップルのジョナサン・アイブなど、機能主義的なミニマルなデザインを発展させてきた。ファッションではリアルクローズからノームコアまでと「着やすさ」が重視される傾向になるが、それらはいずれも、この脱「面倒臭い」と相性が良かった。
今日、私たちがスポーツカーに乗っているのを見て、あまり「カッコいい」と感じないとすれば、何となく、面倒臭そうな感じがするからだろう。
しかし、好きな人にとっては、その面倒こそがいいのだとも言える。かつて私たちが音楽にあれほどまでに「しびれた」のは、レコードやCDを手に入れるための手間にじらされたからでもあった。新譜の発売日にレコード店に駆けつけ、家に帰るなり、荷物を放り出してプレイヤーに飛びついたあの時の興奮は、ネットで音楽を聴くことが当たり前になった今では失われて久しい。結果、私たちは以前よりも音楽そのものに「しびれ」にくくなっているかもしれない。
将来的に、いつまで人が「カッコよさ」を求め続けるのかはわからない。しかし、「カッコいい」には、人間にポジティヴな活動を促す大きな力がある。人と人とを結びつけ、新しい価値を創造し、社会を更新する。
私たちは、「カッコいい」の、時に暴力的なまでの力を抑制しつつ、まだ当面はこの価値観と共に生きてゆくこととなるのではあるまいか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
