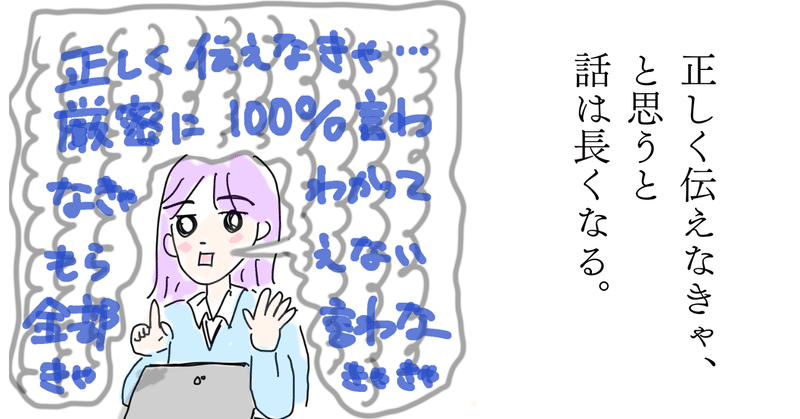
正しく伝えなきゃ、と思うと話は長くなる。
そのことについて、
ちょっとかじったぐらいの時は、
わかった気になって、
あれこれ書けたりするんだけど
勉強すればするほど、
「奥にとんでもない広がりがある」ことがわかって何も書けなくなる。
何か一つを例にとっても、
「いろんなケースがある」ことがわかってくると、
安易に断定できないし、
話はどんどん長くなる。
安易に断定して、これしかない、と言えればラクだけど、
それは正確ではない。
こういう葛藤は、専門分野を持って仕事をしている人が抱える、
しごく真っ当な感情だと思う。
「文章は断定的に書け」で、いいんだっけ?
それに目を向けずに、「文章は断定的に書け」とか、
「長い話は読まれない」とかバッサリ切るのは
なんか違う。
学べば学ぶほど、わからなくなる。
「わかった気」になっていた自分が恥ずかしくなる。
だからもっと知りたくなる。
探究という名の、深い森の奥の奥へ歩を進めて、気づいたら沼である。
私は、人に対しても、ビジネスに対しても、自分に対しても
「わかった気にならない」ことを大事にしている。
「わかった」と思ったらそれで終わりだと思うから。
一生をかけて、わかんないな、自分は小さいな、まだまだだな、と泣きながら愚痴りながら進んでいくんだと思う。
人は「断定してくれるもの」に弱い。
自分で決めなくてもいいから。
人間の脳は「あやふやなこと」をがまんできない。
決めないと気持ち悪いから。
でも、断定できないこと、言葉になんかできないことこそが、
「その人の深み」であり「奥行き」なんだと思う。
言葉にする、という仕事をしているからこそ、
「言葉にできること」だけが全てじゃない、ということに打ちひしがれるし、
言葉になんかできないことを大切にしていきたいと思う。
わかりやすく伝えるために、できる4つのこと




結局、「いま、相手が求めているのは何か」を掴むことが全て。
相手が求めている解像度で、
相手が求めている言葉で、
相手が求めている順番で、
相手が求めている内容を、伝える。
自分が不安だから、詳しく伝えなきゃ!ではなく、
相手がどれぐらいのレベル感の話を求めているかを掴む。
「ただしく、丁寧に、厳密に伝えなきゃ」は、相手のことを考えているようで、結局は、自分が不安なだけかもしれない。
「受け手側」と一緒に成長していく、という感覚が今っぽい
一方で、どこまで詳しく書くか、伝えるかを考えたときには、
読み手、聞き手、受け手側のリテラシーや、理解力も大事になってくる。
だから、発信者は自分のメディアで繰り返し繰り返し伝えて、読者やフォロワーさんと一緒に成長していく、というスタンスも必要なんだろうなと思います。
いきなり、自分の言いたいことを、短く切り取って1回だけ伝えただけで、全てが伝わるわけではない。だから繰り返し発信する。
言葉で仕事をつくるメルマガ
さわらぎ寛子のラジオ
さわらぎ寛子の書籍
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
