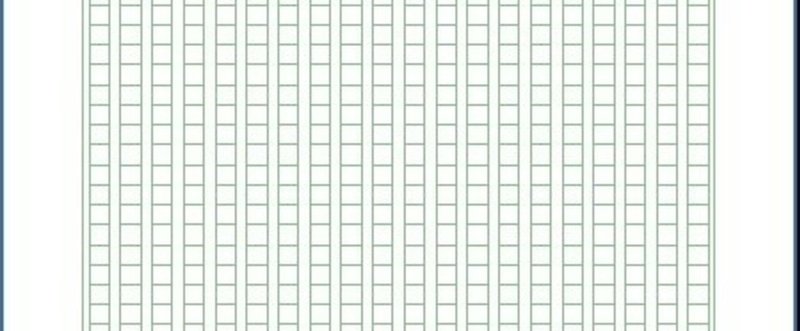
永遠の高嶺のフラワー、その街の名は神戸。
仕事で縁のあった呉高校が甲子園に初出場するので、応援のため私は妻を半ば無理やり連れて西へ向かった。試合は朝の第一試合だということで、私たちは神戸に前泊することにした。
久しぶりの三宮、元町を歩く。私は関西出身とはいえ、出自は奈良である。しかも高校生までしかいなかった。奈良の高校生から見る港町神戸は地理的にも、気持ち的にも遥か遠くにあり、同じ関西圏だからといって、全く詳しくもなく、また懐かしくもない街なのであるが、その分イメージだけが膨張して、ただただ憧れと偏見だけはある。
東京でも見ないほどのハイブランドの巨大な路面店が密集した通りを抜けると、雑多ではあるがどこか品のあるこじんまりとした中華街が現れ、美味しくて安い北京ダックなんかを食べ歩きをしているといつの間にか夜景と海が広がっている。関西圏特有のコンプレックスも手伝って、そんな神戸は未だに何故か緊張する街であった。
しかし私もいい年齢の大人である。ちょうど前夜にカラオケバーで改めて青春が終わったことを痛感したほどの大人である(前日投稿参照)。神戸牛のひとつでも食べてやる。ただ食べるだけでなく、当たり前のように食べてやる。そう決めていた私は、予約をしていた鉄板焼きの有名店へ向かった。超高級店というわけではないがそれなりに奮発したその店はカウンターが15席程度。
しかしそこにもあった「神戸感」。
私たち夫婦の隣の席にいた家族連れ。彼らが絵に描いたような、いや私の偏見という絵筆がコンプレックスという絵の具で描いたような「神戸の家族連れ」だったのである。お洒落を主張しすぎない小綺麗な良い物を着ている60代の父親、若い頃はさぞかしが服を着ているような母親、関西人らしく明るくよく喋るが愛されて育ったが故の笑顔の華やかさがそのお喋りを決して下品に見せない20代の娘、そして一見地味かつ寡黙でヲタクっぽいが年齢のわりにとてもキレイな食べ方をする大学生の息子。そしてそんな家族は、定年を迎えた父親へのお疲れ様会をしていたのである。これが神戸。店内には神戸牛を食べる前から神戸牛以上の神戸感(私にとっては)があったわけである。
滞在数時間で神戸に完敗した私は、まだ夜景とか見たいと言う妻を説得し、いろいろとお腹いっぱいで宿泊先のホテルがある甲子園駅に向かった。三宮駅から甲子園駅は阪神電車で20分ほどの道のりである。電車は土曜日ということもあり座席は空いておらず、私たちは旅の疲れもあったが立って発車を待った。
すると前の座席に座っていた女子高生4人組みが何やら盛り上がっていた。彼女たちは「JK」などと呼ぶには良い意味でスレておらぬ雰囲気で、黒髪で、スッピンで、吹奏楽部だった(休日練習なのだろう、ひとりがバイオリンを膝に乗せていた)。しかし盛り上がっている理由はやはり恋愛話だったらしく、ムードメーカーらしい彼女が恋をしたがっていて、その思いを大袈裟に話しているようであった。そこまでなら私も気にはとめない。しかしムードメーカーちゃんの隣に座る女の子が発車を待つ電車の車窓からホームを指差してこう聞いたのだ。
「あんなんがしたいってこと?」
彼女が「あんなん」と指差したのはホームにいた20代のカップルだった。それはまあ美男美女で駅のホームにも「神戸感(私にとっては)」なカップルであった。男はしっかりと固めた短髪に、日々の摂生を感じさせるタイトなニットの上にダウンベスト。女は巻いているようで巻いていないようで巻いているロングヘアと、ファッションに疎い私ですら茶色ではなくキャメル!と呼びたくなる絶妙な色味のコート。そして恋バナ中の女子高生が「あんなんがしたいってこと?」と言いたくなる嫌味のない絵になるイチャつき具合。
しかし美男美女に罪はないのだが、直後彼らのタイミングが悪かった。いざホームから電車が動き出すまでの数十秒間、彼女は何やら彼氏の目元についたゴミか何かを取ろうとしていたのである。繰り返す。美男美女に罪はない。しかしムードメーカーちゃんが友だちのひとりが「あんなんがしたいってこと?」と聞かれて見たときの「あんなん」は彼氏の目元のゴミをとる彼女の姿だったのである。
「アホか、男の汚ったない目ヤニなんかとりたないわ」
ムードメーカーちゃんはわりと大きな声で言った。友だちも大笑いした。私の視界には爆笑している女子高生たちと車窓越しに目ヤニかは分からんが目元のゴミを取り取られしている美男美女が同居した。
私は思わず声を出して笑ってしまった。もちろん何の罪もない美男美女を笑ったわけではなく、女子高生の会話のセンスに笑ったわけであるが、女子高生たちも目の前に立つオッサンが自分たちの会話で声を出して笑ったと気がつくと、さらに「目ヤニはいかん」「まだ靴下は許せる」「塩顔なら許せる」などとワケのわからん会話を続け、明らかに私を笑わそうとしてきたのである。
観念した私はついに彼女たちに「あかん、君らオモロイわ」と言った。そのときの女子高生の表情は、大人が仕事をしていてもなかなか出せぬ達成感に溢れていた。しかし達成感を得た彼女たちは、次の瞬間から何事もなかったように面白くもない部活の話をしはじめ、まさに出番を終えたコメディアンの如き切り替えを見せた。
東京育ちの妻は電車で見知らぬ人同士が会話をするという状況に戸惑っていた、というより自分の夫が女子高生にいきなり話しかけて問題にでもなりやしないかという不安を覚えていたかと思うが、私は自らが引き起こしたこの状況を懐かしく思っていた。これは別に関西圏に限ったことではなく、田舎にはよくあることだった。そして今日一日改めて自分勝手に「神戸感」にやられていた私は安堵もしていた。憧れ、恐れ、僻んでいた「パーフェクト神戸」にも可愛いところがある。私、神戸に親近感持ってもいいですか?などと思い始めたときである。
女子高生のひとりが膝に乗せていたバイオリンケースを落としたのである。それはわりと派手に私の妻の足に落ち、妻は小さく「痛っ」声を出した。
するとだ。その女子高生は先ほどまでのテンション、芸風は何処へやら、大人が惚れ惚れするほどしっかりとした謝り方をしてくるではないか。黒髪で、スッピンで、吹奏楽部で、恋に恋するけれども友だちと話している方が今はまだ楽しい。そんな女子高生がバイオリンケースを落としたことを丁寧に謝るのだ。もう一度言う。「バイオリンケース」を落として謝るのだ。
私たちはもちろん恐縮して「いいよ、いいよ」と言うしかなかったわけであるが、私は心の中で思うのである。
ここまできてまだ顔を出すか「神戸感」と。
などと長文を今ホテルの一室で書いているのは、私のイビキが酷いため、せめて妻が深く寝付くまではと言われもせぬのにひとり起きていて暇だからである。この優しさのようなものはもしかして「神戸感」であろうか、私にも知らぬ間に備わっていたかと一瞬喜んでみたが、そんなはずはない。分かっている。
これはただの「メタボ感」である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
