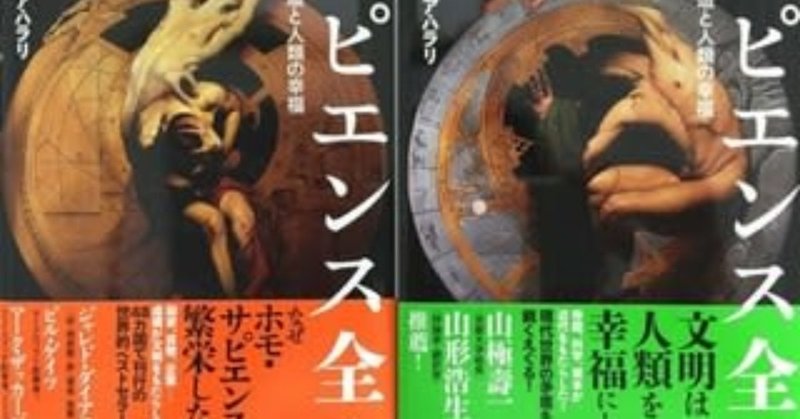
信仰とは、卵の殻である。
『サピエンス全史』という著書がある。
日本でも累計100万部を突破しているベストセラーなので、読んだことがある方も多いかもしれない。
『サピエンス全史』は、その名の通り、ホモ・サピエンス(我々現生人類の学術名)の発生から現在までの全ての歴史について書かれた本である。
しかし従来の歴史書と違って、歴史学・考古学・生物学的な視点だけではなく、文化人類学や主に社会学的な視点も取り入れて「なぜホモ・サピエンスはこの様に繁栄したのか?」について述べているのが本書だ。
内容は多少難解ではあるが、実に面白く、一読をおすすめしたい著書の一つである。
本書を特におすすめしたい理由の一つは、現代と歴史を結び付けて論じている点である。
単に歴史について説明するだけでなく、「なぜ、現代はこのような社会になっているのか?」を、歴史的な観点から説明してくれている。
「今」とは、「過去」の積み重ねによって成り立っている。
そしてその積み重ねのことを「歴史」と呼ぶ。
「歴史を知れば、現代についてよく分かる」ということを、この本は何よりも証明してくれている。
その点で、本書は歴史と共に「現代」について論じている書であるとも言える。
さて、前回のnote「宗教の衰退の原因と、残された3つの生存戦略https://note.mu/hitokotohanashi/n/n9579011df64b、」において、宗教がなぜ現代日本社会において衰退しているか、について述べてきた。
本noteでは、その歴史的な要因について、述べていきたいと思う。
自由 VS 信仰
さて、少し難しい提言から論じ始めていきたい。
「信仰」とは、ある意味においては、人間の自由意志を神などの超越的存在に譲渡することであるとも言える。
これはどういうことかと言えば、人間は何でも自由に考えることができ、何でも自由に行動ができるが、そこに「信仰」が入ると、その自由に多少の制限がかかる。
神の意志に反するような思想や、行動は、信仰者にとっては慎まなくてはならないものとなる。
つまり、人間が「自由」を神に献上すること、こそが「信仰」であるとも言える(天理教の教理においてはこれは成り立たないことは注記しておく)。
しかし、その意味での「信仰」があったお陰で、人類がここまで発展してきたというのも、歴史的に見れば事実なのである。
思うに、信仰とは、人類の精神的進化の過程において、卵の殻のような働きをしてきた。
卵の殻、というのが分かりにくければ、母親の子宮、と言い換えても良いかもしれない。
人間の精神がまだ未成熟で、規範も道徳も倫理も無い頃には、人類の自由意志とは非常に危険な物であった。
それこそ、自由に殺し合い、奪い合い、自然を破壊することを咎めるものがなかったし、また感染症から逃れる術も持たなかった。
そんな人類を最初に救ったのが「信仰」である。
目に見えない超越的な存在を想像することは、人類を非常に謙虚で慎み深い種族へと一変させた。
信仰が、「自由」を「慎み」に変えたのである。
そのお陰で、人類は協力し合うことを知り、ここまで発展してきたのだと言っても過言ではないと、私は考えている。
信仰という卵の殻の中に納まって考えている限り、結果的に人間は守られることになったのだ。
しかし、卵の殻(子宮)の中にいることで人間はどんどん成長する。
その内に法律というものを作り、哲学などを考え、倫理・道徳・規範のようなものが確立されてくる。
そうなると、急に「信仰」が、人間の自由な意思を束縛する、鎖のように思えてくる。
ちょうど、一人立ちを始めた少年が、母親から庇護されることを嫌がって、反抗期に陥る感覚と似ている。
そうして起こったのが「ルネサンス」である(ここでの「信仰」や「宗教」は、主にキリスト教のものを指している。全ての宗教に通じるものではない)。
14世紀から16世紀にかけて西欧で起こったこの動きは、「神中心」であった価値観を、「人間中心」の価値観に書き換える運動であったとも言える。
つまり、人間は「信仰」という卵の殻を割ることによって、「自由」を勝ち取ったのだ。
そして、現代の科学の発達や、高度な社会制度の確立も、全てこの信仰の克服と自由の獲得という出来事の延長線上に起こってきた事柄である。
なので、現代において、信仰とは必要の無くなった「卵の殻」のようなものだと言うのである。
現代の人類は、せっかく手に入れた自由を再び手放して、子宮や卵の中に逆戻りすることには、潜在的な抵抗を感じている。
それが、現代において「信仰」の素晴らしさを再び説くことは、非常にハードルの高いことだと言える理由である。
では、こんな状況が、この先いつまでも続いていくのかというと、そうではない。
いや、そうであってはならない。
現代人類が共有している思想の中で、今最も幅広く受け入れられているものは、「自由主義」の考え方だろう。
この自由主義というのは、一つのイデオロギーではあるが、その実、宗教と何ら変わりのない一つの教義である。
「自由主義教」の教義とはどのようなものであるか、簡単に説明しよう。
「人間は、全ての個人が、生まれながらにして「自由」と「人権」を持っている。そして全ての人間は、他の「人権」を害しない限り、いかなることでも「自由」に行うことができる」
といったものだ。
こう聞くと、最もな教えだと思われるであろう。
日本人である我々も、実際に学校でそのように教育されてきたからだ。
しかし、実はこの教義は現在、確実に「破綻」に向かって進んでいることに気付いている人は、今はまだ少ない。
その原因は、「自由主義」が、「人間中心主義」の上にあって初めて成り立つものだからである。
自由主義が唱える思想の主語は、「人間は、」で始まる。
そして、「自由」も「人権」も、人間だけに与えられたものである。
そして人間は、他の「人間」に迷惑をかけない限りは、何でも自由にすることができるのである。
自由主義とは、まさに人間中心主義の考えに外ならない。
しかし、昨今の地球温暖化に代表される環境問題は、人間の行き過ぎた「自由」は、回りまわって自らの首を絞めることを教えてくれた。
人間だけではなく、「自然」へも配慮しないと人間は生きてはいけないのだ。
さらに、「自由」表現の最終形態である「戦争」は、度重なる世界戦争と兵器開発の行き過ぎにより、人間をいつ滅亡してもおかしくない絶滅危惧種にしてしまった。
現代世界における主要国が揃いも揃って掲げんとしている「自国中心主義」も、「自由」の成れの果てである。
「自由」とは、とても甘い蜜であると同時に、劇薬でもある。
行き過ぎた自由は、必ずいつかその自由を行ったものを破滅に追いやる。
そして、人類が自由によって殺されんとする日は、そう遠くない未来まで迫っていると感じられる。
かつて、人類が自由によって滅びようとしていた時、「自由」を「慎み」に変えて救ったのは「信仰」であったと言った。
それと同じことが、今人類史の中に、必要とされているのかもしれない。
そもそも、自由主義の基となった「人間中心主義」を、人間に教えたのはキリスト教・イスラム教に代表されるセム系一神教である。
人間が信仰から自由を勝ち取れたのも、そもそもは信仰という卵の殻の中で守られながら精神的に育っていく過程の中で、自由という概念を育てることができたからである。
宗教は、人間にとっての精神的母親の役目を果たしてきたのだ。
しかし、現代は歴史的に宗教に守られすぎた(違う見方をすれば縛られすぎた)ことによる反動で、宗教に対する反抗期が起こっているというのは、既に述べた通りである。
反抗期はいつまでも続きはしない。
しかし、反抗期を経た全ての親子が、再び良好な関係を築けるわけではない。
反抗期を経た後には、再び良好な関係を築き直せるか、「無関係」へと至っていくかのどちらかである。
これから、人間と宗教が、良好な関係を取り戻せるのか、無関係へと進んでいくのか、今はまだ分からない。
しかし、「歩み寄り」が無ければ、無関係へと進むのは必至である。
「子ども」から自然に歩み寄ってくるのか、「母親」の方から歩み寄っていくのかは分からない。
が、現代社会の混迷と、先行きの見えない不安は、宗教の責任の負うところも少なくはない。
宗教は、そんな現代において、人々に対して何ができるのか、どんなメッセージを発信できるのか、真剣に考え、実行に移していかなくてはならないと思う。
そうでなければ、信仰はいつまで経っても、卵の殻のままである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
