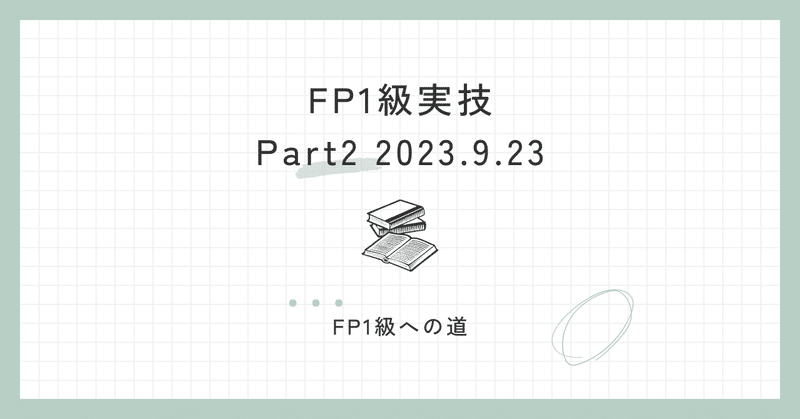
FP1級実技 Part2 2023.9.23
試験問題
ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 試験問題:2023年9月1級実技試験 | 一般社団法人 金融財政事情研究会 (kinzai.or.jp) より
メモ
問題文を読みながら、ポイントをメモしていきます。
Aさんは大きな家に住み替えたい
甲建物の管理をやめたい
甲土地(の借地権)を売るか、借地権と底地を交換するか

解答
必要な情報(聞くこと)
甲土地の賃借の内容、資料の有無
Aさんの年収(所得)、妻の年収
必要な家の面積
地主の承諾は得られそうか
リフォーム⇒自宅or賃貸に出す意向はないか
2022年の相続税の額
必要な情報(調べること)
甲土地の登記記録
甲土地の都市計画や建築制限
甲土地付近の不動産価格の相場、市況
甲建物の図面など(リフォームの可能性)
Aさんの、住宅費と教育費をふまえたライフプラン
売却する場合に必要な承諾
借地権の譲渡の承諾が必要です。
注意するのは、必ず建物を残したまま借地権の譲渡の承諾を得ることです。借地権はその土地上に建物があるときだけ存在する権利なので、建物が古いからと言って先に解体してしまうと、借地権が消えてなくなってしまいます。
また、借地権の譲渡の際には「承諾料」という費用が発生するのが一般的です。承諾料は借地権者が地主に支払い、相場は借地権の額の10%なので、このケースの場合おおよそ900万円程度の承諾料が必要になると考えます。(9000万円×10%)
なお、地主がその土地を使いたいなどの理由で、第三者への譲渡を承諾してくれない場合も考えられます。家を取り壊せば、借地権も同時に消えるので、地主としては更地にして土地を返してもらい、一円も払わないで借地権が戻ってくるのですから理想的です。
そのような場合に借地人が知っておくべきは、裁判所が地主の代わりに許可をだす制度があるということです。ただし、この許可にも一定の費用が必要です。
売却する場合の課税関係
不動産の譲渡になるので、売却額から費用を引いたものが譲渡所得になります。不動産の譲渡所得は分離課税で、10年以上所有していたので、長期譲渡所得の特例を使うことができます。
費用には取得費と仲介手数料、承諾料、2022年に支払った相続税のうちその土地の借地権に相当する額などが含まれます。
なお、自用地であれば相続の日から3年以内に空き家を除却し、更地として土地を譲渡すると「空き家の譲渡所得の特別控除」を使うことができますが、借地権にこれを使用することはできません。なぜかというと、更地にすると借地権がなくなるからです。
借地権と底地の交換
図から借地権割合は60%と読み取れるので、借地権と底地の交換により、Aさんは甲土地の60%にあたる180㎡を所有することができます。
この場合、固定資産の交換の特例が使えます。今回の交換では本来、借地権の時価9000万円からもともとの借地権の取得費用1800万円と更新費用1000万円を引いた6200万円が譲渡所得となるのですが、この特例により現時点での譲渡所得は発生せず、100%繰り延べされます。
交換後に古い建物を除却し、新しい自宅を建設することになります。この場合、Aさんの土地は自用地、建物は自宅として評価されます。
関与する専門職業家
土地家屋調査士…甲土地の分筆登記
不動産鑑定士…甲土地の鑑定評価
司法書士…所有権の移転登記
税理士…甲土地の譲渡や交換にかかる課税関係の相談
宅地建物取引業者…甲土地を譲渡する場合、仲介を依頼
感想
ここに書いていること、確信持てませんので、信じないでください。
特にAさんの相続時の評価が疑問です。普通に自用地しかないと思うんですが、問題になっているくらいだから何かあるはずなんです。それが何かわからない。(つд⊂)エーン
それではまた、FP~(@^^)/~~~
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
