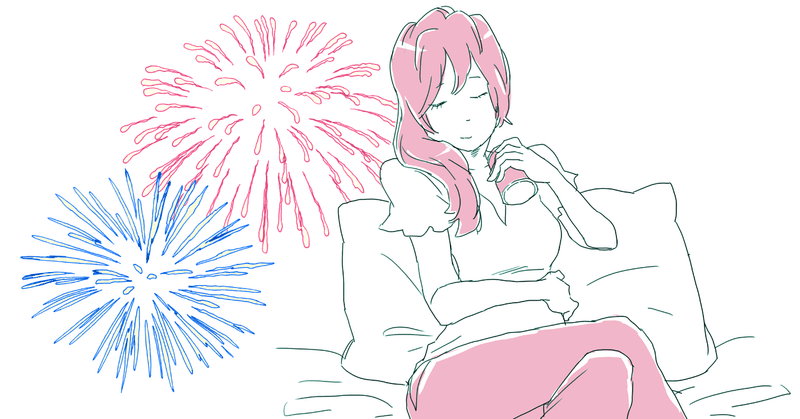
遠い夏の日の花びらのかおりに、想う。
いまでも時々、あなたのことを思い出す。
休み時間の廊下であなたとふたり、窓の外の青空に浮かぶ真っ白い入道雲の、もくもくと盛り上がった天辺あたりを眺めながら、わたあめ食べたいねえ、いや、かき氷じゃねえ?なんて、他愛ない話をしていたら、
「花火、見に行かない?」
不意に訊かれて、わたしは少し緊張しながら答えた。
「いいね。じゃあ沖さんも行けるか、訊いてみる。澤井さんは来れるのかな?」
「来れるんじゃない?訊いとくよ」
あなたは少し何かを考えるように視線を泳がせた。そうだなあ、とちいさく呟く。
「混むしさ、早めに行って場所取りして、向こうで何か買って食おうよ。敷物ひろげてさ」
「なんだかお花見みたいだね」
思わず口元がほころんだ。みんなで敷物の上に並んで座って、お弁当やおにぎりを食べながら花ならぬ花火を見上げてるさまを想像すると、小学校の遠足みたいでなんだか胸がくすぐったい。
「いいじゃん。夏の花見」
あなたも歯を見せて少年みたいににかっと笑った。
花火の当日、午後6時。最寄りの駅の改札を抜けた所で待ち合わせた。
わたしが一番乗りで、駅の屋根の柱に軽く背中を預けて待った。辺りはほんのりと薄いベールを一枚ずつゆっくりと重ねていくように、穏やかに暮れ始めていた。改札をくぐる人の大半が駅前のロータリーを曲がって河川敷へ向かっていた。わたしの脇を大輪の花をあしらった紺色の浴衣姿の女性が通り過ぎる。可愛いな、なんて目で追って眺めた。
花火に誘われたとき、一瞬、ふたりでって意味なら良いのにと思って、緊張した。でもそんなのはすぐに頭の隅へ追いやった。本当は浴衣も着たかったけれど、恥ずかしくってやっぱり止めた。
わたしはぼうっと空を見た。よく晴れた空に雲がちいさな群れを作っていた。海の魚が泳ぐみたいにみたいで気持ちよさそうだった。あなたにそう言ったら俺も泳ぎたいって言い出しそうだな、なんて考えていたら、
「早いなあ」
と、すぐ近くから聞き慣れた声がした。
声の方へ振り返ると、隣にあなたが立っていて、胸の奥がちいさく騒いだ。静かな水面が風に揺らされるみたいだった。いつ頃からかこんな風に、あなたの近くにいると落ち着かない。
間を置かずに沖くんと澤井さんが連れ立ってやってきて、改札の向こう側からわたしたちに手を振った。あなたはすぐにふたりに気付いて、「なんだ、同じ車両だったのか」と笑いながら手を振り返した。
駅前のコンビニエンスストアは混み合っていた。みんな考えることは同じだった。レジにも長い列がついている。
「こっちに来る前に買っておけば良かったなあ」
わたしは言いながら、ペットボトル飲料が並ぶ棚へ向かった。大きな冷蔵庫の扉を開けて中に手を伸ばすと、暑さでほっていた肌に冷気がふわりと触れて気持ちよかった。
「飲まないの?」
すこし後ろから声がした。わたしが振り向くと、
「だって花見じゃん」
と缶ビールを片手にあなたがにかっと笑った。
あなたが笑う度に、こころがふわっとあったかくなる。そして、不安定に揺れる。胸を打つ音があなたに聞こえてしまわないかと、焦る。わたしは心の尻尾が出ないように気を付けながら、缶ビールが並ぶ棚を眺めた。青い缶、琥珀色の缶、白や金、銀の缶。改めて選ぼうとすると、種類が多くて迷ってしまう。せいぜいラガーか麦100%か発泡酒かの違いしかわからないから、いつも大体同じものばかり飲んでいる。
「たまにはちがうものが飲みたいなあ」
わたしが呟くと、
「これ、うまいよ。香りもいいし」
あなたは棚の扉を開けて一つ選んで手に取ると、そのままわたしに差し出した。受け取った缶はよく冷えていて、触れていると、すこし指先が痛い。
「香料で匂いをつけてあるの?」
扉がパクンと閉じる音を聞きながら、わたしは缶の側面の文字を拾った。原材料の欄には香料とは書かれていない。
「麦芽とホップの種類で変わるんだ」
と、あなたが答えた。
「ふうん、そうなんだ?麦芽は麦の芽でしょ?ホップって、なんか、音感からふわっとしたものな感じがするけど」
「麦芽は一度発酵させて乾燥させるんだ。乾燥さす温度で麦芽の味が変わる。チョコみたいに甘かったり、苦かったりする。で、ホップは植物なんだ。松ぼっくりを白くした感じで、ぱっと見、花みたいなやつで、苦味と香りの素になるらしい」
「やけに詳しい」
「俺もポップがなにかわからんくて調べた。いつも飲んでるもんなのによく知らんなあって思ってさ」
「ふうん。そういうの調べちゃうくらい、ビールが好きなんだねえ」
わたしがしみじみ言うと、
「すげえすき」
と、嬉しそうににかっと笑った。
「俺、めっちゃ飲むよ。ジョッキに五杯くらい、全然平気」
「ビールでおなか一杯になっちゃうよ」
あなたに笑い返しながら、すげえすき、に無駄にドキドキしているわたしは、かなりしょうもない。
広場をくるりと見渡すと、まわりのひとたちは、みんな同じように敷物を広げて、思い思いにくつろぎながら、花火が打ち上がるのを待ちかねていた。わたしたちも空いているスペースに敷物を広げながら、ここがいいかな、木が邪魔じゃない?あっちのほうがいいよ、砂利でデコボコしてて座りにくくない?なんて言い合った。
「やっぱりお花見みたいだね」
座りながらわたしが言うと、
「いいねえ」
と、あなたが可笑しそうに笑いながら腰を下ろした。すぐ右隣にあなたが座るから、体の右半分が、肩と腕と指先が、緊張でひりひりした。
今日見た雲の話をしたら、やっぱりあなたが泳ぎたいと言い出して、じゃあ今度海に行こうかとか、それなら浮き輪がいるねとか、いやいやビーチボールでしょうなんて、みんなと話しながら待った。そうこうしているうちに空が音もなく藍色に染まり始めた。広場にいる人たちも気もそぞろに、もうじきかなと囁き合っていた。
「何時からだっけ?」
あなたが缶ビールのプルタブを開けながら訊いた。辺りにほろ苦い香りが広がる。
「たしか、七時半から。九時までには終わるのかな。帰りの電車、すっごく混むだろうね」
わたしは緊張をごまかすみたいに笑った。へんな笑い方になっていても、もう暗くて見えない。わたしはなにもしないで座っているのが落ち着かなくて、あなたの腕に触れてしまわないように気をつけながら、缶ビールを開けた。
口に含むと、ぬるくなったほろ苦さが喉を通り過ぎていく。炭酸の泡がしゅわっと小さくはじけて消えて、花に似た香りがふわりと広がる。思わず「あ」と声がこぼれた。
あなたが声に気づいてこちらに顔を向けたので、ほんとだ、いい香りするねって、続けようとしたけれど、「開演間近です」との場内アナウンスがどこからか流れてきて、言葉が途切れた。
どん、どどんと、花火が打ち上がる音が、体の奥まで重く響いた。
まるで内側で太鼓が鳴っていると錯覚するほど、お腹の底に響く。真っ暗な空に大きく開いた色とりどりの花火が、空一面に光る花びらを散りばめるたびに歓声が上がる。わたしも思わずため息とともに呟いた。
「きれいだねえ」
花火が綺麗なのが嬉しくて、それを一緒に見られるのが嬉しくて、つい、あなたの方を向いた。あなたは僅かにこちらに顔を向けて、
「うん」
とだけ呟くいて、また、空に咲く花を仰いだ。
どん、どどんと、空に、体に、音が響く。花火の鼓動みたいな音。
地面に付いてるわたしの右手の小指と、あなたの左手の人差し指がとても近くて、うっかり誰かがわたしの体をあなたの方へ押してしまったら触れてしまうくらい近くて、なるべく意識しないようにした。それでも、次の花火が打ち上がるのを待つ間や、空一面に騒がしく開いた花火が微かな余韻を残して夜の色に溶けて消えてゆく瞬間に、胸が早鐘を打った。目眩がしてかるく窒息しそうだ。辺りは暗くて、きっとわたしの顔が赤いのは見えていなくて。それでも、心臓の音静まれって思いながら空を見上げた。
花火を見ていると、胸の奥が寂しさで少し苦しくなった。消えてしまう美しさや、形にとどめておけない美しさ。それはあなたと一緒に過ごすいまの時間を止められない切なさと、よく似ている。好きだよって伝えたら、あなたはどんな顔をするだろう。驚くかな、困るかな、それとも、なかったことにしてしまうのかな。
光る花々が艶やかに夜空に色を散らしていく。あなたが不意に、少しだけ体を左に傾げた。指先がほんの一瞬、触れた。びりっと指先から胸を貫いて走った痛みに、わたしは知らないふりが出来なくて、体全部が心臓になったみたいになってしまった。偶然触れただけなんだから、なんてことないんだから、暴れるな心臓。
空一面に大きな菊の花が開いて、夏の宴の終わりを告げた。もっと見ていたいのに、夜の色にすうっと溶けてしまった光。もういかなくちゃ。帰らなきゃ。
「あー、すっごく、きれいだったねえ」
わたしは切ない余韻を消したくて、わざと明るく言った。わたしたちは人の波に流されるように駅に向かった。川沿いの暗い道が、人の体温と夏の暑さでむせ返っていた。川からの風も吹かなくて、汗が滲む。わたしは足元ばかりに気を取られていた。まわりの人に押されて、すぐ隣を歩くあなたに腕や肩が触れてしまわないように気を付けて歩いていた。そうしてるうちに、前を行く友達との間に何人かの人が入り込んできて、わたしたちはすこしずつ離れていった。
「あのさ」
隣でずっと黙っていたあなたが、うつむいて小声で言った。
「はぐれると困るから」
そうして、わたしの手を握った。
それきりあなたは黙ってしまって、わたしもなんにも言えなくなった。骨ばってる指、掌の感触、じっとりと汗ばむのは私の手なのか、あたたかいのはあなたの手なのか、わからない。体温が伝わる、やわらかさが伝わる。神経が全部、手に集中してしまって、頭の中が熱に浮かされたみたいになってしまって、綿で出来た地面の上を歩いているみたいで、歩き方すら忘れてしまいそうだった。
黙って歩いたのが、一時間のことなのかほんの五分のことかすら、わからないくらい、息が詰まってしまって、わたしはなにひとつ、言葉に出来なかった。
街頭の多い明るい道に差し掛かると、あなたは不意に手を離して、道の先で待つ友達に、なんでもなかったみたいに手を振って駆け寄っていった。
あなたに触れたのは、それきり。
あの時、なにか言えてたら、わたしたちはもうすこし変わっていたのかな。きっと臆病になりすぎていたね。
元気でいますか?
蒸し暑い夏の夜に、花みたいに爽やかな香りのするビールを飲んでると、いまでも時々、あなたのことを思い出す。
お読みくださり、ありがとうございます。 スキ、フォロー、励みになります。頂いたお気持ちを進む力に変えて、創作活動に取り組んで参ります。サポートも大切に遣わさせて頂きます。
