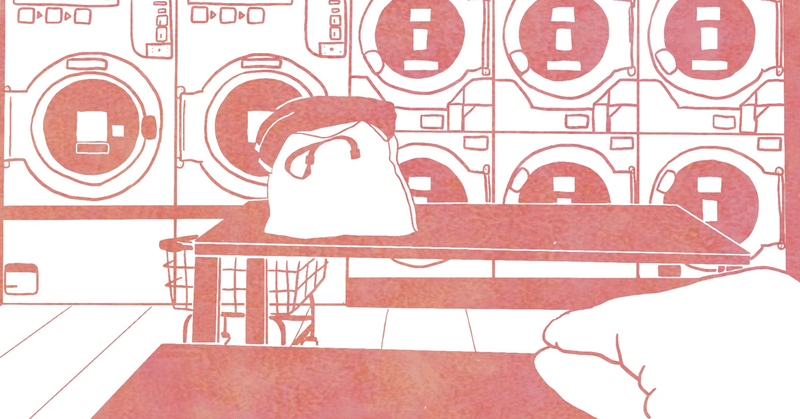
【小説】父に似たひと
十五年近く使った洗濯機が壊れた。センサーの故障で脱水ができなくなってしまい、修理よりも買い替えのほうが安いと言われてしまった。家電はいっぺんに壊れるというが、今月電子レンジも壊れて新調したため、残念ながら家計は逼迫している。
僕は年金暮らしの母と二人暮らしをしている、ヒラの会社員だ。勤めている会社は、中小企業の、どちらかといえば「小」寄りの企業で、そこまでお給料も高くはない。母と相談して、洗濯機を買い替えるのは来月にすることにして、二人分の洗濯物は僕が夜、コインランドリーに持っていくことにした。
会社から帰って、母のつくった夕飯をすませると、僕は三日分の洗濯物を紙袋につめて、歩いて十五分のコインランドリーに向かう。車を出してもいいのだが、歩ける距離だし何より中年太りが怖い。ダイエットというよりも、早死にしないために健康に気を遣うことは大事だと思っている。
路地を抜けて夜道を街灯の明かりを頼りに歩いていくと、大通りに出た。目当てのコインランドリーの看板が、ぴかぴか青く光っていた。隣のパチンコ屋の看板は赤、中華料理屋からは黄色い明かりが漏れている。このけばけばしい原色が、日本はじめアジアの街の夜の色だなと思う。
自動ドアから入り、奥にある両替機で千円札をすべて百円玉にしてしまうと、僕は二人分の洗濯物を機械に放り込み、洗濯から乾燥までを一気に終えてしまえるボタンを押した。すぐに、ドラムが回り始め、洗濯物もそれに合わせてぐるぐる回転し始めた。
僕はほっと息をつくと、店内の後ろのほうに並んでいる椅子のひとつに腰かけ、スマホを取り出し、漫画サイトを開くと適当に読み始めた。楽しみにしているものがとりたててあるわけじゃない、ただの時間つぶしだ。
洗濯乾燥が終わるまで、外に行ってもいいし家に戻ってもいいのだが、パチンコをすればお金が飛ぶし、古本屋に行くのも今の気分ではない。家に帰って、耳の遠くなってきた母が大音量で見るバラエティ番組につき合うのもいまひとつで、とりあえず終わるまで、店内で一人漫画を読むのがこの頃の僕のやり方だった。
コインランドリーには、入れ替わり立ち替わり、さまざまな人が出入りする。僕が今夜見ただけでも、小さい女の子を連れて布団の敷パッドとシーツを洗いにきた三十代くらいの女性や、明らかに一人暮らしをしているだろう耳にピアスをしている前髪の長い男子学生、僕と同じ四十代くらいで山ほど洗濯物を機械に突っ込んでいる男の人。
このあたりは治安も悪くないから、コインランドリーで盗難が起きるということも少ないこともあってか、みんな一度洗濯物がぐるぐる回りはじめるとさっさと店を出て行く。何かとほかにもやる用事があり、忙しいのだろう。僕のように店内で待っているような客は珍しかった。
しかし、ここ何回か、僕はこのコインランドリーに来るたび、なんとなく緊張するのだった。僕が来る時間帯に、何度か出くわす老人の客がいて、その人が妙に気になるのだ。
自動ドアが開いた気配がして、僕はスマホ画面の漫画から顔を上げた。猫背の壮年の男性が、洗濯物の入った風呂敷片手に、片足をひきずりながら入って来る。老人はおぼつかない手つきで洗濯物を機械に入れてしまうと、ボタンを押した。洗濯が始まったのを確認して、老人はゆっくりと、僕から少し離れた席に腰を下ろした。
僕が待っている時間と、この老人が待っている時間が、重なることが多いのだ。向こうから話しかけられるわけでもなし、それは別に構わない。ただ、この老人の立ち姿や気配が、とても似ているのだ。――僕が十二歳のときに、家を出ていった父の姿と。
僕の両親は、僕が十二歳のときに離婚していて、父とは生き別れとなっている。だから、顔つきや体つきも、うろ覚えなのだが、この老人は、妙に記憶の中にしかいない父を想起させるのだった。
父は、母と離婚したあと遠くの街へ一人引っ越したと聞いている。でも、あれから三十年も経っているし、何よりこの町は母と僕が生まれた町でもあるが、父のふるさとでもあるのだった。ほとぼりが冷めたあと、こちらへ戻ってきてひっそりと暮らしていたとしても、おかしくはない。
もし、このコインランドリーで会う老人が、僕の実父だったとしたら。
僕は漫画を読んでいるふりをしながら、ちらちらと老人のほうに視線を走らせた。頬の肉がげっそりと落ちた老人は、お世辞にも美しい身なりとはいえず、ずいぶんとうらぶれて見えた。
父だとしても、別人だとしても、この老人にはこの老人なりの人生の艱難辛苦があったのだろうと、そう思わせる風貌をしていた。
僕が二十歳前後のころ、なぜ両親は離婚して、父が出ていったのか母に聞いたことがある。母はそのときにぽつりと一言言っただけだった。
『あかんかったのよ』
何があかんかったのか、詳しくは語ろうとしない母に、僕もそれ以上突っ込んで聞くのを諦めた。ただ、父と母はあかんかったのだ、とおおざっぱに理解してその会話は終わった。
僕にも、二十代後半ごろ付き合っていた女性がいた。看護師をしていて、気丈な性格の、あゆみという二歳下の女だった。母と一緒に暮らしていた家を出て、一年半ほど同棲したが、結婚の話を切り出したらふられた。
いわく、生活にだらしないあなたが嫌なのだと。私が仕事から疲れて帰ってきても、家事ひとつやっていないところが、もう許せないのだと。どうして不満を最初から言ってくれなかったのか、そう言っても無駄だった。あゆみにはいつしか別の男ができていた。
『あんたが自分で珈琲をこぼしたシーツ、あのとき洗ってくれへんかった。私にぜんぶ押しつけて、あんたはぐうぐう寝てただけやん』
僕にそう言ったあゆみの低く冷たい声を、今でも覚えている。今の自分なら、さっさとコインランドリーに持っていくのだろうか。そう思ったがわからなかった。
あかんとはこういうことか、とあゆみと別れたあと僕は痛感した。あかんものは、あかんのだった。もうあかん、と思われてしまったら、それですべて終わる。
三十代になった僕は、自分のテリトリーに女性を近づけるのをやめた。何をやっても、がんばっても『もうあかん』と最後通牒を突き付けられる気がして怖かった。老いていく母の家に戻り、粛々と職場と実家の往復でやりすごした。ゲームと漫画の発売日だけを楽しみに、人生を低空飛行のまま過ごした。
電子音が鳴り、僕ははっと顔を上げた。自分の分の洗濯乾燥が終わったのだった。のろのろと立ち上がり、ほかほかに乾いた洗濯物を回収した。老人の分は、まだ終わらない。彼のほうを見ると、壁にもたれて座ったまま目を閉じていた。
もしここで、僕があの老人に「もしかして、僕のお父さんですか」と訊いたらどうなるのだろうか。否定されるか、それともまさかの「お前が息子か」という展開になるのだろうか。
どう見ても、健康的な食事を摂っているふうじゃない。服装だって、ぼろのようなものを着ている。下手に関わると、声を荒げられるかもしれない。そういった妙な迫力がその老人にはあった。
話しかけるな、そう本能が危険信号を出していた。そもそも、父に何か思い入れがあるわけではなく、記憶をさらっても感情はなにも湧いてこない。会いたいと願っていたわけでもない。
僕は気持ちを振り切るようにして、自動ドアから夜の街に出た。さきほどまで読んでいた漫画のあらすじを思い出そうとして、全然思い出せなかった。
それから一週間が経ち、二度ほどコインランドリーに行ったが老人は現れなかった。たまたま何度も同じ時間に来ていたのは、偶然だったのかもしれない。月末に給料日が来たので、僕は母に「洗濯機を買い替えようと思っとる」と提案した。母は「あまり複雑な機能のやつにせんといてな、わたし、わからんから」と言った。
明日洗濯機が届く、とメールに配送会社から連絡が届いた夜、僕はまたコインランドリーに向かった。ついてすぐ「あ」と思った。あの老人がいる。背をかがめて、両替機の前にいる。
今日で彼と会うのは最後になるだろう。明日から、また家で洗濯ができるのだから。僕はぼんやりとそう思い、自動ドアを開けて中に入った。
と、僕は気が付いた。老人が両替機の前でもたもたとしている。僕も両替をしたかったのだが、どうもつり銭切れらしかった。赤いランプがついているし、夜つり銭切れとなった場合の対応は翌日と書いてある。僕は勇気を出して話しかけた。
「これ、今日はもう両替できないみたいっすね。買い物でもして、お札をくずさんと、使えないっぽい」
「そうなんか……」
老人はがっくりと肩を落とした。足をひきずっているから、また別の店で買い物をするのもおっくうに違いない。僕は余計なお世話かと思ったが申し出た。
「僕、そこのスーパーまで行って千円札崩してきます。よかったら、おじいさんの分も崩してきましょうか。何か、買ってきてほしいものあります?」
老人は驚いたように目をしばたたかせたが、言葉を発した。
「みかんやな。みかん、食べたいわ。お兄ちゃん、すまんな」
そこで僕は歩いてすぐのスーパーへ行くと、自分用のチーズ鱈と、老人にみかんを買って、ランドリーに戻った。
そうして無事に、老人も僕も洗濯乾燥ボタンを押すことができた。老人はみかんをひとつ、僕にくれて、歯のない笑顔で笑った。
「お兄ちゃん、ひとつやるわ。親切のお礼に。子どもの頃、みかんばっかり食っとったんや、わしは」
声がかすれたが、僕は思わず聞いていた。
「おじいさん、故郷はどちらですか」
「愛媛県」
脱力した。ここは大阪の西のほうだから、この老人は父ではない。そのことがはっきりして、思わず洗濯物を入れてきたバッグを取り落としそうになった。
みかんをきっかけに、僕と老人はぽつぽつ話をした。故郷のこと、住んでいるこの町のこと、冬が近いこと。でも、最後まで「あなたは、僕の父に似ています」とは言えなかった。言う必要もないと思った。
明日から家で普通に洗濯ができる、そのことを思うと、なんともいえない気持ちになる。老人がくれたみかんが、僕の手のなかで少しずつ温まりはじめていた。
いつも温かい応援をありがとうございます。記事がお気に召したらサポートいただけますと大変嬉しいです。いただいたサポ―トで資料本やほしかった本を買わせていただきます。
