
「Aging Well」(よく歳を重ねる)という素晴らしい本
(picture by Edwin & Kelly Tofslie)
本を読みながら自分を深く振り返り、少しずつでも自分を改善したいなあ、と思わせてくれる本に時々出会います。紹介したい、noteに書きたい、と思える本も、ちょいちょいあります。この投稿で紹介する本は、両方に当てはまりながらも、私には珍しくどう紹介してよいか分からず、読み返しては自分をふりかえり、三度読み返しては紹介の仕方で逡巡し、初読から半年近くかけて、やっとnoteを書けるところまでまいりました。
Aging Well (2003)
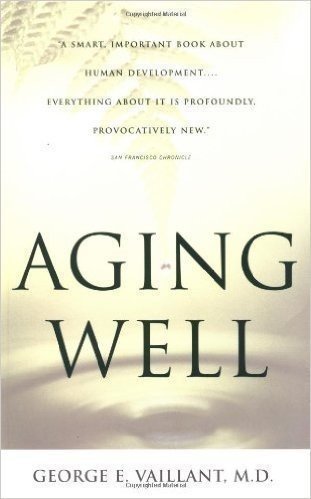
「50歳までに生き生きとした老いを準備する」(ジョージ・E・ヴァイラント(著), 米田隆(翻訳)・ファーストプレス) (2008)

私は英語版を読みました。引用する用語やニュアンスが日本語版と違っている可能性がありますが、あくまで私の読後感ということでご理解ください。
本書は Study of Adult Development at Harvard University という、1940年前後から75年以上にわたって824人を心理学の観点から継続的に追跡調査し続けている研究に基づいています。対象は、①当時ハーバード大の学生だった男子、②同年代のボストンのinner city(中心部の貧困街)で生まれ育った男子、③カリフォルニアの高い知能指数を示した女子(家庭環境はさまざま)(*1)、の3群。ひとりひとりに、2年に一度の詳細なアンケート調査と、数年に一度の心理学者による面談調査を亡くなるまでずっと積み重ねており、調査は今も進行中とのこと。ここから得られたデータに基づいて様々な研究がなされており、論文や書籍がいくつも発表されています。そのうちの1つである本書では①老年期の「幸福感」の度合とそれまでの人生における様々な要素の相関関係、②「幸福感」の高い群は低い群よりも「成長」し「成熟」していること、この2つを、たくさんの実例と分析を通して示しています。
こうした追跡調査がなぜ有効か。いま70歳で「幸せだ」と感じている人に、生い立ちから現在までを面談調査すれば済むのではないか。実際にはそうではないことが、本書冒頭で紹介されたAnthony Pirelliという男性の例を通して理解しました。Pirelliさんはボストンのinner city育ち。両親は移民で英語が使えず、父の収入は不安定で子どもたちは食べるに事欠くことも一度ならずありました。そのうえ父はよく飲み歩き家庭では暴力的、母は精神的に不安定で両親は不仲、のちに離別。幼少時の恵まれない環境にもかかわらず、Pirelliさんは勤勉で、工場労働者だったところからお金をためて勉強しなおし、会計士、さらに事業家として成功し、家庭も円満で、70歳では充実した引退生活を送っています。若いころの面談調査では、彼は両親を評して「なぜ父がもっとよい生活をしたいと努力しなかったのか、なぜ母は子供の頃アメリカに来たのにずっと英語が話せなかったのか、理解に苦しみます」と語っていました。それが、70歳になると「母は、英語ができなくてつらかったと思います。子どもたちを想う気持ちは強いのに、例えば学校で何をしているのか全く分からない。学校行事に顔を出さなかったのも、恥ずかしかったからでしょう。」「父は家族思いでした。子供たちがきちんと学校に行くよう、気を配っていました。父の家庭菜園は立派でね、近所でも評判だったんですよ。暴力?あれは、自分のふがいなさが情けなくてこらえきれず、つい子どもにあたってしまったのでしょう」と変化するのです。そして、年齢と共に過去を許すようになったことに、Pirelliさんは無自覚であった、と面談した著者は書いています。このように、ひとは現在の自分の無意識の考え方に合わせて過去のできごとを解釈しますし、自分の考え方と事実認識を峻別することもできないのです。
このような解釈の変化の事実じたい、継続的な調査をしてみてはじめて把握できることです。いま「幸せ」を感じているお年寄りに「幸せな老後の秘訣は何だと思いますか」などと単発の調査を行ったところで、あまり意味はない。私は、本書の導入部にあったこのエピソードと示唆に心をつかまれ、ぐいっと引き込まれることになりました。
Pirelliさんのエピソードを通して、もう一つ強く印象に残ったのが「He is ill, but does not feel sick」「ill but not sick」という表現です。「病気だが、健やかだ」「病気だが、病んでいない」とでも訳しましょうか。彼は63歳で重い心臓発作に見舞われ、それを機に事業を子どもや信頼できるパートナーに譲って引退します。引退後も身体の許す範囲で奥さんと趣味やスポーツ、社会活動を目いっぱい楽しみ、「引退してよかった。やりたいことがたくさんある」と生き生きと語るのです。この「ill but not sick」という状態は、本書に登場する「幸福感」のあるお年寄りの多くに共通する気構えとして描かれています。
本書の魅力のひとつは、調査対象となっているお年寄りたちの様子が、そこに立ち現われてくるかのようにビビッドに描かれていることです。仮名にはなっているものの、幸せなお年寄りも不幸せなお年寄りも本書を通して数十人に会ったような感がありました。ハーバード大男子、貧困街男子、カリフォルニアのIQの高い女性たち、どのグループにも、Pirelliさんのような素敵な老い方をしているひともいれば、孤独や不信、経済的困窮に悩むひともいます。広大なお屋敷にぽつんと一人で暮らしているお年寄りも、決して裕福ではないけれども、幸福感の高いinner city のおじいさんも登場します。
高い教育を受け経済的に恵まれた家庭に育ったから、知能に恵まれているからといって幸せな老後には必ずしもならないし、恵まれない生い立ちでも幸福感でいっぱいの老後もある。では実際のところ、老年期の「幸福感」の度合は、それまでの人生におけるどんな要素と、どの程度の相関関係があるのでしょうか。「幸福感」の高い群は低い群よりも「成長」し「成熟」しているというが、それは具体的にどういうことでしょうか。
これらの課題について、私が面白いとおもった箇所をご紹介したいと思いますが、長くなったのでまた次回にします。
*1 ハーバード大とボストン貧困街の男性の調査を合わせて Grant Study, カリフォルニアの女性たちの調査は Terman Study と呼ばれています。Terman Studyは、1920年代、女性たちがまだ小学生の頃から調査が始まっています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
