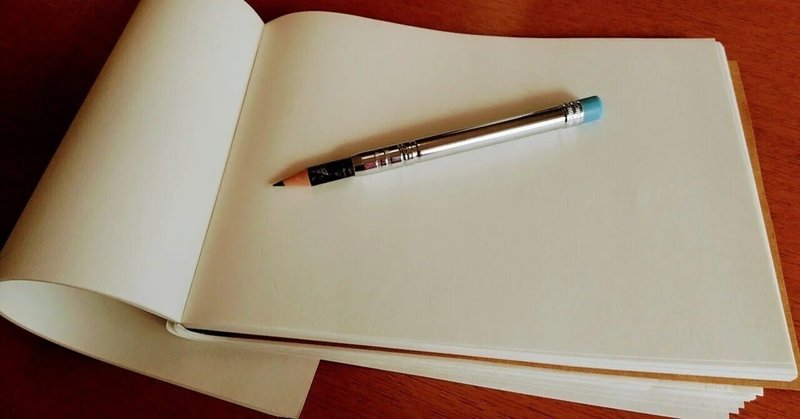
ChatGPTと漫才台本を作ってみた。
最近何かと話題のチャットGPT。私も遅まきながら少し前に無料バージョンを導入してみた。専らわからないことを質問して教えてもらう「対話型の検索エンジン」として使っているのだが、文章の構成から論文作成、プログラミングまでなんでもこなすと噂に聞き、それなら漫才の台本など朝飯前(AIがご飯を食べるはさておき)だろうと試してみた。
もったいぶることでもないので結論から言うと、漫才台本らしきものはできた。だが、チャットGPTに丸投げしてできたわけではない。協力してもらったというのも微妙である。ただ、全くAIの力を借りずに自力で作ったのか、と言われれば、答えはノーだ。
以下は、わたしとチャットGPTによる、台本完成までの記録である。AIを使いこなしている方には、AIに振り回され、まともに相手をしてもらえない私の様を、これから使いこなしたいという方には、同じ轍を踏まないための参考として、見ていただければ幸いに思う。
まず最初にやったこと
チャットGPTの能力に全幅の信頼を置いていたわたしは「漫才の台本を書いてみて」と頼めば瞬時に書いてもらえるものと期待していた。しかし念のため、最低限の情報提示はするべきだと思い、保険のつもりで過去に自分の書いた台本を張り付け、下記のような質問をしてみた。
上記を参考に、漫才の台本を書いてください。場所は古びたスナック。初めて来た客Aが、常連らしき男Bに声をかけられる。Bは中学も卒業していないという苦労人で、なにやら店のママとはわけありの関係らしい。だが、会話が進むうち、男はまだ小学生で、ママとは親子の関係だとわかる、というオチ。
前後するが、参考に張り付けたのは以下の台本。
わたしのサンプルの面白さは関係ない。アイデアがいまいちなのも関係ない。あくまで参考であり、たたき台だ。シチュエーションに沿って、男二人が関西弁でかけあいするという形式さえAIが理解すれば、あとは蓄積された膨大なデータを駆使して面白くしてくれるはず。
何の疑いもなく送信ボタンを押し、自動生成された台本がこれ。
【古びたスナックでの漫才台本】
場所:古びたスナック
A:(独り言)ここが古びたスナックか。初めて来たけど、なんかいい雰囲気だな。
B:おい、初めてか? おまえ新しい顔やな。どないしたん?
A:ああ、そうだな。偶然通りがかって、ちょっと入ってみようかなって思って。
B:ほーな。まあ、ここは昔からの常連客が集まるとこや。おもろい話があるけど、聞いてもええか?
A:おもろい話? もちろん聞きたいよ。教えてくれ。
B:ええか、けっこうええ話やで。俺、中学まで行ってへんのや。苦労人やな。
A:中学まで行ってへんの? それは大変やったろうな。
B:でもな、そんな苦労もあったけど、ここでママと出会ってな。ママがお世話になってるんや。
A:ママ? ここのママのこと?
B:ああ、そうや。なんかな、俺とママはわけありの関係なんや。
A:わけありの関係って、なんやそれ。
B:まあな、おもろい話やで。実はな、ママと俺は親子や。
A:えっ? 親子ってことは、あんたはまだ小学生なん?
B:ああ、そうや。おまえ、気づいたか? 実は俺まだ小学生や。
A:まさか、本当に小学生とは思わなかったよ。驚いたな。
B:まあ、なんやねん。そんなに驚かれても困るわ。
A:ごめんごめん、本当に驚いたんだよ。でも、なんでこんな大人びた言動してるん?
B:そやな、実は俺、いつも大人たちと遊んでるから、そういう風になったんや。
A:それはすごいな。でも、なんでママはおまえのことを親子として扱ってるん?
B:それがな、ママと俺は、なんか運命的な出会いがあってな。だから、親子として接してるんや。
A:なるほど、それは素敵な関係だな。ママっていい人なんやろうな。
B:ああ、まあな。でも、実は俺、今日もママにお小遣いもらいに来たんや。
A:お小遣いもらいに? まだ小学生やのに、そんなことできるん?
B:まあ、ほんまは内緒やで。お小遣いもらうのはここだけの話や。
A:分かったよ。だから、お小遣いもらいにきたんやな。
B:ああ、そうや。それよりおまえ、お酒飲むか?
A:いや、今日はちょっと飲まないな。ありがとな。
B:そうやな。まあ、いつでもおいでや。またお小遣いもらいに来てくれたら、俺がお相手してやるわ。
A:(笑いながら)ありがとうな。また来るよ。
(二人は楽しそうに話しながら店を後にする)
【注意】この漫才台本はフィクションであり、登場人物の設定やセリフは架空のものです。また、登場するキャラクターの関係や設定は台本の中でのみ成立しています。
チャットGPTについてよく言われることだが、AIが作ったとは思えないほど自然な文章である。関西弁も、ネイティブではなさそうだと想像できる程度には自然だ。しかも、台本の最後にはわたしの台本にはない注意書き。想像以上に几帳面で礼儀正しい。
しかし、そんなことはどうでもいい。なんだこれは。ため息が出るほど面白くない。せいぜいが「明るく朗らかな会話」である。無限に拡大解釈しても「ほほえましい」止まりだ。中年の渋い常連客が、実は小学生だったというオチも、AIには全く響かなかったらしく、ママと少年のちょっといい話に書き換えられてしまった。
ここで見切りをつけてもよかったのだが、逆にやる気が出てきた。誰にでも経験があるだろう。他人が自信満々で見せてきた作品が、そうでもない仕上がりだったとき、心の中で(これくらいなら自分でもできる)と思ったことが。
わたしは少しアプローチを変えて、別の質問してみることにした。
つづく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
