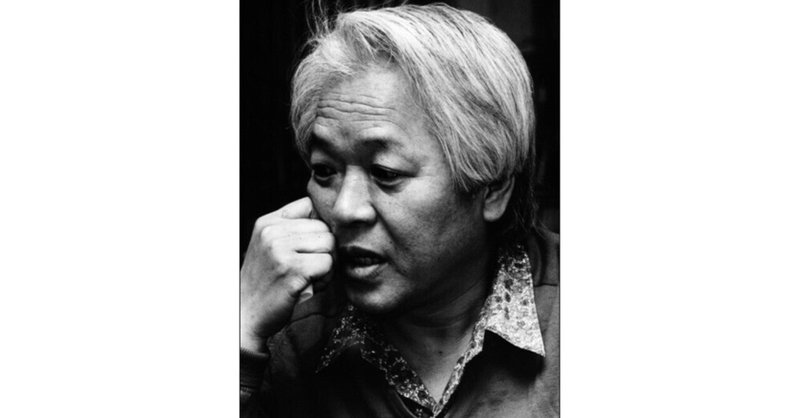
公共性のある小説とは
読書会のメンバーからの紹介で、李清俊の「虫の話」を読む。(頭木弘樹編「絶望図書館」所収。)最愛の息子を誘拐殺人で失った妻の夫が、妻の絶望を理解しようとする小説で、彼女は熱心な隣人のキリスト教信者の「勧誘」をごまかしとして拒否して自死する。このような書かずには救われない小説をぼくは文学として認める。それは小説はエンターテインメントだとする見方と対立する。ぼくは小説を娯楽として読むならそれでいいと思う。ことさら読書会で、つまり小集団で読む必要はない。小集団を公共性の最小単位だとすると、「虫の話」のような小説を公共性の小説と呼びたい。そして先ごろ読んだ黒井千次の「群棲」も、書かずには救われない小説とまでではないが、現代の都会人の群像を活写している点で、公共性な小説だと思う。
おそらく文学にしか自分を受け入れてはくれなかった、という経験を持たれている人がぼくの他にもいると思う。そうは言っても文学は漠然としていてつかみどころがないと思われるかも知れない。ぼくにとってはさしづめ、何でも受け入れる広いこころ、といった場所と言えるだろう。取り合えず文学が自分の居場所だった。何でもありの自由に息のできる場所だ。小林秀雄は「はっきりと目覚めて物事を考えるのが、人間の最上の娯楽だ」と言った。その娯楽を与えるのが読書の楽しみだというのだが、文学が快楽だとより簡潔に言えると思う。簡単に直ぐには得られないかも知れないが、知れば知るほど、体験すればするほど、深い独特な快楽を与えられるのが文学だと思う。恋愛そのものも快楽だが、恋愛小説はそれ以上に快楽だと思う。昨日、黒井千次の「高く手を振る日」を読み終えたが、若い頃の恋愛より年を取ってからの恋愛はもう一度純愛に戻って、愛しく悲しい快楽をもたらす。気持ちがいいという直接性から、抑制の効いた美しい倫理性を良しとするのも、文学的な快楽だと思う。

黒井千次の小説は「春の道標」を読み始めた時、生理的に受けつけない箇所に出くわしてからもう読まないでおこうと決めたのだったが、「夢のいた場所」という作品が作家になってから自分のサラリーマン生活で出くわした体験をどうしても「総括したい」思いにかられて書いたらしいことを知り、もう一度読んでもいいかと自分に許した小説だった。どうやらこの小説家も女性にはモテるタイプらしく、高校卒の年下の同僚の恋愛相談の相手を引きつけてしまい、思わぬ成り行きで自分のものにしてしまう。また社員寮のおばさんと若い社員との秘密の同衾などの場面を描く時にも、決して突き放した描写ではなく微細なところで卑猥な表現も飛び出してくる。だから「春の道標」の時ほど生理的拒否はないものの、軽い嫌悪感はあった。でも全体にストーリーの運びは緊迫感があり、ある大企業の地方工場にある労働問題を取り上げ、主人公の小早川和夫を中心とした人間関係のドラマを安部公房ばりのシュールレアリズムを一部取り入れながら展開する筆さばきは見事だった。つまり十分面白かったのである。現実との距離感がいくぶんぼくと似ていなくもない気が、これまでの黒井千次の小説を読んでしている。それは貴重なことかもしれないので、その貴重さを確かめたくて他の作品も読み続けていく予感がする
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
