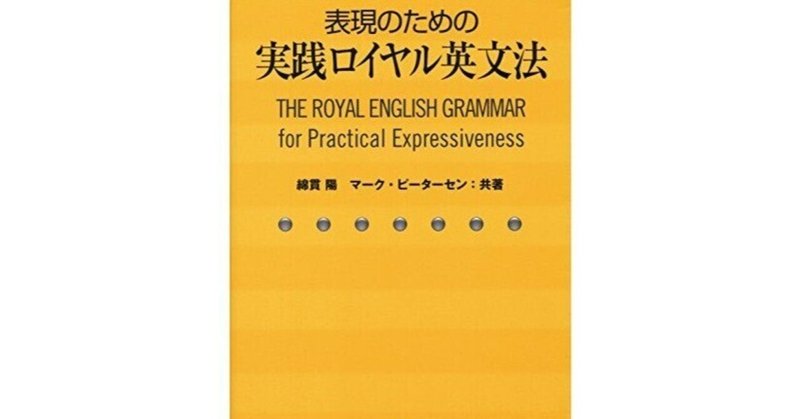
学習参考書を読んだ日
無限にある本から一冊だけを選んで読むことの充足感について。ぼくの中学3年生の夏休みは、高校受験勉強に集中して毎日家にこもって勉強していた。確か5教科まとめた分厚い受験用参考書を一冊買ってきて、ノートを取りながら1ページずつ読んでいった。その一冊だけをとにかく読んでその中の練習問題を解いていった。どういうわけか集中できた。ラジオはつけていたと思う。ニッポン放送の深夜の「オールナイトニッポン」を欠かさず聴いていた。あの時期は充実いていたと思う。成績は2学期に入って自然と上がって、志望校のランクも上がっていった。今から思うと、その時の勢いで進学校に進んだことが良かったのかどうか、高校時代は落ちこぼれ寸前まで行ったのだから、その後の進路がその時の判断で決まったのかもしれないと思う。先日テレビで引きこもり30年だったかの中年男性が、ようやく介護の職場で働けるようになった取材番組をやっていたが、彼も実力以上の高校に運良く受かってから授業について行けなくなって、退学してから引きこもりになったということだった。ぼくも同じような道に陥るところだったとその時思った。ちょっとしたところでぼくは踏ん張っただけで、その彼とぼくは同類だと思う。
それはさて置き、今日書きたかったのは、中学3年生の時の受験参考書のような目的のはっきりした一冊の本の存在についてなのだ。その一冊さえ読み通せば結果が出る、という一冊がとても貴重な存在に思える。そんな本はやはり参考書の類でしかないのだろうか?小説がどんなに古典的な良書と言われるものであっても、それだけを読むことの充足感はないだろう。今日、英文法の参考書「表現のための実践ロイヤル英文法」を書棚から取り出して読んでみた。確かに中学の頃の勉強熱まではいかなくとも、微かな充足感は感じられた気がする。なんというか、決められた動かぬものをたどる安定感という感じが心地よかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
