
声なき声を聞きたい、そんな初心と似た「探し求める、小さな声を」に共感して
私が10代後半に工場勤務のろうあ者と出会ったことが障害者との関わるきっかけでした。手話をマスターすれば全ての聴覚障害者とコミニケーションが取れる。
そんな想いで全国組織の手話通訳問題研究会に入会して全国大会に参加しました。そこで出会った一人の難聴者から中途失聴者は手話が分からない人も多いと聞き軽いショックを覚えました。
その後、障害者団体の全国大会を名古屋で開催する際に各障害ボランティアのリーダーと関わる中でそれぞれ大きな課題がある。自分の所在する団体での障害者支援も大切だけど他の団体(の障害者)を知る事も重要と気づきました。
当時は手話ブームでろうあ者の声が世間に知られた時期でした。その中で全く聞こえない ろうあ者と比べて聞こえの程度が千差万別で、話す事が出来る難聴者に対する世間の理解は私に似たり寄ったりでした。
その時に私のやりたい事は世間が知らない障害者の内なら声を世間に伝えるメッセンジャーになりたいと思っていました。盲ろう者協会に関わったのもその関係でした。
聴覚障害と視覚障害を重複障害をサポートする団体は存在せずに友の介レベルでした。各地に協会が設置されるのを見届けて、私の関心は自閉症/発達障害/愛着障害に移りました。
最近はそれらが取り上げてられる事も少しずつ増えて嬉しく思っています。小さな声は耳をすまして寄り添わないと聞こえ、目の前にいても関心を向けてその事を知らなければ寄り添うことも出来ない。
SNSのフォロワーが1万人居ればそれらの小さな声を広く届け事が出来るそんな事を考えながら数千人のフォロワーになりました。
そんな時に人には役割があり私は「多くの人に小さな声を届ける役割ではなく、目の前の人の小さな声を聴き寄り添うのが役割」と思えるようになりました。
日々の出来事を通して小さな声を聞く1つのポイントは「優しさ」にあるように感じています。
例えば利用者さんが皿を落として割れた時に「皿に目を向ける」のではなく「怪我が無い身体を見る」事が無意識に出来るかどうか。
トイレがパットを履く際に「冷たい」のつぶやきを聞いて「パットの濡れを想像出来て確認、交換」が出来るかどうか。これは小さな声を聞き取れかと合わせて心身の余裕があるかも関係するように思います。
介護施設アルアルで利用者さんの為にやりたいと思っても人数的、時間的にやらない事もあります。
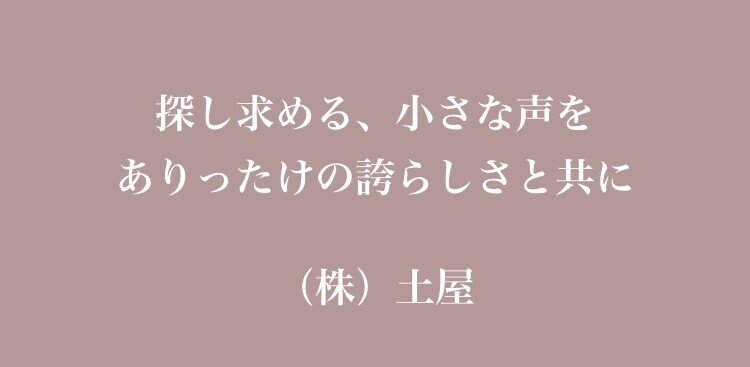
トップ写真は住友生命アプリのバイタリティで当たったスターバックスのドリンクチケットと引き換えたアイスコーヒーと現金清算したあらびきソーセージパイです。

規定の歩数をクリアするとルーレットで各種商品が当たります。少額はペットボトルのお茶か寄付で運が良ければスターバックスの500円ドリンクチケットです。しっかり充電して明日からの勤務に備えます。^_^
最後までお読みいただきありがとうございます。 もし気に入っていただけましたら「スキ」&「フォロー」もよろしくお願いします。
