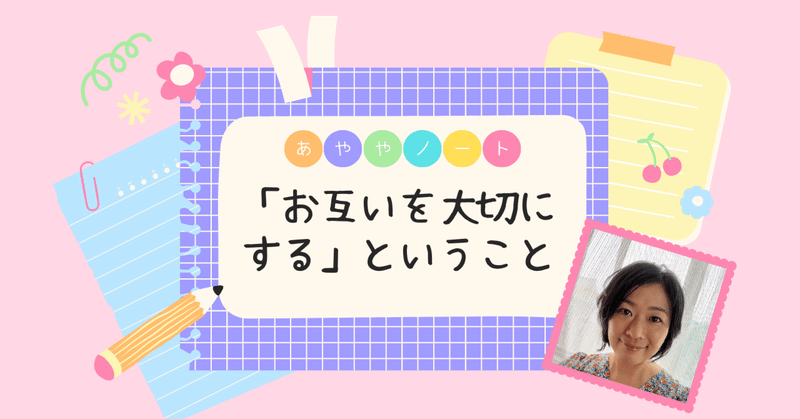
【あややノート】第15回「お互いを大切にする」ということ
こんにちは。
HUG for ALL代表のあややです。
私たちHUG for ALLが掲げる「安心できる居場所」のためには、「お互いを尊重し、大切にすること」が不可欠です。今回はこの「お互い大切にする」ことをテーマに話してみたいと思います。
子どもたちの「安心できる居場所」のために
私が子ども達と接する中で、特に意識していることは「"安心できる居場所"をつくれているかどうか」ということです。
この"安心できる居場所"は、子どもと大人の関係性だけでつくるものではなく、その場にいる人たちみんなでつくるものだと思っています。
子どもに対してどれだけ優しい目を向けていたとしても、大人同士の関係性がギスギスしてしまっていたら。その雰囲気を感じた子どもはきっと”安心”はできない。だから、「子どもたちにとっての”安心できる居場所”」をつくるためには、HUG for ALLが「大人にとっての”安心できる居場所”」であることも必要不可欠なのだと思います。
大人にとっての「安心できる居場所」
大人の「安心できる居場所」というのは、実はすごく難しいことだなと思います。大人同士だからこそ、価値観のぶつかり合いも起こるし、意見や考え方の違いも起こります。
衝突が起きないことはあり得ない。でも、衝突が起きたときに、相手の価値観や相手の存在を否定することなく、ちゃんと対話ができる状態にあること。それが「安心できる居場所」なのではないかと思います。
でも、価値観や存在を否定せずに対話をするというのは、これまたすごく難しいことだと思います。表面上は受け入れたつもりでも、態度や表情にそれが出てしまっていたら絶対に伝わるんですよね…。
自分の価値観を脇にいったんおいて、相手の価値観を心の底から尊重することが大事。それは子ども相手でも大人相手でも一緒なのですが、なぜか大人相手のほうが100倍難しいです…!
そしてこの「相手の価値観を尊重する」というのが、結局のところ、今日のテーマである「相手を大切にする」ということなんじゃないかなと思うのです。
「相手を大切にする」ために
なんだか逆説的ですが、最近私が気づいたのは「相手を大切にするためには、自分を大切にしないといけない」ということです。逆に言うと、自分自身を大切にできていない人は、相手を本当の意味で大切にできないんじゃないかな…と思います。
これは実は私自身のことだったりもします。元来私は「自己犠牲」的なものって嫌いではなくて、他の人のために自分自身の身を削ってでも何かをしたいと思うタイプでした。「他の人を大切にするために、私自身を犠牲にするのは仕方ない」。そんなふうに思っていたと思います。
でも、「自己犠牲」的なところがどこかにあると、どこかで「私はこんなにやってるのに…」という想いが自分の中に生まれてしまって、それはきっと周りにも伝わるんですよね。その「恩着せがましさ」みたいなのって、多分周りの人を息苦しくさせていたんだろうな~ということに、実は最近気づきました。
だから、「他人を大切にするためにも、自分をまずは大切にする」。それが、すごく大事なことなんだといま改めて思っています。
子どもへの言葉と大人・自分への言葉
例えば、子どもたちが今誰か友達のために無理をして、「でも、友達のためだから、私は多少犠牲になってもしょうがないの!」って言っていたとしたら。きっと私は、「友達も大事かもしれないけど、まずは自分を大切にしてほしい!」って、言うと思います。「自分を大切にできない状態で友達を大事にしても、友達はうれしいかな?」と言うかもしれません。
子どもに言う言葉と、他の大人に言う言葉と、自分自身に言う言葉。この「ちがい」って面白いなと思います。自分自身が言語化していないこだわりや思い込みが、その「ちがい」に表れているような気がします。
私はコーチングでよく「同じ立場に子どもがいたら、何て言ってあげる?」という問いをもらうのですが、それに答えているとハッとすることがすごく多いです。
そんなことを何度も繰り返して、ようやく考えるようになったのが、子どもたちに「自分を大切にしてほしい」と願うように、私自身も自分を大切にするということです。
自分を大切にするからこそ、本当の意味で「他の人を大切にする」ということができるのだと思います。だからこそ、今私は、HUG for ALLにかかわるみんなにも、「自分を大切にする」ということを大事にしてほしいと願っています。
まずは「自分を大切にできる」一人ひとりが集まって、そのうえで仲間たちを、子どもたち一人ひとりを尊重し、大切にしていく。私たちは、そんな団体でありたいと願っています。
まだまだ試行錯誤しながらではありますが、こうやって私たちが大切にしたい価値観を一つずつ言葉にしながら、前に進んでいきたいと思います。これからも引き続き、応援いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
