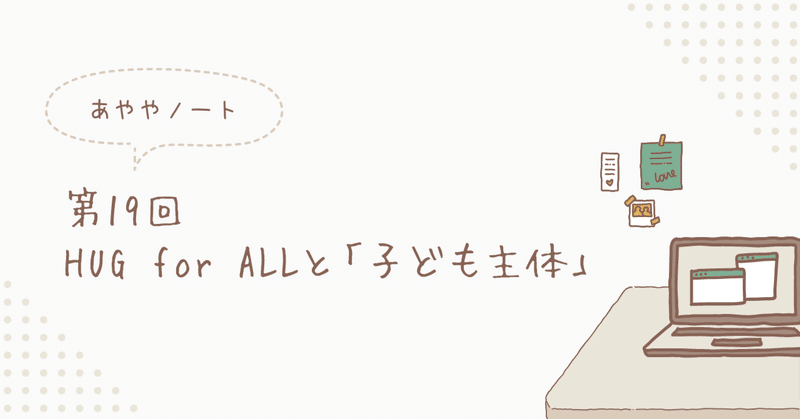
【あややノート】第19回 HUG for ALLと「子ども主体」
こんにちは。「子どもたちとこんなことしたら楽しいだろうな」と考えるのが大好きな、HUG for ALL代表のあややです。
6月はHUG for ALLのことや児童養護施設のことに加えて、「子ども主体」のことをいろんな方と語る機会が多く、いろんなことを考えたので、今日はそんな話を書きたいと思います。
「子ども主体」っていったい何?
こども家庭庁ができて、「こどもまんなか社会」と謳われるようになったけど、結局「子ども主体」が何なのかということって、意外に難しいんだなって思います。
私が思う「子ども主体」の根っこは「子どもの力を信じること」。子どもってすごい。大人の予測を軽く超えて、いろんなことを考えているし、いろんなことをわかってる。子どもたちを見ていると日々そんな驚きを感じます。
もちろん、知識や経験がないから知らないことはあります。そういうときは大人が手助けをすればいい。子どもに手助けが必要なタイミングを見極めて、見計らって、声をかけて情報を伝える。子どもを信じて任せつつ、そばに寄り添って必要なときにちょっと背中を押すような、そんな関わりが大事なんだろうなと思います。
「あなたのことを知りたい」
でも実は、手助けが必要かどうかを見極めるのって、めちゃくちゃ難しいなと感じています。良かれと思って伝えたことが、子どもの興味を削いでしまったり、やる気をしぼませてしまったりすることもあります。
だからこそ、子どもの姿を見つめて、子どもの想いを聴いて、「本当はどういう関わりが良かったんだろう?」と大人側が振り返ることも必要なのだと思います。
「あなたはいま何を考えているの?」
「あなたはいまどんな気持ちなの?」
そんなふうに「あなたのことを知りたい」という思いで子どもに向き合い続けて初めて、「子ども主体」のスタート地点に立てるような気がしています。

大人としての理想の「在り方」
例えば「話を聞かない子」がいたとき、その子のことをどう考えるか?は、大人の「在り方」次第だなと思います。
「話を聞かないなんて悪い子だ!」と思ってしまうこともあれば、「話を聞かないのも子どもの自由だから仕方ない」と諦めてしまうこともある。でも、私の理想は「なぜこの子は話を聞かないんだろう?そこにどんな想いがあるんだろう?」と考えて、子どもの気持ちを知ろうとする在り方です。
うまくいかなくて反省することも多いのですが、「この反省を次につなげよう!」と思いながら、子どもたちとかかわり続けたいなと思っています。
「こどもまんなか」を大事にしたい
HUG for ALLでは「子どもの想い・価値観」を大事にしたいと思っています。大人の価値観を押し付けたり、大人の基準で子どもを評価するのではなく、あくまで子どものそばに寄り添って、子どもと同じ目線で考えていくこと。それが「こどもまんなか」ということなんじゃないかな…と、最近改めて感じています。
子ども一人ひとりの姿、一人ひとりの反応をしっかりと捉えながら、その子が何をどう考えているのか、どんな気持ちでいるのかを考え続けていく。そんなふうに子どもに寄り添い、子ども自身のことを深く知って、いっしょに未来を考えていきたい。
HUG for ALLが目指しているのは、そんな子どもたちとのかかわりです。子どもの「安心できる居場所」となるだけでなく、共に「生きる力」を育む大人になるために。これからもHUG for ALLは活動を続けていきたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
