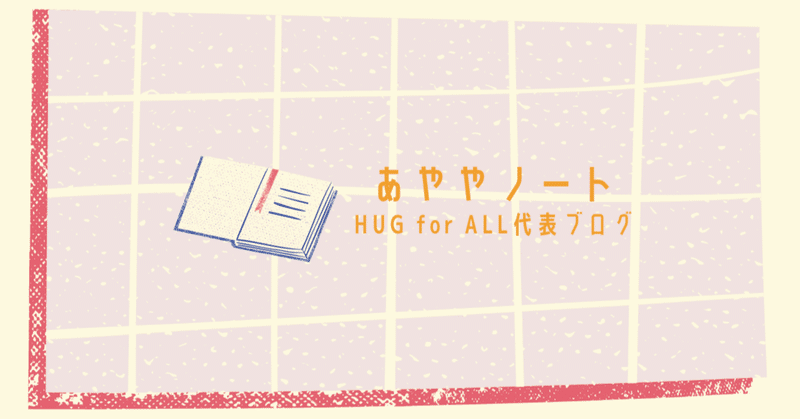
【あややノート】第13回私が描きたい未来
新年明けましておめでとうございます。
HUG for ALL代表のあややです。
2023年という新しい年の節目を迎え、私も初詣で「HUG for ALLの活動を前に進める強さを持ちます」と神様に宣言をしてきました。今日は私がHUG for ALLを通して実現したい社会の姿を、みなさまとシェアしたいと思います。
未来をあきらめる子どもをなくす
生まれ育った家庭環境のせいで、未来をあきらめる子どもをなくしたい。これは私が強く強く願っていることです。
「学校なんていっても意味ないよ。大人になったらお母さんみたいに体売れば生活できるし。生活保護うけたっていいし。」
「将来なんて知らない。30歳くらいでもう死にたい。若いうちはいいけど歳とったらいいことなんてないでしょ。」
「生きててもいいことなんてない。死ぬのも怖いから生きてるだけだし」
「学校でも盗難とかあったら疑われたし。友達っていっても友達のふりしてるだけだと思うし。先生も自分のことが大事なんでしょ。大人の男の人は優しくしてくれるけど体目当てだし。別に誰のことも信頼なんてしないよ。」
私がこれまで出会った子どもや若者の中には、淡々とこのようなことを言う子もいました。生まれ育った環境や、彼らの人生で出会ってきた様々な大人たちから影響を受けて、彼らはこんな価値観を持つようになったのだと思います。私は彼らのこの言葉に、とても苦しさを感じました。
子どもたちは等しく可能性をもって、未来を生きる力を持っている。私はそう信じています。
自分の可能性を信じて、自分は幸せになってもいいんだと思うことができれば、子どもたちはがんばることができる。逆に、自分の未来をあきらめてしまうと、自分のためにがんばることができなくなると私は考えています。
子どもたちが自分のためにがんばれる人になるために。子どもたちが自分の未来をあきらめないようにしたい。そのために、子ども自身の価値を周りの大人が100回でも200回でも伝えていきたいし、みんなの可能性は無限にあることをずっとずっと言い続けたい。一人ひとりのいいところや素敵なところをたくさん見つけて、その子自身にも知ってもらえるようにしたい。
かかわる大人たちが、子どもの未来を信じて、それを言葉にして伝え続けることで、子どもたちは未来をあきらめようとする鎧を1枚ずつ脱いでいくような気がしています。
だから、HUG for ALLでは、子どもたちの可能性を可視化して、それを伝えていくことを大事にしていきたいと思っています。
「自己責任」と言われない世界
実は私は「自己責任」という言葉を聞くととても悲しくなります。犯罪を犯した人や、生活に苦しむ人に対して「それは自己責任ですよね」というコメンテーターの言葉を聞くと「本当にそう?」とつい心の中でつぶやいてしまいます。
裕福な家庭に生まれて、衣食住の心配もなく、両親や親族からも愛されてきた人。毎食手作りの食事が出てきて、毎日おやつも食べられて、ふかふかの布団でぐっすり眠ることができる人。幼少期からさまざまな習い事をして、小学校になったら塾にも通って、家庭教師もつけてもらったりして、私立の学校に通ったりできる人。
両親ともに健康上の理由で働くことができず、生活が苦しい家庭に生まれた人。他に親族もなく、頼れる大人もいない。食事も毎食食べれるわけではないし、おやつなんてもってのほか。両親のケンカも絶えず、家は常にだれかの怒鳴り声が聞こえている。家に帰ったら家事や弟妹の世話もしなくてはならず、学校の宿題どころじゃない。
例えば、こんな生活背景の違いがあったとき、上の人が学校でいい成績をとることと、下の人が同じ成績を収めることって、きっと同じ努力量でできることではないのだと思うのです。だとすると「自己責任」って一体何なんだろう?いったい何を指しているんだろう?そんなふうに思います。
ちなみに私は定期的にこの動画を見て、この「格差」と「自己責任」ということを考えるようにしています。よかったらぜひみなさんも見てみてください。
もちろん厳しい生活環境で育っても、すごくがんばって成果を残している人はたくさんいます。でも、それができない人がいたときに「自己責任」って軽々しく言うのは違うんじゃないかと私は思っています。
「自己責任」というのは、なんだか全部をひっくるめて「結局全部自分自身のせい」ということだなと思うのですが、なんかすごく冷たい言葉のような気がします。
その人の背景に何があったのか。どんな想いがあったのか。そんなことを思いやれるようになりたい。私はそんなふうに願っています。
もちろんだからと言ってすべてを許せばいいというわけではないです。例えば罪を犯したら、罪は罪として償わなければいけない。でも、その背景に何があったのかを、ちょっと考えてみる。
「自己責任」じゃなくて、「彼・彼女に、社会としてできることはなかったんだろうか」と考えてみる。そうすることで、この社会はもっと優しくなるし、もっとお互いを助け合えるようになる豊かな社会になるのではないかと思うのです。
クエストフレンドのみんなから「HUG for ALLの活動を通して、社会の見方が変わった」と言ってもらうことがあります。
様々な背景を持ち、いろんな価値観を持つ子どもたちと対話を重ねていく中で、自分たちの知っている世界と彼らの知っている世界の違いに気づくことができたとき、「みんなそれぞれ違う事情があるんだ」と気づいたときに、「自己責任」って言葉は出てこなくなるのだと思います。
HUG for ALLの活動を通して、そんな優しい社会をつくっていけるとうれしいです。
子どもたちと未来を語るということ
実は本日、「はたちクエスト」というプログラムで高校生の女の子たちと、施設を出たあとのお金の話をしてきました。
日々の生活でどのくらいお金を使うのか、どのくらいのお金が入ってくるのか、貯金はどのくらいしないといけないのか。そんな話をしながら、施設を退所した後の生活の話にも花が咲きました。
小学校の頃から彼女たちを知っていて、その未来を無限の可能性を信じる大人たちが集まって、共に未来を対話するという時間。1.5時間と高校生にとっては長丁場だったと思いますが「もっとしゃべりたかった!」と言ってくれる子もいて、とても豊かな時間でした。
彼女たちは、HUG for ALLで見守ってきた中でも一番上の年代です。これからその下の年代の子どもたちも、どんどん未来に向けて進んでいくことになります。
子どもたちが未来をあきらめずに前に進めるように、そして子どもたちを迎え入れる社会がより優しく、思いやりにあふれたものになるように、これからもHUG for ALLの活動を前に進めていきたいと思います。
1月・2月には来年度のボランティア募集や、運営スタッフの募集もしていく予定です。募集開始時にはまた改めてご案内をさせていただきますので、たくさんの方に仲間になっていただけるとうれしいです。
これからも、応援よろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
