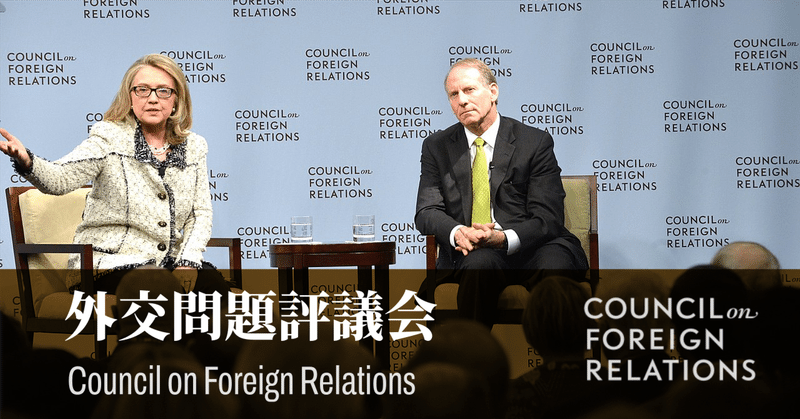
【解説】外交問題評議会
こんにちは。いつもお越しくださる方も、初めての方もご訪問ありがとうございます。
今回は外交問題評議会の動画を作成しましたの、その動画の紹介になります。もしかすると事実に反する内容もあるかもしれませんので、エンターテイメントだと思って、疑いの目をもってご視聴いただければ幸いです。
外交問題評議会
今回は、1921年に設立された、アメリカのシンクタンク、外交問題評議会について見ていきたいと思います。
外交問題評議会は、ニューヨークに本部を置く、外交と国際問題を専門としたシンクタンクです。
会員数は5000人以上におよび、これまでも著名政治家や、国務長官、CIA長官、銀行家、弁護士、教授、メディア関係者らが名を連ねています。
外交問題評議会の会議には、政府高官や、世界的なビジネスリーダー、情報機関や、外交政策コミュニティーなどの著名なメンバーが集まって、国際問題について議論しています。
外交問題評議会は、1922年から、隔月刊誌、フォーリン・アフェアーズを発行しています。
また、あまり広く知られていませんが、シンクタンク、デイヴィッド・ロックフェラー研究プログラムを運営しています。
――外交問題評議会は、ロックフェラー家と関係があるんですね。
このプログラムは、大統領府や外交コミュニティへの提言、議会での証言、メディアとの交流、外交問題に関する出版などを通じて、外交政策に影響を与えていると言われています。
それでは早速、外交問題評議会の起源から見ていきましょう。
外交問題評議会の起源は、第一次世界大戦末期に設立された、ある調査機関にあるとされています。
この機関は、ウッドロウ・ウィルソン大統領の側近であり、友人の、エドワード・マンデル・ハウス大佐や、ウォルター・リップマンなど、150人ほどの学者からなる組織でした。
彼らは、1919年のパリ講和会議にも随行し、その議論に参加しました。
この講和会議で意気投合した、アメリカとイギリス両国の外交官、研究者グループはロンドンとニューヨークに事務所を置く、国際問題研究所という組織を設立しました。
その後、イギリスでは、ロンドンに王立国際問題研究所、別名チャタムハウスが設立されました。
アメリカでは、1918年からニューヨークに存在していた非公式なサロン、外交問題評議会に合流することとなりました。
――外交問題評議会という名前のルーツは、ここにあるんですね。
初代議長は、セオドア・ルーズヴェルト政権時代の国務長官、エリフ・ルートがつとめることになりました。
――外交問題評議会は、イギリスの王立国際問題研究所と協力関係に合ったんですね。
それが、違うんですよ。外交問題評議会のサロン時代のメンバーは、会員をアメリカ市民に限るとしたことで、イギリスの機関とは袂を分かつことになったんです。
1922年、外交問題評議会のエドウィン・フランシス・ゲイは、外交政策の権威ある雑誌の発行に向けて、資金を集め、国際問題を扱う最も権威あるアメリカの評論雑誌「フォーリン・アフェアーズ」を創刊します。
日本でもフォーリン・アフェアーズ・リポート、という形で月刊紙が出版されていますよね。
外交問題評議会は、1930年代後半から、フォード財団、ロックフェラー財団、カーネギー社から、多額の寄付や助成金を受けることとなりました。
これを受けて、ワシントンDCのアメリカ外交委員会を中心とする、様々な委員会が、アメリカ全土に設立されることとなりました。
これらの委員会は、地元の指導者に影響を与え、世論を形成する役割を果たし、評議会や政府に国情を知らせる機関としても機能しました。
1939年からの5年間は、ロックフェラー財団が全額出資し、極秘の戦争と平和研究会が設立されました。
この研究会は評議会メンバーの多くも、その存在を知らされていませんでした。
――アメリカ政府の調査機関が、ロックフェラー家の強い影響下に置かれ、その下で秘密の研究会が創設されたということなんですね。
研究会は、経済・金融、安全保障・軍備、領土、政治という4つのグループに分かれており、安全保障・軍備グループには、後の中央情報局、CIA長官となるアレン・ダレスが参加していたことが知られています。
それでは冷戦時代、外交問題評議会がどのような活動を行っていたのかを見ていきましょう。
ある調査によると、1945年から1972年にかけて、アメリカ政府高官の半数以上が、外交問題評議会のメンバーだったとしています。
トルーマン政権時代は42%、アイゼンハワー政権時代では40%、ケネディー政権では51%に達し、ジョンソン時代には57%にまで上昇しています。
――アメリカでの外交問題評議会の影響力がよくわかる数字ですね。
外交問題評議会の研究会のメンバーであったジョージ・ケナンは、1947年にフォーリン・アフェアーズ誌に、匿名で「ソ連の行動の源泉」という論文を発表し、封じ込めという用語を作り出しました。
ケナンのこの論文は、その後の7代に渡る大統領政権の外交政策に多大な影響を与えることとなりました。
諜報の専門家、ウィリアム・バンディは、外交問題評議会の研究会が、マーシャル・プランや、NATOにつながる枠組みを形作るのに役立ったと評価しています。
――マーシャル・プランは、アメリカが推進した、第二次世界大戦で荒廃したヨーロッパ諸国のための、復興援助計画のことですね。
軍人だった後の大統領、アイゼンハワーは、経済学のイロハをすべて外交問題評議会で学んだとすら言われています。
外交問題評議会は、アイゼンハワーを大統領とすべく、新しい研究会を設立し、大統領となったアイゼンハワーは、多くの閣僚を外交問題評議会のメンバーの中から引き抜いています。
そのメンバーの一人がジョン・フォスター・ダレス国務長官です。
――中央情報局、CIA長官のアレン・ダレスは彼の弟なんですね。
デイヴィッド・ロックフェラーは、ダレス兄弟とは学生時代からの旧知の仲だったことが知られていますね。
ジョン・フォスター・ダレスは、外交政策の新しい方向性を示し、外交問題評議会で「核兵器と外交政策」という会合を開き、議長にヘンリー・キッシンジャーを任命します。
キッシンジャーは、評議会本部でこのプロジェクトに取り組み、その研究成果を同名で出版し、彼の名前をアメリカ全土に知らしめることとなりました。
外交問題評議会は、相互抑止、軍備管理、核不拡散など、アメリカの重要な政策の発信基地の役割を果たしました。
1960年代から米中関係の調査がスタートします。ヘンリー・キッシンジャーは「フォーリン・アフェアーズ」誌に論文を発表しつづけ、1969年にニクソン大統領に任命されて国家安全保障顧問をつとめました。
彼は1971年に極秘で北京を訪問し、中国の指導者と会談します。1972年にニクソン大統領が中国を訪問、カーター政権で国務長官をつとめた、評議会メンバーのサイラス・ヴァンスが国交を完全に正常化しました。
――米中国交正常化は外交問題評議会が主導したんですね。
ベトナム問題によって組織に亀裂が入り、長く外交問題評議会をまとめていた、ハミルトン・フィッシュ・アームストロングが辞任します。新会長となっていたデイヴィッド・ロックフェラーの知人で、タカ派のウィリアム・バンディが後任を打診されましたが、反対意見が多く、彼はその申し出を断りました。
1979年、デイヴィッド・ロックフェラーは、ヘンリー・キッシンジャーらと共に、カーター大統領を説得して、イラン最後の皇帝で、当時亡命生活を送っていた、パフラヴィー2世をガン治療を名目にアメリカへの入国を認めさせました。
この結果、これに反発したイランの学生らがテヘランのアメリカ大使館を占領し、パフラヴィー2世の身柄引き渡しを要求します。
この事件がきっかけとなり、ロックフェラーは初めて公に、厳しいメディアの監視下に置かれることになりました。
それでは現在の外交問題評議会について少し見てみましょう。
現在の理事長は、ユダヤ系のビジネスマンであるデイヴィッド・ルーベンシュタインで、副理事長は、同じくユダヤ系の金融家のブレア・エフロンと、諜報アナリストのジャミ・ミシック、会長は、ユダヤ系の外交官、リチャード・ネイサン・ハースがつとめています。
――外交問題評議会のトップは、ユダヤ系が抑えているんですね。
外交問題評議会のメンバーは、終身会員と、5年間有効の定期会員の2種類があり、アメリカ市民、もしくはアメリカ市民権を申請した永住者のみが対象となっています。
2
019年には、ウラジーミル・プーチンと密接な繋がりを持つ、ユダヤ系でウクライナ生まれのイギリスの投資家、レオナルド・ブラヴァトニックから寄付を受けていたことが問題となりました。
――こちらもユダヤ系なんですね。
国際問題の専門家やロシアの専門家は、リチャード・ハースに手紙を書き、クレムリンと独裁ネットワークと緊密な関係を持ち、西側諸国で慈善活動を行っているプラヴァトニックとの関係を非難しています。
今回の話はここまでとなります。
関連記事
最後に
最後までお付き合いいただきありがとうございました。もし記事を読んで面白かったなと思った方はスキをクリックしていただけますと励みになります。
今度も引き続き読んでみたいなと感じましたらフォローも是非お願いします。何かご感想・ご要望などありましたら気軽にコメントお願いいたします。
Twitterの方も興味がありましたら覗いてみてください。
今回はここまでになります。それではまたのご訪問をお待ちしております。
今後の活動のためにご支援いただけますと助かります。 もし一連の活動にご関心がありましたらサポートのご協力お願いします。
