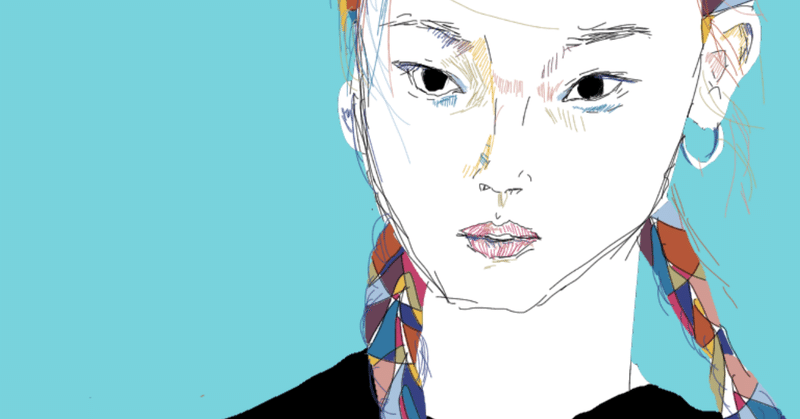
喜怒哀楽の、「怒」が綺麗な人がいる。
「二度と、うちの前を通らないでください。」
わたしは感情が隠せない人だった。
あの時のわたしは、誰かを守りたかったのだろう。誰のことが許せなかったのだろう。悪いのがあなたで、わたしが正しい。そこまでは言い過ぎだけど、きっと近くまできていた。
わたしは人より穏やかな性格だったと思う。それは幼い頃から今までも、ずっと。でも本当は誤魔化している。上品で、艶やかに。仕草ひとつひとつを零さないように心を動かす。そうやって自分を制御しなければ、わたしはまた簡単に人を刺してしまうのかもしれない。
恵まれていた。
わたしの家族は、皆わたしのことが好きだった。父も母も姉も、わたしのことが大好きだった。それはわたしからの気持ちも同じ。家族がわたしにとって一番の味方だった。自分も味方になろうとした、なりたかった。
失敗や、度重なる不幸。理不尽や、怠慢。わたしの全てを見てくれていた気がする。それでも手をいっぱいに広げて「幸せだった」と叫べないのはきっと両親の仲があまり良くなかったからだと思う。いや、これも当て付けだ。
わたしが社会人になり一人暮らしを始めると、すぐに父と母は別居した。ただ今も離婚はしていない。大学生まで実家暮らしだったわたしのために、ふたりがとりあえず同じ空間にいただけ。理由のなくなった両親がわたしの前で別居することを切り出した時、正直わたしは少し胸を撫で下ろしていた。
いつも、夜の10時くらいから始まっていた。
父と母は毎日のように夜、言い争いをしていた。ピークはわたしが大学生の頃だったと思う。何をそんなに言い合うことがあったのか。もう、何もかもが気にいらなかったのかもしれない。わたしは寝ようにも、うまく寝ることができない。父と母の、人を刺すような声色が今もふとした瞬間に脳裏をかすめる。
感覚的には5年か6年くらいの間、両親はぶつかり合っていた。自分の部屋にこもりつつも聞いていたから、わたしにも主となっていた話題はわかる。
" 離婚するか、しないかだった。"
そこで唯一のブレーキになっていたのがわたしの存在だったと、思う。「思いたい」と言うのが率直な気持ちだったりもするが。
わたしが大学を卒業するまでは少なくとも離婚はしない。それがまず父の言い分だった。けれど母は違った。今すぐにでも離婚したいと、毎日のように泣いていた。ただ結局は離婚しなかった。これも想像に過ぎないけれど、離婚したらわたしと姉が何より悲しんでしまうからな気がした。
近所にも怒鳴り声が届いていそうだった。それくらいの声が出た瞬間に、わたしは大学の課題をやっていようが、ベッドで横になっていようが、ふたりの間に入って泣きじゃくっていた。
" ふたりが言い争いをしているのが悲しい。"
それを当時わたしは必死にアピールしていた気がする。いまでも「泣いて」と言われればわたしはすぐに涙を流せる。俳優の人がしているものとは違う。誰も得をしない演技だけが身に付いてわたしは大人になった。
怒りのような感情に自分の悲しみを間に差し込み、中和させようとした。けれど感情を収めるためには、人と人との心をぶつけあうことによって解決するものではない、喜怒哀楽の、どの感情だとしても。
もっと、"余白"に近いもの。
それか"傾聴"という言葉が近いのだろうか。
今更思っても遅いのかもしれない。
わたしは両親の話をもっと聞くべきであった。自分が悲しんでいる、そんな訴えはかぎりなく無意味だった。
◇
悲しんでばかりだったわたしも人が変わったかのように、父と母、ひとりずつと話をする時は喜びと、楽しさで溢れていた。
ある日、母が仕事で外へ出かけ、かわって父が仕事が休みで家にいる日。逆のパターンでもいい。たまにあるそんな日だけは「哀」も「怒」も必要がなかった。仮初めにすぎないしれない。だとしてもわたしの家族がやっと許されているような心地になった。
わたしは幼い頃から父親っ子だった。
毎晩のように母と言い争いをしていようと、父にわたしはすり寄っていた。わたしと母の仲が悪かったわけではない、母が姉につきっきりなことが多かったのだ。
父の仕事が休みの日は、決まって家の庭でものづくりをしていた。木を切り、釘を打ち、今で言うDIYがわたしは好きだったのだ。
でも本当はわかっている。大人になってからわたしはものづくりをとんとしなくなった。父の「怒」を収める方法が、父の好きなものづくりを手伝うことだと子どもながらに気づいていたのだ。
「しをりと一緒にこうしているだけで、父さんは幸せだよ。」
わたしといる時の父の声色は弱々しく、母の前で激昂している姿とはまるで別人だった。
父も母も、本当は弱い人なのだと思う。
そもそも強い人なんてこの世には、少ない。強がることができるくらいで、人は皆悲しみの感情を引き出してしまう。それを隠すように喜び、怒り、楽しみがある。そして傾聴というのは、相手が弱いことを当たり前のように認めることから始まるのだと思う。もちろんこれは全てわたしの持論だ。
◇
父と庭でいつものように作業をしていた。
するとわたしたちの目の前で、自転車に乗った男が通り過ぎる。煙草を吸っており、男はわたしたちの家の前でそれをポイ捨てしたのだ。
その姿を見てわたしの頭は熱く腫れ上がり、音を立てた。怒りを整理するのであれば、わたしは自分の愛する人が傷つけられると黙っていられない性格だった。
解釈は勝手かもしれない。
ただ父の家の前で煙草をポイ捨てする行為が、父を侮辱されているような気がしたのだ。
わたしは自転車に乗っていた男を走って追いかけた。サンダルを履いていたけれど、遅くなると思いわたしは迷わず裸足になっていた。
「許さない、許さない。」
わたしは感情が隠せない人だった。
男を強引にわたしは呼び止め、ポイ捨てされた煙草を男に渡した。
「二度と、うちの前を通らないでください。」
男は明らかに怒りすぎなわたしを見て、すぐさま逃げていった。言い返されるかと思い、本当は少し怖かった。でもそんなことを考える余裕もなかった。
そんな怒ったわたしを見て、父はどうしていたか。
同じように怒っていたか、はたまた悲しんでいたか。
その、どちらでもなかった。
父はわたしの目線までおり、風のように体を包んでくれた。
「しをりが怒ってくれて、父さん少しホッとしたよ。ありがとう。」
その言葉を聞いた瞬間、わたしの目から涙がぽろぽろと溢れてくる。
どうしてわたし、こんなに怒っていたんだっけ。
どうしてわたし、こんなに泣いているんだっけ。
どうしてわたし、どうして。
わたしの感情は、父の"余白"によって瞬く間に薄まっていた。わたしも父に対して、母に対して、そうすればよかった。全てにおいて、遅い。人に寄り添う愛は、さざなみのように優しかったのだ。
◇
両親の怒りの日々、わたしが怒ったあの日。それを思い出したきっかけは"彼"の存在だった。
わたしは最愛の彼と同棲している。
大人になってから同性愛者になったわたしは、彼のことを心の底から愛していた。愛しているからこそ、彼のことが知りたくなる、心も全て。
彼はあまり感情を表に出さない人だった。それでもここまで彼と過ごしてきた日々で、喜びと楽しみ、そして悲しみは側で感じることができた。
彼の感情で、わたしが目にしたことがないもの、それは"怒り"だった。
穏やかだった。
わたしも芯からそうありたかった。
わたしは彼に、生活の一瞬で聞いていた。
「怒ることとか、あるんですか。」
「ありますよ全然、しをりさんは?」
「わたしはここ数年はないです、でも昔は何度か…」
「そうなんですね。僕は怒っても表に出すのが下手なんだと思います。だからかわかりませんが、街で怒っている人を見かけると、圧倒されます。」
「わたしは怒りが、すぐに恐怖に変わりますね。」
「喜怒哀楽のどれかがない人って、少ないと思うんです。だから怒ってしまうのは、しょうがない。傷は自分にも周りにも増えますけど、他人がどうにかできる問題ではない。ただ愛する人同士だったら話は変わりますね。」
「というと?」
「わたしは、愛する人が傷ついた、もしくは傷つく可能性が見えた瞬間に、怒ります。」
わたしは心の中でほくそ笑んでしまった。少しだけ自分に似ている彼に安心していたのかもしれない。ただその後、わたしの心はざわついた。
「ただ怒っても、心の中でじっくりじっくり感情をかき混ぜるんです。大きなお鍋に火をかけて、それをまた大きなおたまか何かでゆっくり混ぜる。そうすると、自分の気持ちの行き場も作れて、尚且つ相手も傷つけない、そんな結果に大抵落ち着くんです。」
わたしは彼のその言葉を聞いて、零れるように「綺麗ですね」と言った。
◇
わたしは喜怒哀楽がはっきりしている人を見ると安心する。見下しているわけではなく、「この人も人間なんだな」と思うのだ。感情があって当たり前。自分がそうだったからこそ、イコールにし、安堵を刷り込む。
わたしは"喜怒哀楽"という言葉が好き。
それを愛する人と共にし、生きてこそ幸せだと思っていた。こうして文章を書くときも思う。感情を、生傷を曝すようにわたしは描きたい。
彼のことを知って、わたしはまた一歩前に進んだ気がする。包む感情の尊さ。自分の心との向き合い方。
わたしは感情が隠せない人だった。
"隠せない"というのは、もしかするとわたしが愛されていたからなのかもしれない。
誰かを愛するために、喜怒哀楽を隠してもよかった。彼がわたしの隣にいる。もしこれから先、彼が傷つく姿を目の当たりにしたとき、わたしはどう生きるのだろう。
喜ぶだろうか、怒るだろうか、悲しむだろうか、楽しむだろうか。わたしは彼を守るために、かぎりなく無となり、余白を生み出したい。
心と体が破裂してしまわないように、マグマのような感情をわたしへと流し込む。熱を冷まし、傷を癒す。そのためにわたしは誰よりも喜怒哀楽を知っていなければいけない。
わたしは弱い人が、好き。
弱ければ弱いほど、人の痛みを知っている。
強くなった人が、またそれ以上に痛みを理解しているのだと思う。
家族もいて、わたしには彼もいる。
書いていて、わたしには友達もできた。
これからも、人の形を色付けるため。
生き方に、上手も、下手もない。
あなたから見たわたしは、ずっと弱いままでいい。
書き続ける勇気になっています。
