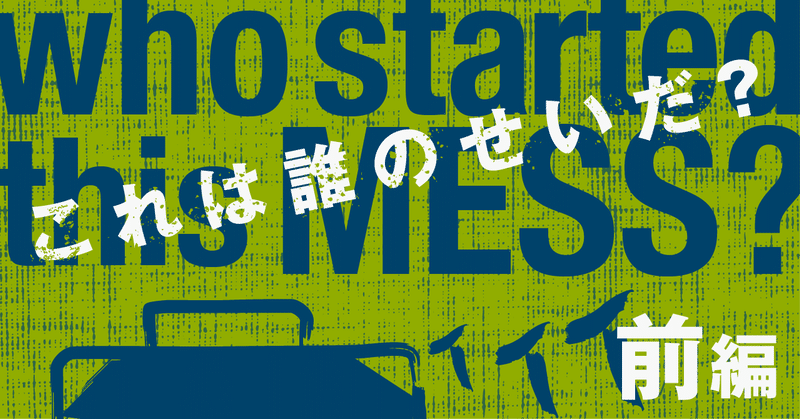
スピンオフ小説『これは誰のせいだ?』前編
この短編は、NovelJam2018秋(テーマ「家」)にて出版した小説『みんな釘のせいだ』のスピンオフ・ストーリー第二弾です!本編を読むとより楽しめる作品です。(著:最堂四期)
『これは誰のせいだ?』
釘の声が聞こえる男、宗方永治。相変わらずこの現象は、超能力かノイローゼかハッキリしない。
そして彼は再びノイローゼ気味になっていた。原因は、自宅に届く奇妙な手紙…。そんな中、特注の和釘を納品先に「直接」届けてほしいと叔母にお願いをされる。なぜ自分が? わからない。場所どこ? 隣県のはずれ。
和釘職人・宗方永治。賑やかな釘たちの声に振りまわされつつ、いざ出発、納品旅行!
――――――――――――――
宗方永治(むなかた・えいじ)は、和釘職人だ。それと同時に、悩みの多い男でもあった。その悩みは普通ではなく、どれもこれもが他人に想像しづらい内容だ。
そのうちひとつが「釘の声が聞こえる」という現象。
そういう力が目覚めたのか、ノイローゼが原因か。このことで苦労は続いているが、今の所、生活に支障はきたしていない。
もうひとつの悩みの方が今は深刻だ。
永治の自宅、テーブルの上にある、何通かの手紙。
「███て█ます」
歪んだ文字で綴られた、解読できない奇妙な言葉。差出人の住所氏名は無し、消印は隣県、身に覚えなし。宛先は確かに『宗方永治』。明確な嫌がらせとも言いがたく、しかしこのような手紙を受け取る覚えもないので気味が悪い。
これは誰のせいだ。まるで身に覚えがない。気味が悪い……。
今までに届いたのは四通という絶妙な数であり、こんなことで警察に相談してよいかも悩みどころだ。さらにはこの手紙が届くようになってから、釘の声がより鮮明に聞こえだしたことにもうんざりしている。
永治の精神状況と、釘の声が聞こえる事象は密接に絡んでいて、永治はひたすらノイローゼの悪化を感じていた。悪い連鎖である。
*
「なんだい、永治どうしたんだ。おっきなため息だったなぁ!」
永治の職場である工房。共に働いている叔父が、努めて明るく声をかける。
「なんか悩みごとかい?」
永治はその労りに「いや」とだけ返答する。世話になっている叔父に心配はかけたくないという、消極的な感情の吐露だ。
この和釘工房は、もともと宗方一族で運営していた小さな工房だ。その中心的存在だった永治の両親が火事で亡くなった後、叔父・叔母夫妻は永治の支えになってくれた。精神的な面でも、技術の指導という面でも。
何より叔父がつくった釘は賢くて良い……と思考を巡らせたところで、永治は「釘の声が聞こえる」ことを、当然の事象と認識していることを自覚した。
これはいけないと頬を叩く。眉間にシワを寄せて黙りこくっていた永治を見つめていた叔父は、改めて「本当に大丈夫か? 」と尋ねた。
「ありがとう。なんでも、ないんだ」
「相談ならいつでものるからさ、どーんと頼ってくれよな? 永治はほら、いろいろと抱えこむ所があるからなぁ!」
肩をポンポン叩き労ってくれる叔父の思いやりに、永治は一瞬、ほだされた。
「……実は、妙な手紙がきて」
「なんだなんだ、妙な手紙って。詐欺か、どんなだ? 警察よぶか! 」
顔色を変えた叔父を、今度は永治がおさめる側にまわった。
「詐欺じゃない、そんな大げさなものでもないんだ」
「いや最近な? 円佳宛てにもな、詐欺ハガキが来るようになってよお」
宗方円佳(むなかた・まどか)、叔母の名前である。
「訴訟だとかなんだって、ビビって調べたら、これが詐欺のハガキらしくてさ!」
「そういうものが……」
「ま、無視していいモンらしいから、腹いせにビリビリ破いてゴミ箱にぽい、よ。永治もそうすりゃいいさ」
『無視りょうかーい!』
『ムシするー』
『そしょうはんたーい』
永治の代わりに返事をしたのは、卓上に並べられたできたての和釘たちだ。
永治の耳が拾う釘の声は、和釘のみという条件があった。世間一般に流通している釘、いわゆる洋釘の声は聞こえない。普通に過ごしていれば、だが。
一度だけ、永治が姉と喧嘩した時に、街中の釘の声が聞こえるようになったことがある。ストレスが限界まで達した果ての出来事であり、そのこともあって永治はこの怪奇現象が「ノイローゼの症状」という疑いを捨てきれていない。どちらにせよ永治にとって好ましくない現象であることには変わりがない。
「さーて、もうひと仕事がんばろうか。最近は依頼もバリエーション豊かになって、忙しいなぁ、わはは」
空気を変えるために、叔父はカラカラと明るく笑いとばす。
『がんばれがんばれー』
『さて私たちは、出荷までひと眠りしましょ』
近年は伝統工芸が注目を浴びていて、やれ瓦の皿だ、だるまの花瓶だ、和釘の画鋲だと、和を感じさせる工芸品を生活に取り込もうとするブームが続いていた。宗方家の工房はもともと建造用の和釘をつくっていたが、最近は企画に応じた和釘をつくったり、伝統工芸ブームに着目した取材に応じたりと、仕事にも幅が生まれている。
『背が高い男がいるじゃん、あいつが僕らの言葉に反応してくれるんだって』
『ほんと? ちょっとやってみよう。おーいおーいおにいさーん』
永治は釘の声を無視するために視線を泳がせる。工房の壁に貼られた雑誌の切り抜きが目に入った。叔父が受けたインタビュー記事、字が細かいのでこの位置からは内容までは分からない。
ちょうど壁と永治の間に、叔母が割って入ってきた。永治と目があうと、にっこりとわざとらしい笑みを浮かべた。こういう笑顔をする時、叔母の言うことは決まっている。
「永ちゃんに、頼みたいことがあるの!」
返答をする前から、おねがい、とウィンクしつつ片手で拝む叔母。永治は反抗しようとは思わない。素直に次の言葉を待つ。
「和釘をね、届けてほしいのよ」
「郵便局に?」
「ううん、お客さんがね、永ちゃんに直接届けて欲しいって。本当に、本当に熱心にお願いされちゃってね」
「相手が来ればいい話だろうに」
理不尽な要求に愚痴っぽく言葉を返す永治。
「そうだそうだ!」
叔父も同調し、援護射撃をしてくれる。
「うちはなあ、イケメンを宅配するサービスはやっていないんだぞ~」
「叔父さんそうじゃない」
「それがね、お客さんが重実さんの古い知人らしくってねぇ。叔母さん断れなくって、オホホホ」
重実(かさね)とは、亡くなった永治の父の名だ。バツの悪さをわざとらしい笑みでごまかす叔母。兄さんの客ならしょうがないかと、叔父もすごすごと引き下がった。
*
日付指定で、明日の午後五時。提示されたのは隣県のはずれの住所。
依頼人の名は藍槌燈界(あいづち・とうかい)。アクのある字面なので、ペンネームかと永治は疑った。
そして、届けるべき荷物。てっきり箱いっぱいの和釘を運ばされると思いきや、渡されたのは造りの立派な桐の箱。開けてみれば、白い中敷きに三本の大振りな和釘が並べられていた。
『あっようやく開けてくれた』
声が聞こえたので、すぐに蓋を閉じる。蓋の内側から三本分 の文句が聞こえたが、永治は無視して箱を玄関先に放置した。永治の住む家は「釘が一切使われていない」という、まさに彼にとっての安息の地なのだ。自宅で釘に関わる気は無い。
『えーん、お話しましょうよ~』
『納品前夜ですよ! 話しあって士気を高めるべきではありませんか!』
『ここ狭ぇーんだよ!』
いつにもましてやかましい釘たちだ。ニ週間前に叔父から「ちょいと特殊なんだよね」と前置きされ、共に造った特注の和釘であることを永治は覚えている。
大ぶりのペンほどのサイズのそれは、銀色と黒色金属のまだら模様だ。永治は思わず「現代アートの展示にでも使うのか」と尋ねるくらいにはデザイン性を優先したような一品で。叔父ですら冗談半分に『マーブル釘』と呼んでいた。
「ちょっとした旅行と思って、おいしいもの食べてきなさい!」
叔母はそう告げ、なんだったら泊りがけでもいいから、と多めに交通費を託してくれた。
旅行、とひとりごちると永治はクローゼット奥深くに眠っていたボストンバッグ をひっぱりだした。とはいえ必要な荷物は下着の替え程度しか思い浮かばない。乱雑に放り込んでも、バッグにはまだまだ余裕があった。
『明日は何時出発ですか? モーニングコールしてあげますよ!』
『アイツ工房に来るのもギリギリだもんな。多分寝坊するタイプだぜ』
『わあ、わたしたち、責任重大だね!』
勝手に永治のモーニングコールを引き受ける気満々の釘たち。永治は無言で玄関に足を運ぶと、下着だけ入ったボストンバッグに桐の箱を押し込んだ。チャックを締めると声が遠くなる。これでよし、と永治は満足そうに玄関先にバッグを置いた。
この家は怪奇現象ないし神経症に侵食されてたまるものか。そう思ってテーブルに目を向ければ、そこには差出人不明の手紙が重ねられている。
『ま、無視していいモンらしいから、腹いせにビリビリ破いてゴミ箱にぽい、よ。永治もそうすりゃいいさ』
叔父の声が脳裏をよぎった。永治はテーブルに近づくと、白い便箋に指先を這わせ、「███て█ます」の文字をなぞって……しかし迷ったままの指先は、便箋から離れてそれっきり。
実はポストに五通目が届いていたのだが、永治が気づくことはなく、一日が終わった。
*
『いやもうほんっと信じらんねぇ、薄情者だよテメェは! オレらがどんだけ声を枯らしたと思ってんだ! 精神が鬼! 鬼畜ってやつ!』
『無視ですか。まだ無視するんですね。昨夜からずっとそうでしたもんね。そういうスタンスでいくんですね永治さん!』
『箱の中、やなんですよー、外だしてエイジさん!』
永治の格好はTシャツにジーパン、その上にパーカー、そしてキャップ。腕にはきりの箱入りボストンバッグ。面倒なおつかいに舌打ちをしつつ、永治は駅のホームで電車を待つ。
釘たちは昨晩の対応に思うことがあるようだったが、肝心の永治はぐっすりと眠ったので釘の声なんて聞こえていなかった。朝は釘によるモーニングコールではなく、五分起きになるアラームの六回目で起床した。
『永治さんの性格上、すぐに箱の中から出してくれるとは限りませんね』
『どうすりゃいいんだよ、オレだって外がみてぇよ』
『まずは簡単な要求をして、それに応じさせましょう。どんどん段階的に要求をあげていけば、最終的に大きな要望も通るんです。フット・イン・ザ・ドアというテクニックだそうですよ』
どこでそんなことを知ったんだ、と永治は思わず苦虫を噛み潰したような顔を浮かべる。これまでに付きあってきた和釘とは、一線を画する饒舌さと思考回路を持つ釘だ。
それとも永治の知らない先で、和釘も人間の子のように成長していくのかもしれない。この和釘たちは工房内の神棚近くにある棚に、二週間も安置されていたものだ……。
『おっけ、まずは簡単な要求だね。エイジさーん、呼吸して?』
永治はそっと、息をとめる。
『……どうかな。うまくいったと思う?』
『見えないからわかんねぇ』
『息遣いで把握しましょう。彼は……なんと、呼吸をしていないようです!』
『ええ、死んじゃうじゃん!』
永治は素潜りで二十五メートルプールを泳ぎきれる男だ。
『やだやだエイジさん死なないで!』
永治は、生きている。
『……今のも僕らの要求にカウントしておきましょうね』
『見えないから、生きてんのかもわかんねぇな』
『シュレディンガーの永治さんですね』
快速電車がホームに滑り込む。そこそこ人が乗っていたので、永治は躊躇した。他人に釘の声は聞こえないというのは理解している。それでもこの饒舌な三本の釘入りカバンを抱えて飛び込むのは、勇気がいることだった。
少しだけ迷って、結局反対側で待機していた、人のまばらな普通電車に乗り込む。
『揺れを感じます!』
『生きてる! エイジさん、生きてる! よかった!』
『よーし、要求を飲ませる第一関門は突破だぜ!』
バカバカしい、と永治は大きな大きなため息をついた。
*
早めに家を出たので、普通電車でも指定の時間には間に合うだろう。それを見越して永治は、スマートフォンで現地の食事処を探す。叔母のいうとおり、美味しいものでも食べて気分転換をしようと思っていた。
しかし、電車に揺られる思考領域の大半を占めるのは、あの手紙の存在だ。
己は誰かから、嫌がらせを受けるようなことをしたのだろうか?
日常生活は工房と自宅の間を行き来するだけの毎日。同業者から恨みを買ったとも思いがたい。たまにある交流会は終始ほがらかな雰囲気で進行している。酒にはめっぽう強いので、酔って不興を買った覚えもない。
釘の声案件や、姉の離婚の話もあって、恋愛を意識する心の余裕はない。自分の技術の向上と、商売繁盛を願うばかりだ。
じゃあ、これは誰のせいだ?
真意の見えない謎の手紙の存在は、恐怖というより困惑が増すばかり。
『あーもうお手あげだ。生きててほしい、呼吸をしてほしい、ここからどうやって箱から出せに繋げりゃいーんだ? フット・イン・ザ・ドアめっちゃむずいわ』
『んふふ、今これって電車にいるんだよね! 振動すごいよ、くせになりそう!』
『僕は不快ですよ。僕らはVIP待遇だと芳成さんは言っていたのに、この扱いはまるで囚人の輸送……!』
宗方芳成(むなかた・ほうせい)、これは叔父の名前である。この和釘たちは職人たちを名前で区別する程度には知能がある。永治は空恐ろしく感じてつばを飲みこんだ。
一方、心のどこかでは、己が叔父の名前を知っているから「ノイローゼの発露」が名を認識していてもおかしくはないと、ゆらゆらした現実逃避を試みてもいた。
『ああ、そういえば、永治さんは芳成さんに非常に弱いようでしたね』
『そんな感じしたね!』
『おーいエイジ、オレらの要求飲まねぇと、ホウセイにチクっぞ!』
釘に上下関係まで把握されている。イラつきが頂点に達し、永治はボストンバッグに口を寄せて小声で呟いた。
「納品されるのに、どうチクるって言うんだよ」
バッグの中から返ってきたのは、歓喜の声だ。
『返事してくれた! 会話できたよ!』
『効いたみたいだな、今の作戦!』
『たしかな手応えを得ましたね!』
騒ぐ和釘たちの声に、永治は大きめの舌打ちを返す。前の座席に座っていた老人が、驚いて永治を見た。永治はすみませんと小声でつぶやき頭を下げる。
どうしてこんな目に……イラつきから、永治の貧乏ゆすりが加速する。今度は近くに座っていた親子連れが、永治から距離を取るために席を立って移動した。
『おい、誰かマドカの声真似できねぇか?』
『そうか、永治さんは円佳さんにも、とんでもなく従順でしたね!』
『でも、あのまったりした声、再現難しいよ~』
『外が見たいわぁ、永ちゃん』
『うわあ、言い方似てる! スッゴイ! モノマネ芸人になれるよ!』
むしろ言い方しか似ていないともいえる。
さらには釘に「永ちゃん」呼ばわりされるのは地味にこたえる。
永治は釘たちから距離をとるために、ボストンバッグを網棚の上に置いた。乗車口脇に立つ学生たちが、ボストンバッグを指差しひそひそと喋っている。
まさか彼らにも釘の声が、と疑問に思って耳をすますと。
「あれさ、荷物放置するつもりじゃない」
「ああ、危険物放置、最近多いってニュースでやってたやつ」
見ず知らずの男を犯罪者扱いする不遜な会話が聞こえてきた。キャップ帽を深くかぶっていることが、永治の不審者感を増長しているのかもしれない。
『建物がみた~い~』
『ビルディング!!』
『タワーマンションー!』
網棚の上からは、フット・イン・ザ・ドアの次の段階に入ろうとする和釘たちの声。ちなみに今走っている電車は郊外に向けたものなので、窓の外を通り過ぎるのは川と田んぼと低い家屋ばかりだ。
ようやく今日の昼食の店のあたりをつけた所で、電車が急カーブに差し掛かる。運悪く、網棚からボストンバッグが落ちてきた。深刻な音はしなかったので、下着がうまいことクッションの機能を果たしたのかもしれない。
『いったぁい!』
『なにすんだエイジ!』
『釘の虐待は許されないことですよ!』
己のせいではないのに和釘たちに責められる。
『さっきのでケガしちゃったかも~! 開けて確認してみない?』
『あ、それいい作戦ですね! とてもいい誘導です』
『オラ、傷だらけの釘を先方にお渡しする気かエイジ!』
『僕ら特注の釘ですよ! 特別製なんですよ!』
「ああっ、くそっ」
業を煮やして立ち上がる永治。彼のイライラした動作に注目していた乗客たちは、急な大声に驚いた反応を見せる。電車はタイミングよく次の駅のホームに到着したところだ。
永治はバッグをひっつかむと、逃げるように電車を飛び出した。
*
「チッ」
機嫌が悪くなるにつれ、すっかり柄が悪くなった永治。今はレンタカーの運転席に座っている。場所は駅近くのコンビニの駐車場。昼食代わりのおにぎりを、もっさもっさと食べている。
助手席には蓋をはずされた桐の箱。その中におさめられた、大ぶりの和釘が三本。
『フット・イン・ザ・ドア大成功……』
『陽の光が、あったけぇな……』
『僕らは打ち込まれた場所によっては、日光を浴びることはできないですからね。このぬくもりをいつまでも覚えておきましょう』
和釘の会話を、永治は白い目で見ながらおにぎりを食す。永治の精神状況を反映してか、鮭おにぎりは粘土のような食べ心地だった。その昔、きょうだいゲンカをして母親にこっぴどく叱られた後の夕食と同じ食感をしていた。
『どこに刺されてもオレたち、ずっと友達だからな!』
『当たり前だよ!』
『ふふ、同期ですからね』
友情を感じさせるアツい会話だが、見る限りはただ箱に並べられた三本の釘であり、それ以上でもそれ以下でもない。視覚情報と聴覚情報が一致せず、永治は頭痛すら覚える。
『いや~でも本当に、永治さんの判断は正しいですよ』
急に和釘に話しかけられたが、永治は返答をせずにペットボトルの茶を己の胃に流し込む。本来であれば、あたりをつけた店で美味しい食事をとるつもりだったのにと不満も募る。
『電車の中だと、僕らと気軽に喋れないですものね。人目のあるところで騒いで本当に申し訳ありませんでした』
「物分りのいいフリをするんじゃない」
ただ確かに、レンタカーに閉じこもったのは正解だと思える。和釘の要求を聞きながら電車でゆっくりと目的地に向かうのは、永治の気落ちを加速させるだけだった。
『多分エイジさん、恥ずかしがり屋なんだよ。だから人前ではおしゃべりできないの』
「全然ちがう」
『ホウセイ相手に、ずっと恐縮してるもんなあ』
「うるさいな……ほんと、なんなんだよこいつらは」
背もたれにぐったりと全体重を預ける。運転する前から疲弊するのはよくない。カーナビを目的地に設定すると、残り二時間という表示が出た。予定通りなら、電車に乗ってぼんやり外を眺めているだけで着いているはずだったのに。
『せっかくだもんね、楽しくおしゃべりしながら納品先へ向かっちゃお』
「お前らだけでおしゃべりしておけ」
『つれないですねぇ、旅は道連れ世は情けですよ』
「お前らはどこでそんな言葉を覚えるんだ。いや、フット・イン・ザ・ドアとか、シュレディンガーとか……叔父さんと俺だって、工房でそんなことは話さないぞ」
『そんなの、マドカが流しっぱなしのラジオで言ってたぞ』
謎がとけた。この三本がやたら口達者なのは、長らく作業場に置かれ、耳にする情報が多かったからだ。耳にする、という言い方も、釘に対してどうかとは思うが。
「マドカって、おい。他人をそう気安く呼ぶんじゃない」
永治はアクセルを踏む。電車賃が無駄になった永治は、やけっぱちでランクの高い車をレンタルした。走り出しは好調で、気分がわずかに上がる。
『僕らのことも気安く呼んでいいんですよ! これでフェアですね』
「そういう問題じゃない。それにお前たちに名前なんてない」
『そんなら、オレのことは平等院鳳凰って呼べよな!』
『僕のことはドクター宗方でお願いします』
『わたしは恋するウサギちゃんがいいな』
「なぁ、それ、ラジオネームを参考にしただろう?」
勝手にうちの名字を名乗るなとか、ミュージック・アワーはマズイ、だの言いくるめを試みると、今度は永治が名前をつけろと三本に抗議されてしまった。
「そうは言っても、見た目が一緒だから名付けのきっかけがな」
『見た目が一緒、ですって? 人間だって似たようなものでしょうに』
「その考え、本当にラジオから得たものなのか?」
和釘が持論を語ろうとする予兆を声色から感じたので、永治は釘たちの簡単な要求を飲むことに決めた。
「A、B、Cでいいだろう」
赤信号なので車を停める。窓の外、横断歩道を、園児たちが並んで歩いていく。
「お前が釘Aで、お前が釘B。お前が釘Cだ」
指先で順番に触れて指名する。釘に触覚があるかは分からぬことだが、釘たちはそれぞれ把握したようだ。
『クギエイって、エイジから名前をもらったってことかよ?』
「違うなぁ」
『クギビーって、ダサすぎませんか! そんなネーミングセンスでよくこれまで生きていけましたね?』
「名前ひとつで俺の人生まで否定するんじゃない」
『クギシー、エキゾチックでいい感じ……』
「それは……何よりだ」
青信号に変わったので、ゆっくりと加速する。車は海沿いの道を走る。青い空、青い海、助手席には和釘の入った桐の箱。一応、気晴らしにはなっていると。永治は己の心を慰める。奇妙な旅路だ。こんなはずではなかった。
『クギビーはいやです、本当に本当にいやなんですー!』
「じゃあ別案で、釘1号、2号、3号だ」
『1号! それは悪くないな』
『いやです! 番号って序列っぽくていやですよ!』
「序列なんて気にするのか?」
『エーからシーまでは並列っぽいですが、123って、優位性を内包するじゃないですか!』
「釘がそんなことを気にしなくていいと思う」
『私、クギシーの方が好きだった……』
『もう自分で名前を決めます! 僕のことはムナカタって呼んでください!』
「だから、うちの苗字を勝手に名乗るな」
『なぜです、自分の出生地を誇りに思って何が悪いんですか!』
そう言われると、そんなに悪い気はしない。永治は反論しようとしたが、結局言葉が続かなかった。
『オレは1号!』
『僕はムナカタです』
『私はクギシー』
釘たちは、各々の名前を把握した。
「方向性がバラバラの名前だな……」
『そうは言いますけれど、永治さん、近親者で名前が似ていない人だって多いじゃないですか。そういうものですよ、名前なんて』
永治はまず自分の姉の名を、それから叔父と父の名を思い浮かべた。
智世(ちせ)と永治、芳成と重実。
確かにきょうだいで名が似ていると言いきれる名前ではない。方向性は、釘達のそれよりは揃っているように思うが。
『ムナカタかしこい~すごい!』
『完全に論破したな』
「調子に乗るなよ1号」
名前をつけたことで文句の対象がはっきりしたのは良いことかもしれない。しかし見た目はさっぱり区別がつかなかった。
また赤信号に捕まったので、永治は和釘を一本、手にとってみる。
『コラコラ優しく触れよ! 特別製なんだからな!』
「お前が1号か」
光の反射でわかったことだが、釘の表面にひっかき傷のようなものがついていた。鉄の身に傷がそう簡単につくわけではないので、作成段階でわざと付けられたのだろう。永治がやった覚えはないので、おそらく叔父による加工だ。
三本の線に対し、おやと思って、今度は別の釘を手にとる。
『あの、エイジさん』
この弱々しい喋り方はクギシーだ。刻まれている線は、二本。
「ひょっとして、1号は3号という名前が正しかったのかもな」
最後に残ったムナカタを手に取る。刻まれている線は一本。これらは、何らかの意図をもって入れられている。
信号が青に変わったので、永治は投げ捨てるように桐の箱にムナカタを戻した。
『わ、もっと大事に扱ってくださいよ!』
「許せ、運転中だ」
『僕ら特別なんですよ! VIPなんですよ! 作成者のくせにこの自覚のなさ……呆れますね!』
「そう怒るなって」
『円佳さんの爪の垢を煎じて飲んでください! 東京ドーム一杯分!』
「多い、多すぎる」
『あ~でも分かるぜ、マドカの扱い方、気分よかったよな』
『円佳さんは僕たちを丁寧にみがき、桐の箱におさめてくれた……仕事が丁寧なお方です』
『これだけ立派なら先方も喜んでくれる、って話しかけながらみがいてくれて……今でもしっかり思い出せるよ』
「叔母さん、何にでも話しかけるからなぁ」
迷い込む野良猫から、庭先の観葉植物まで。しかし和釘に話しかけていたとは知らなかった。和釘を丁寧に箱に収める叔母を想像し、なるほど彼女なら話しかけそうだと納得を覚える。
『マドカは褒め上手だったよなァ、ハイカラだとかマーベラスとかさ』
『最高の和釘とも言ってくれてましたよ』
『えへへ』
誇らしげに言葉を交わす和釘たち。永治だって、ほんのり嬉しい。
この和釘は、いつも以上に気をつかって生み出した、叔父との共同制作物だ。特別な釘を己にも任せてもらえるようになったということは、永治だって職人として成長していることに他ならない。
もちろんその気持ちを、三本の和釘に悟られるわけにはいかない。茶化される声が容易に思い浮かぶ。
永治は表情を引き締めるとハンドルを強く握りなおした。次の信号を左ですという、無機質なカーナビの音声は釘たちの騒ぐ声でかき消されたのであった。
(前半・了)
スピンオフ小説「これは誰のせいだ?」
後編はこちら!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
