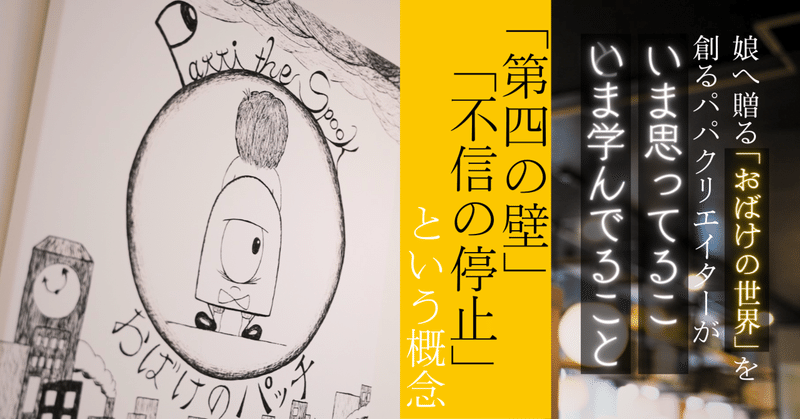
「第四の壁」「不信の停止」という概念
どうも池本です。
今日から私が書くnoteの記事は、メンバーシップ限定公開になります。
と言っても、課金の代わりにみなさんに何か有益な情報を提供するってわけではなく、もう私が「いま思っていること」や「学んでいること」を公開しなくてもいいかなと思ったものの、頭の中の整理という意味で文章を打つことは続けたいのでこういう形になりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
というわけで今日は『第四の壁とか不信の停止という概念』というお話をさせて頂きます。
「第四の壁」とは
この言葉を聞いたことあるだろうか。
第四の壁(だいしのかべ、だいよんのかべ、英: fourth wall)は、舞台と客席を分ける一線のこと。(中略)想像上の見えない壁であり、フィクションである演劇内の世界と観客のいる現実世界との境界を表す概念である。
ウィキペディアにはこう書いてある。
いまメタバース"The Sandbox"に創っている「おばけの街」に、劇場を設置するうえで、「劇場」「舞台」「プロセニアム・アーチ」などについて調べている中でこの言葉を知った。

19世紀ごろ、西洋演劇界で発生した言葉らしいが、要するに下の画像のような昔ながらのアーチのついたTHE劇場の舞台で、その「アーチの中(舞台上)」で起きていることはフィクションであり、その様子を観察しているのだと「アーチの外(観客席)」から見ている人が感じてしまう壁のことらしい。
※このアーチが「プロセニアム・アーチ」っていうらしいよ。

そもそも第四の壁が発生する元となった「プロセニアム・アーチ」が出来上がる前の劇場というのは、舞台が客席に張り出した状態……歌舞伎とかに近い状態だったみたいで。
「プロセニアム・アーチ」の舞台は理論上正面からしか見ることができないのに対し、多方面から舞台を見ることができたみたい。
ちなみに、「プロセニアム・アーチ」自体は「幕を張る」ことを容易にするために設置されていて。
なんでかっていうと、張り出しの舞台に比べて場面転換や美術の移動などが圧倒的に楽だし、大掛かりな転換ができるから。
という歴史も面白いのだけど、今日はそういう話ではなくて大事なことは「第四の壁があると、壁の向こう側を見る人は『観察』している気分になるみたい」ってこと。
「不信の停止」という概念を混ぜてみる
でだ。
この「第四の壁」に「不信の停止」という概念を混ぜてみる。
ちなみに「不信の停止」とはこんな感じ。
(中略)人が作り話を鑑賞するとき、懐疑心を抑制し、それが現実ではないことを忘れ、創作された世界に入り込む様子を指す。
例えばポケモンを見て、「いや10万ボルトの電気を発するネズミなんていないでしょ何言ってんの馬鹿じゃないの訴えるよ?」ってマジレスする人いないでしょっていう。
あれは「ポケモン」っていうゲームの中の「作り話」なので。
「ハリーポッター」を見たときに、「箒で空なんて飛べないだろ頭おかしいんじゃないのほらやってみろよ」っていう人いないでしょっていう。
あれは「ハリーポッター」っていう小説の中の「作り話」なので。
だけど、その作り話の非現実的な部分には目をつむりつつ……。
その創作された世界に入り込んじゃうよね。
「嘘だ」「非現実的だ」と分かっているのに。
これが「不信の停止」。
で、これを「第四の壁」と混ぜてみようって話。
するとどうなる?
人々は安心安全を保障された世界にいながら、海を渡り、炎を縫い、雷を起こす、そんな世界を「観測する側」になれてしまった。
しかもその世界が嘘だとわかっている。
現実にはないお話だと分かっているのにもかかわらず見入ってしまう。
私はこれが「スマホ」なんじゃないかなと思っている。
何かつかんだわけじゃないが
まぁ「第四の壁」は演者と観客の間に生まれる心理の壁なので、どちらかというといいことではないのですよ。
なので「第四の壁」って調べてみると、打破方法がいっぱい出てきます。
けどその壁のおかげで「こっちとあっちは別世界」と認識させることで、「不信の停止」をうまく使えるんじゃないかなって思ってるんです。
しかも私たちには現代の「第四の壁」である「スマホ」を誰もが持っているわけですから。
なのでこれらの概念を知ってるか知らないかでいうと、知っていた方がいいかなってくらいの話でしたがまとめておきました。
では。
スタジオパッチ
いけもとしょう
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
