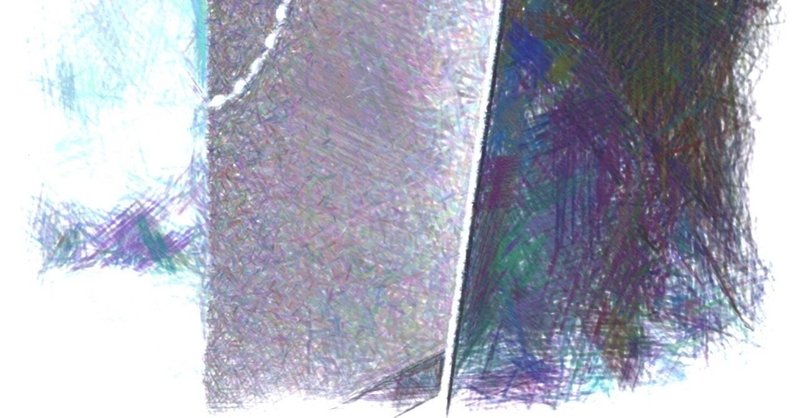
[短編]留守番電話についての考察
20191006
「翻訳作業の途中で申し訳ないのですが、あなた宛に一件留守番電話が入っていましたよ。〇〇研究所のカラトウさんから至急折り返しの電話を入れて欲しいだそうです。」
「わかった、伝言ありがとう。」
埃をかぶった午後の日曜日は、残暑を少しばかりと秋の匂いが少し混ざった空気を部屋の中に広げていた。普段なら、昼寝から目を覚ましてキッチンへとコーヒーを入れに行くタイミングだが、生憎、締め切り期限の仕事を処理し切ることに精一杯だった。だから、この唐突な電話に対して、私は少しばかりめんどくささを感じていた。急な用事とは一体なんなのだろうかと少しばかり疑問には思うものの、目下のところは今ある仕事を片付けることに集中した今気分だった。私は、沈むようなため息をついた後、電話を手に持った。
「クミニチです。カラトウさんいらっしゃいますか?」
「カラトウだ、先ほど電話をかけたのだが、どうやらいなかったみたいなのでね少し焦ったよ。折り返しの電話ありがとう。」
カラトウはいつもより少し早口で、いかにも冷静を装った風に答えた。
「実は、君に頼みがあって。いや、君が忙しいのならいいのだけれどもね。私にとっては切実な頼みでね、是非とも聞いてほしいと思っているんだ。いや、無理にとは言わない、できればでいいんだ、謝礼は払う、今度飲みにいった時に、奢らせてもらうよ。」
私は、面倒くさいことになったと頭の中で考えつつ彼の話を聞いていた、第一、わたしにはそんな余裕はないのだ、立て込んでいる仕事もあるし、今夜は、クライアントとのディナーもある。私はカラトウの話を遮って、申し訳ないけれど、今はとても無理だと答えようとした、そう、まさに答えようとした。それを遮るように、カラトウは電話口でいつもより大きな声で、アクセントをつけるように、言った。
「今日は娘のピアノの発表会だったんだ、私はすっかり忘れていた。娘を怒らせてしまう、今度怒らせたらもう口を聞いてもらえなくなるんだ。せめてもとして、会場に近い君に見に行って欲しい。お願いだ、できればで父の代わりに来たと娘に伝えてくれ。」
私はやれやれとため息をついた。
映画を観に行きます。
