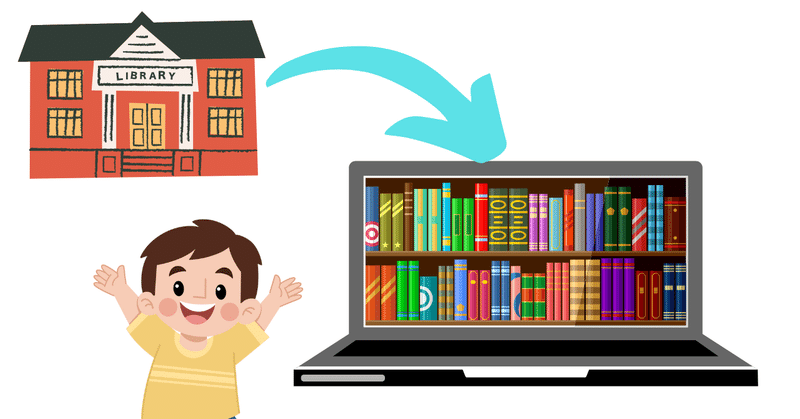
情報紹介25「国会図書館から学校図書館を経由して個人端末にわいわい文庫を貸し出す」
読みに困難がある子も読める音声付きの図書を、
学校図書館から貸し出せる方法です(⌒▽⌒)
ここ数年、めっちゃあちこちで激推し中なんで、
すっかりここにも書いた気でいましたが、
気でいただけだったんで、慌てて記事にしてます(^_^;)
「私のnoteに記事であげてますから、ぜひそちらをみてくださいね」
といい加減なことをお伝えしてしまった皆様、申し訳ありません(反省中)
で、ココから本題です。
読むことに困難を持つ子がすべての学校、すべての教室にいると言われている今なのに、
依然として学校図書館には「紙の本」しかないことが圧倒的に多いです。
本=紙のもの
という意識があまりにも「当たり前」になりすぎていて、
「学校図書館」なのにそこを活用できない子がいることはおかしい
と気づいてもらえない状況。
読むことに困難がある子たちだからこそ、実はたっぷり読書が必要なんですよね。
読むことに困難があると、言葉や文章に触れる機会がどうしても少なくなってしまうので。
そのためには「紙の本以外」での読書が選べる必要があります。
それなのに「学校図書館」には紙の本しかない・・・。
こんな状況をなんとかしたくて、読書バリアフリーなんて言葉が出てくる前から、いろいろと取り組んでいました。
でも、続かなかった・・・。
「これはいい」「有効だ」と感じても、推進する人が転勤すると、フェイドアウトしてしまうんですよね( ; ; )
そこには、「紙以外の読書」を支えるための
・コンテンツの準備
・端末の準備
の両方に負担が大きい現実があったからではないかと思っています。
電子書籍をいろいろと試してみた時のまとめがこちらになります。
この時もかなり成果は上がったし、
なんとかアクセスしやすいように工夫もしたんですが、
やっぱり私が転勤して以降、継続は難しかったようです。
読書は日常のものだと思うし、
「読みたい本が読める」
「読みたい本が選べる」
って本当に大切だと思うし、
なんとかならないかなあと思っていたら、、、
「わいわい文庫が国会図書館に入る」
「国会図書館から、学校図書館経由で子供たちに貸し出すこともできる」
という情報が入ってきました。
もう「これだ!!」でしたね。
時はギガ端末の整備が進み始めたタイミングです。
・図書館で借りることができるシステム
・自分の端末で自分のペースで読むことができる環境
この2つがあれば、今度こそ「継続可能な読書環境」ができると思ったんですよね。
で、いろいろ準備をしてスタートしたのが2021年の2学期末でした。
準備もそんなに難しくないです。
・学校図書館が承認館になるための書類の提出→通るとIDとパスワードが発行され、国会図書館からのデータの貸し出しシステムにアクセスできるようになります。
・共有と読み上げのためのアプリのアカウント取得(うちはChromebookなのでChattyBooks オンラインのアカウントの取得
・児童の端末にChattyBooks のアプリをインストールしてアカウントを設定
上の3つをすれば、国会図書館→学校図書館→児童端末
への貸し出しが可能になります。
もちろん、周辺準備として
・読みたい本を選ぶための書影ポスターを閲覧できるようにする

・「読みたいですカード」「読みましたカード」の準備をする
といったことは必要です。
まずは本を選ぶのはこんな感じ

さらに、従来の貸し出しがこんな感じだとすると

端末への貸し出しはこんな感じ

これ、最初の設定関係が終わったら、そこからは本当にスムーズ!!
2021年の2学期末から始めて1年半以上になりますが、
子ども達にも一部の教員にも負担になることがないため、
継続し、広がりも見せています!!
もちろん、手続きをしてくださる司書さんにはお仕事が増えてしまいますが、
「子どもたちが「本を楽しめる」環境を作るのが仕事だから」と、
ものすごく協力的です(⌒▽⌒)
市内の司書会で共有して、他校でもこのシステムを入れる学校が出てきています。
どの学校にも読みに困難がある子がいるというなら、
どの学校でのこのシステムを入れて欲しい!!!
というか、
その選択肢がなければいけないと思うんですよね。
「国会図書館から貸し出さなくても、わいわい文庫のCDがあれば、そこからChattyBooksオンラインに送ればいいのでは?」と思われた方もおられると思います。
もちろん、それでも同じように貸し出しはできます。
しかし、どんどん国会図書館からの貸し出しを利用することで、「このサービスを必要としている子がたくさんいる」ことを示していくことが、読書バリアフリーの広がりにつながると考えています。
そして、公立の図書館にはこうしたシステムが多く入っていますし、入っていなければ要望して入れてもらうこともできると思います。
学校図書館で親しんだ読書の方法や本へのアクセスの手立ては、
大人になっても公共図書館で利用しますよね。
それは、紙の本では読むことの困難が大きな子たちにとっても同じだと思います。
生涯にわたって読書を楽しんでいくために、学校図書館のバリアフリー化を今後も進めていきたいです(⌒▽⌒)
関連資料として
先日読書バリアフリーの会でお話しさせていただいた時の資料を置いときますね(⌒▽⌒)
今回ご紹介したシステムに至るまでの話も載ってます(⌒▽⌒)
それから、6月に文科省のページに掲載されたリーフレットにも、
うちの学校でやっている貸し出しシステムの話が出ています(⌒▽⌒)
上のリンクを開けていただいて、少し下の方
「子供の読書活動の推進等に関する調査研究」のところの
R4_リーフレット(電子図書館・電子書籍と子供の読書活動推進に関する実態調査)
からダウンロードできます(⌒▽⌒)
それから、去年のLD学会の自主進歩で発表したご縁で会報誌から声をかけていただき、会報124号に「インクルーシブな学校図書館を目指しての取り組み」として掲載していただいていますので、会員の方はマイページからもご覧いただけます(⌒▽⌒)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
