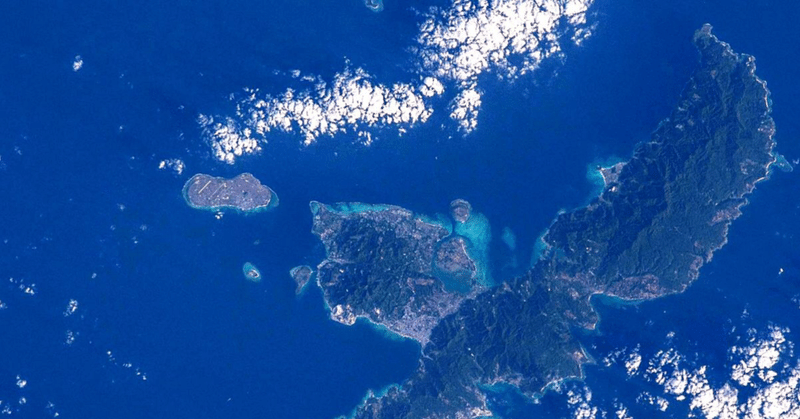
琉球廻戦 9
【玖】
島袋は自らが野球を始めた頃の事を思い出していた。あれは小学生の頃だったか、両親に初めて連れられていったプロ野球の試合に感動したからだったと思う。野球をやりたいと言った自分に、父親は最高級のバットとグローブをプレゼントしてくれた。両親は交通事故で他界してしまったが、自分が腐らず前向きに生きてこれたのはプロ野球選手になる夢があったからだ。県内屈指の野球名門校の豪南高校に野球推薦で入ってからは、それまで以上に更に練習に打ち込んだ。
プロ野球選手になるという夢は、両親から与えられた最大の贈り物だった。
それをたかだか甲子園に出場できなかったから、ぐらいの理由で諦めて自暴自棄になり、剰えヤクザになりたいとか、そんな刹那的で破滅的な人生の選択を考えた自分を恥じた。
今自分の眼下に広がっている光景は愚米仙という酒の齎すものではあるにせよ、詰まるところ「真面目に生きなかった」人間の末路そのものの様に思えたからだ。
「551がある時ぃぃぃ!」
暑川は再びそう叫ぶと今度は反対の左耳をむしり取って口に入れて咀嚼し、ぶるぶると震えながら今度は
「無い時ぃぃぃ!」
と叫んで右手の親指を力一杯噛み締めて骨ごと食いちぎった。辺りには血の霧が漂っている。
551がある時ー!と、無い時ー!を繰り返し叫びながら自らの体を少しづつ食いちぎっていく暑川の眼に灯っているのはまさしく狂気の光。恐ろしいのは暑川自身が、そうして血塗れになりながらも満面の笑みを浮かべている事である。愚米仙をたらふく飲み込んだ人間の、壮絶な末路と言えよう。
「ねぇ、兄弟揃ってこうやって漫才やり始めてからもう10年程経ちますけれども。」
その横で、同じく愚米仙を大量に浴びた舞浜兄弟の弟が何故か漫才口調で喋り始めた。その隣で舞浜兄はポケットからジッポオイルを取り出し、自分と弟の頭の上からジョボジョボとオイルをかけ始めたかと思うとライターで自分のオイル塗れの体に火を引火させた。勢いよく双子の身体が炎に包まれ、辺りにはグズグズと肉の焦げる嫌な匂いが充満した。
「この歳になって昔の友達にばったり会う事があるんですけれどもね、こないだ会った時は参りましたよ。知り合いに会わないようにこっそり行ったストリップ劇場でしたからね!」
「そうそう、こいつストリップ劇場良く通っててね、何が羨ましいって入場料無料なんですよ。」
「無料なことあるかい!なんでワシが顔パスでストリップ通えるんよ!」
「なんでってホラ、奥さん出てはんねやろ?」
「出てるか!辞めたわアホ!」
「あんなん退職制度あるんでっか!?」
「それは無いわい!」
双子の漫才は無観客にも関わらずハリのある声だったが、全身の皮膚を炎が焦がし、喉の粘膜を直接炙られる痛みに耐えかねて、次第に弱々しい声へと変わっていった。
「…なんで…辞めたんでっか…?」
「そらお前歳食って…身体の線がだんだん崩れて来て…辞めなしゃあないやないか…い…」
「あー…それはやっぱり…踊る度にオッパイが…ペターン、ビヨーンて…なる…から…」
「…ヒュー…ヒヒュー…ヒュー…」
「……ピョー…ピピョー…ピー…」
喉仏が焼き切れた影響なのか2人の声は言葉にならず、小学生が与えられたばかりでふざけて吹いたリコーダーの様な音を立てながら2人はその場に同時に焼け崩れた。
「551の…肉まんがある時イイイ!!!!」
黒焦げになった双子の隣で暑川はフラフラと蹌踉めきながら叫んだ。両目、両耳、鼻、その他あらゆる身体の部位を引きちぎった様子であり、前後不覚に陥りながらやがて血の海に倒れ臥し、ピクリとも動かなくなった。
愚米仙の魔性に魅入られた暑川、舞浜兄弟の3人はそうして壮絶な死を遂げたのである。
彦はそうした様子を眺め終わった後欠伸をしながら屈伸する様に何度か膝を曲げ、島袋が避難していた屋根の垂木に飛び上がった。島袋はあまりの光景に子供の様に涙しており、彦は島袋を背負って床に飛び降りて酒蔵から出ようと自らが粉砕して作った壁の大穴へと歩み始めた。
そこへ、3メートルはあろうかという巨大な生物が立ちはだかった。その生物は愚米仙を大量に摂取した影響で全身が普段以上に膨れ上がっており、浮き上がった血管がビクビクと脈打っていた。赤いワンピースは肥大化した全身の筋肉により引きちぎれる寸前であり、その表情は死亡した3人と同じように狂気に満ちていた。
舞浜母は口から舌を高速で発射して彦の体に巻き付けて動きを封じた後、彦の口にディープキスをする様に唇を重ね、渾身の力を込めて彦の全身を吸い上げた。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
