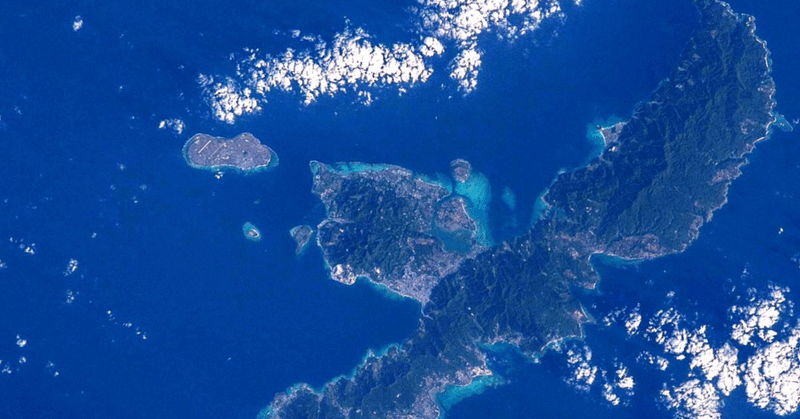
琉球廻戦
【壱】
どこまでもダラダラと続く坂を登った先に、高校があった。
季節が初夏という事もあり、モノレール古島駅の改札を出た生徒たちは日増しに強くなる日差しを全身に浴びながらこれから坂道を登る苦労を思い辟易するのだった。油照りして凪いだ道を汗を垂らして歩きながら学び舎を目指して歩く経験は、後々彼らにとって青春の思い出となるのであろうが、当の本人達の表情は険しい。
生徒たちが目指す学び舎はその名を豪南高校と言う。終戦後の荒廃した沖縄の将来を憂いた男達が作り上げた、沖縄最古の私立学校である。高校野球の超名門校であり、沖縄で野球をやる球児達にとっての登竜門でもある。今年の夏の甲子園にも出場が内定していて、校内からの期待と羨望の眼差しを浴びていた。
そういった場合甲子園へ向けて更に厳しい練習を行うのかと考えるのはいかにも素人考えで、強豪校ほどきっちりとした練習メニューが常に存在しており、普段のペースを崩さない事に重きを置いている。とは言え精神的には、スタメンはおろかベンチ入りのメンバーでさえ、校内からの期待がどれ程の重圧としてのしかかっているのかは想像に難くない。
ではベンチ入りすら出来なかった部員は何を思うのだろうか。練習を終えた部員達はグラウンド横のプレハブ小屋で着替えを行うのだが、ここで2人の三年生が着替えながら話をしていた。
「卒業した後どうする?大学行ってまた野球やる?」
「甲子園ベンチ入り出来なかったし、どうでもいいさ。社会人野球とかもいまいち乗らんし、かと言って今更切り替えて受験勉強したって大した大学行けんしね。」
「やる気失せるね。今年の甲子園にしたって、ベンチ入りすらしてない訳だから豪南応援する気にもならんしね。」
「大城は実家の焼き鳥屋継ぐの?」
「いや、正直それもピンときてないさ。」
「じゃあどうするの」
大城と呼ばれた球児はそう聞かれると少し悩みながらも、間を置いた後で声のトーンを落として話し始めた。
「知念先輩ていたでしょ、OBの。」
「いたね。あの人も今は野球やってないでしょ。」
「ヤクザやってるわけ。内緒なんだけど。」
「あいえなー!(ヤバ!)」
「俺実は誘われててね、迷ってるわけ。島袋さ、俺と一緒にヤクザやらない?」
島袋という球児はあまりの話の急さに狼狽したが、満更無しでも無いと考えた。島袋の家は両親が居らず、祖母と島袋の二人暮らしでこの先の展望なども特に無かったからだ。ヤクザで人生一発逆転、悪く無いかもしれない。
「いきなり言われてもって感じだけどね。ちょっと暇潰しに話だけでも聞いてみたいさ。」
「じゃ今度の日曜サンエー前集合で…」
大城が話そうとすると数人の足音が勢いよく近づいて来た。恐らくスタメンの部員達が練習を終えて着替えにやって来ようとしているのだ。大城と島袋はなんだか鉢合わせるのも気まずい感じがしたので、そそくさと荷物をまとめてプレハブ小屋を後にした。
暦は6月を過ぎて7月。「今年の夏は特に暑くなりそうです。」などと、天気予報士が毎年の決まり文句を述べている頃だった。
※
沖縄県の読谷村という地に、コンクリート造りで表札も掛かっていない殺風景な建物があった。ただでさえ真っ白なコンクリートの建物が、強い日差しと同化して遠目からは実在しているかどうか分かりづらい。
その建物の地下で、3人の男達が歩きながら話をしていた。
「なはは!いやぁ、お前がホントにヤクザになりたいって言ってくれるとは思わなかったさ。」
髭面で小太り、日焼けした肌に薄らと汗の滲んだ白いポロシャツ姿の男が大城にそう話しかけた。知念と名乗ったその男は、かつての高校球児の面影の無い弛んだ腹の肉を波打たせながら2人の球児に向けて話を続ける。
「島袋君って言ったよね?君もヤクザになりたいそうだし嬉しいよ。俺が口利いてあげたら割と早く組員になれるはず。よろしくね。なはは!」
島袋は話を聞くだけのつもりが半ば強引に連れてこられてここに居る。知念は豪南高校野球部のOBとの事だったが、気さくな笑顔の奥に昆虫の様な冷静さを湛えた別世界の人間に思えた。
建物の地下を進んでいくと更に地下へと続く階段があり、この建物は地下二階まであるのだと説明された。地下二階まで下りると空気が冷んやりとしていて、なんだか後戻り出来ない世界に来てしまったような気がした。
「とは言ってもね、高校生の君達をいきなり組員にしたりだとか言う事は流石に出来ないわけ。ほら、ヤクザ映画とか観ててもさ、ビシッとしたスーツ着たオールバックの渋いヤクザの隣で、坊主頭の若い兄ちゃん達がジャージ姿でテキパキお茶汲みとかしてるよね?そういう事なのよ。どこの業界にも言える事だけど、下積みってのはあるわけ。」
知念は廊下の行き止まりまで行くと、2人の高校球児達にそう告げて頑丈そうな鉄の扉のドアノブに手を掛けた。
「だからね、これから2人にお願いするのはその下積みだと思ってくれたら良いから。こういう雑用をこなして、やっと組員になれるわけ。」
知念はそう言うと自らの太い腕が更に膨張する程の力を込めて扉を押した。んんっ、という知念の唸り声がコンクリート造りの壁に冷たく谺した。
扉の向こうは薄暗くて良く見えなかったが、次第に目が慣れてきてぼんやりと輪郭が掴めてきた。
檻だ。
開かれたドアの向こうには、鉄の檻があった。
島袋は反射的に小さく悲鳴を上げた。大城も声こそ上げなかったものの、表情が引き攣っている。
檻の中には、一匹の巨大なオランウータンが鎮座していた。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
