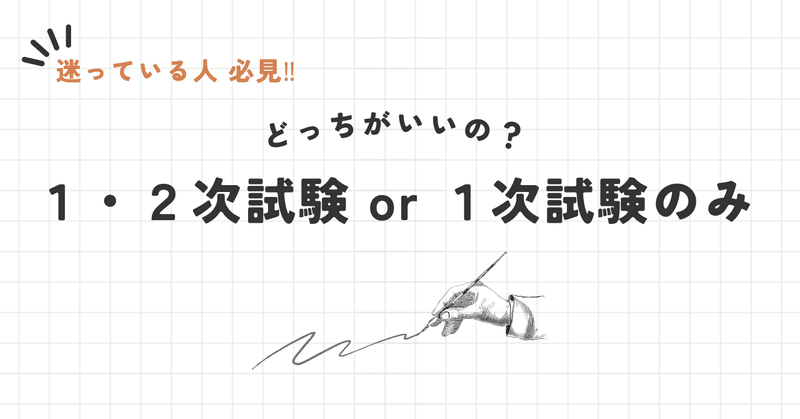
インテリアコーディネーター受験区分について
おはようございます。
interiakoです𓅮
今回はインテリアコーディネーター試験の受験区分について、お話しさせていただきます。
表紙にあります通り、
インテリアコーディネーター試験では
① 基本タイプ(1次試験→2次試験)
② 1次試験<先取り>タイプ(1次試験のみ)
の二通りが試験方法としてあります。
私が受験のときは迷いました。
『どっちが良いのだろう?』
でも、試験が終わった後の私は強く言いたい…
『① 基本タイプ(1次試験→2次試験)』
にしなさい!(笑)
理由は次の通り、
【1次試験<先取り>タイプ(1次試験のみ)にした場合、次年度のときに1次試験の内容を忘れるケースが多い】
からです。
もしかして、自分だけかな?と思って、
二次試験終わりに当時ツイッターで
エゴサーチしてみたんです。
するとまぁ多かった…
『1次試験の内容覚えてないよ〜』
といった意見。
勿論、1次試験が覚えてなくても問題自体解ける年もあったりするんですがここに関しては何が出題されるのか分からないため『運』です。
そうなってくる場合、合格率を高めるためには
『記憶として残っている可能性』を高める
しかないのです。
そして、云えたいのは2次試験のプレゼンテーションでここ数年1次試験の内容を踏まえた単語が、出てくるようになりつつあるということです。
プレゼンテーションでの過去例)
・ペニンシュランキッチン 第38回
・ネストテーブル 第39回
・コーブ照明 第39回
また、プレゼンテーションだけでなく
論文でも1次試験の内容を覚えていないと解けない問題が存在します。
論文での過去例)
・クイーン・アン様式 に関する記述 第27回
・無垢材 コルク 漆喰 珪藻土 和紙 キーワード参考問題 第29回 等
論文でも、1年後に試験に挑むのと1次試験を終えた3、4ヶ月後に試験を受けるのでは絶対的に後者の方が有利になるわけです。
ですが、
絶対的に否定するわけではありません。
1次試験が終わった後の9月〜12月がどうしても忙しくて…
という方は、必然と1次試験<先取り>タイプ(1次試験のみ)になるかと思います。
もしそうなった場合は、合間合間に1次試験の内容を思い返すような習慣にする。
例えば、移動時間に1次試験の内容をまとめたノートを読み返すとか、シャワーしながら自分でQ&Aをしてみるとか…そのような工夫で、空いた時間をみつけて勉強すると良いです◎
私の場合は、あれだけ自信のあった論文が
半年後には不安だらけになっていた…
1次試験の内容を半年後にまた覚えようとする時間は、効率も悪くオススメできません。
3ヶ月しかないのにどうやって勉強すれば…?
次回は『スケジュール管理』について話していきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
