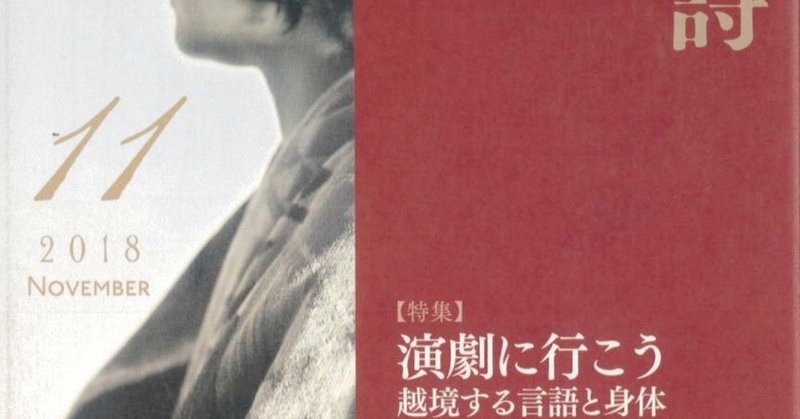
新聞家さんとのイベントに向けたメモ⑤ エッセイ・ステイトメント等をめぐってA
(承前)(文責・山本)
前回までは、『現代詩手帖』に掲載された対談記事をめぐって書いてきた。ここからは、村社氏の他のエッセイやステイトメントを確認し、そこで論じられている事柄の体系化を試みたい。
村社氏がこれまで発表してきたテクストの多くは、新聞家のホームページで読むことができる。以下で論じる際にもそれぞれにリンクを貼るので、詳細については原典にあたってもらうとして、本稿ではなるべく駆け足で紹介する。
まず最初に取り上げるのは、「「演劇のデザイン」のコンセプト」というテクストである。2018年4月に「Whenever Wherever Festival 2018」のプログラムとして開催された演劇コンペティション「演劇のデザイン」をめぐるステイトメントだ。
村社氏はそこで、劇作家・演出家の太田省吾のテクストを取り上げている。※太田省吾については、フェスティバル「これは演劇ではない」関連ペーパーでの村社氏の連載「走尸行肉」でも毎回論じられている。第一回と第二回は「これは演劇ではない」ウェブサイトからPDFをダウンロードしてよむことができる。内容については次回紹介する。
「―自分は結婚して何をし何を得たかといったら、ほとんど何もない。子供を産んで育ててきたことと、男というものについて、夫を通じて多少知ったぐらいのことで、そのほかには何もなかったという気がしてならない。―ある中年の女性が、カウンセラーにこう訴えたそうだ。なんだか、身体に力を失った女の顔が浮かぶ。(中略)彼女の生活に〈何も〉ないわけではなかった。毎日の、毎時の細々としたこと、それにまつわる息づかいがあったはずだ。そういうものが、〈何も〉と見えている。〈何も〉としか見えていない。そう見るのは〈劇〉の目である。(中略)〈劇的作法〉は、常に〈何か〉であろうとし、〈何か〉として見せる作法であり、そのことによって〈何も〉の中身を見落とす作法であり無化する作法であることは見てきた。そして、この〈劇的作法〉を破ろうとする表現は、その〈何も〉が〈何も〉でないというところを見ることである。〈劇的〉な目によって〈何も〉とされているところにあるものが〈これ〉なのである。」(太田省吾『劇の希望』)
「「演劇のデザイン」のコンセプト」
このテクストをめぐって村社氏は、まず〈これ〉と呼ばれているものを「本質」と呼び直し、それをめぐる模索の手立てについて検討する。太田は「本質」を見出す方法として、いったんは《「よく見なくては見えないものに価値を見出す」といった仕方を提案しているが、すぐにこの思いつきを「なにかいやなものを口に入れたような気持が湧」くと言って退けている。退けた理由は「よく見ないと」では結局、本質がそこにあると信じるか信じないかの問題に論点がすり替わってしまうから、だとしている。ではどんな仕方を提案すればいいだろう。》
村社氏は、太田が参照していた哲学者のメルロ=ポンティによる議論や、あるいは建築家のアドルフ・ロースのエッセイを参照しつつ、徐々に答えに近付こうとする。興味深いのは、画家・美術教育者のジョセフ・アルバースの書物『配色の設計』を引きながら語られる以下の箇所である。少し長めに引く。
「教師が、自分が知らない、断定できないこと、そして色彩に関してはよくあることだが、選択することも断言することもできないということを認めた時、教師は実際に正しく、必ず自信がもてるようになる。」(同上)
「教師」という単語はいくぶんか違和感をここに持ち込むかもしれないが、事実わたしが太田省吾の論から発して「演劇のデザイン」という名でコンペティションを、あるいは演劇の実験の場を設けようと思ったのは、アルバースがここで指し示しているような本来的な「教育」の視座を借り受けたいからである。ここで語られている教育はおよそ私たちが思う教育の印象とは異なっている。教育はいつもひとつ強烈な参照項を設定して、いつのまにか「信」の問題を高らかに喧伝している。しかし本来は「信」の問題から最も遠くにある場こそ教育の本質でなければならない。アルバースが言うように、「異なるケースの発見」と「複数の回答」が待たれるような「場」でなければならないのだ。そして重要なのは、その議論の中心にあるのはいつもどんなときも鮮明で具体的なかたちであり、そしてまた同時にそのかたちは決して知覚され得ない「かたち」だということである。
わたしがデザインという言葉にここで託すのは、色彩の知覚不可能性、あるいは具体の目まぐるしい可謬性を相手取った、グループワークの重要性である。決して断定し得ぬ具体について語らい続けるということがいかにして可能になるか。アルバースが光学スペクトルの数値を「事実」とし、一方でその数値に反する「明るい」や「暖かい」といった色彩に対する私たちの諸知覚=錯覚を「実際」と呼んでみせたように、中年女性の生活から事実としての行為・出来事を取り出し、一方で彼女の体験を実際と捉え直すことは可能なのだろうか。問題は何が錯覚なのかということだ。わたしたちの日常に、共有可能な錯覚などあるのだろうか。
「「演劇のデザイン」のコンセプト」
村社氏は、「本質」と「信」をめぐる問題を、グループワーク的対話の場における相互教育の問題へと変換することで、解決しようとしている。「本質」の発見は、数値化しうるような客観的事実を指し示すことでも、また、「ここに本質がある」と信じてそれに向き合うことでもない。事実をめぐって人々が生じさせざるをえない《諸知覚=錯覚》を、抽出し、対話の俎上にのせ、複数人で検分していくことを通してそれを(特定の個人にのみ還元されるのではない)一定の共有可能性に満ちたものとして見いだすことである、と。
いわば、「本質」とそれを探ろうとする個人の一対一関係ではなく、また個人そのものが無化されるような数値化された事実でもなく、個人の複数化のようなものが目指されているのである。「本質」を探ることは、それを探ろうとする場(人々の相互教育関係)の設計であり、また、そこに日常的な人々の振る舞いを食い込ませるための手立ての設計である。
ここで、客観的事実とは別に想定されるところの《諸知覚=錯覚》、あるいは《決して知覚され得ない「かたち」》として論じられているものは、村社氏のテクストにおいて一貫して問われている。
たとえば「演劇論「語の反響」草稿1 序」というエッセイで《諸知覚=錯覚》は、祖母とのエピソードを通して検討されている。耳の聞こえが悪い祖母は、村社氏が口にした《「スーパーに行くけど何かある?」》という言葉や《小さな笑い返し》、さらには誤作動した目覚まし時計の音などから、村社氏が《祖母の聞こえの悪さをからかって「これがきこえるか」と何か異様な音をかき鳴らしているものだと思っ》てしまったのだという。
そこで村社氏が注目するのが、《「文字通り」の〈聞こえ〉》と、それが《〈聞こえの悪さ〉》の中で起こす、いびつな反響である。《〈聞こえの悪さ〉は、祖母が耳が悪くなる以前に実践していた人の話の聞き方、言葉の端々への気の巡らせ方をいまも同じようにし通そうとするのを遮るようにして、顕わになる》。村社氏はそれを《ある空間のよう》だと記し、その空間では、《もともと対面する人の言葉や身ぶりがもっていた〈聞こえ〉がよもや歪に“反響”して、とんでもない〈聞こえ〉として祖母に受け取られるようなことがある》という。
わたしが口にした「スーパーに行くけど何かある?」や、小さな笑い返し〔…〕この2つの言動が本来持っていたおよそ「文字通り」の〈聞こえ〉が、祖母の〈聞こえの悪さ〉の中で歪に反響し、例えば「いたずらの前触れ」や「その先が想定されている何らかのポーズ」といった〈聞こえ〉として受け取られてしまったのだろう。またもちろんもう一歩踏み込むと「あえて真面目にやりとりすることでその後のいたずらの質を高める」という〈聞こえ〉になっていた可能性もある。そしてこの三つ目の〈聞こえ〉を想像した時に、では元々の言動が持していたとされる「文字通り」という〈聞こえ〉は、この「あえて真面目に…」と実際どんな違いがあるのだろうかと疑問が湧く。つまり言い換えれば、仮に〈聞こえの悪さ〉という空間を挟まずに「スーパーに行くけど何かある?」が交わされるのであれば、「文字通り」と「あえて真面目に…」は確実に峻別できるはず、という保障はどこにあるのだろうか。
「演劇論「語の反響」草稿1 序」
ある言葉が発せられ、別の人がそれを聞き取りその真意を測定する。そうした極めて日常的な営みは、祖母の耳の聞こえの悪さに由来する読み取りの誤りによって、うまくいかなかった。Aという意味で発された言葉は、大きく歪んでBという言葉として読み取られてしまった。
だが、そうした歪みは、耳の聞こえの悪さという、ある限定された条件のもとでのみ生じるものなのか。「Aという意味で発された言葉」というとき意識される「文字通りの意味=A」というものは、そのまま相手に伝わるのが自然なのか。いや、そうではなく、常に人々のあいだには、AをB等へと歪ませる《〈聞こえの悪さ〉》が挟まっているのであり、祖母のケースは、ただそうした《〈聞こえの悪さ〉》のもたらす歪みの反響が、通常よりも大きく露骨にあらわれでてしまっただけなのではないか――そのような流れで村社氏は論じていく。
ここで用いられている《「文字通り」》という言葉は、先ほどの太田省吾のテクストをめぐって記されていた「本質」という言葉と地続きにあるものだと考えられるだろう。それは、発話者によって想定されることで十全にその存在が確かめられるものでは決して無い、発話者によっても不確かな何かとしてあるのである。それゆえ、《「文字通り」》=「本質」は、やはり自他のいずれかに位置づけることのできない、極めて集団的なものとして想定されることになる。
入力された(と想像される)〈聞こえ〉と、実際に祖母が受け取った〈聞こえ〉は、そのシルエットさえも、似ているが別のものではないかということだ。欠損と補填という想像できる限りでは2つの処置が、〈聞こえ〉を形作る別々の要素からなされたように思うのだ。そしてこのどちらをも〈聞こえの悪さ〉の中で起きた“反響”と、名付けてみてこの序を閉じることとしたい。自他のどちらにも属さない場所で起こる語の反響の鏡面として、現在の(会話の)文脈と、過去の(視覚)経験を束ねてみたところで。
「演劇論「語の反響」草稿1 序」
重要なのは、《入力された(と想像される)〈聞こえ〉》=《「文字通り」の〈聞こえ〉》と、《実際に祖母が受け取った〈聞こえ〉》が、いずれか一方に還元されるようなものとしてではなく、自律した各々として想定されるべきと考えられていることだ。
ここで《〈聞こえの悪さ〉》は、自他がともに存在し、様々な身振りや音を行き交わせる公共的空間のなかから生成された、各々の身体的パースペクティヴとでも言いうるようなものとしてある。つまりそれは、言葉を発する「わたし」の側にも、それを聞く「祖母」の側にも、別々だがしかし平等に存在しているのであり、それらは言葉や身振りといった「事物」的なものに還元しきれないものとして考えられるのである。
この《〈聞こえの悪さ〉》という個人的空間が、冒頭のステイトメントで《諸知覚=錯覚》とされていたものであり、そこで機能する《語の反響》の持つ(持ちうるとされる?)共有可能性が、《決して知覚され得ない「かたち」》だと言える。それは《入力された(と想像される)〈聞こえ〉》=《「文字通り」の〈聞こえ〉》と、《実際に祖母が受け取った〈聞こえ〉》の、それぞれのシルエットが《似ているが別のもの》であるということのなかから見出される、奇妙な一致性、あるいはかろうじての共同性である。
忘れてはならないのは、これが、自他の滅却の先にあるものというよりは、一種の私の過剰のなかにこそあるものだと想定されることだ。私もあなたもおらずテクストや身振りだけがある、のではない。しかし私やあなたが単にばらばらに自律してあるだけ、というのでもない。ここで問われるのは、各々の身体が《〈聞こえの悪さ〉》=《諸知覚=錯覚》というかたちで持つ「私」というメディウムの、機能・性質の分析・検証なのである。
さて、もういくつかのテクストを軽く参照することで、議論の輪郭をさらにはっきりさせていこう。
「ワークショップ〈他者を汲む〉」に関するテクストでは、《決して知覚され得ない「かたち」》は、《「本当のこと」》という名で呼ばれている。新聞家での活動が、テクストを《「理解できないもの」》として認識するための「話し合い」を中心とすること、そしてそこでテクストは――目に見えている文字列を「表面」として位置づけた上でその対比として――《「表面とは言えないかもしれないもの」》を内側に食い込ませていると考えられることなどが論じられている。
注目すべきは、その《「表面とは言えないかもしれないもの」》が、《相手のことを本当に愛しているのか》がわからないような仕方で《自分自身からでさえ離れてい》る《「本当のこと」》として語られている点である。《「本当のこと」》は、単純に私から離れて独立してあるものではない。私というものが持ちうる共同性や、それを起点としてなされる共同制作・相互教育(の場の設計)こそが、明かされようとしているのである。
※ちなみに、テクストをめぐって「表面」という言葉を用いた上でそこから逸脱するものを考えようとする態度は、たとえば蓮實重彦のいう「表層」などのタームや、そこでこぼれていたものこそを扱おうとする意志を、やはり想像させるところがあるだろう。
こうした《「本当のこと」》と、テクストをめぐる問題は、「『帰る』に寄せて2「単純化」」でも、『踊る!さんま御殿!!』という番組のなかで司会の明石家さんまによって語られたエピソードの紹介を通して、提起されている。
5年くらい前にさんま御殿でさんまが、「〜してほしいと確かに言ったが本当はそうして欲しくなかった」という女の理不尽な主張が理解できないという趣旨の話をしていた。多分5年前にしていたのだから先週あたりも似たようなことを言っているのだと想像できるが、このさんまが被っていると思った「理不尽」というのは実際には物事の「複雑さ」のことで、それを見逃すことになったさんまの態度にこそ「単純化」としか言い表せない問題が覆いかぶさっているとは考えられないだろうか。〔…〕大竹しのぶの「〜してほしい」には予め、「〜してほしくない」が刻み込まれていたに違いない〔…〕そして重要なのはこの〈刻み込まれた意味〉と説明できそうな何かが、決して誰かにとってだけ読み取ることができて、一方で決して読み取ることができない人がいるといったような特別な方法で刻み込まれているわけではないということである。〔…〕さんまはこう言えばよかったのかもしれない。「確かに何かがそこにはあった。ただそれを読み取ることが私にはできなかった。だから今度からはもう少し深く刻み込んでほしい。」と。
「『帰る』に寄せて2「単純化」」
ここで《刻み込まれていたに違いない》と考えられているもの、また《もう少し深く刻み込んでほしい》と言われているものこそが、《「本当のこと」》であるだろう。それは、客観的に数値化され把握される事実からも、なにかがそうであるという認識を支える社会通念上の「信」からも隔てられたものだが、しかし同時に、《決して誰かにとってだけ読み取ることができて、一方で決して読み取ることができない人がいるといったような特別な方法で刻み込まれているわけではない》というような仕方で、ある個人に占有されることなく確かに多くの人々によって共有可能である可能性が模索される何かでもあるのだ。
こうして見ていくと、一貫して村社氏は、何者かによってなされた表現を、一方的に単純化して処理してしまおうとする姿勢を批判し、それに対立するものとして、ある個人においては決して答えの見えない持続的な対話の試みや、それを起動させ持続させる場の設計を重視していることがわかる。あらためて整理すれば、そこで模索されているのは、おおまかにわけて以下の3種であると言えるだろう。
①表現されたものの背後にある、しかし表現において刻まれたはずの何か(《決して知覚され得ない「かたち」》、《「本当のこと」》、《「表面とは言えないかもしれないもの」》、《〈刻み込まれた意味〉》、など)
②表現というものが持つ一定の傾向(《諸知覚=錯覚》、《自分自身からでさえ離れてい》るそのあり方、《「本当のこと」》の「表面」への食い込み方、など)
③上記2点をともに探っていくことで見えてくる共有可能性(共同性?)
いわば村社氏は、表現をめぐって生じうる思考や、「私」というものの分解、それをもとにした持続的共同制作の場の設計などを、徹底して考えようとしているのではないだろうか。
ちなみに内野儀氏は、「「「演劇のデザイン」のコンセプト」への応答」というテクストのなかで、村社氏の言う《決して知覚され得ない「かたち」》について、思弁的実在論における「もの自体」をめぐる議論との親和性を指摘している。ただ、若干違和感があるのは、村社氏の言うところの「かたち」とは、「もの自体」というよりは、表現や認識を通して事物らに否応なく食い込む「《諸知覚=錯覚》における一種の法則性」であり、またその法則性の事物におけるあらわれの方にこそ近いのではないか、という点である。
それは私から完全に離れたかたちで想定される事物そのものの純粋な姿でも、あるいは視覚や聴覚など特定の感覚に還元されるものなどでもなく、どちらかというと複数の私らが否応なく辿らざるをえない思考、その共同性、さらにはそれが事物化された姿なのではないだろうか。それを用いることで十全な相互教育の場が開かれうる具体的な何か、極めて個人的なものでありながら同時に多くの人々にもなぜか同様に個人的なものとして共有されてしまいうる何か……。
※こうした観点から、村社氏の試みを、抽象表現主義において問われていたものや、象徴主義における象徴、あるいは生態心理学における不変項をめぐる議論などと関連させて検討する余地はあるだろう。たとえば岡﨑乾二郎が『抽象の力』のなかでジョン・D・グラハムらをめぐって記す、以下のような一節らを参照。
「芸術とは抽象に至るプロセス」であり、抽象とは感覚によって得られた現象をいかに人が把握するかということ、主観的に感覚される現象から、より普遍的、総合的な秩序=形式を把握する能力、その活動に関わるということだ。この意味で、芸術は視覚(より広くいえば感覚)的な現象に還元され定着されるものではない。この抽象作用という認識プロセスそのものに関わり、それを作動させる動的な装置なのである。
岡﨑乾二郎『抽象の力』
作品を外部から入力された感覚与件、および内部で感受される感情の束から、認識=統覚に至る「プロセス」と考え、そのプロセスを構造付けているシステム=論理的マトリックスに至ろうとするグラハムの理論は、芸術を認識と知覚のズレ(隔たり)から生み出される、(主体の自己同一性を含む)既成概念の解体と変容、認識の拡張可能性と考える点において概念芸術をも先取りしていた。社会化され、反復的、安定的に認知されうる(と考えられている)表象システム(記号認識、図像認識、様式認識など)は実際に認識される個々の場面では、常に揺動し、崩壊する可能性に晒されている。彼が依拠しているのは、その表向きの表象秩序を超える、より広く深い、線的な歴史展開に収まらない深層構造のリアリティだった。
岡﨑乾二郎『抽象の力』
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
