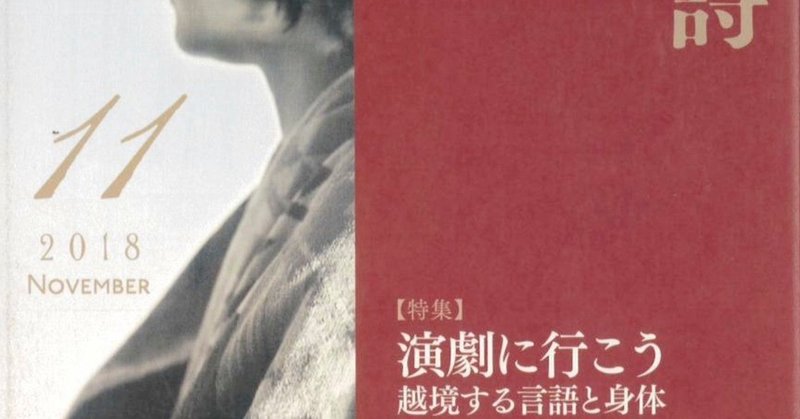
新聞家さんとのイベントに向けたメモ⑥ エッセイ・ステイトメント等をめぐってB
(承前)(文責・山本)
前回冒頭で触れたが、太田省吾について村社氏は、フェスティバル「これは演劇ではない」関連ペーパーでの連載「走尸行肉」において毎回取り上げている。第一回と第二回は「これは演劇ではない」ウェブサイトからPDFをダウンロードして読むことができる。第三回はまだウェブでは公開されていないが、印刷物としては多くの劇場で配布されているようだ。
その連載での議論を一通り見ておこう。
まず第一回。さっそく太田の言葉が引かれる。
《「私たちの目は、名や意味を見てしまう目だが、しかしそれだけをしか見ることができない目でもない」》。
この文を詳しく読んでみて、なぜ太田は演劇の実践者でありながらこの問題に拘っていたのか、と問うのは一種の語弊を招くだろうか。というのも安直に(あるいは勘ぐって)考えて、演劇は「名や意味」とここで示されているいわゆる記号に、芯まで身を浸すことでこそ成り立つ閉鎖空間であるからだ。それは、演者にとっても、観客にとっても共有可能な「名や意味」を嫌という程積み重ねることで、"既に見たことのあるもの"を明滅させるための徒労の場、と言い換えても良い。しかし一義にこの考え方は、ひとつの偏った演劇理解である。この積み重ねは徒労などではなく、突き抜けを目指す繊細な「技巧」の連続だ、と一方で演劇はいつも期待されている。だから太田は私たちに、括弧さえつけてしまえば本質と呼び見つめることができてしまいそうなこの名や意味を指して、ただ、そうでないものにも目を向けることができると訴えたのだ。
「走尸行肉」第一回
そして、《「技巧」の連続》としての「演技」が批判される。《演劇は名や意味を観客と共有し、その存在を信じるために企図されるのではない。私たちが日常の地で嫌でも絡め取られる名や意味を直視することで、それがいかに信じるに値しないものか気づき、その後ろにある括弧の外れた本質に触れんとするために設えられるのだ。》
演劇は、私らにおいて避けがたい《名や意味》を、避けるというよりは直視し、その奥において動く本質=《「本当のこと」》を浮かび上がらせる営みとしてある、という。
第二回では、演劇よりも日常のほうが過剰であるという太田の議論を参照しつつ、その先で「沈黙」について語られる。
太田は、あまりに過剰な情報を持つ日常のなかで、しかし平穏に暮らしていくためには、《ことばを己の身近なところへ限り、その限界をこえることばについては黙ること》が必要であると言う。《「〔…〕だれに誇ることもできぬ、ごく内輪の営みであり、その態度は、限りあるもののなかで自己を承認してゆくという態度、沈黙へと向かう」》。
これに対して、村社氏は批判的に対峙する。なぜ個人として沈黙してしまうのか?
だから私は設えた劇空間で、語ることを選んでいるのかもしれない。自らの失言に気づくことで、汗をかきながら次のチャンスに備えられるように。汗をかくことでもう取り返しの利かない失言の存在に遅ればせながら気づいたということを、あなたに理解してもらえるように。
「走尸行肉」第二回
日常の過剰さに対して、個人として沈黙するのではなく、あえて複数人のもとで語ること。それによって、おのれを超えたかたちで日常を知覚すること……。
第三回では、《「言質をとる」》ことがもたらす関係の破綻について語られる。《関係は言質をとろうとすることで一瞬にして成り立たなくなる。あるいは此岸には、細かく細かく、鋭い目つきの前で不安に打ち震え続ける時間のことを挙げられるかもしれない。言いたいことはそんなことじゃない、という甘ったるい言表を、抜け出すのにこそ意味のある袋小路にいて押し殺すあの時間。》
何者かによってなされた表現を、表面的な発話を理由に一方的に単純化して処理してしまおうとする姿勢がやはりここでも批判される。そのうえで、提示されるのはある種の沈黙に近いなにかだ――しかし先ほど批判された個人的沈黙とは異なる。複数の身体間のあいだの真摯な汲み取りを促すような《“堪え”》こそが求められるのである。
そこから村社氏は、不意に「失恋」と書き記す。《「文字通りです」という送り返しが盲信される今日に、「失恋」の体感をこそほそぼそと申し送りしたい》。
「文字通り」については、「演劇論「語の反響」草稿1 序」で見たように、やはりここでも批判されているわけだが、不意に記された「失恋」とは何か。そこで掛けられているものとは何か。
これについて考えるためには、今回のイベントでも上演されることになる、ワークショップをもとにした作品『失恋』をめぐるテクストを見なければならない。
まず、ワークショップ「失恋の実践」に向けたステイトメント「わたしの失恋と宇多田の失恋」から。そこで「失恋」は《その機会においてしか巡らし得ない「思考」》というかたちでその《醍醐味》を示されている。
《'価値観の違い'といった言い方でしばしば受け入れたフリをされるすれ違いを眼前に据えて、自らの根本的な革新を賭けて取り組む夜通しの思考。》
なるほど「失恋」とは、他テクストでも肯定的に論じられてきた、持続的対話をめぐる営みとして考えられているようだ。《誰にとっても介入したり展開したりすることの叶わない障害を解読可能なコードに零落させ、その解読の手間を想像しため息をつくような傲慢さ》をいかに排除し、《《どうしようもないこととただ出会い続けるための持続的な自覚》》を持つのか――その問いに対して、村社氏は、《言葉が「どうしようもないこと」として、あるいは、それ以上解読できない"そのもの"として再定義されるまでの過程》としての初恋、そしてその裏側にある核心のようなものとしての「失恋」を提示する。
上演『失恋』の当日パンフレットでも、同様のかたちで、新聞家の実践が「失恋」という言葉に託されている。《ただ「もう少し沈黙していましょう」はあまりに私たちに馴染まない》、《言葉にせずとも、どんなことを考えてもいい、という毎度訪れる空隙は、だから失恋の明朝に似ている。誰とどうなってもいい、なんなら君を一度忘れたっていい、とほとんど全てを賭け金にして、またあなたへ戻っていくための革新の誓いに。空隙にさらされて、痛いほどめくれ上がる自らの綻び。ただそれはわたしたちの言葉が甘くなくなったこと。あの奇跡。》
※このような「失恋」という営みを通して目指される《自らの綻び》、《自らの根本的な革新》は、たとえば「『鶯張り』という実践に寄せて」のなかで、次のように語られているものでもあるだろう。《演劇という手段を用いてわたしが描きたいのは、この私たちに課せられたほとんど避けがたい踏み外しを、私たちより少しだけ上手に避けることができる主体です》《なんでもない一歩の足音が響いてしまう場所。新聞家のケースがそんな場所になればと願っています。》
さて、以上のように整理していくと、極めて正しく(?)、他者への取り組みがなされようとしているという感がある。その分、具体的な内実が知りたくなる。
次に進むべきは、『失恋』で用いられた作品テクストの分析かもしれない。ただ、ここでは、イベントのための事前メモという本稿の役割を、あえて徹底するという意味も込めて、村社氏の理論の核心に関わるだろう、テクストと「他者」の問題に、あらためてもうすこしとどまり考えておこう(『失恋』テクスト分析は、間に合えば事前にnoteで、間に合わなければ会場にて上演の感想とともに、語る)。
『現代詩手帖』対談記事を再度検討する。そこで「他者」は、テクストやその上演を通して浮上するものとして考えられていたのだった。
読むという行為においてテキストって不随な対象だと思うんですね。読み手にとって一見して物言わぬ他者なんです。だからこそ読み手には、体を動かしたり、距離を調整したりして、他者を汲み取る責任が負わされていると考えても良い。私の演劇実践において根幹にあるのは、この「他者を汲む」ことなんです。
読みが、本当に現実に跳ね返ってくるためには、すれ違い自体も重要なのではないかと。誤読とか誤解といった前提があるからこそ、実際に他者を眼差してみたときに自分の誤解とか誤読が本当に身から出た錆だということに気づく。
テキストの意味を活躍させると繰り返し言っていますが、活躍させすぎた結果、読めないということが私のテキストには起こっている。それでも読み切るために読み手は、自分の範囲で内容をすり替えたり、自由に連想することでテキストを誤読し、読み切ったことにしようとする。だけど、改めて語の素朴な機能に注目して細かく説明をしていくと、あ、確かにそうとしか読めないということに気がつく。それはまさに錆を認識する過程になる。慣習がぶ厚くおおったその下で、言語の機能はたくましく脈打っていると信じているんです。
役者は、村社氏の書いた《ふだん一人称を読み慣れている人からしたら異常な》、語が《全員むちゃくちゃ働いていて、誰に質問していいかわからない》テクストの持つ「意味」を、なんとかして汲み取ろうとする。そうして生まれた役者の演技を、初めてテクストと接することになる観客らが、またもやなんとかして汲み取ろうとする。
そこで生じるのは、読み手各々がテクストに対して生じさせた《こうとしか読めない》読みが、意見会や稽古を通して得られる《語の素朴な機能に注目》した細かな説明によってより正確な読みへと補正されることで、①各々が自らの内側に抱えていておのれの読みをもたらした《慣習》に気づき、かつ、②もともとあった読みとあらたに教示された十全な読みの二種類の同居を一種のポリフォニーとして意識する、という事態であった。
いわばここでテクストは、グループワーク的対話の場における相互教育を起動させるための一種の道具のようなものとして想定されている。眼の前に提示されたテクストは、自動化された読みを可能な限り失効させるかたちで書かれているため、各々の身体が持つ「《〈聞こえの悪さ〉》という個人的空間」を、通常のコミュニケーションよりもはっきりと露呈させる。ただ、その段階だと人々は、自らが「《〈聞こえの悪さ〉》という個人的空間」を露呈させたことに気づかない(村社氏の言葉を大きく聞き間違えてしまった祖母のように?)。
そこで、よりテクストの読みに習熟した者(主に村社氏をはじめとする制作者側)が、テクスト内部の構造に適した十全な読みの可能性を提示し、人々の持っていた「《〈聞こえの悪さ〉》という個人的空間」の存在を明らかにする。結果、自らの読みが、自らの《身から出た錆》であることがわかった人々は、自らのパースペクティブに還元できていなかった(そしておそらくは日常生活の中でも繰り返し見逃されてきた)他者の思考の可能性に気づき、また、そうした他者の思考によりよく接するための技術をいくらか学ぶ……。
以上のような流れを生むために、テクストが持つべきとされている性質は、ひとまず次の2つと言えるだろう。①読もうとすると誤読が多く生じてしまうくらい負荷のかかるものであること、②しかし同時にただ不明瞭なわけでもなく、多くの人々によって共有可能であるようなかたちでその内部構造を説明できるものであること(そのテクストの背後にある「意味」が、《決して誰かにとってだけ読み取ることができて、一方で決して読み取ることができない人がいるといったような特別な方法で刻み込まれているわけではない》ような仕方で刻まれていることが説明できるものであること)。
※2017年1月18日に行われた「BONUS 第4回超連結クリエイション テクノロジー×ダンス×X(社会的課題)編」での、ダンサー・手塚夏子のワークショップをめぐる村社氏による発表でも、テクストは、《「自分の中に、言い尽くし得ない非自己がある」》ということを明らかにするための《ソース》として語られていた。発表の動画とそれをめぐるテクストが、公式サイトのアーカイブページで閲覧できる。
また、こうしたかたちでテクストによって各々が持つ「《〈聞こえの悪さ〉》という個人的空間」を明らかにする試みは、上演という形式によっても促されると考えられている。「『川のもつれホー』東京公演当日パンフレット掲載文章」では、《〈切れ込み〉(人前で話される言葉を、紋切り型のエラーによって破綻させるための不要な音・誤謬の加筆》を加えられたテクストを、役者が記憶し上演することにともなうものが、《「“わたしは決して意味不明なことは言っていない”という装いの履行」》というかたちで語られている。
すぐに意味の汲み取れない文章があったとして、そこにあるものを真剣に読み取ろうとすることには、多大な労力がかかる。しかし、目の前で、なにかしらの「意味」を伝えようと真剣に語っている人がいれば、その人が語ろうとしていることを汲み取ろうとしなければならないような気持ちになってくる……。こうした、テクストの「汲み取り」を観客らに促すものには、役者の存在だけでなく、金銭を払って特定の時間・場所に趣き、少なくない時間を費やして、何らかの意図でもって制作された作品を見る、といったような、演劇をめぐる諸条件全般もまた、カウントされるだろう。
このように考えていくと、ある問いが徐々に(やはり?)浮上してくる。それは、テクストの内的構造の説明を可能にしているとされる「語の活躍」や「出自」、そしてその先にあるだろう「書き手」をめぐるものである。
引き続き、関連する一節を再度『現代詩手帖』対談記事から引いておこう。
私のこの演出が頓挫しないのは、意味をとるということは結局、みんな「わかって」いるからです。日本語を母語として生きてきた人間にとっては、確かにそこにとらなければならない意味があることはわかる。活躍している状態のテキストは、意味を厳密に説明することができる。そうじゃないテキストって説明できないんですよ。この演出を普通のテキストでやろうとすると、嘘が出てくる。どっちでもいい部分がある限り、説明するときに嘘が入りこむ。それはただの演出家の権威なんですよね。私はそれを結構恐れていて、もともと秘めやかに共有しているものについて議論し続けるということを演出の次の段階として想定している。共有しているものだったら、誰もが同じように介入できる。それを信じているんです。
前回見たように、村社氏の理論においては、共有可能性が極めて重視されていた。客観的事実でも、また閉鎖的な個の感覚でもない、いわば普遍的な構造としての《諸知覚=錯覚》をいかに露わにするかが問題だった。
それを目指すために、上演に用いられるテクストは、読むことに極めて負荷のかかるものでありながら、同時に明晰に内的構造が説明可能であることが求められていたわけだが、その説明可能性の源泉として位置づけられていたのが、「語の活躍」や「出自」なのだった。
曖昧な語を無くし、また、語の配置の必然性をテクスト内部で徹底して醸成していくことで、テクスト外部に想定されるブラックボックス的な「書き手」の持つ感覚などに回収されないようにしていく。それはいわば、「テクストがそのように書かれたこと」を、テクストそのものにおいて露呈させていくことでもあるだろう。
ただそこで、テクスト内部の必然性という話では収集のつかない領域が生じる。それがいわば、《日本語を母語として生きてきた人間にとっては、確かにそこにとらなければならない意味があることはわかる》といったような部分にあらわれるところのものである。
ある語の意味や、語同士の関係性などは、テクストの表層部分を構成する文字列だけですべてを決定することができない。常にその判断には、テクスト外部に存在するだろう、文法や辞書的対応関係、物理法則、身体、事物……などが関わってきてしまう。テクストは、テクスト表面の《「文字通り」》な部分だけでは完結できない。ただ、同時に、テクスト外部を、漠然とした判定不可能な「他者」のようなものとして位置づけてしまうと、テクストのもつ必然性を共有可能な形で説明するということがほぼ不可能になってしまう。
そこで村社氏は、個々人からも離れて存在する、「意味」のテクスト表面への刻み込まれ方を、《日本語を母語として生きてきた人間にとっては、確かにそこにとらなければならない意味があることはわかる》といったかたちで事前に共有可能なものとして設定したと言えるのではないか。
そのように、日本語を母語とする人間ならわかる、というようにして、本来なら事後的にかろうじて獲得されるところだったはずの読みの共有可能性を、しかし事前に確保してしまったとき生じる致命的な危うさについては、すでに『現代詩手帖』対談記事をめぐるここまでの整理を通して多分に記してきたので繰り返さない。
ここからあえて、あらっぽく考えておきたいのは、以上のように徹底してテクスト内部ないしは非人称的な「日本語話者」へと、テクストが書かれることの必然性を解消していったとしても、それでも残り続けてしまうところの「書き手」をめぐる問いである。
どの語をどのように配置するかが、テクストを書く営みであるのなら、その語の「出自」や必然性(ないしはその共有可能性)をめぐる問題は、「書き手」と呼ばれるような、テクスト全体を統括すると想定される何かに、否応なく結びつかざるを得ない。それは具体的個人としての村社氏、などにとどまらず、極めてフィクショナルなものとしても当然想定されうるだろう(たとえコンピュータによってランダムに出力されたテクストであったとしても、根本的な事態はさほど変わらないくらいに)。テクストを読むことそのものに、そのテクストを書いたものをめぐる情報を仮構する身振りが食い込んでしまうこと。それは、ポール・ド・マンやブリュノ・クレマンらによるプロソポペイア(活喩法)をめぐる問題や、私小説をめぐる問題などとも関連するだろうが――前者については「制作的空間と言語 「あそこに私がいる」で編まれた共同体の設計にむけて」を、後者については「新たな距離 大江健三郎における制作と思考」『いぬのせなか座 1号』を、関心のある方はそれぞれご参照いただきたい――新聞家の作品の場合、事態はより複雑なものとしてあらわれるように思われる。
たとえばそこでは、役者による発声というかたちで、(あるテクストをそのように表現したその必然性の宿としての)「書き手」という存在が演じられていると同時に、《日本語を母語として生きてきた人間にとっては、確かにそこにとらなければならない意味があることはわかる》といったかたちで、必然性の宿としての「書き手」の共有可能性が目指されてもいる。はたして私らが、新聞家の上演を前にして否応なく立ち上がらせてしまう「書き手」とは、いったい何なのか。それは、グループワーク的対話の場における相互教育の問題や、汲み取るべき他者という概念とのあいだに、どのような関わりを生じさせているのか。そしてその関わりは新聞家を離れたところでどのように別のテクストや実践へと接続可能なのか――これらが、最もクリティカルなポイントであるように思える。
いちおう確認しておけば、「書き手」という概念は、村社氏の『現代詩手帖』対談記事での発言においてはまず第一に、どこまでいっても《テキストの主体》であるところのものであり、第二に、《誰かが書いたテキストだという事実を、上演においてどこまで有機的に立ち上げることができるか》というようなかたちで上演を目指されるべき存在であり、第三に、《私はテキストの書き手だけど、テキストのすべてを知ってはいない》というようなかたちで微妙に具体的書き手個人とのあいだでの結びつきを絶たれている存在であり、第四に、《「あなたしか見たことのない語の跳躍にはついていけない」》というようなかたちで非共有的な存在として時に批判されうる存在でもあるとされていた。
ある面では決定的に重要視され、ある面では排除されるべき対象とされる「書き手」。その二重性は、テクストの判断基準を《日本語を母語として生きてきた人間》などというかたちで外部に先取りすることや、個としての「書き手」と非人称としての「書き手」のあいだの区別が若干まだ曖昧であるように感じられること、村社氏自身が場の設計者とテクストの書き手の双方を担っていること、先に指摘した先行世代をめぐる批判意識からくるねじれなどに由来しているとも思えるが、それらも含めて、極めて興味深い事例となっているのは間違いないだろう。
書くことと上演すること、場の設計や相互教育について考えること、 《〈聞こえの悪さ〉》という個人的空間が持ちうる共同性を探ること、それらがいかに特権的中心を仮構しないようにするかということ、テクストの内的必然性やそこで生じている思考について諸々の問題の延長線上で考えること……それらをめぐる大きな問いを提示しているものとして、新聞家の作品や村社氏の理論を捉え、検討する。その先には、何があるのか。村社氏や来場者の方々との対話を通して考えてみたい。
(いったんおわり。以下補遺つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
