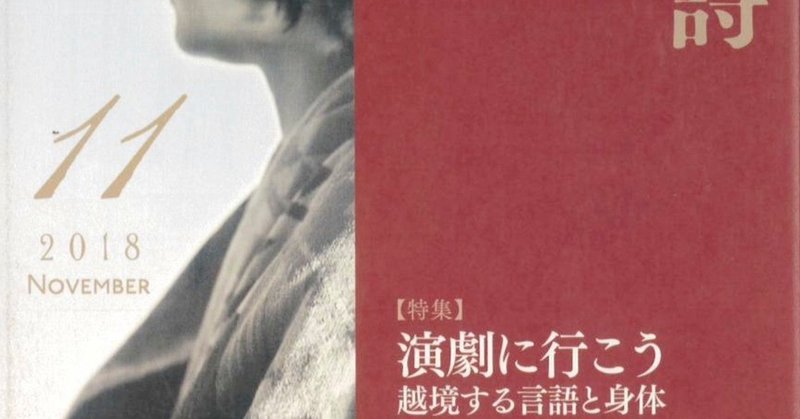
新聞家さんとのイベントに向けたメモ⑦ 補遺(関連テクスト列挙+問いひとつ)
(承前)(文責・山本)
基本的には前回まででイベントに向けたメモは終わりだが、補遺というかたちで、関連する可能性のあるテクストを簡単に数点引いておく。
まず、藤井貞和『文法的詩学その動態』における懸詞をめぐる議論。

ここで藤井貞和は、《作者と別に、また文の論理上の主格と別に、想定される詠み手という存在が考えられる》と記している。詩歌、特に懸詞(相容れないはずの意味が同音によってひとつの表現のなかに同居させられるという技法)が用いられた歌においては、作品を構成する個々の言葉に還元できない《〈手〉ないし〈思い〉のような何か》が存在するという。
《「秋霧が霽れる」と「心が晴れる」とは、遮断されているにもかかわらず、懸け詞として統一されている。この統一させる手を57577というこの詩歌の全体に求めるしかない。》
このような、《詩歌に統一をもたらす真の主格から纏められた関係》をめぐって、藤井は、〈文法〉という言葉をもちこむ。
《一首の表現を統率すると見なされる表現者という格を文法の根源的位置に認める。それが”詠み手”であり、物語的に見れば語り手であり、会話ならば話し手となろう。表現者からは一首一首に統一性がある。》
文法というものは通常、論理的な意味をもたらす法則性として考えられる。そこから言えば、懸詞は、矛盾する意味の同居をもたらすものであるがゆえに、文法から逸脱する技法として捉えられるだろう。だが、藤井はそこまで含めての文法を考えようとする。それは表現がなされること、そして表現を受け取ること、それらの前提に存在する条件としての〈文法〉である。
新聞家における「書き手」や、村社氏が論じるところの言語観と関連させて考えたい。
==============================
続いて同じく藤井貞和の『自由詩学』から、「調べに聴く」というテクスト。長めに引く。
《声》は音読としてあり、神秘な憑依でもなければ、単純な沈黙でもないから、たとい現実に音声をもたないということがあろうとも、能力としての《声》をわれわれのすべては付与されている。私はみぎの詩〔難聴者についての自作の詩「ビラヴド」〕を《朗読》する。わたしは音声によってこれを朗読するにしろ、朗読によってその《声》をとどかせることをしないならば、演技としての朗読でしかなくなる。演技としての朗読というのはありうることだろう。しかし書き手がもし朗読する場合に、芸人の亜流をしてもしょうがない。一般的に言うと、専門の朗読者、演唱者、俳優らに委任すべきことだろう。それにもかかわらず、書き手が朗読しなければならない、としたら、それはどのような場面が考えられるだろうか。〔…〕
……難聴者が詩を書いて、だれかがそれを代読する、というようなことではないような気がする。
ことばとは、そういう性質とちがう、すくなくとも詩のことばの場合には。
朗読は、代読である場合があろうし、そのことを拒否できない、つまり代読が必要なときはあろう、読まれるべきこととしてあろう。
しかし難聴者が難聴者であること事態をことばで表現しようとしたら、すなわちことばであること自体を、その伝達自体を主題に据えるとしたら、何をしなければならないか。
それは現代詩がいま置かれていることばの位置そのものではないか。
朗読について。こういうことだろう。詩がジャンルをこえて舞台芸術になったり、音楽になったり、あるいは画題とかしたりすること自体は大切である。交流や変換を詩が活きることなのだから、そのことはよい。朗読とは、そういう問題ではなくて、詩自体が二次的に詩を再生するみたいな、そんなことでよろしいのか、という疑問としてある。そんな二次的な装置は詩の定型化の試みにほかならない、ということを見ぬいてほしい。
詩の創作そのもののなかに、表情、声や身振りの要素がある。作品の中に、手振りや表情、声が満ちているし、現実の声にしろ、創作の現場で発せられていたかもしれない緊張感としてあろう。あるいは、現実の声をもたなかった場合でも、日本手話なら日本手話が独立した言語であることに示されるように、手振りや表情は言語の一要素をかたどるちからがある。
音韻の一つ一つの階段を、朗読によって降りてゆくとき、そういう表情、声や身振りの要素は、本人がそれをする場合の重要な役わりをもつ。すなわち演じている、という程度のことならどうでもよい副次的な段階だろう。より本格的なこととしては、書き手の創作の秘密を、実験の一部として、すこしは覗かせるような、その場での、創作的とまではいわなくとも、形成的(formative)な朗読を試みるのでなければ意味がない。
村社氏が、事前に書かれたテクストの、それを読み込んではいない不特定多数の観客らに向けた上演を通して実現させようとしている《支度のディティールの伝播》は、藤井の書くところの、《書き手の創作の秘密を、実験の一部として、すこしは覗かせるような、その場での、創作的とまではいわなくとも、形成的(formative)な朗読を試みるのでなければ意味がない》というものと、非常に近いところにあるのではないか。
新聞家の上演は、書き手自身によるテクストの読み上げではないため、詩人による朗読とは直結はしないだろう。しかしそれゆえにこそ、朗読というものがもたらす《書き手の創作の秘密》の伝播を、さらに複数人によるものとして開いていくことがいかにして可能なのかという問いが、見えてくる。具体的個人としての書き手という存在がどうしても持ってしまう特権性を、いかにして複数化するのか。それはテクストの、身体による読み上げを通して、可能となるものなのか?
==============================
3つ目に、岡室美奈子「憑依するテクスト――ベケット『モノローグ一片』の劇構造を再考する」(『サミュエル・ベケットと批評の遠近法』所収)から。

ベケットの作品『モノローグ一片』を分析するこのテクストで、岡室は、〈劇作家〉という概念を提示している。
『モノローグ一片』は、舞台上にいる「スピーカー(話し手)」と名付けられた俳優一人が、「彼」を中心とするテクストを発話しつづける作品だが、そこで、語る「スピーカー(話し手)」と、語られる「彼」は、まず服装の一致によって同一性を仮構される。そしてその上で、両者の同一性がフィクショナルなものであることが、語られるテクスト内部の歪み等によって示されていく。
テクストの中で度々言及されて来た「光」は舞台に当てられるべき照明であり、現在時制の行動描写は舞台上で演じられるべき〈ト書き〉であることが次第に明らかにされ、「彼」の部屋は現実のものではなく今や劇作家と呼び得る語り手の想像上の、やがて舞台上に仮構されるべき虚構の演劇空間であることが示唆される。この語り手は、舞台上でテクストを語る「スピーカー」とも現実の作者ベケットとも異なった次元に位置する、言わばテクストの背後に措定される幻の語り手として実体を持たぬまま、虚構の演劇空間の創造主あるいは操作の主体たる自己を主張するのである。以後、この舞台を想定しつつ語る語り手を、現実の作者ベケットと区別して〈劇作家〉と呼ぶことにしよう。
特異なかたちで上演される「書き手」の姿……ベケットの作品ではそれが役者や舞台とテクストの内容の一致ないしはズレによって立ち上げられていたわけだが、新聞家の場合はどうだろうか。また、そのような「書き手」の姿の立ち上げがもたらすものとは何だろうか。
==============================
また、熊木淳『アントナン・アルトー 自我の変様――〈思考の不可能性〉から〈詩への反抗〉へ』での議論も、関係するかもしれない。
ひとまず著者による要約を、参考として挙げておく。
==============================
最後に、ここまでのメモから溢れてしまった問いをひとつ。
「「演劇のデザイン」のコンセプト」においては、《「信」の問題から最も遠くにある場こそ教育の本質でなければならない》というかたちで、「本質」をめぐる認識を支える社会通念上の「信」が退けられ、相互教育の場でそれが事後的に生まれるという事態が目指されていた。
ただ、「信」が存在しないようなパースペクティヴ、表現、発話などがそもそもありうるのだろうか。たとえば新聞家における「意見会」は、上で言われているような教育の本質の実行を目指して設計されているものだろうが、そこでの発言は、「なぜ発話するのか、それは発話に値するのか」という問いのもとで為されていることが大半だろう。つまり、「これは話すべきだ」という発言者の自己認識のもとで、発話はパブリックなものとして為されるだろう。そこには個々の、そのつどそのつどの、「信」と呼びうるものが否応なく存在してしまっているはずだ。
おそらく目指されるべきは、「信」というものを、単純に退けるのではなく、たとえば「表現がそこにある」という認識が自他問わずなされることそのもの基盤のようなものとして想定すること、そしてそれがひとつの身体において複数行き交いうる状態を場として設計すること、ではないだろうか。
いわば、「《〈聞こえの悪さ〉》という個人的空間」の複数同居。ポリフォニーという言葉で(『現代詩手帖』対談記事において)目指されていたものも、そうした「信」の複数化としてあるように思える。
(おわり)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
