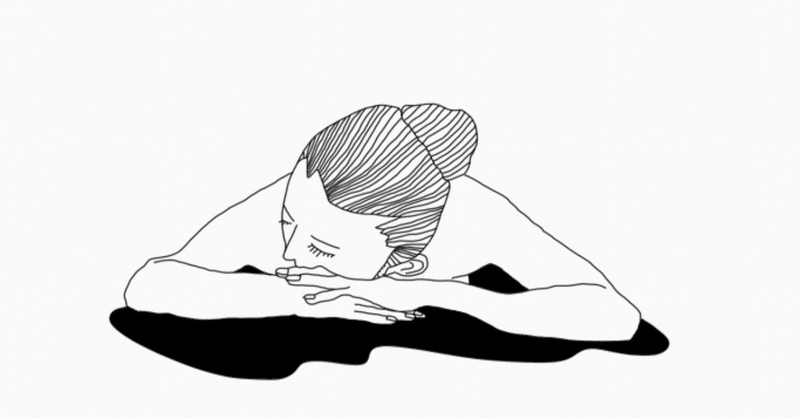
トシ的孤独、ムラ的息苦しさ
おはようございます。本日もお立ち寄り頂き、どうもありがとう。
僕はおよそ10年前にひとつ目の大学を卒業し、会社員やバンドマンなどを経て、この度もう一度大学生活へと戻ることになった。
かつて通ったひとつ目の大学は、超のつく大規模な総合大学。調べてみると学士課程のみで2万8000人、自分の所属していた学部だけで5,300人もいた(唖然)。
一方、現在通うふたつ目の大学はいわゆる単科大学と呼ばれるもので、大学には医学部のみが設置されている。ひと学年は100名と少しだから、全6学年を合わせて800名にも満たない、とても小規模なコミュニティだ。学年でクラス分けがなされる訳でもなく、僕らは大抵、ひとつの教室で講義を受けている。
現在の大学には僕と同じ大学を経てやってきた友人が何名かいて、いつか彼らとこんな話になったことがある。
「あの時と今と、どちらの大学生活が肌に合っている?」
たしか何でもない会話の流れから生まれた質問だったと思うけれど、それぞれ異なる意見が飛び出したりと予想外に盛り上がったことを覚えている。
規模の大きく異なる大学での生活。それらは同じ「大学」という名が付いているものの、似ても似つかぬまったくの別モノだと感じる。そして僕の場合は、現在通っている大学での毎日がより肌に合っているようだ。もっと言うと、僕はひとつ目の大学生活にあまり良い印象がない。その根本は、入学式当時にまで遡ることができる。
中高一貫の男子校に通っていた僕は、その6年間をかなり謳歌していた。運動会、学園祭などお決まりのイベントではあるけれど、そのいちいちに友人と熱苦しく取り組んだことは忘れないだろう。学年には200人超の生徒がいたけれど、6年間クラス替えを繰り返せばそのほとんどとは仲良くなれたし、部活などの壁を越えた関係が築かれていた。そして何より、そこでは「自分」という存在がきちんと認知されている実感があった。思春期真っ只中の当時なりに、自分がいることの価値やコミュニティに貢献することの喜びを感じながら過ごす事ができたのは、とても大きな経験だったと思う。
しかし、ひとつめの大学の入学式当日。最寄駅に着くや否や、そこには只々、人、人、そして人がいた。サークルの名前が書かれたプラカードを持ち騒ぐ人、学ランを着て雄叫びをあげる人、手当たり次第に勧誘チラシを配りまくる人。その中を新入生と思(おぼ)しきスーツ姿の男女たちが、ぞろぞろガヤガヤと式場である体育館に向け、キャンパス内の銀杏並木を歩いてゆく。その喧騒たるや、渋谷のハチ公前や新宿アルタ前と何ら変わることがない。
その時、銀杏並木の途中で感じたことは今でも強く覚えている。
「いまこの光景から自分が消えたところで、誰も気づかないな」。
これは強烈な、僕のひとつ目の大学生活における原体験となっている。つまるところ、僕にとってあの大学はただ人が多すぎた。キャンパスはひとつの巨大な街となっていて、当たり前だけどすれ違う人達のほとんどは面識がない。だからもちろん、会釈をすることもなければ挨拶を交わすこともない。学年やサークル、そしてゼミ内に友人は出来たけれど、その数は全体のごくひと握り。そんな彼らとも、その多くはすれ違う際に「おつかれ」と声を掛け合う程度の距離感だった。あんなに多くの人で溢れかえっていたのに、孤独はいつでもそこにあった。
おそらく僕は、大学でも中高のようなムラ的つながりを期待していた。すれ違えば当然に名が浮かび、ひと言交わすことができるような関係を。そして何かの行事があれば、皆が一丸となって取り組むような環境を。
もしかすると、あのキャンパスにもそのような関係を築けるコミュニティがどこかにあったのだろうか?それを見つける努力を、あるいは自分がただ怠っていただけなのかもしれない。けれど実際にその出会いが叶わなかった自分にとって、あの場は最後まで愛着を持つことのできない、まるで大都市のようなコミュニティだったなと。振り返る度に、そう思うのだった。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
