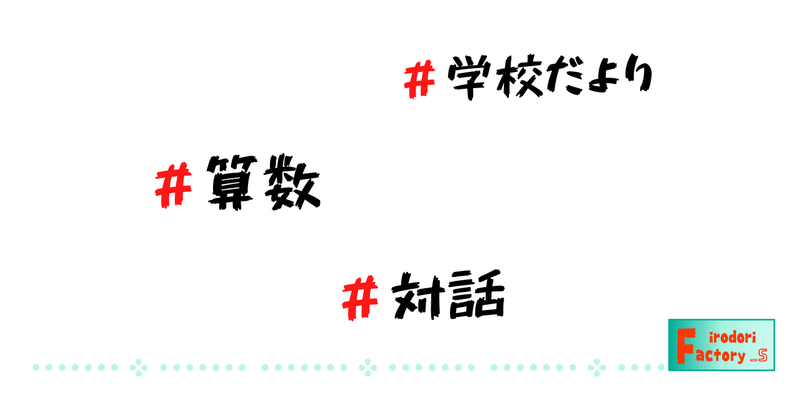
Column_s#5 学校だより③対話
今回のテーマも、#学校だより
学校だよりシリーズも3作目です。引き続き研究部長の立場ということですから、同じことを巻頭言(注1)に書いても仕方がありません。保護者には、いろいろなことを、いろいろな角度から伝えたいのです。その時期に学校教育でキーワードになっていることをネタの中心にしました。それでは実際の文章をどうぞ。
(注1) おたよりの一番はじめに掲載される文章のこと
対話のすすめ ~空港のロビーでの親子のやり取りから考える~
ある知っている先生が、空港で次のような会話をする親子に出会ったそうです。
母「もうそろそろ飛行機に乗る時間だからリュックから水筒とゲームを出しておきなさい。」
子「どうして?」
母「あと、トイレも行っておくのよ。」
子「えー、でも飛行機の中にもトイレあるでしょ?」
母「いいからさっさとしなさい。時間がないのよ。まったくもう。」
呑気な我が子にイライラする母親と、どうして母親がイライラしているのかわからないで親のスマホをいじっている男の子。その先生は親子の隣で、自分だったら子どもにどんな言葉をかけるかと、いろいろ考えたそうです。
今、全国の学校教育の場では「主体的・対話的で深い学び」という言葉をキーワードにして、将来に生きる力を身に付けさせようと、日々の授業づくりに励んでいます。「対話的」とあるように、本校でも一方的な伝達型の授業ではなく、先生と子どもで今日の授業の課題や目標をしっかり確認したり、子ども同士で考えを話し合ったりすることを大切にしています。
最近読んだ本の中に、AI(人工知能)の発達で「飛行機のパイロット」「外科医」といった特別な技術が必要と思っていた仕事もいずれはなくなるという記事を見付け、にわかに信じられない気持ちになりました。その反対にAIで苦手なのは様々な価値観をすり合わせて判断したり、対人的なコミュニケーションをしたりすることであり、「学校教育」「看護」といった世界では、AIではなく人の役割が期待される、という報告があることも知りました。今学校で取り組んでいる「対話」を生かした授業を更により良いものにしていく必要性を感じます。
札幌市では、今年度より5・6年生の算数を少人数の形態で実施する「にーごープロジェクト」が始まりました。児童数の規定で、本校は5年生が該当となっており、5年生は5月より学年を3学級に編成し「にーごープロジェクト」での学習を行っています。1学級の人数が少ない分、子どもたちは自分の考えを発表する機会が増え、先生も子ども一人一人の理解の具合を確認しやすくなるよさがあります。
授業の様子を見に行くと、担当の先生と子どもたちとの間で、いろいろな「対話」が聴こえてきました。
先生「どうやって、そういう考え方を思い付いたの?」
子 「前にやった小数のかけ算のときと同じように…」「あ~確かに!」「違う方法もあるよ。例えば…」
先生「〇〇さんが分からなくて困っているんだけれど…」
子 「多分、どうして分からないか分かる。きっと…」「簡単な数字にするといいよ。僕はね…」
また、放課後の職員室では、5年生の先生と「にーごープロジェクト」講師の先生とで、「今日はこんな考えが出ましたよ。」「こっちの教室では、この問題が難しかったようです。」「明日はこんな風に授業を進めてみようと思っていますが、どうですか?」といったやり取りを見聞きします。相手の気持ちに寄り添い、共通のより良い解決方法を話し合いながら見付けていく。これは、大人同士、先生同士も同様であり、まさに「対話」の姿です。
さて、冒頭の親子の話に戻ります。保護者の皆さんだったら、お子さんにどのような言葉をかけるでしょうか。その場にいた先生は、「自分だったら…」と次のように考えたそうです。
●「飛行機に乗ると上空に行ってベルト着用サインが消えるまでしばらくはトイレに行くことができないこと」「荷物を上の棚に入れた後だと出し入れが大変なこと」の2点を伝えて、本人に考えさせる。
●その結果本人が困っても笑って見ておく。でも、帰りの飛行機に乗るときに「来るとき困ったことは?」とだけ尋ねてみる。
子どもはしっかりと思考をする力があり、思考し失敗し、それを繰り返して学びます。ぜひ御家庭でも「対話」を充実させてみませんか?お子さんの成長や意外な発見がきっと感じられることと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
