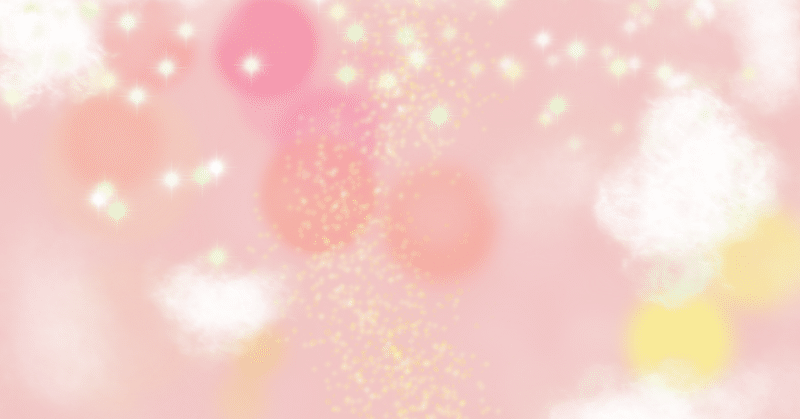
【完結小説】「愛のカタチ・サイドストーリー ~いびつな二人の物語~」
連載小説「愛のカタチ・サイドストーリー」全10話を通しで読めるようにまとめたものです。まとめるに当たり、加筆、誤字脱字修正をしています。
執筆後記も合わせてご覧下さい(*^-^*)
前編
鶴見かおり
ハイヒールとスキニージーンズから解放されたわたしは、脇目も振らずにベッドに飛び込んだ。一人の部屋に帰った瞬間、何もかもを脱ぎ捨てて素の自分に戻る。そして、もふもふのぬいぐるみをぎゅうっと抱きしめる。そうすることで今日一日、頑張った自分を癒やせるのだ。
このまま寝てしまおうかしら……。
みっちり詰まった大学の講義に疲れたわたしは、チラリとそんなことを考えたが、直後に一件の着信があったのを思い出してベッドから起き上がる。
メールでのやりとりが苦手なわたしのために、わざわざ電話でメッセージをくれる唯一の友人――後藤凜――からだ。
高校で親しくなり、卒業後も連絡を取り合っている。今回の電話の内容は、今週末に会いたい、というものだった。午前10時に都内のS駅前で。わたしはすぐに折り返しの電話をかけたが、あいにく繋がらずに留守電に切り替わった。
「電話の件、了解です。その日にS駅で会いましょう」
メッセージを残し、通話を終えたわたしは激しい睡魔に襲われた。今度こそ眠る支度を始める。
わたしの部屋には、全く趣向の異なるアイテムが混在している。まるで、性格の違う二人が同居しているかのようだ。しかしそれはどちらもわたしの持ち物である。
外に出る時は出来る女のイメージ。反面、在宅中はゆるキャラのぬいぐるみやグッズに癒やされている。本当のわたしはどちらなのかと言われれば両方なのだが、後藤さん以外にわたしの裏の顔を知る人間はいない。
しかし、自分がこんなにもかわいい物好きだったことに気づいたのは、つい最近である。それまではオンオフの切り替えという概念もなく、ひたすらに優等生であり続けてきた。それが後藤さんに出会って少しずつ、力を抜けるようになった。結果、想像もしなかった自分が顔を出したというわけだ。
もちろん戸惑いは大きかったが、ごまかすことはしなかった。こんなふうにして、いままで知らなかった自分の一面を探し出していく作業も面白いかもしれない、と思えたからだ。
大学生になってからはじめた一人旅も、新たな自分探しのひとつ。行ったことのない場所や見たことのない景色を見た時の、閉じていた心が開くような感じがたまらなく好き。だから、大学の講義がない日や週末には、愛車に乗って各地へ出かけている。
*
S駅は駅舎を出たところに銅像が建っていて、待ち合わせスポットになっている。わたしたちも普段会う約束をする時はそこで落ち合うのだが、電車が到着したあとは右も左も分からないほどの人で溢れる。これだけの人の中から目的の人物を探し出すのは毎回至難の業だ。
「鶴見さん、こっちこっち!」
声のする方を見ると、後藤さんが手招きしているのが見えた。やはりこの人混みで彼女の姿に気がつかなかったようだ。しかし、足を向けようとして立ち止まる。
(どうして高野君と橋本君が一緒に……?)
後藤さんの恋人とその友人。彼らとは高校の同級生だから、一応の面識はあった。しかし今日、彼らと会う約束はしていない。が、後藤さんの謝るような仕草を見て悟る。彼女ははじめからそのつもりで黙っていたのだ、と。彼らを連れてきた目的は何……? 不信感が募る。
「事情を説明してくれる?」
怒りが伝わらないように言ったつもりが、我ながら刺々しい声だったと思う。目も彼女を睨み付けているかもしれない。そのくらい、いらだっていた。
「ごめんなさい。実は……」
心底申し訳なさそうな後藤さんは、街中へ歩きながら、ここまでに至る経緯を順に話し始めた。
きっかけはわたしが後藤さんに渡した、旅先で購入したお菓子だったという。それを何の気なしに彼らにも分けたところ反応が良く、ことさらブログを書いている橋本君が自分のサイトで紹介したいと言い出したために、わたしと繋がっている後藤さん経由で会うことになったというのだ。
「ご当地のお菓子や名物なんて、今ならネットでも買えると思うのだけど? わざわざわたしの買ってきたものを紹介したいっていうのは、いったいどういうことなの?」
経緯を聞いて、最初に浮かんだ疑問をぶつける。しかし橋本君は、
「いやいや、旅先で直接買うって言うのが大事なんだよ。なんでそこに行ったのか、どうしてそれを買おうと思ったのか。ストーリーをつけることで、ブログを読んだ人もそこに行きたくなる。同じものを買ってみようと思う。おれはブログの読者に、行動のきっかけを与えたいんだよね」
「それってつまり、あなたのブログの読者を増やすためにわたしを利用するってこと?」
「どうしてそう邪推するかなあ? おれはただ、おいしいものはおいしいと言いたいだけ」
「なら、あなたが旅行して買ってくればいいじゃない?」
「まあ、それはごもっともなんだけど、おれ、一人で出かけらんない質だから、ここは行動力のある鶴見さんにお願いしたいわけ。もちろん、お土産代はこっちが出すからさ。悪い話じゃないと思うんだけど」
行動力を買われてのことだと言うのは分かった。けれども、まだ今ひとつ納得できないでいる。悩んでいると、高野君がそばにあったお店を指さす。
「まあ、歩きながら話すのもなんだから、適当なカフェにでも入ろうぜ?」
「え? 四人でカフェに?」
「あ、二人きりで話したい? それならおれと凜は失礼するけど」
彼が意地悪そうに笑った。橋本君と二人きりで話すなんて、間が持つわけがない。
「……このまま帰してはくれないんでしょう?」
「こいつがどうしても、って言うんだ。聞くだけ聞いてやってくれないかな」
高野君はそう言いながら橋本君に目をやった。
橋本君とは高校生の時、一緒にクラス委員をしたことがあるけれども、プライベートな会話は一切しなかった。知っていることと言えば、彼がどうやら同性愛者らしいということくらい。だからといって真相を確かめたことはないし、どちらにしろわたしには関係のないことだ。だってわたし自身、恋愛に全く関心がないのだから。
橋本純
高校で同じクラスだった、彼女との接点はそれだけだ。だから、理由を聞いた彼女が怒り出して帰ってしまうことも充分考えられた。それでも想いを伝えたかった。どうやらおれは、一度想いが膨らんだら伝えずにはいられない性格らしい。
どちらかと言えば嫌いなタイプである。なのにどういうわけか、会って旅先での話を聞いてみたくなった。単純に、鶴見さんの話を伝える、後藤さんの話術が優れていただけなのかもしれない。けれど、一人でふらりと、それも自分で車を運転をして出かけることの出来る女性がどういう思考をしているのか知りたくなったのだ。
カフェで話し合う時間を作ってくれた鶴見さんにまずは感謝だ。四人がけの席に女子と男子に分かれて座る。おれは大好きな斗和君の隣。思わずぎゅーっと抱きしめたくなる衝動を抑え、今日の任務を完遂すべく、正面に座った鶴見さんに意識を向ける。目が合うなり、彼女から話し始める。
「ブログに書くって聞いたけど、よくよく考えてみれば、どうしてわたしに白羽の矢が立ったのかしら? 別にわたしでなくても、頼めそうな人はいくらでもいそうな気がするけど? 例えば高野君とか。恋人ならともかく、いささか不快ね。……まさか、恋人になれという相談? それなら最初からお断りしておくわ」
「早とちりが過ぎるなあ。あくまでもおれは、かつての学友が旅して回ってるって聞いたから、許可を取った上で旅日記書かせてって言ってんの」
「あら、そう……」
鶴見さんはそう言って窓の外に視線を外した。彼女の興味がなくならないうちに話を続ける。
「もちろん、ブログはおれが勝手にやってることだから、鶴見さんは旅先でのエピソードを、これまで通り後藤さんに話してくれればいい。写真を送ってくれとか、細かい旅程を教えて欲しいなんてことも言わない。……確か、パソコンとかネットとか、苦手なんだよね?」
「えっ? あなたに話さなくていいの?」
「鶴見さんが嫌じゃなけりゃ、直接話してもらった方がいいけど、そこは任せる。それと、個人情報は伏せるんで、安心してもらって大丈夫。まあ、興味を持った人から何かしらのコメントはあるだろうけど、鶴見さんのことは一切書くつもりないし、所詮は一般人の書いてるブログ記事だからね。よほどのことがない限り、拡散することもないよ」
「ふーん……」
「……で、許可してくれる?」
素っ気ない返事に、ドキドキしながら問いかける。
「まあ、いいわ。わたしがやることは何も変わらないし。そこまでして載せたいと言うのなら」
「ありがとう」
目的が達成され、一安心する。
「それはそうと後藤さん。わたしはあなたにだけ旅の話をしたはずなのに、どうしてこんなことになったのかしら?」
「えっ?! えーとぉ……」
メインの話が終わると今度は女子トークが始まる。そっちには興味がないので、おれは手元にあるオレンジジュースのストローに口をつけた。
ジュースを飲む脇で斗和君が言う。
「今更だけど、意外だったよ。純が鶴見と連絡とりたいって言ったこと。高校の時、苦手なタイプって言ってたのに、本人に会ってまで許可とろうとするなんてさ。……何か心境の変化があった? 例えば、女を好きになれるようになったとか」
「まさか。おれが好きなのは……」
ちょっとムキになって身体を押しつける。
「あー、悪かった悪かった。お前の気持ちはわかったけど、外で引っ付くのはやめろよ? それだけは約束してるはずだからな?」
「つれないなあ、斗和君は」
「外向きはどうしたって、お前とは男同士の友だちなんだ。分かるだろ?」
「うん。分かってるよ……? でも……」
おれは幼少の頃から女の子より男の子の方が好きだった。今夢中なのは隣に座る斗和君。斗和君には後藤さんって言う彼女がいるけど、おれの気持ちを知っていながら彼は友人として付き合い続けてくれる。有り難いことだけど、時々空しい気持ちになるのも事実である。だって、斗和君がおれを好きになる日は永遠に来ないんだもん。だから、いつか斗和君と決別しなくちゃいけないんだけど、分かっていても、それを考えるとメチャクチャ苦しくなる。
辛い思いをする前に、何かしら他に夢中になれることを見つけなければと思うのに、焦れば焦るほど空回り。バイトの予定を詰め込んだって、意識が目の前の作業に向かない日も多い。もしかすると、鶴見さんへのアプローチは、こんな日々から抜け出したいというおれの内なる心がそうさせたのかもしれない。
一人ずつ会計を済ませる。先に支払いを終えたおれは店の外で待っていた。そこへ鶴見さんがやってくる。
「さっきの話だけど、なんなら、一緒に行かない?」
イッショニ、イカナイ……? 一瞬意味が分からずに固まる。鶴見さんは続ける。
「わたしが運転する車の助手席に乗るってこと。旅って、人それぞれに感じ方が違うと思うの。だからわたしの体験談より、橋本君が直に感じたことをブログに書くのが一番いい気がして。そうすれば、お土産だって自分好みのものを選べるじゃない?」
「…………」
「あなた、一人で旅に行けないって言ったわね? でもそれは、誰かと一緒なら行きたいって意味よね? ……本当は自分で体験したい、違う?」
「……でも、おれがいたら楽しめないっしょ。逆に、鶴見さんは一人旅したいんじゃないの?」
「どうかしら……?」
彼女は曖昧に返事をした。
……なんなんだ? この、微妙な反応は? 戸惑いを隠せない。
「……あのー、一応確認したいんだけど、いきなりおれを好きになった、なんてこと、ないよね……? おれ、女の子は好きになれない体質でさ」
思い切って正直に打ち明けると、「何を言っているの?」と睨まれた。
「思い上がりも大概にしなさい。……断っておくけれど、わたしは恋愛には興味がないの。あなたに提案したのは、一人で行くも二人で行くも、わたしの労力は変わらないと言うシンプルな理由からよ。ただし、日帰りできる近場限定ね」
彼女に言われるまでもなく、おれのブログなんだから、おれの体験を書くのが一番いいに決まっている。おれが行けば、土産物に限らず、そこでしか味わえない郷土料理を食べた感想も書ける。分かっていたことだけど、そうか、二人で旅すりゃいいのか。その発想はなかった。
「……そういうことなら、便乗させてもらおうかな」
想定外の展開になったが、こうなった以上流れに身を委ねてしまうのも悪くないかもしれない。
かおり
「いつから知っていたの? 橋本君が同性愛者だってこと」
カフェを出て駅へ向かう途中、こっそり後藤さんに尋ねた。彼は高野君と話をしながらわたしたちの後ろを歩いている。
「いつって、高校生の時から」
「知っていながら、頻繁に三人で会っているの? ……高野君は同性として平気なの?」
「うーん。一応二人の間の決め事はあるっぽいけど、詳しくは……」
彼女は後ろの高野君を気にするように視線を動かした。そのとき、唐突にある考えが浮かぶ。
(もしかして、橋本君は高野君のこと愛している……? そして後藤さんはそれを知っていて、橋本君を気遣っている……?)
後藤さんと高野君。恋人同士なら二人で会えばいいと思うのに、なぜ橋本君を交えた三人で行動するのか、疑問に思っていたのだ。しかしそう考えれば納得できる。
考え事に耽っていると、後藤さんが話し始める。
「斗和はね、橋本の想いを全部知った上で友だちでいるの。私も同じ。……っていうか、同性愛者かどうかは抜きにしても、私は橋本のこと、尊敬してるんだ。何でも知ってるし、達観してるし、それでいて話していて楽しいし」
「だからこうやって三人で会っている、というわけ?」
「そうだけど……何か、おかしいかなあ?」
「あなたって、相変わらず暢気なのね……」
恋敵から友だちだなんて言われ、橋本君もさぞかし立場がないだろうと想像する。
一人で旅に行けない性格だ、といった彼の表情がよみがえる。あの場では単に行動力のなさが原因だと思ったけれど、本当は、高野君を愛するがゆえの葛藤から身動きがとれなくなっているのではないだろうか。
「こんなことを言うのは酷だけど、橋本君とは少し距離をとるべきだとわたしは思う。本当に友だちを想うならばね」
「えっ、どうして……?」
「もう少し、恋人の高野君を見てあげなさい、ってこと。八方美人は嫌われるわよ」
「そ、そうかなあ? そんなつもりはないんだけど……」
後藤さんは高二の時まで神と対話が出来たらしく、そのせいか人との接し方に難がある。高野君も、幼なじみから恋人になれたとは言え、後藤さんの扱いに苦労しているのでは? と他人事ながらも心配してしまう。
気づけば駅に到着していた。後ろを歩いていた橋本君に声をかけられる。
「鶴見さん、連絡先教えてくれる? 次に出かける時は連絡して欲しいから」
「わかったわ。でもわたし、メールのやりとりが苦手で。連絡する時はたぶん、電話をかけると思う」
「OK、すぐに出られないかもしれないけど、そのときはかけ直すよ」
「ええ。面倒でも、よろしくね」
わたしはカバンから、スマホではなく、手帳とペンを取り出した。電話番号と下宿先の住所を書き始めると、橋本君は目を丸くし、口をあんぐりと開けた。破った紙を手渡してもまだぽかんとしている。
「……ああ、本当に苦手なんだ」
「……橋本君もここに連絡先を書いてくれるかしら?」
「あ、はい……」
大きな手で小さな手帳に文字を書くのは難しそうだったが、なんとか記入してもらうことが出来た。
これからもう少し遊んでいくという三人を残し、一足先に帰路につく。埼玉方面に向かう電車は空いていた。席に座り、落ち着いたところで先ほど書いてもらった彼の連絡先を確認する。
「あら……?」
無骨な文字で読みにくかったが、そこはわたしがいま下宿しているアパートから、バス停二つ分ほどしか離れていない番地だった。まさか、こんなに近くに住んでいたとは。これも何かの縁だろうか。
下車駅に着くまで時間があったので、不慣れな手つきながらも彼の電話番号だけはスマホに登録した。これで向こうから連絡が来ても大丈夫。安心したわたしは、ほんの少しだけ夢を見ようと目を閉じた。
ここから先は
¥ 480
いつも最後まで読んでくださって感謝です💖私の気づきや考え方に共感したという方は他の方へどんどんシェア&拡散してください💕たくさんの方に読んでもらうのが何よりのサポートです🥰スキ&コメント&フォローもぜひ💖内気な性格ですが、あなたの突撃は大歓迎😆よろしくお願いします💖
