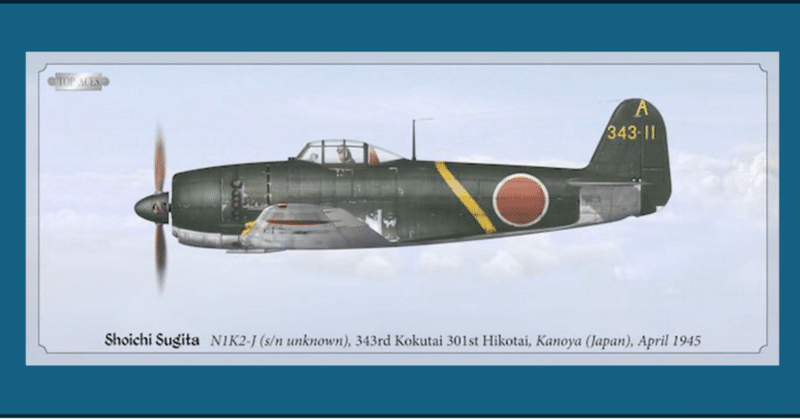
杉田庄一物語 第三部「ミッドウェイ海戦」 その25 ガダルカナル島攻防戦はじまる
ガダルカナル島は大小百の島が連なるソロモン諸島の南端にあり、大きさは四国の三分の一ほどで、南岸に狭い平地があり急な山地へと続いている。北側に飛行場を建設できるわずかな平地があった。昭和十七年六月ミッドウェイ戦が日本軍の事実上の敗北で終了したあと、大本営は「米豪遮断」をあきらめず、いやむしろ戦略的な重要性が増してきたと考えていた。
五月三日に占領下においたツラギ島付近で基地候補を探していた横浜航空隊司令の宮崎重敏大佐は、ガダルカナル島の中部北岸に滑走路を確保できそうな適地をみつけた。これに基づいて同地の調査が本格的に行われ、六月下旬から第十三設営隊(約千二百名)、第十一設営隊(約千三百名)が約二百五十名の陸戦隊とともに派遣された。スコップやツルハシなどを使って、八月五日には長さ八百メートル、幅六十メートルの滑走路予定地を切り拓いた。
しかし、八月六日に米豪の海兵隊が上陸し、完成間近な滑走路をおさえた。すぐに米軍は、滑走路を整備しヘンダーソン基地と名付けて制空権を確保しようとした。その日から昭和十八年二月までガダルカナル島をめぐった攻防戦が続くことになる。
「米豪遮断作戦」計画は、ポートモレスビーへの攻略作戦(MO作戦)とニューカレドニア、フィジー、サモアへの攻略作戦(FS作戦)から成っていた。ミッドウェイ作戦の失敗とともにMO作戦、FS作戦も頓挫したが、連合艦隊司令部はその中間にあるガダルカナル島に飛行場を建設することでソロモン海域の制空権をおさめようと考えた。
この時期の連合艦隊司令部は、参謀長、先任参謀、砲術参謀、航海参謀、水雷参謀、通信参謀、航空甲参謀、航空乙参謀、戦務参謀、機関参謀の十人で構成されていて、参謀長は宇垣纏少将であった。
八月五日、ようやく滑走路の第一期工事が終わったところへ米豪の海兵隊一万九百名が上陸を開始し、約二千五百名の日本兵や建設作業員などをあっというまに駆逐して滑走路を占領してしまう。でこぼこだった滑走路にすぐに鉄板を敷いて米軍機の発着を可能に整備し、ヘンダーソン飛行場と名付けられた。
これより、ガダルカナル島を再び奪い返そうとする日本軍とここを反攻の拠点としようとする米豪軍との壮絶な攻防戦がはじまった。ガダルカナル島攻防戦は、ジャングルに囲まれた島内での米軍、日本軍の地上戦だけでなく、兵や物資を送り込むための補給戦、主力艦を伴う海戦、制空権をとるための航空戦が同時に展開する総力戦になった。
特に、補給を確保することの重要性を日本軍に痛感させることになる。まだ軍事力を残している日本軍と準備が十分に整っていたわけではない米軍が、がっちり四つに組み合った壮絶な戦いが半年以上続いた。杉田が送り込まれるのは、このガダルカナル島攻防戦の最前線の航空部隊になる。
ガダルカナル島奪還を目的とした日本陸海軍の協同作戦は「カ」号作戦と名付けられた。ラバウルの南東方面艦隊(日本海軍)と第八方面軍(日本陸軍)の参謀たちの関係はあまりよくなかった。相互に信頼をしておらず、陸海軍航空兵力の統一指揮も研究だけに終わり、結局はばらばらなままの戦いになってしまう。
しかし、連合艦隊司令長官の山本五十六と第八方面軍司令官の今村均は旧知の仲で個人的には深い信頼関係で結ばれていた。今村の強い指導によって陸軍と海軍の協力関係は引き続き研究されることになり、次第に具体化されていく。
今村は、山本と同い年であり、仙台生まれなのだが新潟の新発田中学校を主席で卒業している。

ラバウルの零戦隊は、ガダルカナル島上空での制空権を得ることが任務となるが、約千キロメートルも離れていることが問題だった。零戦の航続距離からいえばアウトレンジで戦うことは十分に可能である。 むしろ、アウトレンジでの作戦可能であったことが問題だった。連日、零戦搭乗員たちは、千キロメートルを洋上飛行し、敵と戦って、また千キロメートルもどってくる戦いを強いられた。結果、戦って死ぬよりも疲れて眠ってしまったり雲中で衝突したりという遭難事故で多くの優秀な搭乗員が失われた。ことに辛かったのが眠気との戦いだったという。搭乗員はキリを持参して腿を刺したり大声で歌を歌ったりさまざまな工夫をしたが、空戦を行ったあとの帰路、疲労困憊してそのまま寝落ちて墜落する零戦が多くあったという。卓越した零戦の能力が「人が操縦する」というファクターを除いた無謀な作戦計画を参謀に作らせることになってしまったのだ。 もう一つ問題が生じていた。ラバウル基地の零戦が二号戦(32型)に転換を図り出した時期に重なったのだ。二号戦は航続距離が短く、ラバウルからガダルカナル島まで往復して戦うことはできない。新しく補充されてくる零戦が二号戦では戦えないのだ。急遽、一号戦(21型)をかき集めてラバウルに向けなければならなかった。
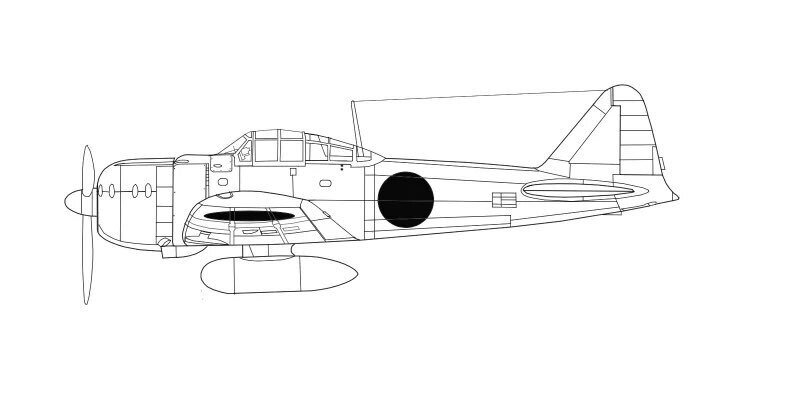

<参考>
※ 今村均:今村均に関するnote
大きくなっても夜尿症に悩まされ、熟睡する夜はなかったという。新発田中学校では成績優秀なため将来を期待されながらも家庭の事情でお金のかからぬ陸軍士官学校に進む。現場よりも研究のできる陸軍内の教員を目指すも優秀なためエリートコースにいれられてしまう。中枢部に入ると今度は軍の暴走を糾す言動で外地の軍司令官に出されてしまう。地域住民に喜ばれる軍政を行うと再激戦地(ラバウル)の司令官に任命される。ラバウル基地は激戦の末、米軍からも日本軍からも見放されてしまう。何万人もの生き残った陸海軍の兵士を海軍の草鹿中将と協力して終戦まで自給自足体制を築き、最後は軍としての威厳を保ったまま米軍に軍旗を渡す。戦後は全ての責任は自分にあるとして自ら外地の刑務所に入るも、出てくる証言は今村を称賛するものばかり。収容所では刑死を宣告された収容者たちに寄り添い、言葉をかけて送り出す。14年後に釈放されて自宅に戻ると小屋をたてて蟄居し、自伝や回顧録を執筆する。その印税をもって死ぬまで刑死者や遺族の補助をつづけた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
