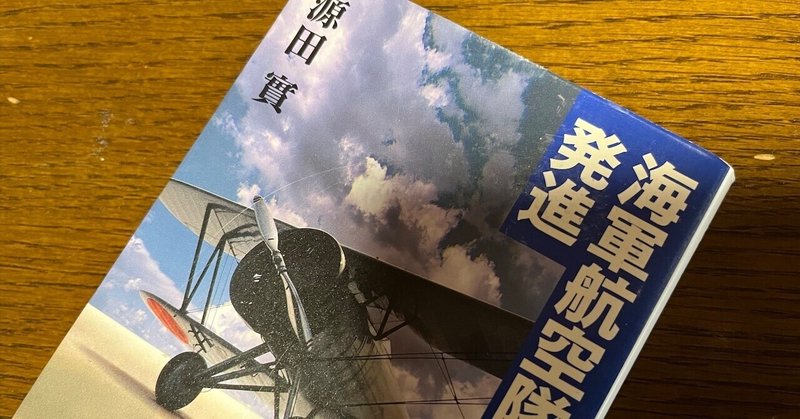
飛行機の本#41『海軍航空隊、発進』(源田実)
元参議院議員源田実が昭和三十六年に書いた「海軍航空隊始末記 発進編」の改題である。姉妹編に昭和三十七年発行の「海軍航空隊始末記 戦闘編」があるが、それは同じく「海軍航空隊始末記」と改題されている。
源田は明治三十七年(1904)に広島県の加計町に生まれ、海兵五十二期を卒業し飛行士官になった。横須賀海軍航空隊(横空)、空母「赤城」空、霞ヶ浦空などを経てから横空に戻り、戦闘機の空戦性能の審査、研究を行った。民間から献納される戦闘機「報告号」の献納式のセレモニー時に、分隊を率いて編隊アクロバット飛行を行ったことから「源田サーカス」の名前で世に知られるようになる。また、艦隊決戦が主流の海軍の中で、早くから航空主兵論を唱えたことから海軍条約派との人脈ができ、とくに大西瀧治郎、そして山本五十六から目をかけられた。
ロンドン軍縮会議後、山本五十六がとなえた「艦隊決戦より航空決戦」を支持するあまり、当初は戦闘機無用をとなえていたが、のちに前言をひるがえし、逆に制空権を得るために戦闘機の活用を訴える。戦闘機無用論とは、複葉戦闘機のかなわない高速でしかも長距離を往復できる攻撃機(九六陸上攻撃機)が登場したことから、もはや戦闘機は無用になったというのがその主張である。そこには戦闘機は、敵の攻撃を防御するための飛行機という概念が根底に存在していた。「戦闘機=防御兵器」という考えだ。なまじ戦闘機乗りなので、格闘戦重視のこれまでの戦闘機の概念から離れなかったのかもしれない。のちに零戦の計画要求論争でも強く格闘性能にこだわって開発者を困らせる。このとき論争相手は海軍兵学校同期の柴田武雄だった。碇義朗氏の「激闘 海軍航空隊」によると源田と柴田は終生対立していたようである。
駐英大使館付き武官として英国にいるときに英独航空戦が起こり、航空戦に対しての認識を深める。真珠湾攻撃の素案をたてたり、ミッドウェイ戦での航空作戦をたてたりと、日本海軍航空隊の中心的な参謀であった。
本書では、海軍航空隊がまだ大正末期から日中戦争初期までの日本海軍航空隊の揺籃期を書いたものである。自身の少年時代から航空参謀になるまでの半生を軸に海軍航空隊が世界の航空界の発展に遅れまじと日本独自の新機種開発に取り組んでいくナラティブである。
自らは優れた戦闘機パイロットになりたいと精進しているのだが、まわりはそうさせず、拒んでいた海軍大学校に進むことになる。海軍大学校では「航空主兵論」ををまとめ、その後は軍令部で航空戦略計画立案にたずさわるようになっていく。結局、一度も実際の空戦をさせてもらえなかったという。しかし、常に戦闘機操縦の腕を磨き続けており、戦争末期には三四三航空隊を創設し、自ら司令になった。最後は自分で操縦して戦うつもりで紫電改の操縦を訓練していたという。
新しい戦闘機開発時に何度もかかわるが、本書ではそのあたりのことが主に書かれている。こだわったのは格闘戦性能だった。複葉機の旋回性能や上昇性能に単葉機はかなわない。単に空中戦=格闘戦とはいえず、速力という要素もあり、エンジンの発達と共にその要素の方が大きく影響してくる。源田は、格闘戦性能にこだわりつつも速度をとりいれた空中戦を受け入れていく。九〇艦戦と三式艦戦の模擬空戦での比較の経緯がそれである。ちなみに三式艦戦の後継機が九〇艦戦(一葉半複葉機)である。九〇艦戦開発の経緯を詳しくかいているが、この論争は零戦開発までひきずっていくことになる。
また、南京空襲などから九六戦によって「制空権」を得る戦いなどについての詳細が書かれている。「制空権」をとることの重要性を源田はこのあと太平洋戦争でも主張し、作戦立案のもとにしていく。
空戦においては、海軍搭乗員の伝統となる「ひねり」が当時の下士官搭乗員によって開発されていたことがわかる。この「ひねり」は先輩から盗むものとして伝承されていく。この「ひねり」についても前述の柴田は自分が編み出した「旋転戦法」がもとになっていると主張している。
本書では、三菱の堀越技師による九試単戦(九十六戦)開発の経緯をも詳細に書いているが、そこに宮崎駿監督の『風立ちぬ』の世界の実際を見ることができる。源田氏が海軍の審査側でこの開発にたずさわっていたのだ。この立場はそのまま十二試艦戦(零戦)開発につながっていくことになる。
日本の航空機発達史として読んでみても貴重な資料となる書籍である。あわせて碇義朗の「激闘海軍航空隊」も読むと別の側面が見えてくる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
