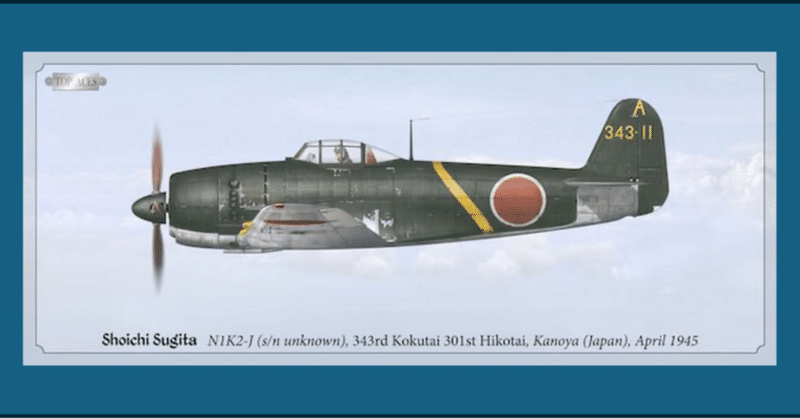
杉田庄一物語 第三部「ミッドウェイ海戦」 その26 第一次ソロモン海戦
昭和十七年八月七日、この日から、連合国軍の本格的な反攻がはじまった。米軍及び豪軍によるソロモン諸島ガダルカナル島をめぐる攻防戦とツラギ島方面への逆上陸である。
ガダルカナル島へ上陸した日本軍が航空基地の第一期工事を終えたのは二日前だった。まだ、滑走路として機能していない状態だ。ツラギには横浜空の水上機基地が駐留していた。米軍は、反攻をここからスタートすることにしたのだ。
大本営では、連合国軍の反攻開始を昭和十八年以降と想定しており、まさしく虚をつかれることになった。まさか、米軍がもう反攻に入るとは思ってもいなかったのだ。B25による東京空襲につぐ鋭い米軍の一撃だった。もちろん米軍が準備万端の準備をしていたわけではない。やられっぱなしではいけないという闘争心が優先した作戦であった。

こうして始まったガダルカナル島攻防戦は、その後の日本軍の趨勢を決める分岐点となった。島の制空権を得ることは、上陸部隊の支援や補給線の確保につながり、最終的には戦いの勝敗を決めていく。ガダルカナル島航空基地の奪い合いに双方の海軍艦艇まで乗り出し、三回のソロモン海戦や南太平洋海戦という正面衝突となる軍艦同士の戦いも起きる。
当初は無理を承知の無謀ともいえる戦いを行なっていた米軍であるが粘り強く消耗戦にもちこみ次第に装備や補給物資が整っていく。逆に、日本軍は軍艦、航空機、燃料、武器等を失っても補給が定まらず、とうとう餓死者や戦病死者を多く出すようになる。また、陸上戦でも航空戦でもタフな戦いをする米軍に対し、いさぎよさを尊ぶ日本軍は優秀な指揮官や兵が真っ先に戦死し、当然であるが米軍が優勢になっていくことになる。
七日の早朝、豪軍の支援を受けた米海兵隊約一万九百名が艦砲射撃と航空機による爆撃のあとテナル川東岸付近に上陸した。また、ツラギ島へは四個大隊千五百名が上陸した。
当時の米軍は四軍体制で陸軍、海軍、空軍、海兵隊で構成されていた。海兵隊は、敵前上陸して戦線の突破口を開くことを専門とし、常に最前線で戦うため犠牲者を出すことも多く、勇猛果敢であることが最低条件として求められていた。海兵隊は士気の高さを保つため、志願者だけで構成されている。そして、米軍反攻の第一波に選ばれたのは最も歴史がある米海兵隊第一海兵師団であった。
奇襲を受けた日本軍は設営隊と海軍陸戦隊合わせて当初六百名ほどであったが善戦し、当初よくしのいでいる。米軍海兵隊も準備が十分整っていたわけではなく、この時期の米軍海兵隊は日本軍から物資を奪ってしのぐような厳しい戦いを行なっている。
海軍航空隊もすぐに反撃を開始する。ポートモレスビーからB17爆撃機十三機がラバウルに来襲したが、二空飛行隊などから二十八機が邀撃し、一機を撃墜している。二空は、五日の朝にラバウルに着いたばかりであった。
ツラギ方面でも航空戦が行われている。台南空の中島正少佐を指揮官とする零戦隊十七機と四空の一式陸攻二十七機が敵機動部隊を目指して出撃するが、発見できなかった。しかし、二空の井上文刀大尉が指揮する九九艦爆隊九機が護衛をつけないまま、ツラギ沖の敵船団攻撃に向かい、爆撃を行なっている。航続距離の短い艦爆は、攻撃後にショートランド島付近で不時着水を行い、飛行艇に搭乗員のみ拾い上げてもらうという捨て身の作戦だった。この攻撃により、駆逐艦一隻を撃沈している。対空砲火や敵戦闘機の邀撃により三機を失った。帰途に三機が行方不明になる。井上大尉の指揮官機も邂逅場所に辿り着けず、別の島付近に不時着水。予定通りに救助されたのは二機のみだった。二空艦爆隊は、ラバウルについてすぐに壊滅状態になる。このあと二空は旧式の九六艦爆が補充されるが攻撃にはつかえず、零戦隊が台南空と合流し、ガダルカナル上空の制空権を争う熾烈な戦いに駆り出されることになる。
鹿屋空に所属していた本田稔も、このとき一式陸攻の護衛隊としてガダルカナル島へ出撃している。『本田稔空戦記』(本田稔、光人社)にその時の様子が記載されている。
「午前三時起床、三時半整列。 四時発進だ。のんびりしていた今までとは違い、いかにも戦場へおもむくという緊張感が漂い溢れて身が引きしまる思いがした。これより少し前、すでに上の飛行場からは一式陸攻二十六機が離陸していた。足の速い我々戦闘機隊二十一機は、その後を追いかけるように、ようやく明け始めたラバウル東飛行場を一機、また一機、砂塵を巻いて離陸していった。
上空から見ると払暁のラバウルは一面霧に包まれ、白いベールにおおわれて幽玄な感じさえした
編隊を組みなおし、一式陸攻隊に追いつくとたちまち堂々たる戦爆連合の大編隊となり、進路百十五度にとって一路ガダルカナル島に向かった。
この堂々たる大編隊を見ている限り。ガダルカナル島にどんな敵が押しかけたのかは知らぬが、そんなものはモノの数ではないという自信に溢れていた
私にとっては初めてのコースであり、このコースを再び帰るとなれば、常に目標となるものを覚えておくのが飛行機乗りの常道であった。 ここラバウルとガダルカナル島間の距離は東京と下関間に相当するのである。しかも戦闘時間を入れると帰着するまでに八時間以上も飛ばねばならないので、少しでもコースを間違えたり、回り道をしたりすれば燃料切れになる恐れがある。
私は眼下の島々や湾の形をチャートと併せ印象づけながら飛行を続けた。ブーゲンビル島を過ぎチョイセル島を左に見下ろし、コロンバンガラ島を飛び越えるといよいよあと一時間とちょっとで目指すガダルカナル島上空に達する。腹が減っては戦はできぬというわけで、弁当の巻き寿司を食べる
単調な飛行を三時間も続けると、出発の時の緊張もいつしかやわらぎ、巻寿司などを食べているとふと昔日の遠足にでも出かけているようなのどかな気分になり、つかの間ではあるが今から天下分け目の決戦場におもむくことなど忘れていた。
やがて隊長機の合図により戦闘隊形に入る。 いよいよ戦場近し、と思うと、先ほどのほんのつかの間のピクニックムードも吹っ飛んで再び緊張する。イサベル島のセントジョージ岬を過ぎるとガダルカナル島の北端エスペランス岬が見える。わが攻撃隊は既に米軍の手に渡ったルンガ飛行場をめざして高度を下げ爆撃態勢に入った。この時、地上でピカッピカッと何かが光ってみえた。それはかつてほとんど体験しなかった敵地上部隊による対空砲火であった。 それでも苦戦のしたことのない我々零戦隊は恐れを知らず、一糸も乱さず陸攻隊を護衛し続けたのである。 陸攻隊の爆弾が全弾投下されると、やがて滑走路をはじめ飛行場周辺はもうもうたる煙に包まれ全弾命中であった。
またしても向かうところ敵なしと思って再び上昇、全機無事、帰途についたとき右上方にチカッと光ったような気配を感じた。
非常に遠距離の敵を発見するときはたいていの場合、何か霊感のごとくひらめくものがあり、そうするときっとその方向から敵が来るのである。霊感とっても瞑想からひらめくものとは違って、そこにはやはり視神経を刺激する何かがあるのだ。
これが誰の眼にも見えるような距離になってから発見したのではすでに敵も発見しており、優位な態勢は取れない。 従って互角の条件ならまず先に発見して態勢を整えた方が有利である。
敵はアメリカ戦闘機F4F約三十機の編隊であった。 かつてイギリスのスピットファイアを、まさか敵とは思わずすれ違いざま気づいてあわてて退避した、あののんびりしていた東南アジア当時とは違い、今は敵との遭遇は必定と教えられていただけに、いよいよ来たかと胸の高鳴るを禁じ得なかった」
三時間飛行して、命懸けの戦闘を行い、疲れた精神と身体で再び海上を三時間飛行して戻ってくるという非常識な航空作戦を搭乗員たちは日常的に強いられた。
八月八日、この日も敵機動部隊を探して台南空、四空、三沢空の合同攻撃部隊が出撃したが、発見できなかった。そのため目標を変更し、ツラギ沖に集積している敵艦船を強襲する。
航空魚雷による攻撃で大戦果をあげたと報告するが、米軍の調査では輸送船一隻の沈没と駆逐艦一隻中破だけだった。それに比して、日本軍側の損害は大きかった。四空と前日ラバウルに来たばかりの三沢空の一式陸攻二十三機は、対空砲火により十八機が未帰還となってしまう。一式陸攻の防御の弱さが露呈したのだ。陸攻には七名が搭乗するので戦死者の数が一気に増加した。また、零戦が十五機に対して米軍戦闘機は十機程度であったのに、零戦も一機自爆、一機未帰還となる。
同日深夜、三川軍一中将に率いられた第八艦隊が米軍上陸部隊に夜襲をしかけ、重巡洋艦四隻を撃沈した。第一次ソロモン海戦と名付けられた。日本海軍は訓練してきた伝統の夜戦の成果を発揮し大戦果をあげる。米海軍にとっては真珠湾攻撃に匹敵する敗北を喫することになった。しかし、日本海軍は米軍輸送船を攻撃することなく、勝利に甘んじてそのまま引き揚げてしまう。輸送船をそのまま残したことの意味に気付かないことが、日本海軍の大きな欠陥でもあった。
海軍だけでなく日本軍全体に通じる思想として、補給に関しての意識や優先順位が低かった。「艦隊決戦」で勝負がつくと考えていた艦長がまだ多くいて、まずは戦艦などの主力艦、ついで補助艦が優先され、輸送艦など見向きもされなかったのだ。そのおかげで米軍は重火器を含む大量の物資の揚陸に成功し、その後のガダルカナル島の戦いの戦略的な帰趨に大きく影響する。以後、補給線を確保するための戦いが続き、兵站の重要性を思い知ることになる。
上陸当初の米海兵隊は、前述のように補給がなく、一日一食に制限してジャングルの厳しい生活に耐えていた。日本軍も島を奪還するために一木清直陸軍大佐を隊長とする歩兵第二八連隊一木支隊九百名を上陸させる。敵主力は撤退したという誤情報があり、軽装(一人当たり小銃弾二百五十発、食料七日分)の部隊であった。両軍とも飢えながらの戦いになった。八月二十日、イル川をはさんで全面衝突するが、米軍は重火器を届けられたあとであり、圧倒的な火力の差で一木支隊を翻弄する。
同日、海軍軍令部が二十六航戦を主力とする「第六空襲部隊」を編成し、ラバウルに派遣することを決定する。同時期の六空は日本にいてラバウル進出の準備を行っていたが、それは後述する。
<参考>
〜〜 ただいま、書籍化にむけてクラウドファンデイングを実施中! 〜〜
クラウドファンディングのページ
QRコードから支援のページ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

