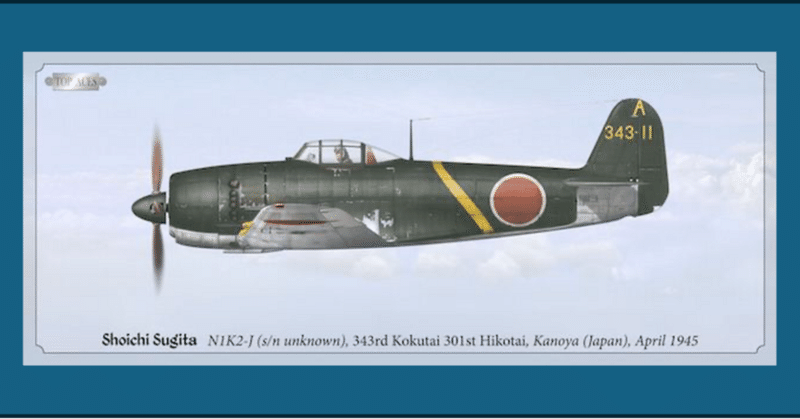
杉田庄一物語その33 第四部「ガダルカナル島攻防戦」六空主力隊合流
十月七日、空母「瑞鳳」に便乗していた六空主力隊が、カビエン北方百五十浬から発艦しラバウルまで洋上飛行で向かう。約一時間の行程である。発艦経験のない搭乗員がほとんどということで機の重量を減らすために、増槽タンクの燃料搭載量を半分以下の百五十リッターにし、使用時間も一時間と指示される。
午前十時、宮野大尉の前言どおり発艦だけはみな無事に行うことができた。しかし、基地に到着できない機が出るという重大事故を起こしてしまう。
発艦後五十分、積乱雲でおおわれたニューアイルランド島が見えてくる。若手はまだ編隊飛行に慣れていない。宮野の航法にたよってついていく。しかし、ニューアイルランド島の手前には厚い雲の壁が立ちはだかっていた。日本では見ることのできない一万メートルを超える巨大な積乱雲である。
七千メートルから八千メートルで飛んでいると雲と稜線の隙間が少しあらわれた。宮野は雲の下を飛ぶことを決意し、高度を数百メートルまで落とした。編隊はのめりすぎたり遅くなったりで整わないまま増速し、次第に密集隊形になって雲と山の稜線の間をすりぬけるように進んでいく。
ようやくニューアイルランド島を越えると、各機は増槽タンクから翼内タンクへ燃料の切り替えを行う。ところが島川小隊三番機の庄司吉郎二飛は、切り替えがうまくいかず高度を下げていった。切り替え操作が遅れたか、空気を吸い込んでベーパーロックしたかでエンジンが止まった。庄司機は海上に着水し、マフラーを振るのが確認された。しばらく浮いていた機体が沈み、庄司は泳ぎ出したが、その後行方不明になる。
ラバウルに着くと他にも細野政治三飛曹と川上荘六二飛が到着していなかった。おそらく稜線の隙間をねらって高度を下げた時に、編隊の端の方にいた二機が雲中で接触をしたか山にぶつかったと判断されている。搭乗員三人とも杉田と同期の丙三期だった。
ラバウルに到着すると宮野は熟練搭乗員八名を率いて不時着機捜索に向かった。水上機で庄司を捜索に向かった平井飛曹長は、海面の油とたくさんのサメを発見するが庄司の姿は見つけられなかった。
島川正明は、著書「島川正明空戦記録」の中で
「零戦の搭乗経験も浅く、大型編成による未経験の編隊飛行、くわえての雲中突入、これらの悪条件がかさなっては無理もなかったのかもしれない。やはり搭乗経験のすくない者にとっては無理だったようだ。」
と、この日の感想を記している。戦闘する前の移動中に、二十四機の内三機が失われることになった。
このときの二十四機の中にいた柳谷も戦後次のように証言している。
「ラバウルに着くまでに犠牲になったのはいずれも同期生だった。細野政治、川上荘六の二人は天候不良のため、庄司吉郎は燃料切れが原因だった。発艦してニューブリテン島を超えるあたりから天候が悪化したが、細野と川上は後ろの方にいたのでついてこれなかったのではないか。何しろ、母艦を発進して三時間も飛ぶのは初めてだったのだ。記録は天候不良となっているが、細野と川上は誤って翼を接触させたとも聞いた。
翌日、上空哨戒を兼ねて行方不明の捜索を二時間ほどやったが、たとえ落下傘降下したとしても、あの海域はサメが多いので、生きのびることはできなかったろう。
私は最初の遺品整理の手伝いをすることになったが、内地でこれを受け取る遺族のことを思うと、何ともいえない気持ちだった。互いにそれを誓い合った仲ではあったが、彼らの方が先に死んでしまった。武運がなかったとでも言うのだろうか」
小福田率いる先遣隊が日本内地からラバウルまでの大遠征で全機無事到着していることが、今さらながら大快挙であったことがわかる。
なんとかラバウルについた新人たちであるが、先輩たちの厳しい出迎えを受けることになる。下士官宿舎では先遣隊の先輩下士官が酒に酔って日本刀を抜いて暴れる出来事があり、寄せ集め部隊のせいなのか、ミッドウェイを引きずっているのか、嫌な気分になったと島川は書いている。
しかし、若年同期生同士では打ち解けて気楽にすごしていた。ラバウルについたときの様子について、『NHK戦争証言アーカイブス』で大原は次のように語っている。
「私らの同期生が七〜八人いたんですけどね。大分の戦闘機部隊を卒業して、一番最初の配置が木更津の六空にはいったんだけど、戦場に行くという殺伐とした部隊ではなかったですよ。夕方になると酒を飲んだり、遊ぶ話をしたり、さかな釣りをしたり・・・淡々たるもんでしたよ。ラバウルについたってこんなこと(肩をすぼめて身構える姿を示す)にはならんかったですよ。ただ、ついたその日から大型爆撃機による空襲があって防空壕に入った時、これが戦場かと思いました。高高度で来て爆弾をポタンポタンと落としていくんだ。」
ラバウルはもともと大型船舶が停泊できる良港をかかえたオーストラリア(豪州)の委任統治領であった。この年(昭和十七年)の一月に海軍の第一航空艦隊が制圧し、陸海軍ともに本格的な航空基地を築いていた。活火山の通称花吹山と休火山の通称西吹山とが向かい合っている。六空は花吹山に近い海べりの東飛行場に零戦約八十機からなる拠点を設けた。西吹山方面には西飛行場があり、陸攻隊が使用していた。
しかし、六空はこのラバウルにとどまらず東南二百キロメートルのブカ島に集結し、ここを前進基地とする計画がたてられていた。ガダルカナル島への補給路を確保するための航空支援を行うためである。六空の内地からの移動が終えた時点で、ブカに零戦二十一機を進出させることになった。
この時点で六空の全使用可能機数は一号戦四十三機、二号戦三六機であった。機体はなんとか定数を揃えたにしても操縦できる搭乗員の補充は間に合わなかった。特に指揮官搭乗員が不足しており、編隊を組むにしても島川のような一年しか戦場経験のない一飛(一等飛行兵)を一番機(小隊長)に充てなければならない状況だった。
実はミッドウェイ海戦後の補充が必要なのは米軍にとっても同様であった。ミッドウェイでの戦いで主に活躍したのはグラマンF4Fワイルドキャットやブリュースターバッファローなどの少し時代遅れの航空機で、一番活躍したのは急降下爆撃機であるダグラスSBDドーントレスだった。ミッドウェイ海戦での空戦や離発着事故で多くの艦載機や搭乗員たちが失われていて、補充が必要だったのだ。そして、日米の補充の違いがその後の戦いを決定的なものにする。
ニミッツの強い政治力が効いて、米軍は圧倒的な数の新型機と訓練を終えた民間人からの大量の志願パイロットたちをこのあと全力で投入してくる。日本軍の補充は、予科練を繰り上げて前線に出した搭乗員となんとか数をそろえた零戦だった。しかも定数にはほど遠い数だった。
この日、海軍兵学校長から十月一日付で南東方面艦隊司令長官および第十一航空艦隊司令長官に親補された草鹿任一中将がラバウルへ赴任する途中にトラック島の戦艦「大和」に立ち寄り、山本長官と夕食を共にしている。第四艦隊司令長官の井上も招かれ同席している。
山本も井上もこれからのいくさは航空戦になると戦前から主張し、「艦隊派」の連中と戦ってきたのだが、結局戦艦「大和」や「武蔵」が作られてしまう。皮肉なことに、その「武蔵」に山本は司令官旗を掲げているのだが、大切な燃料を無駄遣いすることができず足止めされている状態だった。戦艦「大和」は「大和ホテル」と陰口をたたかれている始末だった。
このとき、井上は草鹿の入れ代わりに海軍兵学校長に内定していることを告げられる。珊瑚海海戦での指揮ぶりが中央で話題になっており、「いくさ下手」と言われていたのが原因かと井上は思ったが、山本から自分が推薦したと告げられる。「山本は戦後の海軍を自分に託そうとしている」、井上は山本の意を感じていた。
戦争はいつか終わる。そのときを見据えた若者の教育をせねばと井上は決断する。実際、井上はこのあと海軍兵学校長になったとき、兵学校のカリキュラムを軍事優先から教養中心に変えている。太平洋戦争末期、巷では敵性語として徹底的に英語を廃していたにもかかわらず、井上の強い指示のもと海軍兵学校は日本で最も英語を重視した授業を行うことになる。
ところで陸軍はガダルカナル島に部隊を逐次導入していたが、十月に入ってから送られた陸軍第二師団は新発田の歩兵第十六連隊や高田の独立第一山砲兵連隊で構成されており、長岡出身者も多くいた。極端に郷土思いの山本にとっては大いに気がかりになっていた。山本は郷里の反町栄一に「郷党子弟の苦難を総見すれば一向に快心ならず」という手紙を書いている。
この後、「大和」でガダルカナル島まで出撃するとまで言い出し、宇垣主席参謀を困らせるほどガダルカナル島に強いこだわりをみせることになる。
十月八日、ラバウルについた六空本隊はこの日すぐに四直交代でラバウル上空哨戒任務についている。まずは、ラバウル島の周辺地形をおさえる必要がある。哨戒任務は二時間で交代になる。三機で編隊を組む編成で、一番機(小隊長)には原則として下士官以上が搭乗することになっている。しかし、指揮官搭乗員が不足しており、前述したようにわずかな実戦経験のあった島川が小隊長として三直の任務についている。
そのほかに森崎予備少尉が昨日の不時着機捜索を行っているが見つけられなかった。また、ブカ基地では岡崎一飛曹、中野智弌一飛、藤定正一二飛が、輸送船団の直掩でSBD二機を撃墜している。六空はラバウルに展開したとたんにフル稼働となる。
搭乗員を養成するにはとてつもなく時間がかかるのに、戦争を始めてからその不足を痛感することになった。それは、戦前から山本や井上が指摘し続けていたことであった。
ラバウル基地へのB17爆撃機による不定期の爆撃は連日続いており、たとえ単機での来襲であっても在住する日本軍全員に対し常に緊張感を抱かせるものだった。そのためB17に対する哨戒任務も連日のものとなっていた。この日常的なラバウル上空哨戒任務は、遠征をともなわない基地上空の飛行任務であり、二番機や三番機に丙三や丙四の新人搭乗員が割り当てられて訓練の仕上げも兼ねることになった。
ところで十月八日の夕方遅く、二空の角田飛曹長指揮下の零戦九機が、水上機母艦「日進」の上空哨戒を行ったあと、整備中のブイン基地に着陸した。ブイン基地は同じブーゲンビル島の中に位置するが、ブカよりもさらにガダルカナル島に近いため、ここを整備することが急務となっていた。この時の様子を『修羅の翼』(角田和男、光人社)に次のように描かれている。
「往路に確認しておいた飛行場は、上空から見るとコンクリート舗装か、と見間違えるほど立派な滑走路だったが、到着してみて、驚いたことに、赤青灯の誘導灯のほか地面を示すカンテラは四個しかない。目標灯も飛行場の端を示す灯も一切見えない。若い搭乗員も連れていたので、ちょっと不安を感じたが、今さらどうにもならない。『着陸宜しきや』の信号を点滅する。ただちに『着陸せよ』の発光信号が飛行場中央西側あたりに見える。ただちに解散、縦陣となり順次地上の指揮に随って着陸を開始した。 暗夜に関わらずラバウルと違い新しい滑走路は快適な着陸ができた。 北の端にクルクル回る懐中電灯の方へ滑走して行く時に、何か爆音の中にグワァーンという異様な音を聞き、エンジンを絞る。ところが意志とは関係なく、飛行機はどんどん前に進んでしまう。おかしいと思ってブレーキを踏む。それでも止まらない。いささか あわて気味のところに『スイッチオフ、スイッチオフ』と悲鳴のような整備員の声が聞こえ、ただちにスイッチを切ると。 とたんに何百人とも知れぬ万歳の嵐が起こった」
実は、滑走路整備を手伝っていた海軍設営隊員と陸軍守備隊員たちが初めて見る飛行機に感激して飛行機にむらがって勝手に収納作業をしていたのだ。零戦のプロペラがまだ回っている状態で、危険を感じた角田は、「退がれ退がれ」と繰り返したが、暗闇の中の万歳の声でかき消されてしまった。結局、角田に続く列機の着陸にも多くの人々が群がったため、まだ速力の落ちていない機に跳ね飛ばされ死んでしまう者まで出てしまう。
<参考>
〜〜 ただいま、書籍化にむけてクラウドファンデイングを実施中! 〜〜
クラウドファンディングのページ
QRコードから支援のページ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

