
読書録/スローカーブを、もう一球
▪️「スローカーブを、もう一球」山際淳司著 角川文庫
スポーツ・ノンフィクション作家としての地位を確立した「江夏の21球」をはじめ、1970年代末~80年代の日本を舞 台に、様々なスポーツに取り組む人物を取り上げたノンフィクション短編集。「八月のカクテル光線」(夏の甲子園高校野球・箕島VS星稜)「江夏の21球」 (日本シリーズ・大阪近鉄VS広島)「たった一人のオリンピック」(ボート・シングルスカル)「背番号94」(プロ野球入りした高校生)「ザ・シティー・ ボクサー」(プロボクシング)「ジムナジウムのスーパーマン」(スカッシュ)、そして「スローカーブを、もう一球」(高校野球関東大会・群馬県立高崎高校)「ポール・ヴォルター」(棒高跳び)の8編が収録されている。
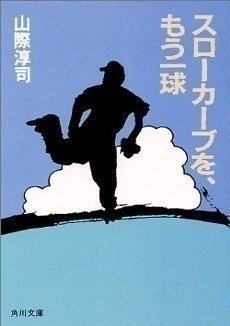
球史に残る1979年夏の甲子園・箕島高校 対星稜高校の延長18回の死闘を描く「八月のカクテル光線」。ナイター照明のカクテル光線が照らし出すこのゲームを、その舞台で戦った選手一人ひとりの心 情を読み解きながら描き出している。新聞のスポーツ欄やスポーツニュースの紋切り型の文章によって描かれる高校野球の一試合とは、まったく違った光景が、ページからあざやかに浮かび上がってくる。延長18回、始めてのナイター照明の下での試合。高校球児がそれまで体験したことのない限界に踏み込み、そして力尽きていく一瞬の一瞬の輝きを、その筆はとらえる。
双方3勝3敗で最終戦を迎えた、1979年の日本シリー ズ、大阪近鉄対広島戦。「江夏の21球」は、広島の1点リードで迎えた9回裏、リリーフとしてマウンドに上がった江夏豊投手が、21球を投じてチームに勝利をもたらすまでのドラマを克明に描く。ノーアウト満塁というピンチを迎え、「同点になっても仕方ない」と達観していた江夏の目に、ブルペンで投球練習を始めるリリーフ投手の姿が飛び込む。その光景に感情を揺さぶられ、駆け寄ってきた衣笠選手の一言で、限界で踏みとどまる、そのときの心理。
この短編集の作品のテーマは?ともし問われたら、私は「スポーツにおける限界の心理」と答えるだろう。ここには、様々な限界がある。肉体の限界。状況的 な限界。精神的な限界。本人だけに見えてきた限界。本人だけに見えていない限界。描かれることによって、はじめて明らかにされた限界。超えられる限界。超えられない限界。その限界の前で、力尽きる者と踏みとどまる者とがいる。今はまだいけるように見えても、間もなく力尽きるであろう者がいる。いずれにして も、スポーツに取り組まなければ、決して現れず、立ちはだかることのない限界である。その意味で、この「限界」を見るこそが、アスリートにとって特権といえるだろう。
表題にもなっている「スローカーブを、もう一球」は、そんな息詰るような短編の中にあって、ほっとするような、思わず頬がゆるむような、緩やかなカーブのような一編である。春の甲子園選抜高校野球に出場することになった群馬県立高崎高校が、関東大会で準優勝するまでの軌跡を描く。チームを牽引してきたのは、エースの川端俊介投手。130キロ台の直球と、60~70キロというスローカーブというたた2つの持ち球でバッターを打ち取り、これまでほとんど勝利に縁のなかった公立進学校の野球部が、面白いように勝ち上がっていく。その野球部の監督も部員も、 私たちが「甲子園」「高校野球」というキーワードから連想するような人物像とは、まったくかけ離れた存在である。中でも川端投手は、「らしい」ところが一 つもない。そんな彼らの快進撃に、思わず頬がゆるむのだ。しかし、そこにも「限界」はある。あるいはそれは、エースの川端投手自身が掲げた目標を達成してしまったがゆえの「限界」だったのかもしれない。
特に野球を題材にした作品をピックアップしてみたが、恐らく、野球を知らない、あるいは興味のない人にとって、これらの作品は、少々暗号めいたものに感じられるかもしれない。9回裏、1点リードで迎えたマウンド で、ノーアウト満塁を迎えた、という状況の緊迫感。そのこと自体が、野球という別の言語によっているかのようだ。スポーツが文化として根付いているかどうか、それは、スポーツの言語がどれだけ通じるかにかかっている。山際淳司は、その言葉を用いてドラマを描いた。試合を見る「目」、そして人物を見る「目」 の素晴らしさがあってこそ、普通の人には見えない「限界」をめぐるドラマを描くことができた。紋切り型でない本当のスポーツ・ノンフィクションがここにある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
