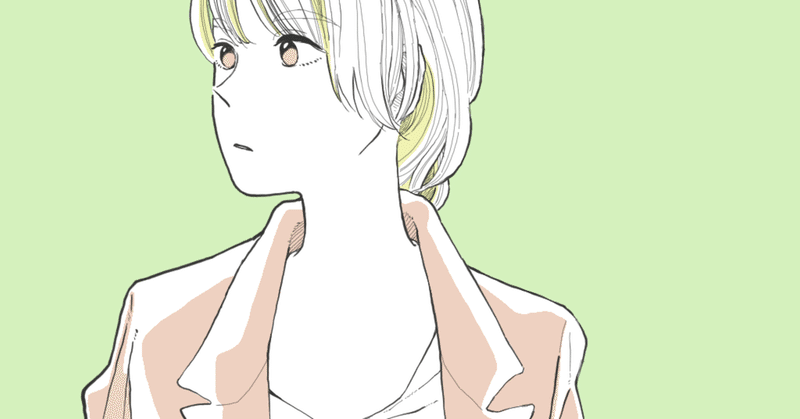
Photo by
cactuses_manga
秋風にさらわれる(小説)
とおくで電車の音がする。仕事終わりの人間の疲労感とか、冷房の臭い風があの鉄の塊に閉じ込められて高速移動しているのだと思うと何だか面白い。
夏が終わって、秋が顔を覗かせていた。夜は風がつめたくて気持ちがいい。エアコンなんて要らない。ありのままの風がいちばん好きだ。
コンビニで200円のプリンを買った。表面の薄皮みたいな部分が好きで、最初にスプーンで剥がしとって食べてしまう癖がわたしにはあった。
薄皮がすべてなくなると、半分以上残っているプリンはもう8割がた消失したも同然で、残りを食べる所作には作業感が出る。惜しみなく残りのプリンをずるずると平らげてしまった。
目をつぶると、朝がきてしまう。それが嫌でベッドの中でスマホの明かりを見つめる。
ふっ、とスマホの画面が暗くなった。しまった、充電器を挿すのをわすれていた。電池残量のバーがずいぶん前から赤くなっていたことに対して見て見ぬふりをしていた。
仕方なくわたしはスマホを枕の横に置き、目をつぶった。夜に屈することを決意したのだ。
その瞬間、強い風が部屋を通り抜けた。机の上の書類がパラパラと床に落ちる音がする。
古い空気がみんないなくなった。
スマホの充電がない、とか明日の仕事が嫌、とか気持ちが全部、部屋の空気に溶けていたんだ。嫌な気分がガスのように充満して、肺から侵入して心をきっと蝕んでいたんだ。
わたしは眠りについた。もう朝は怖くない。
床にちらばった書類は明日の朝片づけよう。
(終)
スキしていただけるだけで嬉しいです。
